小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

原典 http://www.trussel.com/f_hearn.htm
連続テレビ小説『ばけばけ』で、主人公・松野トキは、本当は雨清水家の子だと明かされる。
そのモデルとなった小泉セツも、生まれた家から養女に出された身だった。ここでは、小泉セツの実父の人物像と、小泉家の家柄を紹介しよう。
※本稿は、鷹橋忍著『小泉セツと夫・八雲』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
セツの誕生と時代背景
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主人公・松野トキのモデルである小泉セツは、松江藩の上級士族・小泉弥右衛門湊(やえもんみなと)とその妻・チエの次女として、慶応4年(1868)2月4日、松江城下の島根県松江市南田町で生まれた。
生まれた日が節分だったため、セツと名付けられている。セツは「節子」という名を好み、後年、「節子」と名乗ったり、書いたりしているが、戸籍名はセツである。古来の習慣により、当時はかなり高貴な生まれの女子を除き、名前に「子」を付けない傾向が強かった。
セツが生を享けたのは、激動の時代だった。
前年の慶応3年(1867)12月には王政復古の大号令が発せられ、新政府が成立するも、セツが誕生する1カ月前の慶応4年正月3日には、鳥羽・伏見の戦いが勃発し、戊辰戦争の幕が開いた。同年の9月8日には、明治に改元されている。
セツの長男・小泉一雄の随筆『父小泉八雲』によれば、小泉湊とチエは、セツを含めて11人の子宝に恵まれた。セツは上から数えても下から数えても6番目だったというが、無事に育ったのは、長男とされる氏太郎、長女のスエ、次男の武松、次女のセツ、三男の藤三郎、四男の千代之助の6人だけだった。
セツが生まれた小泉家は、三百石取りの由緒ある家柄だ。松江藩に代々仕え、組士50人を統率する番頭(ばんがしら)を担っていた。セツの父・小泉湊も、慶応4年7月から、番頭を務めている。
松江藩には約1000人の士分の侍がいたが、小泉家はそのなかでも、「上士」と呼ばれる最上位の家柄で、周囲の尊敬を集めていた。
セツの父・小泉湊は、天保7年(1836)12月27日に生まれた。セツの誕生時、湊は31歳で、その前年の慶応3年(1867)に家督を相続したばかりだった。
湊は小柄だが、痩せて引き締まった体軀の持ち主で、「活躍家で進取的気質のハイカラ」だったという(小泉一雄『父小泉八雲』)。
湊は青年時代から武芸に長けており、藩の軍隊の小隊長を務めていた。セツの手記「幼少の頃の思い出」(小泉節子『思ひ出の記』所収)によれば、湊の号令は素晴らしかったらしい。湊の号令で軍隊がピリッと引き締まり、わざわざ号令を聞きにくる人も多かったという。
母方の祖父は、講談や劇の主人公のモデルとなった忠臣
小泉家は由緒ある家柄だが、セツの母・チエの実家のほうが格上だった。
チエの父は、松江藩の名家老と謳われた塩見増右衛門(しおみますえもん)である。松江城二の丸御殿のすぐ前に狐や狸が棲み、化けていたずらをしたという噂が伝わるほどの広大な敷地に、屋敷を構えていた。禄高は千四百石、召使いを30人近く抱えていたという。
チエの父、セツにとって母方の祖父にあたる塩見増右衛門は、「出羽守やんちゃ殿様」と称された、出雲松平家九代目の松江藩主・松平出羽守斉貴(なりたけ。1815〜1863)を、死を以て諫めたことで知られる。
松平斉貴は将軍家の一門であり、弘化3年(1846)の孝明天皇の即位に際しては、将軍の名代を務めている。ペリー来航以前の時代において、西洋の砲術や医学などを取り入れ、数多の鷹場を設けるなど多くの文化事業を発展させた英主であるが、贅沢と放蕩が度を超えていた。
当時の諸大名と同じく、松平斉貴も参勤交代の制により一年ごとに江戸詰めしていたが、品川にある松江藩の下屋敷に五階建ての屋敷を造営し、望遠鏡、渡来時計、その他オランダ物などを集め、日々、酒盛りを繰り返している。
もともと好きだった相撲と鷹狩りに加え、祭り囃子の一種である馬鹿囃子に凝り出し、赤坂の上屋敷に馬鹿囃子の名手を集めて演奏させ、山王祭では、邸内に山車を通した。酒、女、乱暴についてのひどい話も残っているという。
嘉永4年(1851)はお国入りの年であるにもかかわらず、幕府には病気と偽り、江戸で、酒色に溺れる日々を送った。
斉貴の放蕩は、藩の財政を疲弊させていく。また、藩主が江戸にずっといるため、出雲の政治も乱れ、謀反を企む者も現われた。
江戸家老として赤坂の藩邸に入っていたセツの祖父・塩見増右衛門は、事態を憂い、諫言を2度も行なっている。だが、斉貴が聞く耳を持たなかったため、増右衛門は陰腹を切り、その上に白木綿を強く巻き付けて、同年11月2日、3度目の諫言に踏み切った。
最後となる諫言を終えた増右衛門が退出した時、斉貴は増右衛門の顔色が尋常でないことに気付き、急ぎ近侍に増右衛門を呼び戻すよう命じた。近侍は家老の詰所に駆けつけ、「御家老様、御家老様」と幾度も呼びかけたが、返事はない。
近侍が堅く閉まった襖を開けて中を見ると、増右衛門はすでに息絶えていた。まさに命と引き換えに、主君を諫めたのである。
辞世の句は、
君のため 思ふ心は 一筋に はや消えて行く 赤坂の露
だった(長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』)。
やんちゃ殿様と称された斉貴も、さすがに目が覚めた。翌年早々に、国元に戻っている。
増右衛門の長男・小兵衛は松江にいたが、斉貴を恨み、出迎えもしないだろうと、誰もが懸念していた。ところが小兵衛は、定まりである松江城下外れの津田の松原ではなく、国境の安来まで数里も遠出し、心から喜んで、「よくこそ御帰国」と出迎えたという。
「増右衛門の諫死、伜小兵衛の忠誠なる出迎え等奇特の至りとあつて、それ迄は千石の禄高がこの時四百石加増となつた由」と、小泉一雄は『父小泉八雲』に記している。
セツの手記「オヂイ様のはなし」(小泉節子『思ひ出の記』所収)によれば、この増右衛門の話は江戸の町々にも知れ渡り、「線香山」という題で講談となり、「三本杉家老鏡」という劇にもなっている。
セツは子どもの頃、友人の家に行くと、そこの老人から、よく祖父・増右衛門の話を聴かされた。「あなたのお祖父様は忠義なえらい方でございました」
と称えられると、自分が褒められたように誇りに感じたという。
祖父の話を繰り返し聴いて育ったセツは、祖父を誇りに思い続けた。セツの長男・一雄は明治32〜33年(1899〜1900)の秋、セツに連れられて赤坂の寺を訪れ、増右衛門の墓を探している。
住職とともに探し回り、ようやく墓を見つけた後に、本堂で小泉家の定紋(三本杉)がついた金色の位牌を探し当てると、「これはお前の偉い曾祖父様だ、よく拝みなさい」と、セツは涙を流しながら一雄に告げ、拝ませたという(小泉一雄『父小泉八雲』)。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月16日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

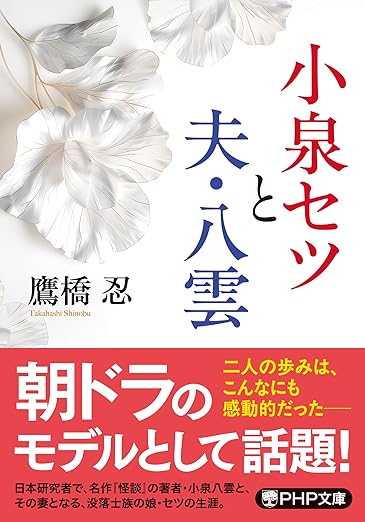

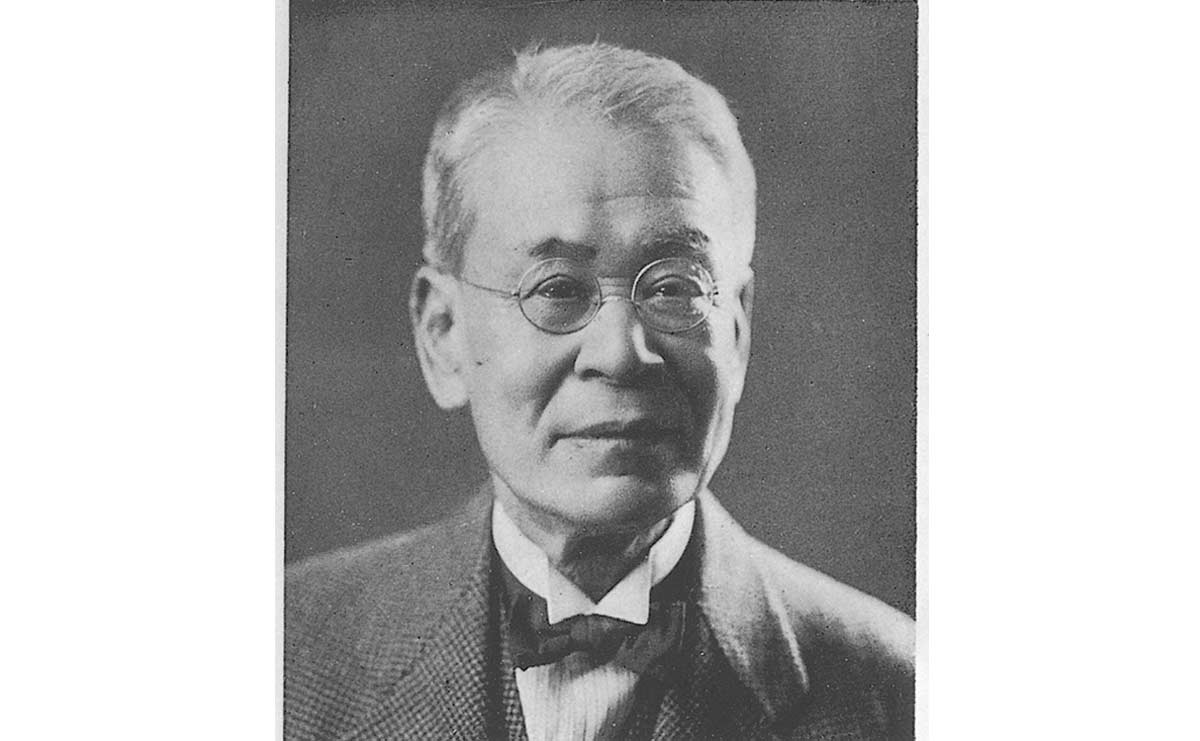
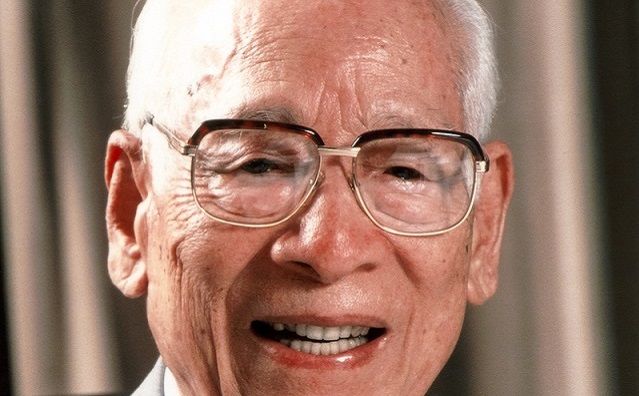
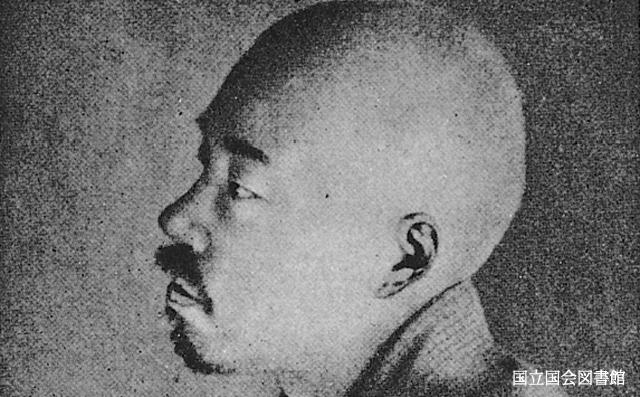

.jpg)


