インパール作戦はなぜ失敗したのか 牟田口廉也が犯した致命的ミス

太平洋戦争中の日本陸軍というと、失策を重ねたイメージが強い。しかし、南方攻略作戦のように成功を収めたものもある。一方で、インパール作戦のように悪名高いものもあるのも事実だ。2つの作戦の明暗を分けたものは何だったのか。ここでは、インパール作戦について解説しよう。
※本稿は、大木毅著『太平洋戦争』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
戦略的に防衛困難なビルマ
昭和19年(1944)、ビルマの日本軍は苦境にあった。昭和17年には、およそ4か月で連合軍を駆逐し、およそ60万平方キロメートルにおよぶ広大な地域を占領した日本軍であったが、いまや、そのビルマの地を保持しかねていたのである。
前年、昭和18年(1943)に新編され、同地域を担当することになったビルマ方面軍(河辺正三中将)が置かれていた状況は、つぎの通りである。
ビルマ西部、インパールからアラカン山脈にかけての正面では、イギリス軍ならびにインド軍と対峙。
ビルマ北部、レド方面では、米・中国国民政府の連合軍相手に戦線を保持。
ビルマ北東、中国雲南省と国境を接する正面では、米式装備の中国国民政府軍に対している。
これらに加え、有名な英軍ウィンゲート空挺部隊の空からの進攻と、ベンガル湾からの上陸作戦の脅威もあった。
とどのつまり、タイと接する東部国境方面以外は、すべて敵に囲まれているといっても過言ではない。当時の日本軍にしてみれば、ビルマは敵中に突出した陣地といった様相を呈していたのだ。
だが、いかに防衛困難とはいえ、政戦略上の影響を考えれば、ビルマを放棄するわけにはいかなかった。
ビルマ撤退は、大日本帝国の退勢を全世界に知らしめることになってしまう。また、ビルマを押さえていてこそ、同地を経由する連合軍の中国援助を妨害し得るという大きなメリットがあるのに、手放してしまえば、この大動脈が開いてしまうのである。
戦略的には防衛はきわめて困難。さりとて、自らビルマを去ることもできない。
このジレンマを解決すべく、禁断の方策が頭をもたげた。インドに侵攻し、英印(イギリス・インド)軍のビルマ作戦の策源地を先んじて奪ってしまおうというのだ。
攻勢防御か、インド侵攻か
実は、レド方面に攻勢を実施し、インドに侵攻するとともに、援蔣(中国支援)ルートを遮断するとの構想は、ビルマ占領直後よりくすぶっていた。昭和18年3月、第15軍司令官に補せられた牟田口廉也中将も、当初は補給の困難があると判断していたものの、やがて攻勢を主唱するようになる。
連合軍の航空優勢がしだいに高まり、ビルマ各正面で攻撃に出てくる可能性が大きくなる一方であるから、ビルマ方面軍主力を拘束されるレド攻勢は不可である。こうした判断のもと、牟田口は、いわゆる「攻勢防御」、インパール方面の英印軍策源地を奪取し、敵が攻撃に出るためのスプリングボードをなくすことによって、味方の防御態勢を安んじる作戦の実施を強く求めはじめたのである。
すでに触れたように、当時のビルマは、放置しておけば、どの正面も維持不可能になりかねない状況にあったから、限定攻勢で態勢を安定させるという議論には説得力があった。
ゆえに、牟田口の第15軍司令部が立案・上申したインパール攻勢計画「ウ号作戦」は、さまざまな異論や慎重論に遭ったものの、上部組織のビルマ方面軍、南方軍を経て、ついに東京の大本営陸軍部も認可した。昭和19年1月には、「ウ号作戦」実行命令が下達される。
このように、インパール作戦は、発案の段階から問題をはらんでいたといえる。
一般に戦争は、先述したごとく、上の階層から順に、「戦略」「作戦」「戦術」の3次元から成るといわれ、上位次元の失敗を下位次元の成功で回復することはきわめて困難だとされる。たとえば、作戦次元で決定的な過ちを犯していれば、いくら戦術次元、すなわち戦闘で将兵が奮戦しても、勝敗を覆すことはできない。
ところが、インパール作戦には、最初から、戦略的な苦境を作戦次元の離れわざによって逆転させようとする無理が内包されていたのである。
加えて、作戦目的にもぶれがあった。上部組織である大本営、南方軍、ビルマ方面軍が、インパール作戦は英印軍の攻勢を封じるための行動であると釘を刺していたにもかかわらず、実施部隊の第15軍を指揮する牟田口には、敢えて攻勢防御の域を超えて、インド侵攻を実施する企図があったと思われるのだ。
自分は日中戦争の発火点となった盧溝橋で、現場の連隊長を務めていた、いわば、戦争をはじめた責任があるのだから、なんとしても、この手で決着をつけたいと、牟田口は公言していた。
もし日本軍がインドに侵攻すれば、たちまち独立の機運が高まり、同国は連合国の陣営から離脱する。そうなれば、イギリス、ひいては連合国の戦争継続は不可能になろう。だからこそ、自分がインド侵攻をやらなければならないというのが、牟田口の論理だった。
実際、インパール作戦中、牟田口は、攻勢防御よりも、インド領内へのいっそうの進撃を狙ったと思われる指示を多々出している。
インパール作戦には、補給や航空戦力が劣勢であることの軽視、投機性など、多数の批判が向けられている。しかし、それら以外にも、この作戦には、戦略次元の事象を作戦次元で回復しようという危うさ、上級組織と実施部隊における目的の乖離といった、原則的なレベルで戦理にそむいた欠陥が含まれていたのである。
英印軍の巧妙な作戦
昭和19年3月8日、インパール作戦は発動され──よく知られているように、惨憺たる失敗に終わった。第15軍は、インド解放どころか、インパールの占領にも失敗し、数万の死傷者を出して、敗退したのだ。
しかも、その退却行は、補給がなされぬなか、悪天候と困難な地形を押してのものとなったから、「白骨街道」と形容されるような悲惨なありさまをみせた。さらに、第15軍の指揮下にあった3個師団の長すべてが更迭されるという、日本陸軍史上前代未聞の不祥事まで生じたのである。
戦略次元の前提に問題を有する作戦が、実行にあたって、その欠陥をむきだしにしたわけだが、意外なことに、第15軍は当初快調な進撃を示している。このような補給困難な地域で大規模な攻勢がただちに行なわれるはずがないという英印軍の油断を突き、準備未成のところを奇襲したかたちになったためである。
もっとも、だからといって、日本軍の作戦が当を得ていたとは評価できない。というのは、英印軍を指揮するイギリス第14軍司令官ウィリアム・スリム中将は、日本軍を引き寄せて叩くとの方針で、戦略・作戦を立てていたからだ。
昭和19年初頭、日本軍の集結状況をみて、近く攻勢があると確信したスリムは、重大な方針転換を決意した。より敵の策源地に近いチンドウィン川東岸を固守するのではなく、決戦場を後方のインパール平地に選定し、敢えて日本軍の前進を許すことにしたのである。
この進撃路は、アラカンの巍々たる山々を踏破しなければならない。その山越えによって、日本軍将兵は疲弊し、インパール平地に到達するころには補給線も延びきる。
そこに、孫子の「佚を以て労を待つ」という言葉のままに、間近となった策源地から充分な補給と補充を受けた英印軍が攻撃にかかる。しかも、インパール平地に入れば、道路事情も良好になるから、英印軍の機甲戦力の優位を活用することも期待できた。
このスリムの策を打ち破るには、「ウ号作戦」の初期段階、つまり英印軍がインパール平地に退却する前に、これを捕捉・撃滅しなければならなかったのだが、おおむね徒歩で移動するほかない日本軍には、とても無理なことであった。英印軍が航空優勢を生かして、退却途上の拠点に適宜、増援と補給を行なったとあっては、なおさらである。
かくて、牟田口の第15軍は、英印軍主力を撃破できぬまま、延びきった態勢でインパールに取りつき、さりとて、その攻略もならぬままに潰滅していった。いわば、牟田口は、スリムの掌の上で踊らされたのだ。
インパール作戦は、牟田口をはじめとする日本軍高級指揮官たちの愚かさによる第15軍の自滅のように描かれることが多いし、そうした解釈も間違いではない。
けれども、作戦に競り負けたという側面も無視できないであろう。戦略的な問題を作戦次元で解決しようと無理を重ね、作戦次元でも破局をもたらす。インパール作戦において、日本陸軍は、その最低の部分を暴露したのである。
* * *
日本陸軍は、南方攻略作戦において、戦理にもとづいて、水ぎわだった戦いぶりをみせた。いわば、普遍的な用兵思想によって、成功を収めたのだ。
一方、インパール攻勢では、戦理にそむいた作戦を敢えて強行し、惨敗した。さらに、その過程で、作戦偏重ゆえの補給・情報の軽視、無責任の体系といったことまでも露呈したのである。
したがって、かかる明暗のうち、後者のほうが、昭和陸軍の病弊をあきらかにするには適切であり、より詳細な分析に価すると思われる。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月24日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

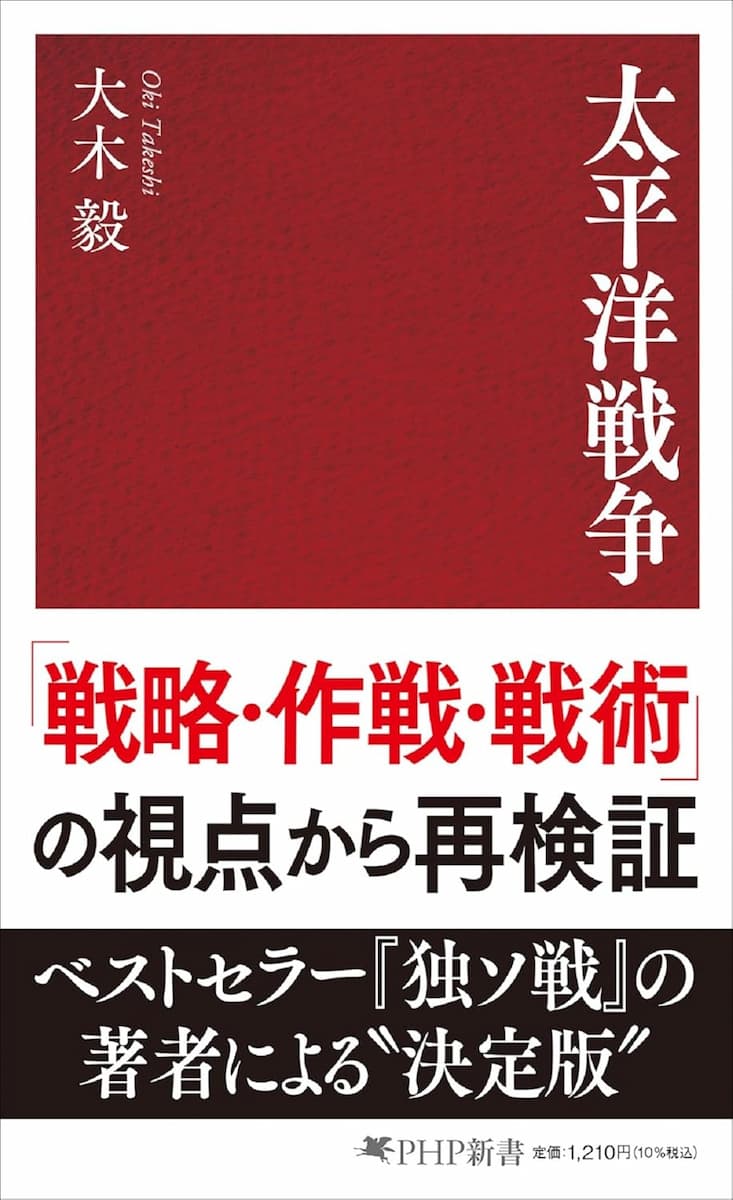






.jpg)


