直江兼続と傾奇者が日本最大級の山城で...向羽黒山城ものがたり3
 写真:向羽黒山城
写真:向羽黒山城
東北屈指の名城で、蘆名盛氏、伊達政宗、蒲生氏郷、上杉景勝といった名将らがかかわった向羽黒山城は、知られざるドラマに満ちた城でもあります。
この向羽黒山城を軸に、作家・天津佳之氏が手がける特別読み切り連作小説「向羽黒山城ものがたり」。第3回は、徳川家康による会津征伐前夜の向羽黒山城が舞台となります。
会津の大名・上杉景勝を支える直江兼続のもとに、傾奇者として名を轟かせる前田慶次郎がやってきて、向羽黒山城でひと戦(いくさ)することに......。
会津征伐――直江兼続と前田慶次郎
『六韜(りくとう)』に曰く、「凡(およ)そ兵の道は一に過ぎたる莫(な)し。一は道に階(よ)り、神に幾(ちか)し」という。一意専心して他に惑わず、以(もっ)て自在であればこそ、変化不測の神妙に近づける、との謂(い)いである。
まさに、上杉家中のためにあるような言葉だと、直江山城守兼続は思う。家中をそう変えたのは、いまは亡き先代の謙信公であり、それが故に、上杉の武名は天下に轟くほどに高まったと言えた。
主のことながら、当代の景勝はその影法師に徹していると、兼続は思う。最早この世にはいないはずの謙信の影を求める者たちの、理想の器。そうなることを、景勝自身が望んでいたのはまちがいない。だからこそ景勝は、内府・徳川家康のやり方に否を唱えた。
「人道、災無ければ、先(ま)ず謀(はか)るべからず」。これもまた、『六韜』の教えである。豊臣の政が人民に災いとなっているわけではないにもかかわらず、兵を謀るのは天道にもとる。このうえ、まるで天下人のように上杉を下に扱うというならば、是非もなかった。
最早、戦は避け得ない。避ける向きの者は、家中から召し放っている。その者たちの言い分も含んだうえで、景勝は立っている。
『良い城だな、与六(よろく)』
過日、目の前の巨大な山城を睨み据えながら、景勝は言った。いま、同じところに立つ兼続もまた、わずかに新緑を纏(まと)った威容を見上げた。
高さは100間(約180メートル)を優に超え、3つの連山を丸ごと縄張りとした巨城である。下から望めば、三層の曲輪に、厳重な防柵と並べ立てられた旗の類が末広がりに連なるさまは、小札(こざね)に綾糸で縅(おど)した錣(しころ)のようである。そうして見れば、山頂に向かう城道は筋金のように、櫓(やぐら)や実城(みじょう)は立物(たてもの)にも似ており、全体を眺めれば筋兜(すじかぶと)のように見えないこともない。
向羽黒山城。会津に覇を唱えた大名・蘆名盛氏が築城したという堅城である。以来30年余り、蘆名、伊達、蒲生と、この会津を治めた者たちは、すべからくこの城を"詰め城"として頼みにしてきた。その意味では、大将首を守る兜という兼続の連想は、あながち遠くもなかった。
とはいえ、その首をただ黙って獲らせるわけにはいかなかった。この城が堅牢であるからこそ、いま必要なのは自ら討って出るための矛(ほこ)であった。
『あの者は来るのか』
景勝の思いもまた、同じである。この主従の考えることに、寸分のちがいもない。いま、上杉の矛としてふたりが求める男。だが、決して誰の思い通りにもならない男であることを、彼らはよく知っていた。その男が、果たして遠く会津まで来てくれるものかどうか。
(来てくれるんだろうね。頼むよ)
祈るように思いながらも、改築が進む城を見上げていた。
「何とも雄大な城ではないか。それに見ろよ、昔ながらの雅な縄張りだな。品がある」
想念に埋没していた兼続は、不意の大声に思わず身をすくめると、声のほうを振り返った。
目に飛び込んできたのは、色も鮮やかな虎皮の陣羽織に、銀糸でかたどった髑髏(どくろ)の紋所。朱革の袴を膝下で絞り、黒革の脛巾(はばき)を括ったさまは、何とも珍妙である。だが、それをこの男が纏うと、何故だかすっきりとして風流な装いに見えるのだから不思議だった。
「よお。山城」
軽く手を上げて呼び掛けてきた男は、相も変わらぬ屈託のない笑顔を兼続に向けた。ちなみに山城とは、兼続の名乗りである山城守のことである。
「遅かったじゃないか。慶次郎」
内心の安堵を面(おもて)に出さず、兼続は憎まれ口で返した。その言葉に慶次郎――前田慶次郎利益(とします)は、すまなげに頭を搔くと、
「何、肉が付きすぎた内府殿よりはましだ」
そう言って、にやりと笑った。
慶長3年(1598)8月、天下人・豊臣秀吉が死去。豊臣家中が後継者の秀頼を守(も)り立てて政権の維持を図るなか、つぎなる天下人として台頭してきたのが、内府・徳川家康であった。
家康は秀吉が定めた法度を公然と破り、各地の大名家と姻戚を結んで誼(よしみ)を通じはじめた。そのうえで、豊臣家中の権勢争いに乗じて政敵の石田三成を中央から排除し、実質的な政権の領袖となったのである。
これに先立つ同年3月、上杉景勝は秀吉の命により、蒲生家のお家騒動である「蒲生騒動」の後を受け、越後から会津へ転封したばかりだった。新たな領国経営に取り組みはじめた矢先の秀吉の死、そして上方での政争を彼方に聞きながらも、景勝と兼続の主従は実直に会津の治政と向き合った。
ふたりからしてみれば、上方の騒動などは政権内の、いわば身内同士の争いである。家康の露骨な動きには眉をひそめたものの、そんなことにいちいち口を出しても仕方がない、というのが上杉家中の在り方だった。
同時に兼続は、秀吉という屋台骨が失われたいま、遺された政治機構だけで天下を支え切れないことも見通していた。秀吉のように、誰にとっても分かりやすく、しかも諸大名の重石となる天下人が居なければ、日の本は再び戦の巷(ちまた)となりかねなかった。その意味で、自ら天下の重石となろうとする家康の意図は理解できたし、再び世が乱れるというならば、その災いの芽を刈り取ろうという気概さえ、景勝と兼続にはあった。
だが家康は、ふたりが思うよりもさらに現実的だった。己の天下を乱し得る者をまとめて排除し、同時に自身が天下人であることを示すための大戦(おおいくさ)を求めたのである。そのための生贄として選ばれたのが、五大老の一角である加賀前田家だった。
慶長4年(1599)、家康は自身の暗殺を企んだとして、浅野長政ら政権の奉行たちを処罰し、それに関与した廉(かど)で前田家の征伐に動いたのである。秀吉の親友として、その覇業を支えた前田利家はすでに亡く、後継者の利長に家康と渡り合うほどの器量はない。生母の芳春院が自ら徳川の人質となって事態を収めなければ、加賀征伐は現実のものとなっていただろう。
そして、前田家に矛先をかわされた家康が標的としたのが、会津上杉家だった。理由は何でも良かったのだろうが、家康が殊更に問題にしたのは城である。当初、景勝は己の居城を、蘆名以来の会津の中心地である若松の鶴ヶ城とした。しかし、若松の町は山が近く手狭だったため、大川(阿賀川)沿いの神指原(こうざしはら)に新たな居城を築城することにしたのだが、これを叛意の証であるとの讒言(ざんげん)があったのである。
家康は、豊臣政権の相談役であった禅僧・西笑承兌(さいしょうじょうたい)を交渉役として、景勝に罪を問うた。慶長5年(1600)4月のことである。無論、これは誘いの手だった。上杉征伐を理由に兵を整え、上方を留守にする。それによって豊臣政権内の反家康派に兵を挙げさせ、合戦によって彼らを一網打尽にする策である。
誰しもが、つぎの天下人は家康だと暗に認めているし、景勝も兼続もそれは同じである。しかも、国替えしたばかりの上杉家中に、諸大名を従えた徳川の大軍に抗し得る兵力を確保できないのも当然だった。
そこまで分かっていて、景勝と兼続は家康の挑戦を受けた。上杉家の面目のためではない、世に義のあることを示すためである。それを明確に示したのが、後世に名高い「直江状」であろう。
景勝に代わって書いたこの書状において、兼続は"景勝に異心がないことは明白であり、讒言した者の言い分を確かめることもせず、我らに逆心があるというのであれば、最早是非もない"と言い切っている。そのうえ、いざ戦となれば勝つのは容易(たやす)いが、故なく戦を起こして悪人と呼ばれるのは末代までの恥となるため、上杉から手を出すことはない、と家康のやり方を痛快なまでに皮肉ってさえいた。
この兼続の反駁(はんばく)は、すぐさま上方に広まり評判となった。その心映え見事なるを褒めそやす者もいれば、無謀で無礼な物言いだと憤る者もいた。そして、戦の匂いを嗅ぎつけて、最後の徒花(あだばな)を咲かせようという者も。血気を余らせた牢人たちが各地から集まり、会津は早くも戦の前の剣呑(けんのん)さに包まれていた。
「にしても、でかい城だな。どのくらいあるんだ」
ただ、同じように戦を求めていながら、その手の物騒さとは無縁なのが慶次郎だった。いまも兼続の横で向羽黒山城を見上げ、子どものように目を輝かせている。
とうに還暦もすぎたというのに、顔の造作からして落ち着きとは無縁の男だった。歳の割に皺(しわ)の少ない面、好奇心丸出しの大きな目。太い眉に獅子鼻、よく動く口もとはいつも何かを楽しんでいるようである。中肉中背ながら、よく見れば胸板厚く腕も太く、特に首から肩、背中に掛けての肉が山のように盛り上がっている。それが珍奇な装いに身を包むと、じつによい男ぶりに見えるのである。
「それに高い。山々に頼らず己ひとつで立っておる」
城とはこうでなくては、などと高らかに笑う姿はどこか剽(ひょう)げてさえ見え、とても名にし負う"いくさ人"とも思えない。
前田慶次郎利益。亡き前田利家の義理の甥である。義理の、というのは、利家の兄・利久が滝川益氏(ますうじ)の妾にひと目惚れし、すでに身ごもっていた慶次郎ごと前田家に迎え入れたからだった。それゆえ慶次郎は、当時織田信長の麾下にあった前田と滝川双方の軍陣に入り浸り、戦のやり方を存分に学んだらしい。本能寺の変以前から、その武勇は有名であった。
やがて天正18年(1590)ごろになると、慶次郎は利家と反りが合わずに前田家を出奔。牢人ながらも京に屋敷を持ち、里村紹巴(じょうは)や古田織部など、上方の雅人(がじん)や大名たちと連歌に興じて親しく交わるなど、優雅に暮らしたという。
何より慶次郎の名を天下に轟かせたのは、その傾奇ぶりである。亡き天下人・豊臣秀吉の前で猿舞を披露して見せたというのだから、その生きざまは徹底していた。秀吉が猿に似ていたのは周知のことだが、それを露骨に揶揄した慶次郎も流石(さすが)、許した秀吉も大したものだと、上方では一時その話題で持ちきりになったほどである。
兼続と慶次郎が知己になったのも、上方でのことである。連歌の交流のなかで上杉の京屋敷に出入りするようになり、そこで兼続にぞっこん惚れ込んだ、とは慶次郎本人の弁だが、ふたりの交流はすでに18年に及び、莫逆(ばくぎゃく)の友と言っていいほどとなっていた。
だからこそ、兼続は慶次郎に知らせることなく会津に向かったし、慶次郎は会津まで下ってきた。
「おい。聞いているのか、山城」
「山は13町四方、高さは105間ほどだ。山を3つも覆いながら、城下以外に隙がない堅城よ。さすがは蘆名の大殿が築いた城よな」
「なるほど。こいつはいい死に場所じゃあないか。なあ、お主ら」
すらすらと答える兼続に笑い掛けると、慶次郎は伴ってきた一行を振り返った。慶次郎とともに前田家を出た野崎知通(のざきともみち)こそ士分の格好だが、残りの3人は、朱革の羽織に派手な染めの小袖を着た異様な風体である。何でも朝鮮の陣のとき、海を渡った慶次郎と馬が合ったとかで、そのまま近習として日の本に渡ってきた男たちだという。
そして、彼らが牽(ひ)く巨馬。黒鹿毛よりもさらに濃い、ほとんど漆黒に近い毛並みの馬こそ、慶次郎の愛馬・松風(まつかぜ)である。この松風もまた、もともと野生馬でありながら慶次郎にほだされた悍馬(かんば)で、余人には決して懐かない。
(まったく、この男はどこへ行っても人たらしだな)
事ほど左様に、慶次郎は誰にでも何にでも好かれたし、彼自身が何に対しても分け隔てがなかった。兼続もまた例外ではなく、20ほども歳が離れているにもかかわらず、完全に同等の友である。下手に敬語で話そうものなら、心から怪訝な顔をして、風邪でも引いたか、などと聞かれるのが落ちだった。
「措(お)け。ここで死ぬときは、殿も同じなのだぞ」
「詰め城というわけか。いいな、戦のし甲斐がある」
心底から戦が待ち遠しいと言わんばかりの慶次郎の笑みに、兼続は肩をすくめるしかない。それが頼もしさと嬉しさの裏返しであることを、兼続も自覚していた。
「慶次郎、お主の出番はもっと前だ」
「もちろんよ。どうせ内府殿は余計なものを引き摺って、陸奥に参るのにも時が掛かるだろうからな。こちらから打って出る隙はいくらでもある」
「その隙のあいだに、できるだけの備えをせねばならぬ。お主にも手伝ってもらうぞ」
「ああ。その分、酒を弾めよ」
言って呵々(かか)と笑う慶次郎に、兼続は呆れるしかなかった。
慶次郎の言う通り、家康は会津征伐に向けて念入りな根回しを進めた。無論、会津のつぎに待つ、天下人を決める戦に向けた準備である。そのうえで、家康が会津征伐の陣触れを関東以北の諸大名に下したのは、6月に入ってからのことだった。直江状が上方に届いたのが5月初旬だったことを思えば、およそひと月もの時間を掛けたことになる。実際に家康が大坂を出陣したのは、6月16日だった。
一方の景勝は、与えられた時を存分に活かした。神指の新城普請を一旦止めると、その資材を使って領内の要害を改築し、より強固な防衛網を敷いた。なかでも向羽黒山城は最後に依る詰め城として、兼続が自ら普請を指揮して増強を施している。
元来の向羽黒山城は、永禄11年(1568)に築かれた古い山城である。しかし、32年のあいだに、歴代の領主たちによってたびたび手を入れられ、石積石垣や各所の虎口(こぐち)など、時代ごとの最新の技術が取り入れられていた。
そのなかで、兼続が重視したのは竪堀(たてぼり)だった。広大な縄張りを持つ向羽黒山城だからこそ、攻め手の展開を制限する大小無数の竪堀こそが防御の要である。兼続はこれらの竪堀群に、上杉家が得意とする畝状(うねじょう)竪堀の工夫を加えた。
防備を固めると同時に、景勝は徳川軍に確実に勝つ算段をめぐらせた。家康の興味は明らかに天下分け目の大戦にあり、会津征伐はその呼び水に過ぎない。それが、景勝を激怒させていた。
「我ら上杉を当て馬にしようというのか」
謙信公以来の武名を馳せ、誇り高い上杉の当主として、それが我慢ならなかった。要するに、家康は上杉を舐めたのである。そんな恥辱を許す上杉ではないと、家康に知らしめねばならない。それが景勝と兼続の思いだった。
「喧嘩は意地を通してこそよ。さすがは景勝公だ」
手を叩いて褒めそやす慶次郎を、景勝は新たに会津に集った牢人衆をまとめた「組外衆(くみそとしゅう)」の筆頭として召し抱えた。この組外衆、豊臣政権が築いた泰平に飽き飽きとした各地の牢人が押し掛け助っ人として集まったものであり、上杉の名のもとで己の武勇を存分に振るいたいという剛の者ばかりだった。それだけに統制が難しい連中だったが、
「お主が最も曲者(くせもの)だからな。何とかしろ」
兼続は事も無げに言い、慶次郎に差配を丸投げした。それよりも、いまは徳川軍を邀撃(ようげき)するための備えが先決だった。
『六韜』の豹(ひょう)の巻に曰く、「敵衆(おお)くして強きを震寇(しんこう)と謂う。以て出でて戦うに利あり、以て守るべからず」という。相手が強固かつ大軍であればこそ、内に籠もっていては勝ち目などないことは自明だった。守る戦でなく、家康を討つ戦でなければならない。そのための決戦の地を、景勝は白河の革籠原(かわごはら)と定め、入念に備えた。
「景勝以下、上杉家中は尽(ことごと)くここを枕に討死するばかりである」
景勝はそう宣言したが、兼続としては次善の策も用意するのは当然だった。それが会津であり、向羽黒山城であった。すでに、おおよその改修は済ませたが、もとが古い山城である。広大な縄張りも併せて、実際の防備が如何ほどのものか、兼続にも未知数である。
「殿。組外衆にございますが」
鶴ヶ城の自室で思案していた兼続だったが、不意の声に思わず眉をしかめた。戸を開けて入ってきたのは、上泉主水泰綱(かみいずみもんどやすつな)。新陰流兵法を創始した"剣聖"上泉伊勢守信綱の孫であり、いまは兼続子飼いの「与板衆(よいたしゅう)」のひとりとして、組外衆の取次を命じた男である。祖父から受け継いだ剣術の達者で、その武名が牢人たちの抑えになろうかと期待した兼続だったが、生真面目な性格が災いし、牢人たちに面倒事を押し付けられること頻(しき)りだった。
「殿に注進したきことがあると、押し掛けて参ってございます」
すでに泰綱は言い慣れてしまった調子で告げ、
「また前田殿か」
兼続も皆まで聞かずに腰を上げている。
組外衆をまかされた慶次郎だったが、相変わらずの気ままさで牢人たちをあしらい、その不平不満が泰綱と兼続のもとに持ち込まれることになった。
今回も、じつに下らないことではあった。牢人たちが槍玉に挙げたのは慶次郎の武具、皆朱(かいしゅ)の槍と総朱塗の鎧である。皆朱の槍とは、柄を朱一色に塗り上げた大槍で、家中第一の武辺を示すものである。慶次郎は前田家にいたときに皆朱の槍を許されて以来、つねにこれを戦場に伴ってきたが、
「いま、上杉家中に加わったばかりの前田殿に、いったい何の功があって皆朱の槍を許されるのか」
牢人たちから、そんな抗議が上がったのである。総朱塗の鎧もまた、よほどの功名を上げた者でなければ許されぬ装い。自尊心の塊のような牢人たちからすれば、還暦過ぎの爺が年甲斐もなく、という思いもあったろう。
「このうえは、前田殿との決闘で白黒つけるのだと、殿に許しをいただきたいと申す者もおる始末で」
「まったく......あの男は、どこにでも騒ぎを持ち込むのだな」
実際のところ、慶次郎は老いてなお剛健そのものではある。数年前には、慶長の朝鮮への出兵に参戦して武功を上げ、嘘か真か、かの国では猛虎を狩ってその皮で例の陣羽織を仕立てたという。とはいえ、それを牢人たちに納得させねば、組外衆はただの烏合の衆となり、上杉の足手まといにならざるを得ない。
この問題は、上杉家中を取り締まる者として、また慶次郎の友として、兼続自身が解決しなければならないことだった。
「前田殿は何と言っているのだ」
「異を唱えた者すべてに、皆朱の槍を渡せと」
返ってきた答えに、兼続は思わず肚のなかで唸った。
全員に皆朱の槍を渡すとなれば勢い、つぎの戦で誰が本当の武功第一かを争うことになる。戦場での不要な手柄争いなど、迂闊な死に直結する。そのうえ、己の武功を証明しようと思えば、その働きを互いに間近で見せつける他ない。特に、慶次郎とは離れられない。つまるところ、慶次郎はこの策で、己とともに動く屈強の配下を得ることになる。
見事な策だが、それでは牢人たちの憤懣は溜まる一方である。何か手を打たなければ牢人たちが暴発する可能性もあった。
「前田殿、牢人たち、上杉家中、三方が丸く収まる手はないか」
兼続が口に出すと、泰綱は露骨に顔をしかめた。
「殿と前田殿のご友誼は存じておりますが、前田殿に筆頭を下りていただく他ございませぬ。あたら喧嘩を売ってまわるような傾奇者では、此度(こたび)の戦でお役に立つとは思えませぬ」
実直そのものの泰綱が、そんな風に感情を表に出すことは珍しく、兼続は意外の思いで彼の顔を見返した。
「そなたも、前田殿に不満があるようだな」
兼続の問いに、泰綱は答えずにかぶりを振るばかりだった。
剣術の家に生まれ、ひたすらその道を研鑽してきた泰綱にとって、慶次郎の振る舞いはよほど増上慢に見えることだろう。確かにそういう面があるのは事実である。だが、景勝と兼続が上杉の矛として慶次郎を求めたのには、それを越えた理由があった。だからこそ牢人たち、そして泰綱の納得は必要である。
兼続はしばらく思案すると、ふと気がついたように手を打った。
「あの城を試しとしよう」
そう言うと兼続は、早速にも泰綱に組外衆を集めさせると、
「皆朱の槍は意見を述べた者、皆に渡すこととする。これは前田殿の計らいである」
出し抜けにそう宣言した。拍子抜けした顔、驚きの顔、憤懣をたぎらせたままの顔、慶次郎を睨みつける顔、それぞれの思いを見定めながら、兼続は言葉を継いだ。
「しかし、皆朱の槍は本来、家中にひと振り。故に方々には、"我こそが家中一の槍である"と証を立てていただかねばならぬ」
これには、慶次郎が意外そうに兼続を見遣(みや)った。手柄争いという、あたら死につながることを兼続が勧めるとは思わなかったのであろう。いつも振り回される側の兼続には、その顔を引き出せただけでも溜飲が下がる思いだった。
「とは申せ、戦にその争いを持ち込むのでは本末転倒である。そこで、だ」
兼続は芝居掛かった調子で、一同をぐるりと見渡した。
「組外衆に、向羽黒山城を攻めてもらう」
「何ですと!」
誰よりもまず驚きの声を上げたのは、泰綱であった。
「無論、試しよ。城兵には我が麾下の一軍を入れ、手前が指揮を執る。そこで各々方の腕を見せてもらいたい」
これが、兼続が考えた策だった。実戦での手柄争いができぬなら、模擬戦でそれに代える。牢人のうち、一軍を率いた経験を持つ者は少なく、必然、古強者(ふるつわもの)の慶次郎が主導することになろう。そのうえで、彼が指揮と武勇の双方を証明してくれれば、泰綱も含めて組外衆は自然とまとまるはずである。
加えて、兼続にとっては向羽黒山城の改修が確実に機能するか、そもそも城の防備に穴はないかを確かめることにもなる。そのうえ、麾下の兵たちの訓練もできるという、一石二鳥の策である。
騒然とする組外衆のなかにあって、慶次郎は目を瞬かせて兼続を見つめた。しかし、その狙いに気づいたのであろう、
「はっはっはっ! 山城殿も悪戯(いたずら)がお好きと見える。付き合(お)うてやろうではないか、我らで難攻不落の向羽黒山城、落としてみせようぞ!」
仰(の)け反(ぞ)るように大笑すると、拳を振り上げて威勢を上げた。つられるように声を上げる牢人たちを前に、兼続の意識は早くも城へと翔んでいた。
兼続は己の案を景勝に奏して許しを得ると、早速にも与板衆の兵1000を向羽黒山城に入れた。一方の組外衆の兵も、およそ1000。通常、城攻めには守勢の3倍の兵力が必要と言われるが、数は互角である。
「考えたもんだな。俺の策に乗っかって、城の試しまでやるとは」
麓から山体を覆う縄張りを見上げる兼続に、慶次郎の声が掛かる。その声音にある楽しむ色を聞き分け、兼続はわずかに口角を上げると、
「お主の悪戯に応えたまでだ。それに、あのままでは槍に文句をつけた者たちが、あたら死ぬことになったかもしれぬ」
そう返した。兼続が纏う戦装束は、金小札(きんこざね)に浅葱糸縅(あさぎいとおどし)の具足に白の陣羽織。脇に控える泰綱が抱えた兜には、白銀作りの「愛」の字に瑞雲の前立て、かつて上杉謙信から与えられた代物である。手にした軍配を弄(もてあそ)びながら笑う兼続に、慶次郎もにやりと笑った。
「下らん言い掛かりをつけた罰さ。まあ、あいつらは命拾いしたな」
慶次郎の言い方は恬淡(てんたん)としてこだわるところがなく、自分の策で己や味方が死地に踏み込むことを気にした風もない。生き死にに特段の価値を置かないのは武人の習いだが、ここまで徹底している男を、兼続は慶次郎の他に知らなかった。
この日の慶次郎の出で立ちは、例の総朱塗の具足。草摺の下に黒革の袴を履き、足元は黒の足甲を付け、全身が朱と黒の装いである。肩口には山吹色に黒を差した魚鱗の袖を配し、それが虎皮の陣羽織とよく合っていて、こんなところにも慶次郎一流の美学を感じる兼続である。
伴の野崎知通が抱えた黒塗りの兜は、南蛮笠を模しているらしく、尖った鉢につばまでついた珍妙な形。これに皆朱の槍を携えた鎧姿が、敵の目を引くのは当然だった。それでも、己の美学に徹して命を埒外(らちがい)に置きながら、50年来戦場で生き残ってきたのが、慶次郎という男の在り方である。
「失礼ながら」
ふと、硬い声がふたりのあいだに挟まった。声の主はと兼続が見れば、脇に控えた泰綱である。
「その出で立ちで、前田殿は如何に戦われるのか」
「無論、一騎駆けよ」
「筆頭がそのように迂闊に振る舞われて、戦が成り立つとお思いか」
泰綱の声は、ほとんど問い詰める調子である。
「上泉殿、思いちがいをされておるようだが、わしは頭になったつもりなどない」
「慶次郎、その辺にしておけ」
泰綱の気配に危ういものを感じ、思わず兼続は慶次郎を制止した。が、むしろ止まらなかったのは泰綱だった。
「己の責を放り投げて勝手気ままに振る舞うなど、上杉の軍法では許されませぬぞっ」
「わしは天の法に従っておるまでよ。人が思うままに生きてこそ、現(うつ)し世が華やぐというものよ」
ああ言えばこう言う、慶次郎の悪い癖に兼続は思わず額を押さえた。その刹那、泰綱が不意に兜を慶次郎に投げ寄越した。思わず受け取ろうと手を伸ばした隙に、泰綱の凄まじい抜き打ちが襲い掛かった。
「主水っ!」
声が響くより早く、泰綱の刀は止まっていた。
「見事な業前(わざまえ)ですな。それも新陰流の手にござるか」
慶次郎はのんびりと口を開きながら、左手で兜を受け取り、右手で半ばまで腰の刀を抜いて泰綱の胴打ちを阻んでいた。それを兼続が確かめる間もなく、泰綱の刀は鞘にもどっている。
「だが、主のものを粗末に扱うのは感心しないな。気をつけられよ」
もっとも、そんな凄まじい剣撃を向けられた慶次郎のほうは、あっさりとしたものだった。涼しい顔で兜を泰綱に渡すと、野崎が牽いてきた愛馬・松風の背に跨(またが)り、
「やはり戦はいい。上泉殿のような男と戦えるのだからな」
そう嘯(うそぶ)くと、組外衆の陣へと去っていく。
「仕方のない奴だ」
見送る兼続が言ったのは、慶次郎と泰綱、双方に対してである。
「申し訳ございませぬ。しかし、前田殿は悪戯が過ぎまする。あれでは、組外衆はまとまりませぬ」
「そなたは、そうであろうな」
兼続は、わずかに笑みを含んで返した。泰綱の憤懣は、上杉の行く末を案じてのことだからだ。いざ徳川が動き出せば、兵力は7、8万を超える。一方、上杉はどれだけ振り絞っても兵3万がせいぜいであろう。そのうえに、烏合の衆を抱えたまま負けるようでは、景勝と兼続の恥となる。そんな泰綱の考えが、兼続には手に取るように分かった。
そして何より、泰綱は上泉の嫡流として、武の道に対してもあまりにも誠実だった。武辺を弄ぶような慶次郎の振る舞いが、心に引っかかるだろうことは想像に難くない。
(まあ、槍を交えれば分かることもあろう)
兼続はそう判断して城に入ると、早速にも兵に指図して防備を固めた。三の曲輪の兵400の指揮は上泉主水泰綱、守りの中枢たる二の曲輪には兵500を腹心の溝口左馬助勝路(さまのすけかつはる)にまかせ、兼続自身は城の最高地点である実城で模擬戦のようすを見聞する構えである。
城の防御を確かめる意味もあり、正面からの力攻めをするよう組外衆には指示している。武器は先を丸めた木槍と木矢を使い、討たれたか否かは各自の判断にまかせるが、甲冑に覆われていない生身を打たれたら死と判定するよう申し合わせた。模擬戦で門を傷つけては本末転倒と、各門扉は閂を掛けずに閉じたのみで、周囲の城兵が手薄となれば開けても良いこととしたが、この取り決めはほとんど意味を成さないであろうと、兼続は考えている。
城攻めでは防御側が圧倒的に有利であり、攻め手の組外衆が早々に全滅することは目に見えていた。故に、ある程度勝負の趨勢が見えた際には一旦仕切り直しとし、防衛線を後方に下げてから再開することとした。この手順で、三の曲輪から実城までの主立った防御機構を確かめるのである。
実城の前に置いた床几に腰を据え、兼続は城の構えを眺めやる。その麓で気勢を上げる組外衆がかすかに見え、
「さて、お手並み拝見と行こうか」
そうつぶやいて近習に太鼓を叩かせる。模擬戦のはじまりを告げる太い音が、6月の蒼天に高く響き渡った。
組外衆は城の北、若松方面とつながる北大手口から攻め掛かった。北曲輪へと雪崩を打って攻めかかる牢人たちだったが、早速の竪堀に隊列を引き延ばされたうえに、その姿は周囲に配された平場から丸見えである。
「放て!」
泰綱の号令一下、城兵たちの弓が一斉に鳴った。放たれた木矢は土塁と防柵を越え、組外衆の頭上に降り注ぐ。彼らの行く手には、かつては蘆名盛氏が暮らしたという城主屋敷があるが、その周囲には横堀が深く掘られ、組外衆の行く手を阻んだ。そのうえ、薄くなった隊伍の脇を衝くように馬出しから城兵が襲い掛かったのだから、武辺自慢の牢人たちと言えど耐えるのが精いっぱいだった。
そうして見れば、縦横にめぐらされた空堀も、それらによって複雑に屈曲した城道も、計算の上で取りまわされているのは一目瞭然である。攻め手はただ進軍するだけで丸裸にされ、城兵に隙を曝(さら)すことにならざるを得ない。そうなるように入念に平場が配置されているのは自明で、牢人たちには矢をしのぐ死角さえなく、多くの者が木矢を受けて倒れていった。
ただでさえ急な斜面には高く土塁が盛られ、這(は)ってでも乗り越えるのは難しかった。仮に這い登れたとしても、防柵から突き出される槍衾(やりぶすま)に貫かれるばかりであろう。
先鋒は、とみれば、三の曲輪と接続する虎口に攻め掛かっている。が、虎口はそれこそ防御の要であり、もちろん容易に抜けるはずもない。むしろ誘い込まれた体で、組外衆はその数を減らすばかりだった。
もし、これが本当の籠城であったなら、三の曲輪に敵軍を釘付けにしたうえで、西側の搦手口(からめてぐち)から別働隊を繰り出し、後背を衝くことも容易である。さらに言えば、隣の羽黒山に配した曲輪から横矢を掛けることもでき、時に応じて守りを自在にする縄張りの巧みさは、とても30余年前に築かれたと思えないほどだった。
「......城づくりの名手だな、蘆名盛氏という方は」
まだ三の曲輪の一部を試したに過ぎないというのに、兼続はほとほと感心してつぶやく。
土塁に防柵、空堀、平場、虎口。この城は、どこを取っても攻め手にとっての死地だった。しかも、深く攻め入れば攻め入るほどに攻め手に危難をもたらす。それは、いかな大軍で押し寄せようと変わらない。むしろ、大軍であるほど攻めにくさが増す仕組みだった。
しかも、城兵がより多ければ、手は自在に変化していく。さすがの兼続も、自分ならどう攻めるか考えあぐねた。攻めたくない、とさえ思えた。
――手柄争いどころの騒ぎではないな。
慶次郎をはじめ、皆朱の槍衆がどこで戦っているか分からないが、これでは互いの腕を試す暇さえないであろう。実際、三の曲輪の虎口での戦いも小康状態になりつつあり、一旦仕切り直すべく兼続は腰を上げ、合図を送ろうとした。
が、そのとき。彼方からの大きな喊声が、兼続の耳を震わせた。
何事かと視線をめぐらし、兼続は我が目を疑った。三の曲輪に入る虎口が、いつの間にか突破されているのである。それどころか、勢いを取り戻した組外衆の一団は三の曲輪を破り、二の曲輪に襲い掛かっていた。油断していたか、それとも牢人たちの迅速な進軍に追いつけなかったものか。組外衆は手薄になっていた囲みを食いちぎり、二の曲輪の門に殺到した。
「何が起こった!」
思わず喚(わめ)いた兼続だったが、物見櫓からは不明瞭な答えしか返ってこない。慌てて使番を遣(や)ろうとしたときには、すでに組外衆が二の曲輪に雪崩を打って攻め寄せる有り様だった。
「備えよっ、すぐにこちらに来るぞ!」
二の曲輪から実城のあいだには、独立した一東曲輪と一北曲輪があるが、2カ所の防備が間に合わないと判断した兼続は、実城直下の平場に兵を集中させた。周囲には縦横に空堀をめぐらせて攻め手の勢いを殺し、さらに天然の大岩を残した岩場と防柵を利用したこの要害ならば、組外衆も容易には突破できないはずである。
早くも牢人たちの喧騒が迫るなかで、兼続は後手に回らざるを得ない己を自覚した。
「直江様っ、これはどういうことか!」
そうこうするうち、実城で防備を固める兼続のもとに駆け込んできたのは、二の曲輪をまかせた溝口左馬助だった。その武骨な顔は、困惑と怒りで歪んでいる。
「溝口、いったい何が」
「前田殿にござる!」
左馬助が叫んだ、ちょうどその時だった。勁烈(けいれつ)な雄叫(おたけ)びとともに実城を守る兵たちを蹴散らして、一騎の赤黒い騎馬が一の曲輪に躍り込んだ。手にした朱色の木槍を旋風のように振り回しながら、当たるを幸いに城兵たちを薙ぎ倒し、一気に兼続へと殺到した。
兼続が身構える間もなかった。気が付けば、木槍の丸い先端を突きつけられている。その後ろを見れば、この一騎が突破した防御のほころびに乗じ、後続の牢人たちが曲輪の内へと攻め込んでいた
「俺の勝ちだな、山城」
木槍の向こうから、巨馬にまたがった慶次郎が見下ろしていた。
「何が勝ちなものかっ。お主ら、生死の申し合わせを破っておったではないか!」
激怒する左馬助の言い分で、兼続にもおおよその事情は呑み込めた。確かに、兼続もおかしいとは思っていたのだ。木矢や木槍で打たれたはずの者たちが、申し合わせを反故(ほご)にして攻め手に加わりつづけたのである。そうでなければ、あれほどに組外衆の攻めが継続するはずがなかった。
「慶次郎、先に言ったはずだな」
「何を言うか、山城。武人が木矢で打たれた程度で死ぬのか。おいっ、どうなんだ、言ってみろ」
慶次郎の言い草はほとんど恫喝(どうかつ)であったし、屁理屈に過ぎなかった。確かに木矢に当たった程度で死ぬ者などいない。それはそうだが、そんなことを言い出せば、模擬戦などできたものではない。
「だいたい、城を守るのに門をまともに閉じぬなど、不行き届きではないか」
「死んだはずの者が蘇るほうが、よほど不法だろうっ」
左馬助の怒りはもっともだったが、このままでは与板衆と組外衆のあいだで戦がはじまり兼ねない。だが、兼続は成り行きにまかせるかのように、ふたりの言い合いを聞くのみだった。
「お待ちあれ、溝口殿」
そこへ、新たな声が届いた。
「おお、上泉殿。お手前からも言うてくだされ。これ以上前田殿に勝手されては、試しにならぬ」
やってきたのは、三の曲輪をまかされていた上泉泰綱だった。具足の胴はひしゃげ、顔から落馬でもしたのか、半面は泥に汚れている。それでも、兵法者らしい鋭い眼光で慶次郎を見上げ、そして兼続を見た。
「前田殿はここまで、確かに討たれてはおりませぬ」
「な、何を申されるか。これほどの乱戦で、いったいどうやって」
「三の曲輪からここまで、すべて見聞いたした。前田殿は真っ先に三の曲輪に攻め掛かり、手前を打ち倒すと組外衆を励まして、一気に攻め上られた。真、見事な一騎駆けにござった」
泰綱の言い振りに、兼続もまた頷いた。兼続は、この無法な友が突撃するさまを、何度も目にしていた。凄まじい速度で疾駆する松風を自在に操り、大柄の槍を軽々と振り回しながら一散に敵陣へと飛び込んでいくさまは、男であれば誰もが血を湧き立たせずにはおられないほど見事だった。
そして、その速さゆえに敵の弓は狙いを外し、松風の巨体と大槍が真っ先に敵を打ち倒す。そんなだから、この模擬戦において慶次郎が手傷を負わなかったのも事実であろう。あれほど慶次郎を嫌っていた泰綱が、素直にそれを認めたくなるほどに、慶次郎の一騎駆けには何とも言えない華があった。
見れば、皆朱の槍をめぐって険悪だった牢人たちも慶次郎の後ろに集まり、互いの健闘を称え合い、慶次郎と松風を頼もしげに見上げている。その姿に、兼続は己の策が成ったことを確信した。あとは、仕上げをするだけだった。
「おい、慶次郎。お前が派手に暴れ回っては、城の試しにならぬ」
兼続が呆れて言うと、慶次郎はわらべのように口をとがらせて、
「何を言う。戦場にどんな武辺の者がおるか分からんだろう」
またも屁理屈をこねた。だが、それも兼続は馴れっこである。
「徳川方に、お主ほどの強者がおるか。おらぬだろう」
「それもそうか。では、我らの負けだな」
事も無げに言う兼続に、慶次郎もあっさりとそう返して、がはがはと大きく笑った。その屈託のなさに左馬助も毒気を抜かれたのだろう、肩を落としつつも表情を緩めている。
「それにしても、良い城だ」
出し抜けに、慶次郎が言った。
「門が閉ざされていれば、攻めようもなかったな。そのうえ、これほど固いというのに、城下には人の暮らしもある。蘆名盛氏という御仁、よほどひねくれておったのだろう」
それは兼続にとっても実感だった。
(いや、もしかすれば)
先ほど、この城の堅牢さに攻める気を失った自身を、兼続は思い出す。そう敵に思わせることが、向羽黒山城の最大の防御だったのではないか。「上戦(じょうせん)は与(とも)に戦う無し」。戦わずして勝つことこそ、あらゆる兵法書が目指す最上の勝利であることは、疑いようもない。そして、そんな堅城だからこそ、蘆名盛氏は城に商工の町を置いたのではないか。
『六韜』において、太公望(たいこうぼう)はこうも言っている。「天に常形有り、民に常形有り。天下と其の生を共にすれば、天下静かなり」。天に法則があるのと同じように、民の暮らしにも法則がある。人の暮らしを天道のように敬い、それを間近に置いて国を思うてこそ、泰平に治まる――。いにしえの聖賢も描いた理想を、盛氏はこの城で実現しようとしたのではないか。
「......神指も、このような城にしたいものだな」
かつて会津を治めた男に思いを馳せながら、兼続は、慶次郎以下の組外衆、そして左馬助と泰綱以下の城兵に労(ねぎら)いの声を掛けて、険しい城を下っていった。
その後の7月17日、石田三成をはじめとした豊臣恩顧の大名たちが、家康の留守に乗じて上方で挙兵。下野国小山まで進んでいた家康は、この報を耳にして会津征伐を中止し、反転して三成たちの征伐に向かうことを決断する。これが、天下分け目の大戦「関ヶ原の戦い」の端緒となった。世はまさに、家康の意図のとおりに動いていったのである。
矛先をかわされた形となった景勝と兼続は、かねてから徳川方として振る舞う最上義光、己の旧領を狙う伊達政宗を敵と定め、後顧の憂いを断つべく出羽へと攻め入った。北の関ヶ原と呼ばれる「慶長出羽合戦」の始まりである。
この戦のなかで、慶次郎以下の組外衆はすさまじい戦ぶりを見せた。なかでも、長谷堂城からの撤退戦では、兼続の近習と組外衆合わせて3000の兵で殿軍を担い、2万にもおよぶ最上軍の追撃をしのぎ切って、上杉全軍を無事帰還させたという。
9月15日、関ヶ原で三成らが敗北。西軍方に与(くみ)した諸大名がことごとく処罰を受けるなかで、上杉はしぶとく抵抗をつづけていた。が、それもいよいよ限界となった10月末、ようやく景勝と兼続は徳川との講和を決断し、本庄繁長(ほんじょうしげなが)と千坂景親(ちさかかげちか)を使者として上方に送った。半年以上の交渉を重ねた、慶長6年(1601)7月、景勝と兼続は上洛し、家康に謝罪することとなった。
上方での宿所は伏見の上杉屋敷だったが、ふたりは入洛するとすぐに伏見城に登った。和平の仲介を買って出た結城秀康や西笑承兌らと面談し、その厚情に謝すためである。
「失礼ながら、そちらは直江山城守殿にございますか」
秀康らに挨拶を終え、城を出ようとした兼続に、そんな風に声を掛ける者があった。見れば、仕立ての良い素絹(そけん)に五条袈裟(ごじょうげさ)を掛けた老僧が、柔和な笑みを浮かべて佇んでいる。
「左様ですが、御坊(ごぼう)は」
「武蔵国喜多院(きたいん)の住持、天海と申します」
その名は、兼続も耳に挟んだことがあった。関東の天台宗門をまとめる名僧であり、小田原征伐後、関東に地盤を築く家康に助言してその帰依を得たという。
「御坊が。お噂はかねがね、聞き及んでおります」
天海は若くして天台、法相(ほっそう)、禅など諸宗を修め、関東はおろか畿内の名刹を訪ねて修行に明け暮れ、その伝手(つて)でさまざまな宗門に顔が利くと聞く。あるいは、いよいよ天下人となった家康のため、上方の宗門との折衝を担っているのではないか。そう想像した兼続だったが、そんな天海が己に声を掛けてきた理由が不明だった。
その不審が顔に出ていたのだろう、天海は眼尻を下げると、
「じつは、拙僧は会津の生まれなのでございます。かれこれ故郷を離れて10年、縁なく帰郷することも叶わぬ身の故、かの地のお話が伺えればと」
そう言って、丁寧に頭を下げた。
「左様にございますか。会津のどちらで」
「大沼にございます」
「大沼と申せば、向羽黒山に大きなる城がございますな」
兼続が言った、瞬間だった。天海はわずかに驚いたように目を見開くと、満面に笑みを浮かべた。そこに見えるのは懐旧の情と、わずかなはにかみだった。
「嗚呼......あの城は、まだ残っておりましたか」
まるで、長年音沙汰がなかった友の無事を聞いたかのように、天海は嘆息して言った。
「はい。城下の町もよく栄えておりますれば、新たな城の手本にしようと考えたほどにございます」
「町も、民も、息災なのですね。それは、それは何より」
最早、天海の声は潤み、震えてさえいた。老僧がそれほどの想いを懸ける理由が分からず、兼続は困惑するほかない。
「天海殿は、よほどあの城に縁がござるのですな」
「もちろん。じつは、向羽黒山の城を蘆名の大殿がお建てになる際、少しくご意見を申し上げたのです。大殿はそれを大変喜ばれ、まだ若輩の拙僧に何くれとなくお気遣いを賜りました」
蘆名の大殿、盛氏のことを話す天海の声音は敬慕に満ちて、聞く兼続も思わず胸を締め付けられた。だが、それにも増して尋ねたいことがあった。
「御坊は、向羽黒山の城に如何なる策を与えましたか」
過日、あの城に見た願いが正しかったかどうか。兼続はそれが知りたかった。問いに、天海は一瞬で笑みを収めた。深い色を宿した目を兼続に注ぎ、
「一円、と」
そう答えた。
仏道にいう"一"とは、すべてであり、自在である。兼続は、それに似た言葉を知っていた。
「一は道に階り、神に幾し......ですな」
謙信から受け取り、なお兼続の心に一本の軸としてある言葉である。『六韜』が語る兵法は、単なる戦術ではない。道に通じ、国に、そして天に通じる法である。その極意こそが"一"であり、神妙自在を以て乱を鎮め、天下を泰平に導くのだと。
兼続の返答に、天海は今度こそ相好(そうごう)を崩して、深く頷いた。そして、兼続と天海は手近な部屋に腰を落ち着けると、会津の思い出話に花を咲かせたのだった。
翌8月、景勝と兼続のふたりは、大坂城にて家康と対面し、正式に謝罪した。家康はそれを受け容れたうえ、上杉家を取り潰しにせず、会津120万石から米沢30万石への減封との沙汰を下した。そこに天海からの執り成しがあったかどうかは、定かではない。
向羽黒山城は、上杉の米沢転封に伴って廃城とされた。築城から33年、一度として本当の戦場になることはなかった。防柵や屋形などの建物は破却され、その後に再興されることもなく、やがて縄張りも時の流れに飲まれ、自然に覆われるばかりとなった。
ただ、蘆名盛氏が興した城下町は、蒲生氏郷が育てた人々の暮らしは、変わらずそこに残った。その人々によって城が再発見されるのは、ゆうに400年後のことである。
【「向羽黒山城特設サイト」はこちら!】
https://www.mukaihaguro-yabou.jp/
【天津佳之(あまつ・よしゆき)】
昭和54年(1979)、静岡県生まれ。大正大学文学部卒業。
書店員、編集プロダクションのライターを経て、業界新聞記者。令和2年(2020)、足利尊氏と楠木正成を、理想を同じくする同門として捉えた『利生の人 尊氏と正成』で日経小説大賞を受賞して作家デビュー(文庫化にあたり、『尊氏と正成 ともに見た夢』と改題)。著書に『和らぎの国 小説・推古天皇』『あるじなしとて』『菊の剣』がある。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月30日 00:05
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

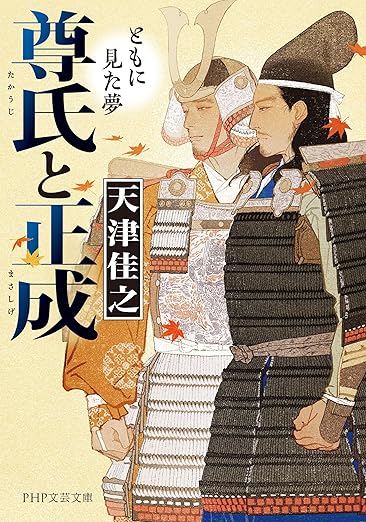



.jpg)


