「日本最大級の山城」で伊達と蒲生の忍びが…向羽黒山城ものがたり2

写真:向羽黒山城
東北屈指の名城で、蘆名盛氏、伊達政宗、蒲生氏郷、上杉景勝といった名将らがかかわった向羽黒山城は、知られざるドラマに満ちた城でもあります。
この向羽黒山城を軸に、作家・天津佳之氏が手がける特別読み切り連作小説「向羽黒山城ものがたり」。第2回は、豊臣秀吉による奥州仕置き後の向羽黒山城が舞台となります。
会津に封じられた蒲生氏郷と対立する伊達政宗が、向羽黒山城に忍びを派遣。そこで忍びは、恐るべき相手と戦うこととなり、さらに驚愕の事実を知ることに……。
「黒脛巾――伊達政宗と蒲生氏郷」
夜闇のなかに、ぼんやりと雪の白が浮かぶ。一面の積雪は、松明(たいまつ)の灯りに照らされて、ほんのりと朱に染まっていた。
それをかき分けるように城道を進む吉六(きちろく)は、いい加減うんざりしはじめていた。雪など、彼の故郷である近江国日野では、真冬に数日降るかどうか。積もりはするが、これほどの量ではないし、歩く妨げになるほどでもなかった。
会津は、雪深い土地である。霜月(しもつき)の末ともなれば、山はもちろん、開けた平野までもたっぷりと降る雪に埋まる。
(降りすぎじゃ)
内心で愚痴りながら、吉六は手槍を杖代わりに、松明を掲げて夜に目を凝らす。
会津の南、向羽黒山城。三重の曲輪と2000とも言われる屋形を備えた、奥州一の堅城である。密に張り巡らされた土塁と防柵が山肌を覆い、雪に覆われたさまは、さながら山が白糸縅(しろいとおどし)の鎧を纏ったようでさえあった。
そのなかにあって、東の尾根は山本来の地形が多く残る。すぐ下には暴れ川として名高い大川(阿賀川)が迫るだけでなく、峻険な断崖が高く切り立っており、天然の要害となっているからである。その先の曲輪には、築城以前から鎮座する弁天社(べんてんしゃ)があり、城の鎮守として大切に祀られていた。
吉六の役目は、この社(やしろ)と二の曲輪を結ぶ城道の見回りである。普段、こんなところまで夜廻りをすることはないが、最近は城の防備がやけに厳しく、吉六もまた、寒さに震えながらたった独りで、松明を頼りに歩きまわる羽目になっていた。
本来は、二人一組でする役目だった。が、今宵の相棒は懸想(けそう)した女が急に色よい返事をしたとかで、吉六に口裏を合わせるよう言い含めて出掛けていった。底から冷える寒さもあって、吉六は心細さを抱き締めるように身を縮め、弁天曲輪に入っていく。
青銅の鳥居と、礎石の上に鎮まる社。周囲には申し訳程度に木立が残されているが、それは夜に溶け込んで細々とした影を滲ませているだけだった。
そこで、吉六は気づいた。
(雪が落ちておる)
常(つね)であれば、社の周りは木立が風雪を受け止めるために、積もりかたが浅い。今宵のように風がないときは余計で、地面の土が覗いていることさえある。しかし、いまはそこに新たな雪が点々と落ちていた。
いや、よく見ればその雪も、他所(よそ)から持ってきたものをばら撒いたようで馴染んでいない。
――まるで、つい先ほど、誰かが雪についた足跡を隠したように。
「だっ、誰かいるのかっ」
貼り付いた喉(のど)から誰何(すいか)の声を絞り出し、吉六は松明を掲げた。周囲を照らそうとしたが、炎の輝きは視界を塗り潰し、かえって影を濃くするばかりである。
そのとき、社の裏から何か落ちる音がした。
雪か。山の獣か、寝惚けた鳥か。
あるいは、人か。
恐怖と緊張のあまり、胃の腑が喉元まで迫り上がってくるような感覚に苛(さいな)まれながら、吉六は振り返り槍先を向ける。自身が生唾を飲む音が、耳に大きく響いた。
(人を呼ぼう)
吉六の忍耐はすぐさま尽きた。勘ちがいで城を騒がせることになったとしても、この恐怖と緊張が耐え難かった。
吉六は、音のした方を凝視したまま、松明を振って物見に合図を送ろうと腕を伸ばした。するとそのまま松明は、夜から伸びた手がするりと受け取っていった。
「え?」
疑問の声は、雪に転がり落ちることもない。喉元に鋭い何かが滑り込む感覚を覚えながら、吉六の意識は唐突に絶たれた。
「すまぬが、これも務めゆえな」
力の抜けた城番の身を縛り上げ、社の軒下に押し込みながら、安藤兵衛(あんどうひょうえ)はつぶやいた。
殺しはしていない。薬で眠らせただけである。
血を見るのは苦手だった。できれば無駄な争いもなく、斬り合いもなく事が済めば、それに越したことはない。だが、今回の務めはそうもいかないだろうとも予感していた。
兵衛は、伊達家に仕える忍びである。正確には、かつてそうだった。もともとは"八宗兼学(はっしゅうけんがく)の山"として知られる出羽三山の修験者(しゅげんじゃ)であり、山岳修行のみならず、祝詞(のりと)や仏典をはじめとして神道、仏教、道教、陰陽道までも修めた男である。経典を"喰らう"と言われるほどの厳しい修行のうちに、険しい山々を自在に駆け巡る行法(ぎょうほう)と体術を体得。それを見込まれて、伊達家に招かれた身であった。
獣道(けものみち)や岩場、木の幹、崖、川のようすを瞬間的に把握し、山野を素早く走り抜け、ときに千尋(せんじん)の谷さえ心を乱さず飛び渡ることで心身を鍛え上げる。この行法を、兵衛は「雲心歩法(うんしんほほう)」と名付けた。一見不安定に見えながらも、山肌を雲がすり抜けるが如き、軽やかな身体の運びを喩(たと)えたものである。そしてその術は、崖を防塁に、岩場を防柵に、木の幹を櫓(やぐら)に見立てれば、そのまま敵陣への潜入術となった。
さらに、兵衛は修験者として奥州各地の霊場を渡り歩き、集落に自然に溶け込む術も心得ていた。修験者としての修行は、図らずも兵衛を、敵地潜入の達人としていたのである。
伊達家は、新たな忍び組を組織するなかで、兵衛の評判を聞きつけたらしい。わざわざ家中に招き、その術を忍びたちに伝授させた。その意味では、伊達の忍び組は兵衛の弟子といって差し支えない。
その兵衛も、すでに齢(よわい)50を過ぎた。肉体の限界を感じ、伊達家を辞して再び出羽の霊場に戻ったのが3年前のことである。そんな彼が、難攻不落を謳われる向羽黒山城に潜ることになったのは、かつての主、伊達の若き当主である政宗に命じられたからだった。
『あの城に忍び込んでもらうぞ。得意だろう、兵衛』
虜(とりこ)にした男を軒下の束柱に結びつける兵衛の脳裏に、過日、そう命じられた記憶が蘇った。
虎を思わせるぎょろりとした隻眼(せきがん)に剣呑(けんのん)な色を載せ、平伏する兵衛を見下ろすのは、伊達藤次郎(とうじろう)政宗。齢18で家督を継いで以来、奥州に覇を唱えんとする昇り龍である。一時は、北は胆沢(いさわ)から南は白河までを支配下に収め、正に北の雄といっても過言ではなかった。
しかし、彼が24となった天正18年(1590)、その覇業は足踏みを余儀なくされている。
「猿に使われる小才子(こざいし)が、余計なことをしてくれたものよ」
猿、そして小才子。恨みがましく政宗が揶揄(やゆ)したのは、天下人である関白・豊臣秀吉と、その臣下の蒲生氏郷である。
豊臣政権の小田原征伐につづく奥州仕置により、伊達家は私戦を禁じた惣無事令(そうぶじれい)違反を問われ、会津をはじめ多くの領地を失った。そのうえ、召し上げられた会津以下の所領は、そっくり蒲生氏郷に与えられている。
氏郷は、あの織田信長の寵愛を受けた才子として知られ、豊臣政権でも重用される俊英である。このたびも、仕置に不平を抱く奥州諸大名の目付役として、会津をまかされたのだった。
そういう経緯があったから、政宗と氏郷は、伊達の旧領を巡って事あるごとに対立した。すでに士分でない兵衛でさえ、反目するふたりの噂を耳にするほどである。そして、両者による小競り合いがつづく最中の冬10月に起きたのが、北の旧領である大崎(おおさき)葛西(かさい)での大一揆だった。新たな領主である木村吉清(よしきよ)・清久(きよひさ)親子の悪政に憤った領民たちによる、旧主の大崎氏と葛西氏を領主にもどすことを願っての叛乱であった。
それを陰で糸を引いたのは、もちろん政宗であった。
「そもそもは小才子の政(まつりごと)が拙(つたな)いゆえ、民がもとにもどしてほしいと願ったのだ。それをあやつめが、わしの不手際に仕立て上げようとしておる」
政宗は、大崎と葛西の領民の願いを聞き、表向きは一揆鎮圧に乗り出しながらも積極的には攻めず、むしろ穏便に事を収めようと、一揆方と交渉をはじめたという。
だが、そのやり取りを、叛逆の扇動である、と氏郷に密告する者が現れた。
「曽根四郎助(そねしろうすけ)、お主とは旧知であったな。奴が一揆方とわしが交わした書状を持って、あの小才子に告げ口したのよ」
四郎助は政宗の祐筆(ゆうひつ)であり、兵衛にとっては古くからの畏友(いゆう)であった。兵衛が伊達家に仕えたのも、四郎助の口添えがあったからである。それが、いまは裏切り者として主家に仇なす者となった。
「小才子めは、曽根と書状を以て猿に訴え、わしを追い落とすつもりだ。それは何としても阻まねばならん」
つまりは、政宗の策動の証拠と証人を、氏郷のもとから奪い取れ、ということだった。でなくば、伊達家が秀吉に取り潰されてしまってもおかしくはない。
「この老いぼれには、務めが重すぎまする。ほかに若く優れた者がおりましょう」
そこではじめて、兵衛は政宗に言葉を返した。
旧友絡みとはいえ、何故それほど重要な役を、一線を退いた自分にまかせるのか。疑問に答える代わりに、政宗が示したのは大きな瓶(かめ)だった。味噌の匂いがするそのなかに埋められていたのは、兵衛が術を伝えた弟子のひとりであった。四肢を切断され、味噌瓶に詰められながら、政宗のところに届けられたときには、まだ息があったという。
「せめてもの情けよ。わしが息の根を止めてやった」
その凄惨なさまを前に、仇を取れ、と政宗は言わなかった。弟子の亡骸(なきがら)を黙ったまま見つめる兵衛を、見下ろすばかりである。
修験者である兵衛が、目の前の亡骸に心を乱すことはなかった。だが、それでも、思うことはある。
「……猶予は、いかほどごさいましょうか」
乾いた声で、兵衛が問うた。
「月の内、といったところか」
氏郷は、伊達の叛意の証拠を固めるために、自領で最も安全な場所、音に聞こえた向羽黒山城に四郎助を匿(かくま)っているという。より詳しい証言をまとめ、いずれ証人と証拠を上方に送るにちがいなかった。
このとき、霜月の20日。早ければ師走(しわす)にも、証人は秀吉の政庁である聚楽第(じゅらくだい)に送られるであろう。それより前に、伊達の旧領内で対処しなければならなかった。
向羽黒山城は堅牢なれど、一時は伊達のものとなり、政宗自身が詰め城として手を加え、城下には息の掛かった者も残っている。もちろん、氏郷も手を入れているだろうが、それにも限界があろう。むしろ、堅牢を誇るからこそ、城兵の油断も誘えるというものである。
「頼んだぞ。兵衛」
「御意」
兵衛に否やはなかった。ただ、四郎助の生真面目な面影がちらついた。
兵衛は城を見上げ、物見櫓の位置を確かめてから松明の灯りを消した。すでに夜に慣れた目に、炎の残像が明滅する。そこに城の絵図を重ね、兵衛はこれから向かう先、山頂の一の曲輪にある実城(みじよう)までの道筋を描いた。
道中の城番は、あらかじめ策を以て間引いてある。この弁天曲輪の城番の相方が女のもとへ走ったのも、兵衛が城下の伊達の旧民に裏で手をまわした結果だった。『孫子』の「用間(ようかん)篇」にいう因間(いんかん)、民をそれと自覚なく間諜とする術である。
「これが最後の務めだ」
いちいち声を出すのは、兵衛の癖だった。そうして、我が身の備えを確かめる。
ゆとりの少ない鈍色(にびいろ)の装束に、黒革の脛巾(はばき)。腰に括(くく)り付けているのは、鉤縄(かぎなわ)と小さな道具箱。箱のなかに詰められているのは薬針(くすりばり)――先ほど城番を眠らせた代物である。後ろ腰に差した山刀(やまがたな)の留め革を確かめると、首に巻いた襟巻(えりま)きを引き上げて鼻から下を隠す。
「よし。行くか」
言うと同時に、兵衛は雪を蹴って走り出した。
行く手には城道を囲う防柵、だが兵衛は足を緩めずに駆け寄ると、勢いのまま柵に足を掛けて跳ねた。するりと飛び上がった兵衛の身体は、柵を横につなぐ渡し木の上に収まる。そして、そこで止まることなく渡し木を足場に疾走した。
その速さは、平らかな地面を走るのと然(さ)して変わらない。そのうえ、兵衛は足もとを確かめてさえいない。足には足の感ずるものがあり、その赴くにまかせるのみである。柵の尖端を避けて半身のまま、躊躇(ためら)いなく二の曲輪へと音もなくひた走る。
防柵を走り抜けながら、兵衛は鉤縄を腕に巻き、わずかな腕の振りのみで鉤を投げた。夜空に一直線に伸びたそれが屋形の宇立(うだつ)に掛かるや否や、兵衛の身体が宙に舞う。踏み切りと、鉤縄を引いた反動を使った跳躍は、まるで夜に翔ぶ鷺(さぎ)のように軽い。
音もなく屋形の屋根に着地した兵衛の足は、さらに加速した。密集した屋根の甍(いらか)も、彼にとっては開けた野と変わらない。立ち並ぶ屋形の上を飛び渡りながら、積もる雪さえ落とすことなく、曲輪のなかを翔んだ。
目指すは、山の斜面に深く抜かれた空堀(からぼり)、一の曲輪まで伸びた竪堀(たてぼり)である。本来は攻め寄せた敵軍の動きを制限するものだが、潜入者にとっては身を隠しやすく、城兵にとっても死角になりやすい。一気に二の曲輪を抜け、兵衛は屋根から防柵へ、そして竪堀に向かって跳んだ。
「っ!?」
跳躍した、瞬間だった。耳に届いたのは、鋭いものが空を裂く高い音。兵衛は反射的に身体を捻(ひね)り、音を振り返った。
飛び来(きた)るは、闇に紛れた黒色の刃。苦無(くない)だと認識するや、腰の山刀をわずかに引き出してそれを受ける。重い衝撃に体勢を崩しながらも、兵衛は空堀の深い積雪のなかに飛び込んだ。
埋まった雪から身体を起こし、兵衛は周囲を探った。竪堀は深く、広い。傾斜は上に行くほど急となるが、忍びが立ち回るには十分だった。幸い、いまだ追手は侵入者発見の声を上げておらず、まだ猶予はある。兵衛はすぐさま堀から出ようとしたが、意外なことに、追手もまた空堀に飛び降りて来ていた。
「奥州の忍びは、雪のあしらいが上手いんやな」
低い声で妙な称賛を口にする追手に、兵衛は訝(いぶか)るように目を細めた。一見して猟師に見えるような、毛皮と藁蓑(わらみの)をかぶった出で立ち。小手も脛巾も毛皮に縄巻きで固めているが、身のこなしが決して山の者のそれではなかった。
「伊達の忍びやな」
確認とともに、男は腰を落として身構える。声を上げて城兵を呼ぶこともなく、ここで手を交えるつもりのようだった。
「わしは甲賀衆、日野の平子九郎(ひらこくろう)という。奥州に来て以来、手柄を立てる機会も無(の)ぅてな。お前さんの首をもらいたいとこや」
甲賀衆と言えば、天下に名を知られた忍び衆である。近江甲賀に根を張り、同地の旧主・六角氏に仕えた者どもだった。蒲生家はもともと六角氏の重臣であり、甲賀にほど近い日野の領主だったことを思えば、子飼いの忍びが居て当然ではあった。
それにしても、わざわざ名乗りを上げて己の事情まで話すとは、何とも忍びらしくない男である。それが、兵衛の胸にわずかな共感を呼んだ。
「で、その首の持ち主は何者や」
「出羽の兵衛。黒脛巾(くろはばき)の兵衛と申す」
それは、雲心歩法のために作った黒革の脛巾に由来する呼び名である。名乗りながら、兵衛は腰の山刀の留め革を外し、柄に左手を掛ける。両者の間は、およそ八歩。忍び同士の立ち会いなど、滅多にあるものではない。それを強(し)いて求めるとは、余程の無聊(ぶりよう)をかこっていたのか、あるいは血に取り憑(つ)かれているか。
いずれにしろ、避け得ない。兵衛は覚悟を決め、呼気を整える。襟巻き越しに漏れた息が、わずかに白み、夜に流れた。
先に動いたのは平子だった。
まったく予備動作もなく腕が閃(ひらめ)いたかと思えば、すでに兵衛の眼前に飛苦無(とびくない)がある。それを兵衛が一寸の差で避けたときには、平子は一足に跳んでいた。
「疾(し)っ!」
無手(むて)。いや、鉤爪(かぎづめ)。両の革小手のなかに仕込んでいたそれが、闇を裂いて兵衛の顔に肉迫する。身を引くのが一瞬でも遅れれば、顔の皮を剥がれたであろう一撃を後ろに倒れるように避け、兵衛は足で雪を蹴り上げた。
視界が白く染まるなか、猛然と鉤爪が突き込まれる。が、それを兵衛は鉤縄の尖端で絡め取り、止めた。
「小癪(こしやく)!」
平子は抑えた怒声を上げ、力まかせに縄を引く。瞬間、兵衛の身体が高く宙を舞った。縄を足に掛け、平子が引く力を利用して飛び上がったのである。宙で身体を返しながら、兵衛はこちらを見上げる平子の顔を見た。
(ひと筋縄ではいかんか)
兵衛は空中で素早く縄を手繰(たぐ)り、跳躍の軌道を変えると鋭角に切り込んでいく。瞬転のうちに腰の山刀を抜き放つと、そのまますり抜けるように平子と切り結んだ。
盛大に舞い上がる粉雪のなか、交錯した刃と爪から火花が散った。その残光を振り払うように両者は同時に身体を旋回、そこから伸びた高い蹴りが交差し、闇のなかに乾いた音を発した。互いに弾けるように距離を取り、兵衛は外された鉤縄を一気に引きもどす。
「変わった術やな。面白い」
言って、平子はにんまりと笑った。そのこめかみには、うっすらとした紅い線が浮かんでいる。兵衛の山刀が掠(かす)めた痕(あと)である。一方の兵衛はと見れば、左の肩口が切り裂かれ、覗いた肌には3本の裂傷が開いていた。
「知らせずにいてよいのか」
痛みに乱れる呼吸を整えながら、兵衛は尋ねた。
「そうしてもよいが、久々の手柄首やしな」
「蒲生の殿様は、忍びを使わぬのか」
平子の言動を鑑(かんが)みれば、そういうことになる。
「いや。だが、裏表のない方や。必要ならば使う、不要なら使わん」
返した平子の声には、どこか哀愁がある。
「他所(よそ)に流れぬのか」
「まさか。わしらは日野以来、好きで殿について来とるんやで」
だからこそ、誉(ほま)れを見せたい。そんな言外の思いを滲ませつつも、平子の目にある殺意は変わらない。
「それゆえ伊達の小僧には感謝しとる。我らの出番ができたからなっ!」
獰猛(どうもう)な叫びとともに、平子が動いた。腕のひと振りで三つの苦無を投げ放ちながら、自らも雪に潜るほど低い姿勢で間合いを詰めに掛かる。応じた兵衛も苦無を掻い潜るように体を捌(さば)き、先んじて平子の間合いに踏み込む。
いや、踏み込もうとした。一瞬の違和感が足に這い上り、兵衛は中途半端に動きを止めざるを得ない。自然、彼の意識は足もとに向いた。
(撒菱〈まきびし〉……!)
雪に埋まったそれが、平子によって撒かれたのは疑いようもない。そして、その罠にまんまと掛かった己を兵衛は自覚した。
遅れて投げ放たれていたであろう苦無が、眼前に迫る。平子から一瞬だけ逸れた意識の間隙、それを衝いた刃が迫るさまが、兵衛にはやけにゆっくりと感じられた。
山刀を振るい、苦無を叩き落として視線を前にもどす。そこに、平子の姿はない。苦無、撒菱、そしてふたたび苦無。三重の目眩(めくら)ましだと思う間もなかった。
ほとんど無意識に、兵衛は身体を右に投げ出した。間髪を入れず、その首があったところを鉤爪が薙(な)ぐ。死角から確信とともに繰り出した一撃を躱(かわ)され、平子が驚愕に目を見開くのさえ、兵衛には見えていた。
「何だと!?」
咄嗟(とっさ)だった。倒れながら鉤縄を放ってその爪を捉え、兵衛は己と諸共に平子を引き倒す。散々にかき乱された雪が舞い散るなか、先に身体を起こしたのは平子だった。倒れたままの兵衛を踏みつけるように押さえ、鉤爪を振り上げた。
「獲ったり!」
確信に満ちた声を上げた平子だったが、不意にその動きが止まった。兵衛の身体を踏みつけた足の甲に、細長い何かが突き立てられている。それが針だと理解する間もなく、ほとんど一瞬で彼の意識は闇のなかに落ちていた。
力を失った平子の身体を転がし、雪の下から這い出すように兵衛は身体を起こした。倒れ込んだ拍子に刺さった撒菱を肩から抜き、大きく息をつく。
「すまんが、まだ死にたくはないでな」
兵衛は言って、平子の足から薬針を抜くと腰の道具箱にもどした。含ませたのは、出羽山中の月の輪熊さえ一瞬で眠らせるほどの、強力な眠り薬である。先に城番を眠らせたのもこの針で、人に使えば半日は意識を取り戻すことはないという代物だった。
針と薬もまた、兵衛が修験者として山や霊場を渡るうちに習い覚えたものである。山に籠もるうえで傷や病、さらに野の獣への備えは欠かせず、修験者の多くは必然、山で採れる本草(ほんぞう)に詳しい。兵衛は独自の工夫を重ね、薬や毒を扱う術を得ていた。
「しかし、甲賀衆か」
肩口の傷に金瘡薬(きんそうやく)を塗り、端切れを固く結んで止血を施すと、兵衛はようやくその名の重さを噛み締めた。平子の言葉が真(まこと)ならば、この向羽黒山城には、手柄に飢えた甲賀忍びがまだ潜んでいることになる。
すでに騒ぎを起こしたあとである。忍びでなくとも、侵入者に気づく者がいるとも限らなかった。兵衛は山刀を鞘に収め、鉤縄を巻き取ると、平子の身体に雪を掛けて隠す。そして、竪堀を翔ぶようにして駆け抜けていった。
「おい、城に潜り込んだ奴がおるらしいぞ」
「なんじゃと。伊達の者か」
「分からん。いまは甲賀衆が探しておるそうじゃ」
一の曲輪にまで登った兵衛が身を潜めたのは、物見櫓の屋根の上である。屋根板一枚隔てて城兵が騒いでいるのを聞きながら、伏せたまま口もとを覆う襟巻きを下げ、細く長く息をついた。
空堀での立ち合いからここまでに、すでにふたりの城番と甲賀忍びをひとり、片付けていた。無論、兵衛とて無傷ではない。顔と腹とに新たな傷を増やしている。その止血を終えて、彼は眼下に広がる縄張りを眺めた。
――つくづく、覇道の城ではない。
この城に潜り込んだときから、兵衛はそう感じていた。かつての南奥州の覇者、蘆名盛氏(あしなもりうじ)が詰め城として築いた奥州一の堅城。そう言われながら、向羽黒山の城は忍びの付け入る隙が多い。その最たるものが、賑(にぎ)やかにすぎる城下だった。
兵衛の主である政宗は、会津を獲ったとき、この城を改修したと聞く。が、図面を見る限り、石垣や虎口(こぐち)を新たに設け、防備をより固めることに終始した。あるいは政宗は、弱みになる城下町を、普請後に移転させようとしていたのかもしれない。
しかし、現在の城下を見れば、氏郷の施政はむしろ町を富ませることに重きを置いている。潜入の仕込みのため、数日を城下で過ごした兵衛でさえ、それを実感していた。
伊達の旧民たちによれば、氏郷は旧領の近江から商人や職人を呼び寄せて、茶道具をはじめさまざまな物産を振興した。氏郷自身が、天下人の茶人と謳われる千利休の高弟であり、その美意識に基づいた茶器の数々は、遠く上方でも売れるものとなっているという。
何より驚くのは、利得第一の商人の類いですら氏郷を慕い、郷里での商売をおいて奥州会津まで来ていることである。
「裏表のない方、か」
主をそう評した、平子の言葉が浮かんだ。
もっとも、そんな感慨と目の前の務めは別である。兵衛は凍えた夜の空気を吸い込むと、襟巻きに口もとを埋めて立ち上がり、一の曲輪の最奥にある実城を振り返った。そこに天守にあたる楼閣はなく、簡素な二層建ての屋形があるのみである。
屋形の瓦屋根に向けて鉤縄を放ち、兵衛は跳ぶ。そのまま一層目の屋根に軟らかく着地すると、明かり取りの虫籠窓から、中を窺った。広く仄暗(ほのぐら)い板間に、背を向けた人影がある。侵入者ありの報に浮き足立ったようすもなく、蝋燭(ろうそく)ひとつを置いて端座していた。
(四郎助、か)
音もなく窓を外すと、兵衛はするりと室内に潜り込む。かすかな揺れさえなく板間に降りたとき、彼は目の前の男が四郎助とは別人であることに気づいた。直垂(ひたたれ)をまとい、脇に差料(さしりょう)の刀を置いた姿は、どこかすっきりと端正なものである。
と、刀を取りながら男は立ち上がり、振り返って兵衛を見た。その顔立ちは30半ばながら、どこか若者の爽やかさを残している。眉も髭も形よく整えられ、まっすぐな眼差しを彩っていた。
「余が、蒲生少将(しょうしょう)氏郷である」
張りのある涼やかな名乗りに、兵衛は内心で驚く。氏郷は葛西大崎の一揆鎮圧と、政宗の動きを抑えるために、前線である大崎名生(みょう)城にいるはずである。それがなぜ、50里(約200キロメートル)以上も離れた会津にいるのか。疑問が首をもたげたが、兵衛はそれに心を波立たせることなく、山刀に手を掛けて氏郷の出方を窺った。
「伊達の者と見受けるが、曽根四郎助に用か」
声や佇(たたず)まいそのままの、まっすぐな物言い。明らかな曲者(くせもの)である兵衛に、わざわざ声を掛けたのを見れば、なるほど、裏表のない人物だと納得せざるを得ない。
逆に言えば、そこまで分かっていて、兵衛に声を掛けた理由が不明だった。
「少将様にはご無礼を仕りまする。確かに、手前は四郎助にも用がございます」
「取り戻すか、それとも殺すのか」
「少将様次第、と申し上げるほかございませぬ」
「余は関白殿下に事を知らせるのみ。それをどう判じられるかは、殿下次第だ」
何とも潔い返答だった。政宗の非を述べ処罰を望むのではなく、あくまで裁定を秀吉に委(ゆだ)ねるということである。
「しかしながら、願わくは伊達殿に責を取ってもらいたい。でなくば、民の犠牲が浮かばれぬ」
だが、つぎに氏郷の口から出た声音は、先ほどの潔さに反し、思いの外に苛烈であった。
「そなたら伊達の者が、この一揆をどう捉えておるかは知らぬ。だが、非道を為(な)したは伊達殿よ。それは必ず、殿下に申し上げねばならぬ」
そのための証が四郎助であり、一揆勢とやり取りした政宗の書状である。秀麗な顔を怒りで紅潮させて言い募る氏郷に、兵衛は困惑する。
「葛西大崎の民草は、木村殿らの政拙きを嫌い、一揆に及んだと」
「確かに、木村親子のやり方はまずかった。これも我が目が行き届かなかったゆえ。詮無きことなれど、そこは幾重にも詫びたかった」
一揆の起こりに話が及んだ途端、氏郷の顔が悔悟に固くなる。少なくとも、兵衛にはそう見えた。
「だが、そこに付け込んだのは伊達殿よ。木村の不手際をもとに民の不安を煽り、旧主である大崎義隆殿がために一揆を起こせ、とな」
「それは」
「大崎殿の旧領安堵の旨、すでに余と浅野弾正(だんじょう)殿が関白殿下に願い出ておる」
兵衛の反駁(はんばく)の先を奪い、氏郷はそう告げた。浅野弾正長吉(ながよし)は秀吉の信任篤い側近であり、氏郷とともに奥州仕置を指揮する能吏(のうり)でもある。
「大崎殿ご自身も、上洛して申し開きをなされる。まもなく、民の願いは叶うのだ」
「……では、これは我が主の勇み足である、と」
「勇み足で済ませてよいと思うかっ、無辜(むこ)の民を戦(いくさ)に引き込んだのだぞ!」
あまりにもまっすぐな義憤。その怒声に、兵衛は思わず背筋を張った。同時に、分かったことがある。何故、政宗があれほど氏郷を厭(いと)い、"小才子"などと子どもじみた陰口を叩いたのか。
要するに、氏郷が立派すぎるのである。正しいことを正しいと臆さず口にし、心根から己を律して、一切の私怨を挟まず公正に振る舞う。そのうえで、人としての道に照らして非道に憤る。素養の良さ、真っ当さがそのまま顕れているような涼やかな人格である。
一方の政宗は、幼いころから姻戚間の争い、骨肉の争いさえ味わってきた。純粋なままでは生き残れず、虚勢を張り、自ら手を汚しもした。そうやって形振(なりふ)り構わず己の意志を通してきたからこそ、奥州一の大名に上り詰めたのである。
そんな政宗にとって、氏郷の出来の良さは、鼻について仕方がないのだろう。それが、自分が身を削って手に入れた領地を、横から掠め取った相手なら猶更(なおさら)である。
しかし、だからといって、無関係な民の命をすり潰していい理由にはならなかった。
「次第は伝えた。あとは、そなたにまかせよう」
そう言った氏郷の澄んだ眼差しに、兵衛は身動きの取れない己を自覚する。
これが生粋の忍びであれば、悩むことなどなかっただろう。主命は主命、それを達するためにあらゆる手を尽くすのが忍びである。だが、兵衛はちがった。
――やはり、忍びにはなりきれぬ。
すでに、実城の周りを無数の殺気が取り囲んでいた。それが甲賀衆のものであることは疑いようもない。そして、目の前の氏郷すら、驚くほどに隙が無かった。進退窮(きわ)まったいま、兵衛にできるのは、得物(えもの)を捨てて降ることのみだった。
だが、それでもまだ、心に引っかかるものがある。
「……命と申されるなら何故、伊達の忍びに、あのような無体な仕打ちをなされましたか」
弟子の悲惨な骸(むくろ)。それがよぎった。
「伊達には、影働きの者を五体満足のまま、生かして帰してはならぬ法度(はっと)でもあるのか」
返ってきた答えの意味に、兵衛は一瞬だけ気づけなかった。つまり、氏郷は伊達の忍びを捕らえはしても、手を下さずに放免した、ということである。見れば、氏郷は怪訝(けげん)な顔をしてこちらを見返していた。本当に心当たりがないことは、その表情からも明らかだった。
(そうか。やはり、そうだったか)
先ほどから、あの凄惨な亡骸のようすと、目の前の男の爽やかさがどうしても結びつかなかった。むしろ、己の野心のために民を煽動して戦を起こさせ、その命を使い潰すような酷薄さのほうが、余程近かった。
無事に戻った己の忍びを前に、氏郷に情けを掛けられておめおめ生きて帰ったとさえ、政宗は憤ったにちがいなかった。そして、苛立ちのままに忍びを殺し、亡骸をなぶってまで兵衛を煽ろうとしたのだ。
かつて、兵衛が伊達に仕え、己の術を伝えてもいいと思ったのは、政宗にどこかあっけらかんとした明るさを感じたからである。独善的で露骨な野心でさえ、しょうがないなと思わせる、悪童のような明るさ。いまの政宗に、それを感じることはできなかった。
自身が苦労して切り取った領地を理不尽に奪われた屈辱は、兵衛も気の毒とは思う。だが、その屈辱を晴らそうとするあまりに、政宗は彼自身の大切な部分を忘れている。そう思えてならなかった。
すでに事を起こしてしまった以上、政宗は己の非道の罰を受けるべきであろう。だが、その罰が、政宗の性根をさらに歪(ゆが)めてしまうのではないか。その歪みのまま、奥州に暴威を振りまくのではないか。そうなれば、この一揆で犠牲になった民も、忍びも、何より政宗自身が浮かばれぬ。
道を学ぶ修験者として、兵衛はむしろそれが惜しかった。
(ならば、わしがするべきことは)
兵衛は、ようやく山刀の柄から手を放すと、その場に跪(ひざまず)いた。腰の鞘を外し、鉤縄も道具箱も置いて、害意のないことを氏郷に示す。
「影働きの身なれど、少将様のお志に感服仕(つかまつ)りました。この命は、少将様にお預けしたく存じまするが、ひとつだけ願いがございます」
「許す。申してみよ」
「その前に、四郎助に会わせていただきたく」
言って兵衛は、氏郷の顔を見据えた。氏郷もまた、兵衛の真意を量るように目を細めて見返す。そして頷(うなず)くと、ふたつ手を叩いた。上階から物音がしたかと思えば、梯子(はしご)から姿を現したのは、曽根四郎助であった。その懐かしい姿に、思わず兵衛は安堵の息を漏らす。
「兵衛、すまぬ」
先に口を開いたのは、四郎助だった。
「詫(わ)びはいい。それよりも、例の証文はあるか」
性急に返す兵衛に戸惑いながらも、四郎助は懐(ふところ)から一通の書状を取り出した。受け取った兵衛はそれを開くと、末に書かれた政宗の花押(かおう)を確かめる。己が諱(いみな)と、羽を休める鶺鴒(せきれい)を図案化した、流麗なものである。
兵衛はそれをじっと見つめ、やがて氏郷を振り返った。
「少将様。ひとつ、我が主に届けていただきたきものがございます」
その後、氏郷からの報告と証人を受け取った秀吉は、すぐさま石田三成を奥州に派遣し、事態を収束させることにした。明くる天正19年(1591)正月に奥州に入った三成は、早速調査に乗り出すとともに、政宗に上洛命令を伝えると、氏郷を伴って帰京。遅れて如月(きさらぎ)に政宗も上京し、秀吉の前で申し開きを行った。
争点になったのは、一揆勢を煽動したという書状が果たして本物かどうか、という点であった。これに対して政宗は、
「わたくしは平生、書状の真偽を疑われぬよう、花押の鶺鴒の目に針で穴を開けてございます。なにとぞ、その花押をお確かめいただきたい」
そう要求した。確かめてみればなるほど、件の書状に穴はなく、秀吉は政宗の言い分を認め、改めて一揆の平定を命じたという。
「兵衛に借りができたな」
そう独り言(ご)ちて、聚楽第から退出する政宗の懐には、鶺鴒の絵に包まれた薬針があった。無論、兵衛から送られてきたものである。
件の書状は、確かに政宗が一揆勢に送ったものだったし、鶺鴒の目に穴も開けていたのである。それが、秀吉のもとに届いたときには、穴が塞がっていた。祐筆として政宗の筆跡をよく知る四郎助に新たな書状を書かせたものか、それとも、経典の扱いに長(た)けた兵衛が穴を塞いだか、真相は分からない。ただ、それを仕込んだのが黒脛巾の兵衛であることは疑いようもなかった。
「流れの修験者がひとり、姿を消しただけのことよ。追わずにおいてやる」
政宗は5月にも本拠の米沢に帰還すると、すぐさま一揆鎮圧に動いた。その攻め手が苛烈なものになったのは、己の策謀が実らなかった苛立ちがあったろうことは、想像に難くない。一揆勢も激しく抵抗し、葛西大崎の大一揆が収束するのは、同年7月のことになる。
秀吉は表面上こそ寛大に処したが、その実は政宗を許してはいなかったらしい。事の始末として、伊達の本貫地を含む6郡44万石を取り上げて氏郷に与えると、代わりに一揆で荒廃した葛西大崎30万石を政宗に押し付けた。伊達家は、大幅な所領減と転封に伴う混乱で、大きく力を失うこととなった。
一方の氏郷は、奥州91万石を治める大大名となった。彼は蘆名家以来の会津の中心であった黒川城を、天守を有する絢爛(けんらん)な城郭へと改築。城の名を「鶴ヶ城(つるがじょう)」、地名を「若松」と改めて、奥州第一の町へと育てたのだった。
氏郷は、向羽黒山城を変わらずに詰め城として使いつづけるとともに、城下の発展に力を注いだ。なかでも窯物(かまもの)は、鶴ヶ城の屋根瓦焼きをきっかけに大いに発展。後世に、会津本郷焼(ほんごうやき)の名で伝わっていくことになる。
氏郷の治世のもとで、会津は穏やかな時を過ごし、向羽黒山城が戦場となることはなかった。唯一、城を騒がせた黒脛巾の忍びがいたというが、その行方は杳(よう)として知れない。
【「向羽黒山城特設サイト」はこちら!】
https://www.mukaihaguro-yabou.jp/
【天津佳之(あまつ・よしゆき)】
昭和54年(1979)、静岡県生まれ。大正大学文学部卒業。
書店員、編集プロダクションのライターを経て、業界新聞記者。令和2年(2020)、足利尊氏と楠木正成を、理想を同じくする同門として捉えた『利生の人 尊氏と正成』で日経小説大賞を受賞して作家デビュー(文庫化にあたり、『尊氏と正成 ともに見た夢』と改題)。著書に『和らぎの国 小説・推古天皇』『あるじなしとて』『菊の剣』がある。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

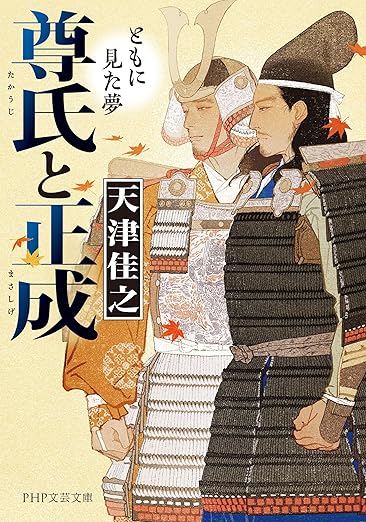




.jpg)


