『キングダム』始皇帝は即位後にどんな改革を行った? 史記にみる実態
大ヒット漫画『キングダム』を読み、秦王政、のちの始皇帝に興味を抱いたという方も多いだろう。彼の時代を知るための貴重な史料が『史記』だ。その中には、始皇帝が即位後に行った改革についても記されている。
本稿では歴史作家・島崎晋氏が、全130巻に及ぶ超大作『史記』原典のおもしろさを損なうことなく一冊にまとめた書籍『いっきに読める史記』よりご紹介する。
※本稿は、島崎晋著『いっきに読める史記』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです
始皇帝の誕生
秦王政の25年、秦は代(だい)と燕(えん)を併合した。
26年、秦は斉(せい)を併合し、ついに天下統一を成し遂げた。政は重臣たちに言った。
「わしは一介の眇々(びょうびょう)の身をもって、軍をおこし、乱を鎮めることができた。これは祖宗(そそう)の神霊によるもので、六国(りっこく)の王はみな罪に伏し、天下が大いに定まった。いま、成功を後世に伝えるためにも、王の称号を改めなければならない。話し合って、帝号を定めるようにせよ」
そこで丞相の王綰(おうわん)、御史大夫([三公の一つ。副丞相の立場にあり、御史府を統轄]の馮劫(ふうきょう)、廷尉(ていい)の李斯(りし)らが話し合って、次のように上奏した。
「古(いにしえ)には、天皇(てんこう)があり地皇(ちこう)があり、泰皇(たいこう)があって、泰皇が最も貴(たっと)いとされました。そこでわたくしらは、あえて尊号をたてまつり、王を泰皇、その命を制(せい)、令を詔(しょう)、天子の自称を朕(ちん)としてはどうかと申し合わせた次第です」
すると政は言った。
「泰皇の泰を去り、上古(じょうこ)の帝位の号をとって皇帝と号し、その他はみなの言うとおりにしよう」
また政はつぎのように言った。
「朕は太古には号があっておくりながなく、中古には号があって、おくりなは死んだのち、生前のおこないによってつけたと聞いている。このようなやり方は、子が親のおこないを、臣下が君主のおこないを議論することで、はなはだいわれがなく、朕のとらぬところである。これより、おくりなの決まりをなくして、朕を始皇帝とし、その後は二世三世と数え、万世に至るまで、これを限りなく伝えよ」
国家の形をつくる
始皇帝は木(もく)・火(か)・土(ど)・金(ごん)・水(すい)の五徳が相次いでめぐるという説(五行説)を採用し、周は火徳(かとく)を得ていたから、周に代わった秦は、火徳に打ち勝つ水徳(すいとく)に従わなければならないとした。水徳では色は黒を尊び、数字は六を基本とすることから、衣服や旗などはみな黒色とし、冠の長さは六寸、輿(こし)は六尺、一歩は六尺、車を引く馬の数は六頭とした。
王綰が遠方の地に公子を配置する封建制の採用を進言したとき、始皇帝は群臣にそのことについて議論するよう命じた。すると、ほとんどの者がこれを上策としたなか、ただ李斯だけが反対意見を述べた。
「周の武王が各地の王に封じた子弟や同族は、非常にたくさんおりました。しかし、後代には一族としてのつながりが疎遠になって、互いに仇敵(きゅうてき)のごとく攻撃しあいました。いま天下は陛下の神のごときお力によって統一され、みな郡と県とに行政区分されるようになりました。諸皇子や功臣には、国家の租税でもって恩賞を賜れば十分で、それであれば統制も容易です。天下に異見をもつ者がいないことこそが安定の良策です。遠方の地に王を立て、諸侯を置くのは良策ではありません」
すると始皇帝は断を下してこう言った。
「天下がやっと安定したのに、また諸侯の国を立てるのは、戦いの原因を残すようなものである。それでいて、天下の安定を求めるのは、実にむずかしい。ゆえに、王を置かないとする廷尉(ていい)の意見がよい」
そこで始皇帝は、天下を区分して三十六郡とし、郡ごとに守(しゅ)、尉(い)、監(かん)の三官を配置した。また民の名を改めて黔首(けんしゅ)と呼び、飲酒を賜った。天下の武器を供出させ、それを溶かして鐘・太鼓の台や銅製の人形をつくり、宮廷に置いた。枡・秤・物差の度量衡(どりょうこう)、車幅・文字の書体を統一した。
版図(はんと)は、東は海と朝鮮に至り、西は臨洮(りんとう)・羌中(きょうちゅう)に至り、南は北戸(ほくこ)に至り、北は黄河に拠って長城(ちょうじょう)を築き、陰山(いんざん)から遼東(りょうとう)に至った。天下の富豪十二万戸を咸陽(かんよう)に強制移住させ、もろもろの廟や章台宮(しょうだいきゅう)、上林苑(じょうりんえん)などはみな渭水(いすい)の南にあった。
秦は諸侯を破るごとに、その宮室とそっくりの建物を咸陽の北阪(ほくはん)の上につくり、それらは南の渭水に面していた。雍(よう)門から以東、涇水(けいすい)・渭水に至る間、宮殿や複道、回廊があいめぐり、どこも諸侯から得た美人や楽器で満たされていた。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月24日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか


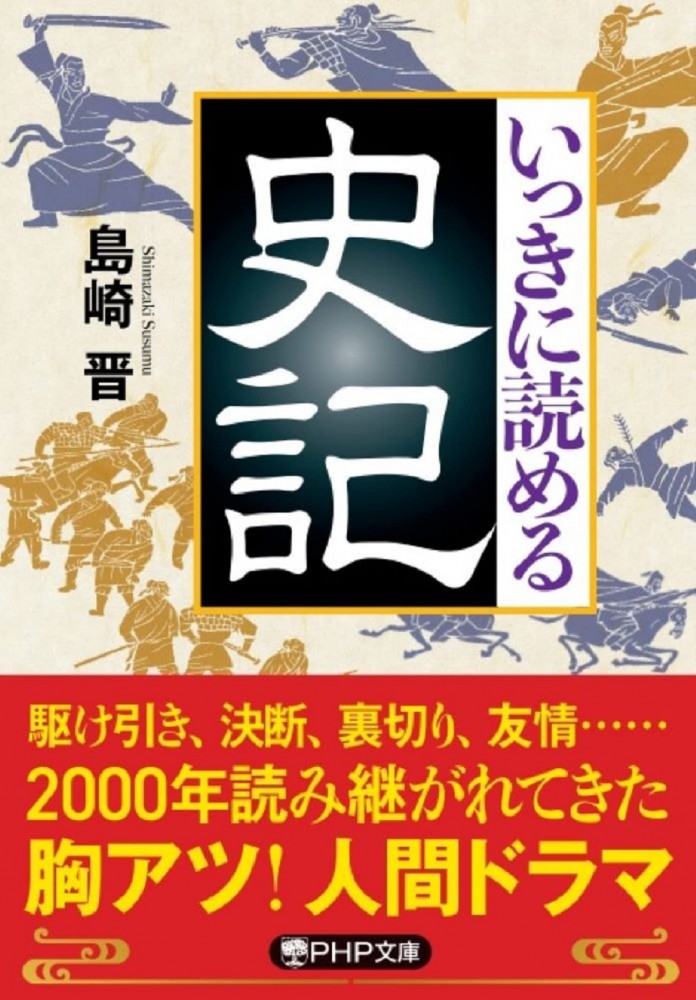





.jpg)


