儒教はなぜ“昔こそ理想”と説くのか? 西洋思想とは真逆の中国的世界観

私たちは「未来に理想がある」と考え、進歩や改善を良いものとして捉えがちだ。しかしこれは西洋思想に根ざした価値観であり、中国の儒教はまったく異なる発想をもっている。儒教は「理想は過去にあり、人間は時が経つほど堕落する」と見るため、めざす方向は"古き理想への回帰"となる。
本稿では、孔子や孟子が形づくった儒教の価値観が、中国社会にどのような影響を与えてきたのかを、『教養としての「中国史」の読み方』より解説する。
※本稿は、岡本隆司著『教養としての「中国史」の読み方』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
儒教の理想社会は昔にある
われわれは、めざすべき「理想」は未来にあると思っています。そして、「理想」に向かって日々進歩向上していくことが善だという意識をもっています。
しかし、こうした考え方が、実は「西洋的」だということは自覚していません。
たゆまぬ努力によって理想に向かって近づいていく。つまり、「進歩向上」が善だという意識は、実はとてもキリスト教的な、西洋的な考え方なのです。
儒教的な考え方は、まったく違います。
理想を掲げるのではなく、いまある現実を受け入れて、その中で自分たちがより良く生きるためにはどうすればよいのか、と考えるのが儒教だからです。
正確にいえば、儒教にもあるべき姿、理想像はあります。あるのですが、それは「大昔」の聖人が体現したとされる姿で、それから見ると人間というのは、どんどん堕落してきて、いまがある。だから、なんとか努力して堕落を食い止めましょう、というのが儒教の考え方なのです。
そのため、儒教には「進歩」という考え方はありません。
すべてにおいて「昔のほうがよい」のです。
ですから孔子の儒教を受け継いだ孟子は「性善説」を説いています。性善説というのは、「人間は本来、善なるものとして生まれる」という思想です。
要するに、人間は、生まれてきたときがもっとも善で、それが時間の経過とともにだんだんと堕落していく、というわけです。
こうした前提のもと、孟子はいかにしてその堕落を食い止めるのか、ということを説いたのです。
儒教における価値観は、このように西洋のそれとは発想が根本的に異なります。目の前の現実をよくしていこうというのは同じでも、めざすベクトルが違うのです。西洋が下から上へ向かって進んでいくことで現実をよくしようと考えるのに対し、中国の儒教は、上から下に落ちていくのを食い止めることでよくしよう、という方向の考え方なのです。
西洋思想が「進歩・前進」に希望を見いだすのは、その基礎にキリスト教があるからだと思います。キリスト教には「原罪」、つまり、すべての人は生まれながらに罪人であるという「性悪説」とでもいうべき思考があります。
また現世は苦難の連続であり、来世にこそ天国があると信じますから、未来ほど希望があって明るいわけです。「進歩」とか「進化」というのは、典型的な西洋的・キリスト教的思考なのです。
では、儒教を最初にとなえた孔子は、なぜ「過去のほうがいまよりすぐれていた」という思想をもつに至ったのでしょう。
孔子がこのような思想に至ったのは、やはりかれの生きた「時代」というものが強く影響していたと思われます。孔子が生きた前6世紀ごろの中国は、混迷の時代です。乱れた世の中で、孔子は昔の書物を集め読み、その結果、現在を「堕落した世界」と見なしたのでしょう。だからこそ、「かつてすばらしい時代があったんだ」ということを希望として人々に伝えようとしたのだと思います。
そういう意味では、孔子というのは理想社会をつくった人ではなく、過去にあった理想社会の復興をめざして、後世にその「理想」を伝えようとした人だといえます。
儒教の教典ともいうべき「経」は、孔子がオリジナルで書いたものではなく、当時まだ残っていた古い時代の記録を孔子が編纂しなおしたものとされています。
これを孔子は、「述べて作らず」といっています。いままでのものを伸ばしていくだけで、新たなものを作らない、ということです。
ですから儒教では、新しいものを作るとか、昔あったものを変えるというのは、孔子の考え方に背く「悪」であると考えます。新しいものによいものはないのです。
改善ではなく「復古」
西洋の思想に染まっている日本人は、「改革」と聞くと、無意識のうちに「改正」「改良」や「改善」をイメージし、改革したほうがよくなると考えます。しかし、儒教では「改革」は「改悪」にほかなりません。
儒教では、変えることは「悪」なのです。よりよくするとは昔に戻すことなので、われわれの考える「改善」は、改革とはいわずに必ず「復古」という言葉を用います。
たとえば、北宋時代の政治家・王安石(1021〜86)が行った改革を、歴史の授業で「王安石の新法」という言葉で習いますが、王安石自身は経典の『周礼』を根拠にして、「新しいこと」をするとは、ひと言もいっていません。
中国では、漢語に儒教の価値観が染み込んでいるので、何かをよりよく変えようと思ったら、「昔に返ります」といわなければ、人々に受け入れてもらえないからです。
ですから実施にあたっては必ず、昔にこういう事例があった、ということを探し出しますし、文書をつくるときにも必ず、権威ある経典からその事例を引用し、これは「復古」なのだと示さなければならないのです。
いかに堕落を食い止めるかというだけで、進歩の側面を描こうとしないので、中国の歴史はくりかえしに見えることが多いのです。
でも、それを「進歩が存在しない」「停滞している」と蔑むのは、西洋の思想に毒されたわれわれの傲慢です。かれらはもともと進歩などに関心がないし、まためざしてもいないのです。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月14日 00:05
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 豊臣秀長は、兄・秀吉のブレーキ役だった? 天下統一を実現させた“真の功労者”

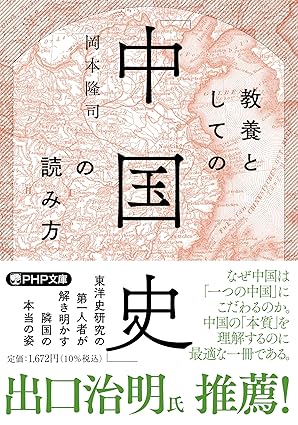





.jpg)


