高野山宿坊の味「胡麻豆腐」 その製法に秘められた信仰と歴史
2025年10月01日 公開
2025年10月01日 更新

写真:高野山の中心、壇上伽藍(だんじょうがらん)に立つ根本大塔(こんぽんだいとう)。真言密教の象徴的建築で、内部は、本尊の胎蔵大日如来を中心に、金剛界四仏如来像、十六大菩薩(ぼさつ)が描かれた柱などが配された立体の曼陀羅(まんだら)となっている
あのまちでしか出会えない、あの逸品。そこには、知られざる物語があるはず!「歴史・文化の宝庫」である関西で、日本の歴史と文化を体感できるルート「歴史街道」をめぐり、その魅力を探求するシリーズ「歴史街道まちめぐり わがまち逸品」。
世界遺産にも登録される、弘法大師・空海が開いた真言密教の聖地、高野山金剛峯寺。和歌山県高野町の中央を占める、山上の仏教都市でもあり、近年は、ほかでは見ることができない、静寂なたたずまいを求めて、ヨーロッパ地域をはじめとした海外の人たちも数多く訪れる。
この町の宿坊などで、精進料理の一品として常に供される特産品が、胡麻(ごま)豆腐である。ただし、高野山の胡麻豆腐は、一般の量販店などで売られているものとは、見た目も味わいもかなり違う。その理由を地域の名店に尋ねると、まさに高野山ならでは背景があり、この地に根付いてきた信仰文化への人々の尊崇が込められていることを教えられた。
【筆者:兼田由紀夫(フリー編集者・ライター)】
昭和31 年(1956)、兵庫県尼崎市生まれ。大阪市在住。歴史街道推進協議会の一般会員組織「歴史街道倶楽部」の季刊会報誌『歴史の旅人』に、編集者・ライターとして平成9 年(1997)より携わる。著書に『歴史街道ウォーキング1』『同2』(ともにウェッジ刊)。
【編者:歴史街道推進協議会】
「歴史を楽しむルート」として、日本の文化と歴史を体感し実感する旅筋「歴史街道」をつくり、内外に発信していくための団体として1991 年に発足。
胡麻──小さな粒に、古く、遠くから運ばれてきた歴史を秘めて
世界中の料理で広く活用されている胡麻は、非常に古くから人類とともにあった食材でもある。原産地はアフリカのサバンナ地域とみられ、乾燥した土地を好み、旱魃(かんばつ)にも強く、現在もサバンナに野生種が自生している。
自然のままでそれなりに生育することから、人による栽培も早く、紀元前14世紀にはエジプト・インド地域で始まっていたといわれる。紀元前3世紀の古代エジプトのパピルス文書には、胡麻を体に良いものと認め、薬用に使っていたことが、象形文字で記されてもいる。
日本においても、紀元前12世紀ごろの埼玉県内の縄文時代後期遺跡から、胡麻が蕎麦(そば)・小豆(あずき)などと一緒に出土している。その伝播(でんぱ)の詳細は不明だが、このころから稲作とともに穀物栽培の農耕技術が、大陸より流入し始めたと考えられている。
文書への記録も古く、『正倉院文書』に残る天平6年(734)から同11年(739)の納税記録に、尾張国(愛知県西部)、伊豆国(静岡県伊豆半島)、淡路国(兵庫県淡路島)、豊後国(大分県)から「胡麻子」「胡麻油」の納付が記され、奈良時代にはすでに国内各地の畑で胡麻が生産されていたことがわかる。
なお、「胡麻」という表記名称は、紀元前2世紀後期から中国で使われたもので、「西方(胡)から来た麻の実に似た小さな実」という意味である。
奈良時代には、実を圧して油を採り、調理や灯りの燃料として主に用いたが、平安時代の制度細則集『延喜式』には、薬用や菓子での利用が記されている。
興味深いのは、新嘗祭(にいなめさい)をはじめとした神事の供物として、米・麦・大豆とともに胡麻が挙げられていることで、神に感謝すべき格別な作物の一つとされていた。

写真:莢(さや)に収まった状態の胡麻の実(上)。ミャンマーの胡麻畑とそこで実る胡麻(下)。日本とは違って、畝などを作らず、平地に種をばらまいて育てている〔写真提供:株式会社角濱(かどはま)総本舗〕
修行僧たちが求めた、貴重な栄養源
胡麻と高野山との関わりとして、胡麻を日本にもたらしたのは、唐から帰国した空海であるという伝承があり、ここから修行僧の精進食に取り入れられたとされる。前述のとおり、空海の誕生以前から胡麻の国内栽培は始まっていたが、遣唐使が練り胡麻の製法を伝えたという説もあり、あながち否定はできない。
ただし、精進料理が国内で本格的に発展するのは、鎌倉時代初期に南宋から禅宗が導入されて以来のことで、食事を作ることも修行の一つとして重要視されたことに始まる。胡麻豆腐が日本で作られるようになった時期などは不明だが、擂鉢(すりばち)もこのときに伝来したといい、禅の教えとともに製法が伝わったと考えるのは、妥当と思える。
精進料理は、仏教の戒めに則して、殺生や煩悩を生むことを避けるために、動物性の食材や、大蒜(にんにく)・韮(にら)などの刺激的な食材を用いず、野菜を主として調理した料理である。
近年は、ベジタリアンやヴィーガンと呼ばれる海外の菜食主義の人たちから注目されてもいる。
しかし、野菜中心の献立では、ミネラルやビタミンはとれるとはいえ、健康を維持するために不可欠な五大栄養素である、たんぱく質をとれる食材が少ない。よってそれを満たすことができる、大豆や大豆を原料とした豆腐が多用される。胡麻豆腐もまた、同じ必要から生まれた料理といえる。
そんな胡麻豆腐のこと、高野山との関わりについて、胡麻豆腐の名店・株式会社角濱総本舗の代表取締役である、角濱功治さんにお話を聞いた。現在は角濱ごまとうふ総本舗本店のほか、創作胡麻豆腐料理などを提供する飲食部2店を高野山内で経営されている。
「子どもたちを対象に胡麻豆腐教室という催しをすることあるのですが、そこで、スプーンで胡麻の粒をすくって食べたら、一杯で何粒ぐらいになるかと尋ねたりします。おそらく100粒くらいでしょうか。ご飯にふりかけて食べるときも、それくらいの量かもしれません。それで二杯もスプーンで口に入れたら、口の中が胡麻で一杯になってしまいます。ところが、胡麻豆腐一個、うち場合は70グラムですが、それに使う胡麻の量を粒でいうと、だいたい4500粒から5000粒ぐらいになります。胡麻豆腐は、いかに胡麻の栄養をとるかということで、昔のお坊さんが考案したものだということが、そこから実感できます」
その同本舗で製造している胡麻豆腐だが、一般的にイメージする茶色いものとは違って、色が白い。理由を尋ねてみた。
「胡麻豆腐は、胡麻をすり潰して作った練り胡麻を、葛(くず)粉を使って固めた料理ですが、実は、永平寺式と高野山式の二系統の作り方があって、見た目や味わいが違います」。
角濱さんによれば、永平寺式は、胡麻をあぶって、いり胡麻にしたのち、皮ごとすり潰して使用する。焙煎(ばいせん)したことで香りが強く、皮を取り除かないことで、製品の色は茶色や灰色になる。現在、一般に流通する胡麻豆腐もこちらに近いものが多そうである。
一方、高野山では、風味にくせがない白胡麻を素材に、生のまま、少し水を加えて攪拌(かくはん)させる。すると摩擦熱で蒸されたような状態になって外皮がむけ、その皮をこして取り除いたものを丁寧にすり潰し、葛を加えて煮たてたのちに固めるという。
生の胡麻の芯部のみを使用した高野山の胡麻豆腐は、白く、まったりとした食感である。ただし、胡麻の香りは控えめで、舌の上でとけるうちに立ちあがり、滋味となる。
「胡麻の香りが強い永平寺の胡麻豆腐には、味噌(みそ)を添えますが、うちの胡麻豆腐だと、味噌の味しかしなくなると思います。高野山の胡麻豆腐は、山葵醤油(わさびじょうゆ)でいただくのが基本です。和歌山が醤油の発祥地だったということもありますが、醤油が当地の胡麻豆腐に合うのです」。
白い胡麻豆腐が好まれたのも、理由が考えられると角濱さんは推察する。現在の宿坊などで提供される精進料理は、多様な器に盛り付けられるが、もともと高野山で僧が使う食器は、赤か黒の漆塗りの器のみであった。特に赤いものは位の高い僧しか使えず、基本は黒い器だったことから、その器に映えるとして、白い胡麻豆腐が好まれたのではないかという。

写真:角濱ごまとうふ総本舗で販売されている生胡麻豆腐。一見、普通の豆腐のよう
今、この時代に伝える、高野山で大切にされてきたこと
角濱さんに創業の経緯を尋ねると、そこに高野山ならではの事情があったことを知らされた。
「当店が高野山で胡麻豆腐の製造を始めたのは、私の曽祖父の時代、昭和の初期のことです。もとは明治の終わりのころから、曽祖父は、高野山の麓で作った野菜や大豆などを、山内の寺院に納めることを生業としていました。こうしたことを『雑事登(ぞうじのぼり)』といい、昭和40年代くらいまで行なわれていました」
高野山内には「禁忌十則」という禁止事項があり、そのなかの一つに「禁植有利竹木」という定めがある。「商売につながる植物を植えることを禁じる」という意味で、これによって、地元では「三忌(さんき)」ともいい、野菜・果樹・花の育成が山内では許可されていない。現在も、個人宅の家庭菜園はともかく、山内には畑といえるような畑はないという。
「高野山では、仏様に花ではなく高野槙(まき)をお供えしますが、それはこうした事情があってのことです。雑事登もその『山』のルールを背景にしたもので、おそらく古い時代には、麓に荘園があり、そこから食物などを運んだのでしょう」。
そうした仏教の戒めを基本としてきた修行の地・高野山であるが、明治の廃仏毀釈(きしゃく)の影響で統廃合されるなど、寺院が減少して山内に空き地ができ、そこに初めて在家の人が入ってくるようになる。角濱さんの曽祖父もその一人であった。
昭和時代に入り、南海電鉄高野線が開通。山上に登るためのケーブルカーも設置され、観光客が増加する。多忙になった宿坊などからの要請を受けて、在家の人たちが胡麻豆腐製造の委託を受けるようになる。
このときに角濱さんの曽祖父も胡麻豆腐店を開業し、現在の会社の起点となった。また、これ以来、高野山の土産物として胡麻豆腐が定着していくことにもなる。
昭和40年(1965)には、2代目の祖父が、高温加熱殺菌処理を施した胡麻豆腐を開発し、特許を取得。レトルトパックにした製品は、品質保持期間を飛躍的に延ばし、遠隔地へ届けることを可能にし、百貨店への卸売など、販路を拡大させた。
そして、功治さんの代になってのち、平成28年(2016)に飲食部門をスタートさせて、多様な創作胡麻豆腐料理などを発信している。
また、日本で流通する胡麻のほとんどが輸入物であるという現状を踏まえて、安心して使える胡麻を確保するために、5年前、主要生産国であるミャンマーに自ら入って村人と交渉し、原料の胡麻の無農薬栽培を実現した。
「飲食のお店を始めた動機として、製造販売だけではお客さんの顔が見えないという心残りがありました。そして、目の前でお客さんの顔を見て、いろいろな声を聞くことができるようになると、安全な食を責任を持って提供しなければという思いが一層、強くなったのです」と語る。
「曽祖父から4代目の私まで、1次産業から2次、3次産業へと変わってきたことになります。そうしたなかで、新しい取り組みも続けてきました。それは高野山で暮らしてきた者として、この地で大切にされてきたこと、自然で安心できて健康につながるもの、昔からの価値あるものを、高野山に思い入れを抱いて訪れる人たちに応えて届けたいという願いがあってのことでした。変えたくないものを変えないために、自分たちが変わっていく、そんな思いでやってきたのです」。
最後に角濱さんに、おすすめの胡麻豆腐の食べ方を聞いてみた。「高野山の胡麻豆腐は、香りが控えめなことで、デザートをはじめ、さまざまな料理に活用できます。私はキムチ鍋や麻婆豆腐にするのが、好きですね。熱を加えるとトロトロになってとても美味しい。といっても、精進料理ではないので、お店ではお出ししてはいませんけれど」と笑う。
飲食部大門店では、替わって冬季限定で自店製造の豆乳を使った鍋を提供している。寒くなる時期の高野山上で、これもまた、体を温めてくれそうである。

写真:高野山奥の院の参道。奥の院最深部の御廟では、今も弘法大師が生身のまま、禅定に入るといい、朝と昼に2回の御膳「生身供(しょうじんぐ)」が運ばれる。角濱ごまとうふ総本舗の製品はその生身供にも用いられている
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月26日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

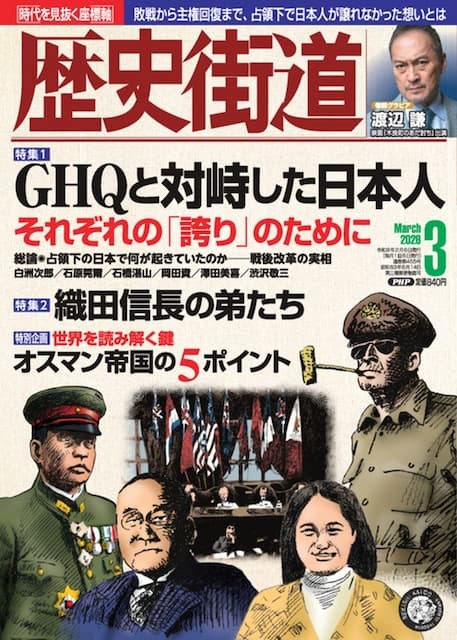




.jpg)


