はるか奈良時代以前から続く蚊帳織りの歴史 その技術は用途を広げブランド化する
2025年07月29日 公開

写真:かつては蚊帳をはじめとした伝統産業の問屋が集まっていた奈良町の街角。近年は、古い町並みをたどる国内外の観光客が増え、各種のショップやカフェのほか、町の歴史を紹介する資料館もあってにぎわう
あのまちでしか出会えない、あの逸品。そこには、知られざる物語があるはず!「歴史・文化の宝庫」である関西で、日本の歴史と文化を体感できるルート「歴史街道」をめぐり、その魅力を探求するシリーズ「歴史街道まちめぐり わがまち逸品」。
かつての日本の夏の暮らしでは、庭に開け放たれた縁側は、夜になってもそのままにして床に就くということが多かった。そうした生活のなかで、広く使われたのが、虫除けの蚊帳(かや)であった。近年は見かけることがほとんどなくなってしまったが、年配者のなかには、青く透けた蚊帳織りの生地の下を潜り込んだ幼少の体験を、蚊取り線香の匂いとともに懐かしく思い出す人もいるだろう。
その蚊帳の古くからの産地として知られたのが奈良県であった。奈良市の中心部「奈良町」には多くの蚊帳の商店・問屋があり、天理市・田原本町・広陵町を中心にした奈良市周辺の機屋(はたや)では、蚊帳の生地が盛んに織られてきた。そして、蚊帳の生産量が減った現在も、その蚊帳織りの技術は多様な分野で活用され、生き続けているのである。伝統産業「奈良の蚊帳織り」の現在を、生産の現場に追った。
【(筆者)兼田由紀夫(フリー編集者・ライター)】
昭和31年(1956)、兵庫県尼崎市生まれ。大阪市在住。歴史街道推進協議会の一般会員組織「歴史街道倶楽部」の季刊会報誌『歴史の旅人』に、編集者・ライターとして平成9年(1997)より携わる。著書に『歴史街道ウォーキング1』『同2』(ともにウェッジ刊)。
【(編者)歴史街道推進協議会】
「歴史を楽しむルート」として、日本の文化と歴史を体感し実感する旅筋「歴史街道」をつくり、内外に発信していくための団体として1991年に発足。
蚊帳の伝来地にして、生産発祥の地にて
『日本書紀』によると、応神天皇が中国江南の地、呉(ご)に阿知使主(あちのおみ)らを派遣して縫工女(きぬぬいめ)を求めたといい、それによって渡来した工女の後を継いだのが、呉衣縫(くれのきぬぬい)・蚊屋衣縫(かやのきぬぬい)であると記される。この蚊屋衣縫が、蚊帳作りの最初の担い手だったのではと考えられている。工女の渡来は5世紀前半のことと推定され、奈良盆地を拠点に繁栄した阿知使主の子孫、倭漢氏(やまとのあやうじ)のもと、衣服とともに蚊帳の製造も行なわれたのであろう。
奈良時代初期に成立した『播磨国風土記』には、飾磨(しかま)郡にあった加野里(かやのさと)という地名について、応神天皇が巡幸した際、この地に御殿を置いて蚊帳を張ったことからと由来を記し、奈良時代以前に蚊帳についての知識があったことがわかる。ただ、当時の蚊帳はのちのものとは異なり、紗(しゃ)のような透過性のある絹織物であったと見られ、一般に広く用いられるものでもなかった。
生活の進化とともに発展した奈良の蚊帳作り
鎌倉時代に成立した『春日権現験記絵巻』に、平安時代の邸宅で使われる蚊帳を描いた場面があり、最古の蚊帳の図像とされる。それは、現在に知られる蚊帳織りによる蚊帳とほぼ同じものと見える。
その蚊帳織りとは、1ミリほどの間隔がある目の粗い単純な平織の織物である。ただ、そのままだと簡単に織り目がずれてしまうので、水溶性の糊などで経糸(たていと)・緯糸(よこいと)の交点を固めて、目が乱れないように加工がされている。素材の繊維は、近代以降には綿やさまざまな化学繊維も使われるが、もともとは麻であった。
奈良興福寺にあった塔頭の室町時代の日誌『大乗院寺社雑事記』には、蚊帳が貴族や武士の間の贈答品として利用されたことが記録され、中世都市化した奈良の物産として蚊帳の生産が始まっていたことが知られる。奈良盆地が、蚊帳織りに適した麻繊維の原料である青苧(からむし)の産地であったことも、この生産を支えたとみられる。
江戸時代初期より、近江八幡を中心に現在の滋賀県内でも蚊帳の生産が始まる。ことに近江商人の西川甚五郎が麻生地を萌黄色に染めて紅布の縁(へり)を付けた蚊帳を考案。これを八幡蚊帳と銘打って江戸で販売して人気商品となり、蚊帳が商家などでも使われるようになる。浮世絵師が題材にも取り上げ、当時の蚊帳を使用する姿を見ることもできる。
もっとも、庶民にとっては麻の蚊帳は高嶺の花であり、代用として紙製の蚊帳も作られた。ただ、これは暑苦しいものだったようで、むしろ冬の防寒具に転用されたらしい。一般に広く蚊帳が普及するのは明治時代に入ってから。明治2年(1868)、奈良で安価な綿麻の蚊帳が開発されたことをきっかけとし、これによって販路は拡大していく。
奈良の織物といえば、奈良晒(ならざらし)が知られる。武士が着用した裃(かみしも)などの素材で、幕府御用品として保護されたが、明治時代を迎えて需要が減り、多くの職人が蚊帳作りに転身した。このことも奈良での蚊帳の増産につながった。さらに大正時代になると、蚊帳織りの機械化が進み、安い綿蚊帳の大量生産が可能となり、戦前の奈良蚊帳産業の全盛期を迎えることになる。
「垂乳根(たらちね)の母が釣りたる青蚊帳(あおがや)をすがしといねつたるみたれども」。歌人・作家の長塚節(たかし)による大正3年(1913)夏の詠歌。咽頭結核で病室暮らしだった長塚が、無理を押して帰郷した際、母が釣った青蚊帳に親心を知った。続けての作歌「小さなる蚊帳もこそよきしめやかに雨を聴きつゝやがて眠らむ」。
奈良の伝統技術を世界の家庭に生かす

写真:蚊帳織りの布巾のイメージ。蚊帳織りの布を6枚ほど重ね合わせた布巾で、糊が抜けると柔らかく、吸水性が高い。通気性もよくて乾燥も早いという。繊維に備長炭を含ませて匂いを付きにくくした製品もある。SDGsの動向を踏まえて、ディッシュクロスとして海外での需要も生まれている〔以下の写真提供:丸山繊維産業株式会社〕
大正時代にピークを迎えた奈良の蚊帳製造業であったが、昭和4年(1929)の昭和恐慌で大きなダメージを受ける。46か所あった事業所が25か所になり、生産額も半減したという。
「昭和恐慌の翌年、大正時代から蚊帳屋に丁稚奉公をしていた祖父が独立して、奈良町に創業したのが当社の前身の丸山商店でした。奈良の蚊帳屋ということでは、新しいほうの事業所になります」とは、蚊帳織り製品の生産を引き継ぐ丸山繊維産業株式会社の代表取締役・丸山欽也さん。現在は本社工場を天理市に構える。
戦時中の経済統制時代を経て戦後の昭和28年(1953)になると、ナイロン繊維による蚊帳の生産が定着。人口の増加と経済成長のなか、奈良蚊帳は全国シェア1位を得て、大正時代とならぶ戦後の需要ピークを迎えた。「奈良町では、蚊帳を縫製するミシンの音があちらこちらで響いていたそうです」と、奈良町生まれの丸山さんは当時を伝える。
丸山商店が天理市内に蚊帳の一貫工場を構えたのは、昭和36年(1961)のこと。しかし、昭和40年代にはいると、蚊帳産業は衰勢へと向かう。上下水道の整備、都市部の河川の暗渠化で蚊が少なくなり、住宅の造りが変わって網戸やエアコンが普及したこともあって、蚊帳の需要が減少していったのである。
時代の変化のなか、奈良の蚊帳産業は技術を生かして、多様な分野へと進出していくことになる。レースカーテンなどのインテリア、下地に蚊帳織りを用いる襖(ふすま)や壁紙の製造などである。「当社の場合は、農業用の寒冷紗(かんれいしゃ)の生産を始めました」と丸山さん。寒冷紗とは、強風・乾燥・日光・霜・潮風から農作物を守るために畑を覆う布のこと。大手繊維メーカーのもと、合成繊維のビニロンの提供を受けての製造という。また、自動車シートの補強素材や建物屋上面に張る防水補強シートの製造も手掛けるようになる。蚊帳織りは強度があるとともに、粗い目には重ねる素材と一体化しやすい利点があり、目立たないながらも産業資材で活用されているのである。

写真:蚊帳織りの技術から生まれた寒冷紗を掛けられた畑。海に近い三浦半島の大根の畑で、台風にあおられた潮が苗にかかるのを防いでいる
産業資材の製造の一方で、丸山繊維産業が進めてきたのが、ラッピングやブックカバー、文具、布巾やタオルなどのオリジナル雑貨の製造である。そして、それらの製品の販売とPRのために平成17年(2005)、奈良町に「ねっとわーくぎゃらりー ならっぷ」をオープンしている。
「以前の丸山商店では、蚊帳を作っている事業所として知られていた感がありましたが、下請けとして産業資材だけを作っていると、一般の方にはなんの会社か、わからなくなってしまいます。自分たちの蚊帳織りの技術を発信して、認知を広げていかないと、これからの生き残りもつらいかなと思い、人が集まる寺のお堂のようなところをこしらえたかったのです」と、ならっぷ立ち上げへの思いを丸山さんは語る。こうした取り組みによって、キッチン・リビング用品をはじめとした生活雑貨の売上は、現在の会社の主となるまでになっている。また、このスペースがあってこそ、集まってきたデザイナーなどのスタッフも少なくないという。
近年は、ならっぷでの売上の3割ほどは、インバウンド客の来店によるものと丸山さん。「平成25年(2013)に奈良県の海外販路開拓事業に選んでいただいて以来、ニューヨークでのギフトショーに参加するなど、海外での展開も探ってきました。昨年は韓国での展示会にも出店しています」。そうした活動から、最近の売上の10パーセントは海外でのものといい、それも商社を通さず、現地の流通業者と直接に交渉しての成果である。
「やはり本業の蚊帳織りの技術から離れてしまうと、会社が終わってしまう気がします。世界にほかにないこの技術をセールスポイントに、蚊帳がそうだったように生活に密着した製品を、かたちを置き換えながらも次世代につなげていきたい」。丸山さんたちが参加する奈良県織物工業協同組合では、伝統技術を後世に継承していくために「奈良の蚊帳織り」のブランド化も推進している。
先の長塚の短歌にも感じられるが、蚊帳には家族を包む思いやりのイメージがある。蚊帳というかたちは失われても、蚊帳織りの素材には、どこかそのやさしい思いが宿っているようである。それがまた、人を呼び、集わせるのではなかろうか。

写真:丸山繊維産業の直営店「ならっぷ」。自社の雑貨の販売のほか、カフェスペースも設けている
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月26日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

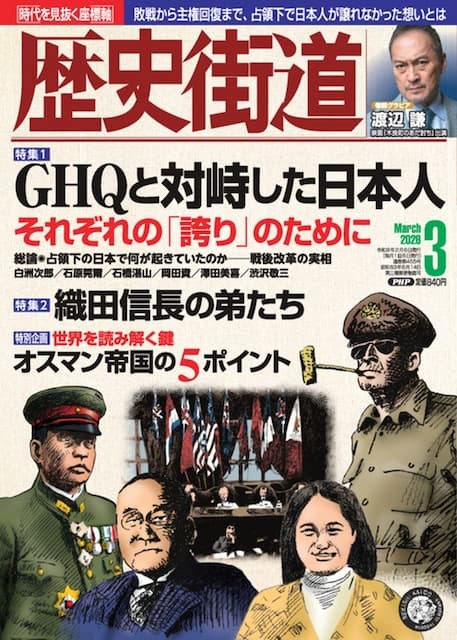




.jpg)


