『べらぼう』で注目の田沼意次 悪役とされた男の最期とは?

大河ドラマ『べらぼう』では、渡辺謙さん演じる田沼意次が注目され、田沼の政治も知られるようになった。そんな田沼だが、政敵・松平定信が登場し、失脚した後はどのような運命をたどったのだろうか。歴史家の安藤優一郎氏が、知られざる最期を紹介する。
※本稿は、安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです
失意の死
田沼意次にとり、自分を敵視する政敵が老中に起用されたことは大きかった。天明6年(1786)閏10月に2万石の没収と謹慎を命じられたが、謹慎は同年12月に解除済みだった。これ以上の処罰はないと思っていただろう。だが、松平定信が、意次の政治を批判する御三家や治済をバックに幕政のトップに立ったことで、さらなる処罰が避けられなくなる。
天明7年10月2日、意次の甥の田沼意致と大目付の松浦信程が、意次の名代として登城。老中在職中の不正を理由として、2万7千石の没収、隠居、蟄居謹慎が意次に申し渡された。前回の処罰ではその理由がはっきり示されていなかったが、今回は在職中の不正が理由と明示された。幕府は意次の政治に対し、はっきりNOを突き付けたのである。
一代にして、600石の旗本から5万7千石の大名に成り上がった意次は、再度の減封によって1万石となってしまう。大名としての身上は保ったものの、家督相続が許された孫の意明(意知の長男)は相良領を取り上げられ、陸奥信夫郡と越後頸城郡で改めて1万石を与えられた。
意次が築城を許された相良城は破却される。意次の象徴でもあった相良城の取り壊しとは、まさに田沼時代の終わりを視覚化する出来事であった。
隠居の上、蟄居謹慎を命じられた意次は下屋敷に移った。翌8年(1788)に入ると、松平康福や水野忠友など、田沼派だった老中も辞職に追い込まれる。大老の井伊直幸は前年9月に辞職していた。
幕府のトップに立った定信からすると、江戸の打ちこわしで噴出した人々の不満を鎮静化させ、田沼時代に代わる新時代の到来を世間に認識させることは、焦眉の課題だった。さもないと、今度は自分が世間の批判の矢面に立たされ、意次のように失脚に追い込まれるかもしれない。
そのためには、意次の政治がいかに悪政であったかをアピールしなければならなかった。つまり、バッシングすることで人々の不満を意次に向け、自分への期待度を高めようと目論んだのだ。
天明7年10月の2度目の処罰とは、世論の誘導を狙ったものだった。要するに、意次には悪役でいてもらう必要があった。
天明8年7月24日、意次は失意のうちに70歳でこの世を去る。名実ともに田沼時代は終焉を迎えるのである。
【執筆者】
安藤優一郎(歴史家)
昭和40年(1965)、千葉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。同大学院 文学研究科博士後期課程満期退学(文学博士)。江戸をテーマとする執筆、講演活動を展開。 おもな著書に、『明治維新 隠された真実』『教科書には載っていない 維新直後の日本』など、近著に『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』がある。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

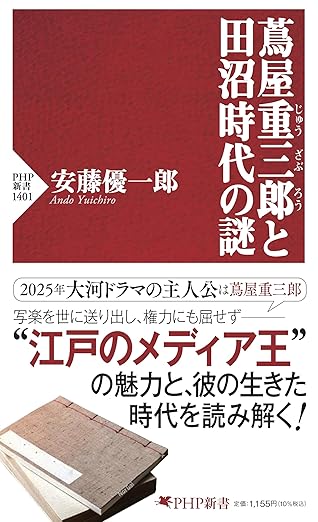


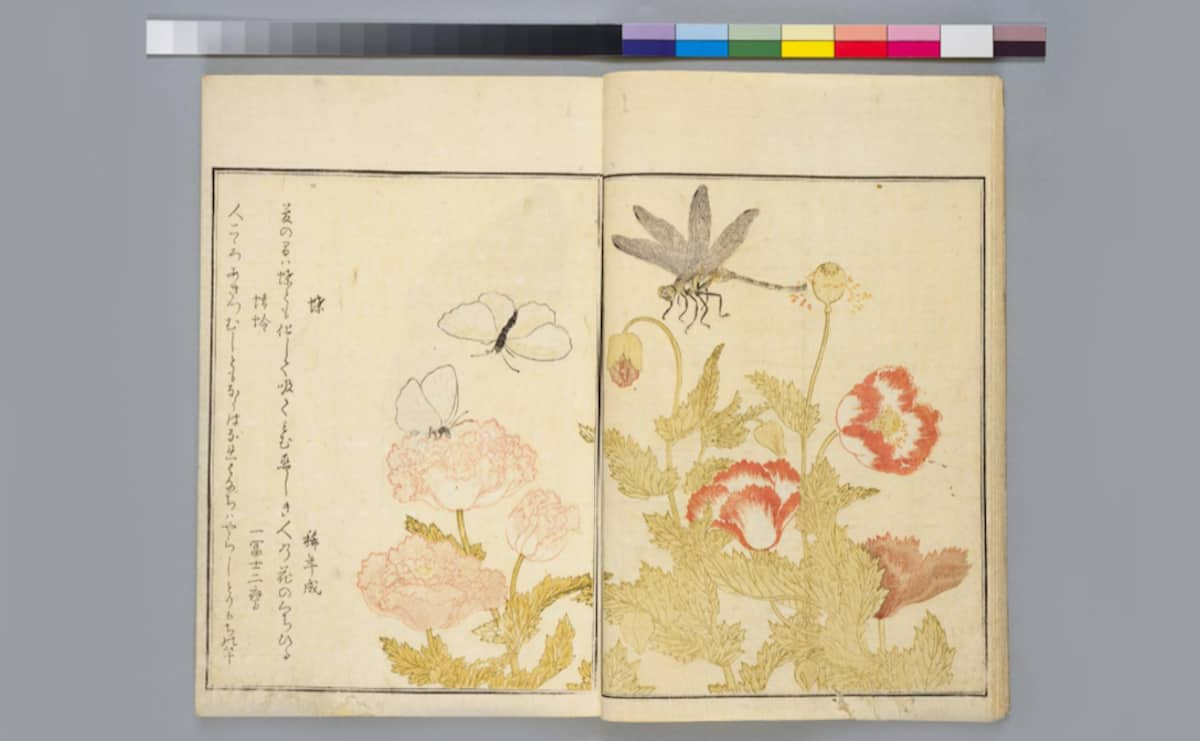

.jpg)


