天下人・関白豊臣秀頼の可能性
2020年03月25日 公開
2024年12月16日 更新

豊臣秀頼
家康は秀頼の関白就任を恐れていた?
ではなぜ、それほど豊臣秀頼は多くの人々に支持され、期待されたのでしょうか。一つには秀頼が、一般に思われているような一大名ではなかったという事実がありました。
近年、矢部健太郎さんの研究で明らかになったように、秀吉の時代に武家の家格が公家のそれに準じて定められ、豊臣家は「摂関家」、徳川や前田、毛利ら五大老の家は「清華家」とされました。清華家は太政大臣まではなれても、摂政・関白にはなれません。関ケ原合戦の後、家康は征夷大将軍となりますが、家格はそのままです。つまり家格は豊臣が徳川よりも上なのです。また、笠谷和比古さんの研究にあるように、大坂冬の陣が起こる慶長19年(1614)になっても、毎年正月には天皇の勅使をはじめ、親王、門跡、公家が残らず秀頼の許に挨拶に出向いていました。一大名では絶対にあり得ないことです。
また秀頼は、東は信濃の善光寺から、西は出雲大社まで、百を超える有名寺社の堂塔社殿を復興しています。国家の安全を祈る寺社の復興ですから、これは本来天下人の責務なのです。そして秀頼は復興事業にあたり、出雲大社では堀尾吉晴、熊野三山では浅野幸長というように地元大名を奉行に任命しました。これまた秀頼が一大名などではなかったことを示しており、豊臣政権が消滅していたわけではなかったことがわかります。
さらに、朝廷には秀頼を関白に就任させようとする動きがありました。私たちは征夷大将軍といえば、すなわち全国を支配する天下人で、絶対的な存在と考えがちですが、家康や秀忠の頃には決してそうではありませんでした。『義演准后日記』によると、朝廷は「秀頼を関白に、秀忠を将軍に」と考えていたようですから、そこには豊臣家の関白と徳川家の将軍は並存できるという認識が示されています。毛利宗瑞(輝元)の手紙にも同様の記述がありますから、それが当時の共通認識だったのでしょう。もちろん関白の方がはるかに上位で、秀頼はいつ関白になってもおかしくない存在でしたから、秀吉同様、天下人となる可能性は十分ありました。慶長16年(1611)の時点でポルトガルやオランダといったヨーロッパ諸国は、家康・秀忠、そして秀頼に贈り物をしていましたが、オランダ東インド会社の日記には、「今は事情があって皇帝(天下人)の位には就ついていないが、秀頼こそが日本の正当な皇帝であり、多くの大々名や民衆がそれを望んでいるので、将来、秀頼が皇帝になる可能性は高い」と記しています。
秀頼にとって有利だった点をもう一つ挙げれば、年齢、すなわち若さです。大坂冬の陣の際、秀頼22歳、家康73歳。武田信玄や上杉謙信、さらに織田信長の例からしても、一人のカリスマの力で成り立つ権力がその存在を喪った時にどうなるかは、明白でした。徳川幕府もまた、家康というカリスマあってのものでしたから、年齢を思えば、豊臣秀頼の逆転劇は大いにあり得ました。事実、イエズス会の宣教師ヴァレンタイン・カルヴァリヨは、大坂冬の陣の真っ最中に「高齢の家康はまもなく死ぬであろうが、そうなると彼の相続者である秀忠も滅びるであろう。そうでなくても秀忠は諸侯の間で嫌われているので、政権を得られないであろう」と記し、そのときには秀頼が「支配者になる」と明言しています。
また、聖ドミニコ会のヤシント・オルファネールは、大坂夏の陣について、将軍秀忠に任せればよいものを、高齢の家康がわざわざ大坂まで出陣してきたのは、秀忠だけであれば、戦況が不利になった途端、諸大名が豊臣方に寝返ることを家康が知っていたからだと述べ、「もし家康が出陣していなければ、秀忠が王座(天下人の地位)につけなかったのは確実である」と言い切っています。
そうした状況を誰よりも痛切に感じていたのは、家康本人だったでしょう。慶長16年(1611)、二条城での秀頼との会見の際、京都の市民は熱狂して秀頼を迎えました。豊臣家の若き主への民衆の期待と信望を目のあたりにした家康は、自分の目の黒いうちに秀頼を滅ぼさないと、徳川の脅威になると感じたはずです。それで方広寺鐘銘事件に見られるように、難癖をつけて強引に戦端を開いたのです。
こうして見ると大坂の陣は、叛旗を掲げた一大名と幕府との戦いではなく、徳川幕府の将来に不安を感じた家康が、その危険因子である摂関家の若き当主・秀頼を事前に取り除くために仕掛けた戦いであったということがわかるのです。
※本稿は歴史街道編集部編『戦国時代を読み解く新視点』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月15日 00:05
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

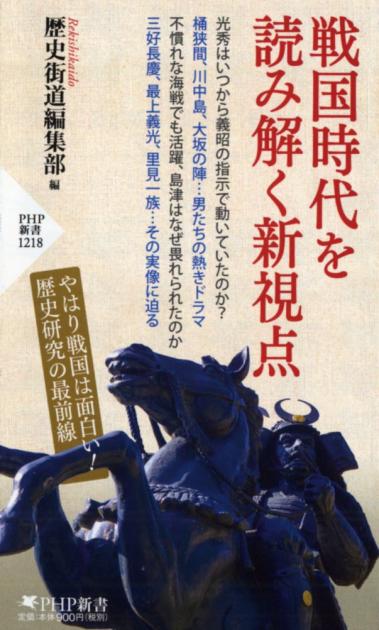





.jpg)


