天下人・関白豊臣秀頼の可能性
2020年03月25日 公開
2024年12月16日 更新

朝廷や公家・諸大名から民衆まで、広く信望を集めていた豊臣家の若き当主・秀頼。そんな秀頼が関白に就任することを、徳川家康は恐れていたという。
※本稿は歴史街道編集部編『戦国時代を読み解く新視点』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。
現実味のある話だった秀頼の薩摩落ち
「花のようなる秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて、退きも退いたよ鹿児島へ」
大坂夏の陣が終わって間もなく、そんなわらべ歌が歌われ、豊臣秀頼は死なずに薩摩に落ち延びたという噂が世間に広まります。そのことは当時平戸のイギリス商館長だったリチャード・コックスも日記に記しており、多くの人が家康よりも秀頼贔屓のためにこんな話が語られるのだろうと冷静に分析しています。ところが、その後も秀頼薩摩落ちの話が頻繁に伝わってくるため、コックスも、「秀頼は本当に生きているのかもしれない」と少し自信が揺らいだりしています。というのも、関ケ原合戦で敗れた西軍の副将宇喜多秀家が薩摩に落ち延びた前例があり、極めて現実味のある話だったのです。実際、寛永10年(1633)には、島津家当主家久の側室の母が、豊臣方の将・明石全登の長男を匿っていたことが発覚し、長男は捕縛されて京都所司代のもとに護送されています。そして元和2年(1616)4月17日に家康が没すると、噂はよりエスカレートし、秀頼がいよいよ島津の殿様とともに決起し、それを朝廷も後押ししている、とさえいわれました。無論これらは噂話に過ぎなかったのですが、当時の雰囲気をよく表わしています。
摂津国西成郡大道村(現、大阪市東淀川区)の庄屋文書によると、大坂の陣を前にして、この地域の村々は豊臣に付くか徳川に付くかで分裂し、豊臣支持派が圧倒的多数を占めて、徳川支持派を追放しました。そして豊臣派の中には大坂城に入城してともに戦った者も多くいましたが、彼らは大坂城が落城すると村に戻りました。そして、あくまでも徳川支持派の帰村を認めなかったのです。同様のことが豊臣家お膝元の摂津・河内・和泉や周辺地域の村落で起こり、戦後もなお彼らは豊臣派で、翌年4月に家康が死ぬと、「徳川はこれで駄目になる」と武装蜂起さえ起こりました。兵農分離されたとはいえ、この頃の農民は戦国の一揆を経験していますし、武士として戦ってきた者も少なくありませんから侮れません。現代の我々は夏の陣が終われば元和偃武、すなわち戦いが終わり、すぐ平和になったと思いがちですが、実際は全くそんな状況ではなかったのです。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月17日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

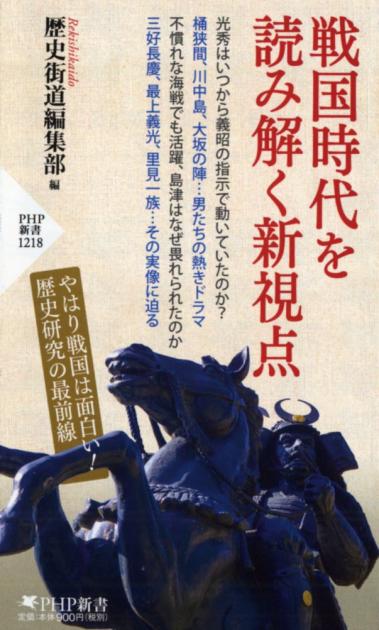





.jpg)


