武士たちのリストラ!「秩禄処分」とは?
2019年12月10日 公開
2024年12月16日 更新

※本稿は、大村大次郎著『土地と財産」で読み解く日本史』より、一部を抜粋編集したものです。
明治新政府の大きな課題
明治新政府は、廃藩置県や地租改正という革命を、奇跡的に無血で成し遂げた。
しかし、明治新政府には、もう一つ大きな課題があった。
それは武士に支給していた「秩禄」を廃止することである。
江戸時代、武士は将軍や大名から俸禄をもらうことで生活を成り立たせていた。明治維新でも、その形式は受け継がれていた。すでに述べたように明治新政府は、「版籍奉還」「廃藩置県」により、幕府や大名が持っていた領地(藩)を、国家に返納させた。
しかし、幕府や大名が持っていた領地(藩)には武士が付随しており、この武士への俸禄はそのままになっていた。
将軍や大名が幕臣や藩士に払っていた俸禄を、明治新政府がまとめて秩禄という形で払い続けたのである。つまり、藩は廃止しても、武士への財政支出は残っていたのだ。
明治新政府の経済改革の中で、この秩禄を廃止することが、もっとも困難なものだったと考えられる。
武士がもらっていた俸禄は、江戸時代の250年にわたって綿々と続いてきた「既得権益」である。
武士にとって、俸禄をもらうことは当たり前のことであり、俸禄をもらうために先祖代々将軍や藩主に忠誠を尽くしてきたのである。その権利を簡単に手放せるものではない。そもそも武士というのは、他に収入を得る方策を持っていなかったのだから、俸禄がなければたちまち食っていけなくなる。
しかし明治新政府にとって、武士に払う「秩禄」は大きな負担となっていた。国家支出の3割にも上っていたのだ。
明治新政府は、きちんと教育を受けた新しい軍隊、新しい官僚組織をつくろうとしており、もう世襲の武士たちには用はない。何の用も足さない武士たちに対して、国家支出の3割も割かなくてはならないのだ。一刻も早く、近代国家としてのインフラを整えたい明治政府にとって、秩禄というものは大きな障害となった。
そのため、タイミングを見計らって秩禄の廃止を行なうことにしたのである。
武士の秩禄は、明治維新時にすでに大幅に削減されていた。上級武士ならば7割程度、中下級武士も3割から5割程度、削減されたのだ。つまり、明治初年の時点で、武士の報酬は江戸時代から比べれば、半減かそれ以上の削減をされたのである。
明治3(1870)年には、武士から農民や商人になるものには、士族から除籍し一時賜金として禄高の5年分を出すという制度をつくった。また秩禄を奉還するもの(放棄するもの)には、禄高の3年分を一括支払いし、樺太、北海道移住者には7年分を一括支払うという制度をつくっている。
明治6(1873)年には、この士族除籍制度をさらに拡充し、百石未満の元下級武士に対し、秩禄奉還した場合は、永世禄のものは禄額の6年分、終身禄のものは禄額の4年分を一時支給することにした。翌年には、百石以上のものにも、同様の制度が設けられた。
これはまるで早期退職奨励金のようなものである。
「6年分の報酬を一度に支払うから武士をやめなさい」
ということである。
ただし、新政府には金がないため、支給は半額を現金、半額を公債証書とした。公債は8%の利子がつき、3年間据え置いた後、7年間で償還されるものだった。
このような制度をつくるということは、秩禄がそのうち廃止されるかもしれない、という雰囲気が社会にあったということである。そうでなければ応募する者などいないはずだからだ。
さらに新政府は、明治6(1873)年に家禄税を創設している。
これは、家禄に対して課せられる税金で、家禄高に応じて累進性になっていたが、平均して11・8%の税率だった。家禄は政府が支給しているものなので、家禄を11・8%削ったのと同じことだった。
こういう処置を段階的に行なっていくことで、家禄が廃止の方向に向かっていくということを士族は肌で感じることになったのだ。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月11日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語




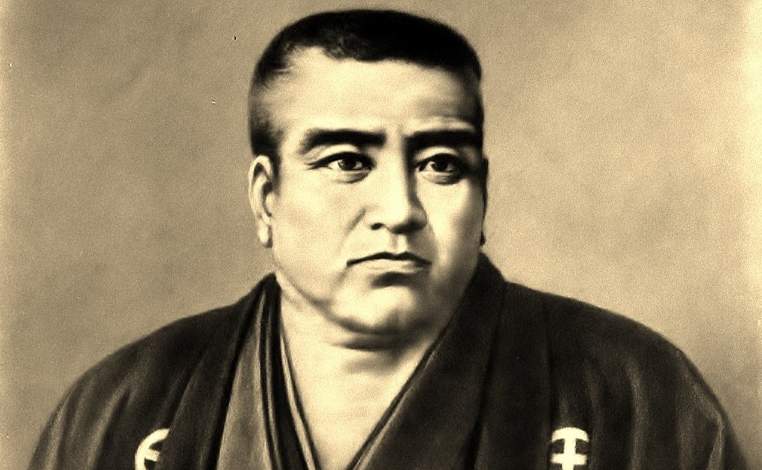


.jpg)


