武士たちのリストラ!「秩禄処分」とは?
2019年12月10日 公開
2024年12月16日 更新
ついに武士の給料を全廃する
そして明治9(1876)年、明治新政府はついに秩禄を廃止し、金禄公債を武士に配布することにした。つまり、秩禄を廃止する代わりに、少しまとまった金(俸禄の5年~14年分)を武士に与えたわけである。
しかし新政府は財政が苦しく、現金では支給できずに、公債という形で支給した。公債なので、利子が支払われる。利子率は220石以上の上級武士が5%、二十二石から220石の中級武士が6%、二十二石以下の下級武士が7%だった。当面はその利子で食っていきなさい、ということである。
新政府にとっては、かなり大きな負担だったが、秩禄を廃止するためには、仕方がなかった。
この金禄公債をもらった武士には、毎年、利子が入ってくる。
しかしその利子は、以前の俸禄と比べれば、もちろん非常に低い。二十二石以下の下級武士が毎年受け取る利子は、平均で29円5銭だった。
武士のほとんどは二十二石以下である。だから、武士の大多数は、平均29円5銭の年収しかなかったわけである。1日あたりにするとわずか8銭であり、大工の手間賃45銭に遠く及ばなかった。武士のほとんどは利子だけでは生活できず、他の収入の途を求めなければならなかった。
金禄公債を売って慣れない商売をはじめ、元も子もなくしてしまう、という武士も大勢いた。いわゆる「没落士族」による「武家の商法」である。彼らは、汁粉屋、団子屋、炭薪屋、古道具屋などを始めたが、ほとんどがうまく行かず、1年持つものは稀だったという。
また士族の多くは、新しい政府での官職を求めようとした。武士というのは、江戸時代は役人でもあったのだから、明治になっても役人になろう、というのは当然のことだといえる。
しかし新政府は、「能力のあるものしか採用しない」という建前をとっていた。欧米化、富国強兵化を目指していた新政府は、何の能力もない武士を役人として雇い入れる余裕はなかった。何らかの能力がなければ到底、官職には就けなかった。
明治14年の帝国年鑑によると、旧武士のうち、明治政府で官職にありつけたものは全体の16%にすぎないという。
西南戦争をはじめとする旧士族の乱も、この秩禄廃止が要因の一つである。
明治新政府は、大きな代償を払うことになったが、これで近代的な財政システムをつくることができたのである。
またこの秩禄奉還に関しては、武士以外の人々は歓迎していた。武士以外の人々にとって、武士であるというだけでもらえる秩禄というのは不愉快なものなので、当然といえば当然である。
当時の新聞の投書などには、華族や士族のことを「平民の厄介」「無為徒食」などと批判するものも多く見られた。また「東京日日新聞」では、「士族に対する家禄は、給金でも褒美でもなく、御情の仕送り、貧院の寄付」とまで書かれている。
国民の大多数は、近代国家をつくるためには莫大な費用がかかることを知っており、何もしていないのに禄をもらえる華士族たちというのは、批判の対象でしかなかったのだ。
旧武士たちもその点は、わきまえていたようで、薩長土肥以外のほとんどの士族たちは半ば仕方ないと感じていたようである。
だからこそ、武士の反乱は西南戦争程度で済んだのである。西南戦争は、当時の日本にとっては大戦争だったが、それでも半年で勝負がついた。近代のアジア諸国の内乱に比べれば、はるかに短期間で終息したものといえる。
これは、当時の武士階級が、時代の流れを受け入れるようになっていたからではないか、と思われる。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月15日 00:05
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- ユダヤ人はなぜ、ナチス・ドイツの標的にされたのか
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本




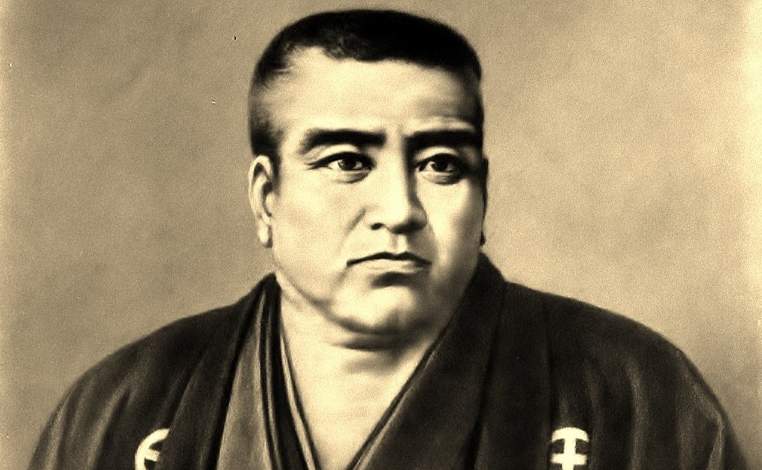


.jpg)


