陸軍兵力・軍艦数で劣る日本が、日清戦争で勝てた理由
2019年06月30日 公開
2024年12月16日 更新

令和元年(2019)の今年は、日清戦争の開戦から125年、日露戦争の開戦から115年にあたる。現在発売中の月刊誌『歴史街道』7月号の特集1では、「日清・日露戦争 名将の決断」と題して、当時のリーダーたちの選択がいかに歴史に影響を与えたかに迫っている。その特集の中で、軍事史研究家の原剛氏が、日清・日露戦争に勝てた要因について軍事的な分析をしているが 、ここでは、日清戦争に関する分析を紹介しよう。
編制、兵力、兵器の比較
日清戦争において、日本が勝利を収めた要因を語る前に、軍事史から見た、日清戦争の位置づけについて触れておきたい。
日清戦争は、総動員戦争形態期に起きた戦争で、近代国家に発展した国家が、国民を総動員して戦う戦争形態がとられた。
兵器の進歩発展史から見ると、古代と中世は白兵戦や投擲兵器の時代で、近世は鉄砲の時代。
そして日清戦争の行なわれた近代は、銃砲全盛期にあたり、銃や大砲などの火力が戦局を左右した。
それでは、日清戦争における両国の編制、兵力、兵器を比べてみよう。
まず編制面では、日本陸軍は明治19年(1886)に「戦時編制概則」を改正し、戦時には歩兵、騎兵、砲兵、工兵といった諸兵種を合わせた基本部隊として、「師団」を編成することとした。
さらに明治21年(1888)には、従来の鎮台制を廃止して、平時から師団制を採用した。
当時、欧米では、諸兵種を合わせた基本部隊は「軍団」であり、これを戦略単位としていたが、日本は国状に応じて、欧米の軍団を小型化した「師団」を戦略単位としたのである。
一方、清国陸軍は、欧米や日本のような近代的な編制ではなく、「営」(約500人、大隊に相当)を基礎単位とした、「歩兵営」と「騎兵営」から成っていた。砲兵は歩兵営に含まれ、工兵・輜重兵の制はなく、数個の営をもって、軍を編成していた。
そのため、軍といっても、諸兵種の戦闘力を総合的に発揮できる部隊編制ではなかった。
次に陸軍の兵力を比較すると、日本陸軍は、第一〜第六師団と近衛師団の七個師団など、約24万人が戦役に関係した。
一方、清国陸軍は、勇軍・練軍の約35万人に、戦争中に新たに募集した63万人を加えると、合計98万人の兵力となった。
もっとも、清国は広大な領土に兵力が散在したため、全兵力が日清戦争に参加するのは困難であった。ただ絶対数では、やはり清国のほうが優勢といえる。
次に海軍を比較すると、日本海軍は、軍艦28隻(57,631トン)、水雷艇24隻(1,475トン)で、総トン数は59,106トン。
一方、清国海軍は、軍艦82隻と水雷艇25隻から成り、総トン数は85,000トン。隻数とトン数において、日本海軍をはるかに凌ぐ。
しかし、これらの軍艦は、北洋水師、南洋水師、福建水師、広東水師に分かれていて、これらを統一する組織はなかった。
そのため、実際に日清戦争に参加したのは、北洋水師の軍艦22隻と水雷艇12隻、広東水師の軍艦3隻で、合計軍艦25隻、水雷艇12隻、総トン数44,000トンであった。なお、日本海軍の脅威となった甲鉄艦「定遠」「鎮遠」は、北洋水師に含まれる。
次に、兵器を見ていきたい。
日本陸軍の小銃は、国産の村田銃に統一され、近衛師団と第四師団は、二二年式連発村田銃(口径8ミリ)、それ以外の師団は、一三年式および一八年式の単発村田銃(口径11ミリ)を装備していた。
大砲は、山地で用いる山砲、野戦に用いる野砲とも75ミリの青銅砲を装備し、射程は山砲が3000メートル、野砲が5000メートルだった。
各師団の砲兵は、野砲12門の野砲大隊二個大隊と、山砲12門の山砲大隊一個大隊から成り、野砲と山砲を合わせて36門装備していた(近衛師団は野砲二個大隊の編制)。
また、師団を束ねる軍の砲兵は、射程約7000メートルの12センチ加農砲と、射程約44000メートルの15センチ臼砲などを装備していた。
一方、清国陸軍は新式のモーゼル銃や旧式のレミントン銃、スナイドル銃など、新旧が入り混じった数種の小銃を装備し、大砲は新式のクルップ式野山砲を装備していた。
また、旅順と威海衛の要塞砲台には、クルップ式、アームストロング式の一二センチ、一五センチ、二四センチの重砲が備えられていた。
これらの装備を見比べると、日本のほうが優れているといえよう。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち



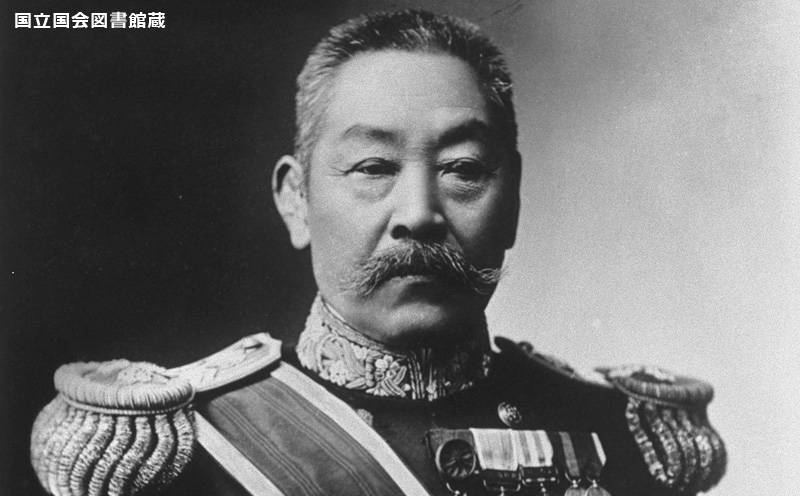


.jpg)


