大奥経費70%削減を断行した松平定信 超緊縮財政は成功したのか?

勝林寺にある田沼意次の墓(東京都豊島区)
大河ドラマ『べらぼう』に登場する松平定信は、大奥や江戸市中にも倹約を求めていく。実際、彼の政策はどのようなものだったのか。そしてその政策に妥当性はあったのか? 経済評論家の岡田晃氏が概説する。
※本稿は、岡田晃著『徳川幕府の経済政策――その光と影』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
田沼意次への追加処分と田沼色の一掃
天明7年(1787)6月、定信は老中に就任した。時に30歳。新将軍の家斉はまだ15歳であり、定信は事実上の政権トップの座に就いた。
定信がまず行ったのが、意次への追加処分と田沼色の一掃だった。
定信の老中就任の時点では、意次は老中免職と減封になったとは言え、3万7000石の大名の身分にとどまっていた。定信はそれを許さなかった。同年10月、意次に相良城を没収のうえ隠居・謹慎を命じ、さらには没収した相良城の建物から石垣の1つ1つに至るまですべてを破却させた。江戸時代に大名改易は数多くあったが、ここまで城を徹底的に破却したのは例がない。田沼の痕跡そのものを消し去ろうとしていたように見える。
政策面では、田沼時代の政策を転換するとともに、賄賂の禁止、質素倹約の徹底と統制強化、農村復興などを次々と打ち出していった。その主なものを見ていこう。
倹約の大号令、42%歳出削減の超緊縮予算
まず、質素倹約の徹底を柱とする超緊縮政策だ。
当時の幕府財政の状況を見ると、吉宗時代末期に180万石の最高を記録した年貢収納高はその後は漸減傾向となっていたが、それでも安永年間(ほぼ1770年代)には150万石余りで推移していた。ところが天明の大飢饉の第1波となった天明3年(1783)に129万石に急減した。その後やや持ち直したものの、次のピークとなった天明6年にはさらに108万石まで落ち込んでいる(大野瑞男『江戸幕府財政史論』)。
天明7年に老中に就任した定信は、幕府財政の深刻さを知って愕然とする。その時の様子について、定信は自伝『宇下人言』で次のように書いている。
「勘定奉行に財政状況を尋ねると、凶作と将軍・家治逝去のため入用が多く、100万両の不足が見込まれると言う。老中1同みな初めて聞いて驚くばかりだった」(筆者が現代語訳)。
この時、幕府の金蔵には81万両しか残っていなかったという。明和7年(1770)には300万両もあったものが、年々減少していたのだ。
そこで定信は、向こう3年間の厳格な倹約を命じる大号令を発した。倹約令は吉宗時代や田沼時代にも発令されているが、定信のそれはより厳しい内容だった。倹約令の翌天明8年(1788)、歳出(金での支出分)を前年の240万両から140万両へと、42%も削減する予算を策定。実際の歳出は予算より19万両余りオーバーしたものの、それでも34%の大幅削減に成功している(飯島千秋『江戸幕府財政の研究』)。
特に大奥の経費を大幅削減した。かつて吉宗が大奥にメスを入れたが、その後は規模が拡大し生活も派手になり経費が膨れ上がっていた。そのため同年の予算では、大奥経費を吉宗時代の享保15年(1730)から70%削減するという大ナタを振るった(同書)。
奢侈を禁止、消費抑制と統制強化
倹約令は幕府の歳出削減にとどまらず、一般庶民の衣食住にわたっても厳しく定め、広く世の中全体の奢侈を抑えることを狙いとしていた。ここに、定信政治の1つの特徴が表れている。
定信は自著『物価論』の中で「生活全般が奢侈となったことにより、物をつくらない町人が増えたり、生活必需品の消費が増えたり、商人が利益の計算に聡く、利益をえるためにあらゆる知恵や手段を用いる悪い風潮を生み出しており、すべての物価騰貴をもたらした根源は奢侈である」としている(高澤憲治『松平定信』)。
ここには「そのような風潮をつくったのは田沼意次」との批判が込められているのだが、奢侈的な消費を抑えるため、華美な箔類の団扇や紙煙草入れの製造を禁止するなど事細かに統制令を頻発し、大きな雛人形や銀製キセルを販売した商人を処罰もしている。
風俗や娯楽への取り締まりも強化した。中でも象徴的なのが、浮世絵の版元・蔦屋重三郎の処罰だ。田沼時代には自由な雰囲気が広がる中で浮世絵や洒落本、狂歌などが流行し、重三郎はヒット作品を次々にプロデュースして巨万の富を築いていた。定信は、山東京伝が出版した洒落本が風俗を乱したとして摘発、本を出版した重三郎に財産の半分没収という厳しい処罰を下した(だが重三郎はそれにもめげず、その後も喜多川歌麿や東洲斎写楽などを世に送り出している)。
高澤氏によると、定信は「倹約令や風俗統制令を発令すると江戸の景気が悪化し、それにより帰村者が増えれば、江戸において奉公人の給金が下がり、農村では就農する者が増え、手余り地(耕作が放棄された土地=筆者注)が復興して生産量が増える。その結果、生産と消費の釣り合いが取れて物価が安定する」と予想していたという(前掲書=引用の1部省略)。
実際、江戸の景気は定信の予想通り悪化した。だが農村は狙い通りにはならなかった。
米の備蓄と増産で農村復興めざす─「米本位制」への回帰
農村の復興対策としては、旧里帰農令が有名だ。当時は飢饉や年貢の取り立てから逃れるため多くの農民が江戸に出て来ていたが、そのうち帰農を望む者に旅費や農具代などを与えて帰農を促すという内容だ。
定信のシナリオそのものだ。同令は寛政2年(1790)、同3年、同5年の3回にわたって発令されている。だが効果は上がらなかった。もともと江戸に出てきた人たちは農村での生活が行き詰まって出てきたのであって、荒廃した村に帰っても生活再建の見通しなど立たない。結局、同制度で帰農した者は、わずか4人だったという。
一方、荒廃した農地の再開発を促進するため、公金貸し付けを大規模に実施した。幕府直轄領の代官が公金を預かって近隣(大名領を含む)の富裕農民に貸し付け、その利子で農村の再開発などを行い復興を図った。
飢饉への備えとしては、幕府直轄領で村ごとに郷蔵を設置して米や穀類を貯蔵させ、大名には1万石に50石の割合で米の貯蔵を命じた。米は、より保存のきく籾で蓄えさせた(囲籾)。
農村人口の回復にも力を入れた。間引きを禁止するとともに、児童手当を支給した。当初は、2人目の子どもに1両とし、後に2両に増額している。現在の少子化対策の先駆けのようなものだ。
このほかさまざまな負担軽減策も実施している。いずれも農村の復興が直接の目的だが根底には「米が国家の基本」という定信の思想があった。飢饉への備えという観点からだけでなく「物価騰貴が起きるのも米の生産が足りないからであり、米の生産を増やすことが農村復興の基本だ」と考えた。農本主義、「米本位制」への回帰である。
定信が発した倹約令には、定信の考え方がよくわかる文面がある。
「百姓は、粗末な服を着て、髪は藁で束ねることが古来の風儀だ。ところが近年いつとなく奢りに長じ、身分の程を忘れ、不相応な品を着用する者もいる。髪は油元結(髪油をつけて束ねること)を用いるなどしている。(中略)百姓が余業の商い(本業である農業以外の商売)をすることや、村々に髪結い床(髪結いを行う店)があることなどは不埒である。今後は奢りがましきことを改め、質素にして農業に励むように」(現代語訳は筆者)
ここに記されているように、定信は、贅沢禁止とともに、農家は米づくりに専念すべきだとの考えを持っていた。そのため、酒造制限令や商品作物栽培の制限、農業の合い間に商業に携わることの禁止などを打ち出した。
酒造は大量の米を使用するため、幕府は江戸初期から1定の酒造制限を実施していたが、田沼時代には「勝手造り令」によって、代官所や奉行所に届け出すれば新規に酒の醸造ができるようになっていた。だが天明の大飢饉によって米を確保する必要性から、酒の生産量を3分の1に制限していた。
定信は飢饉が収束しても、これを継続させた。定信は「酒は嗜好品であり、物価安定が必要な日用品とは違う」と考えていた。酒造制限は、奢侈制限の1環でもあったわけだ。
商品作物の栽培も制限した。菜種や綿は生活必需品の原料(菜種は油、綿は木綿の着物)として栽培を認めたものの、煙草、藍、桑など幅広い作物を制限の対象とした。
だが商品作物の栽培はすでに広く普及しており、地域によっては特産品や重要な収入源として育っている。定信の目にはそれも田沼時代の悪しき商業主義として否定すべきものと映ったのだろうが、明らかに時代に逆行するものだった。
定信は寛政の改革を進めるにあたり、祖父である吉宗の享保の改革を手本にしたと言われている。だがこれらの農業政策を見ると、家康の時代まで戻そうとしていたとさえ言える。いわば、"先祖返り"だ。しかし200年も前の状態に戻すことなどできるはずもなかった。
定信の農業政策には前述のように飢饉への備えや児童手当など、個別に見れば評価すべきものも多い。しかし天明の大飢饉であらわになったように、すでに「米本位制」そのものが矛盾を抱え限界に達していたのだ。
物価上昇についても、定信は商人の買い占めが原因として取り締まったが、より根本的には生活水準の向上によってさまざまな商品への需要が増大するという大きな流れがあった。したがって全体的に供給を構造的に増やすような政策が必要だったのだ。つまり、時代の流れに対応して「米本位制」から脱却して新たな経済体制に移行していくことが必要だったのだが、定信は逆のことをやってしまったのである。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月14日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

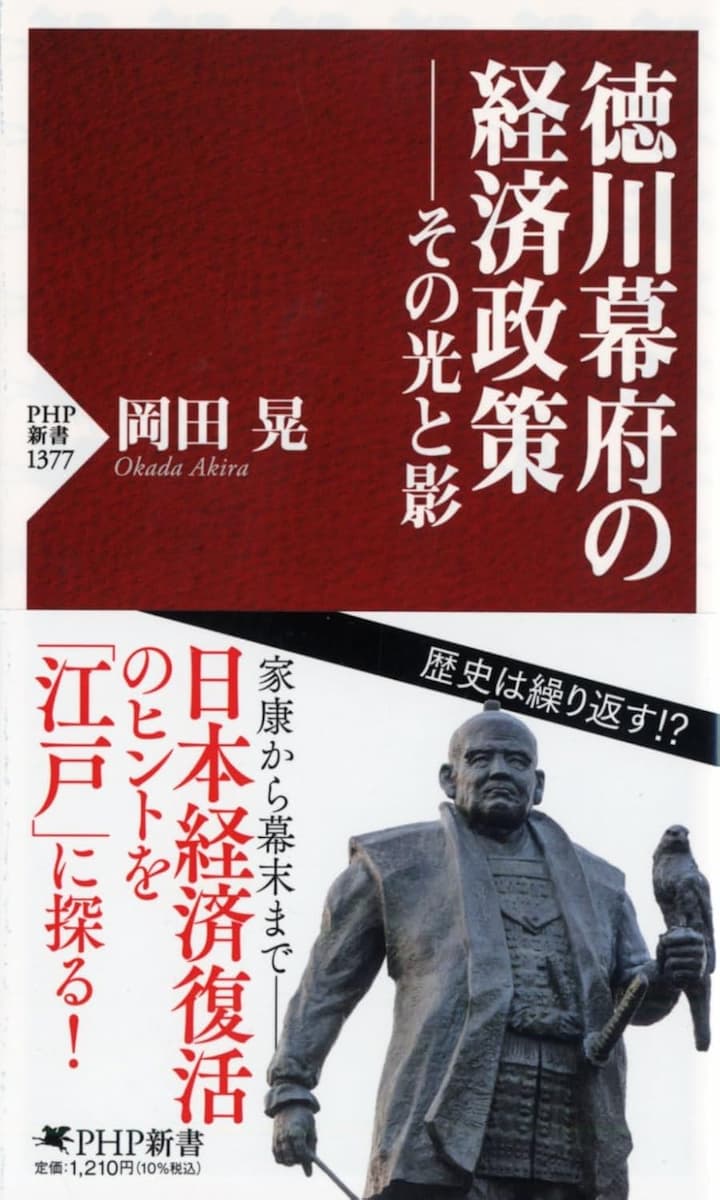




.jpg)


