インド洋作戦での完勝が生んだ慢心 日本海軍はなぜその後敗北へ向かったのか?

セイロン島沖で日本海軍機の激しい爆撃を受け、沈没する航空母艦ハーミスの航空写真
太平洋戦争開戦とともに、日本軍は東南アジアや太平洋各地で一連の攻略作戦を展開した。英国東洋艦隊の行動を封じるべくインド洋作戦を敢行し、完勝を収める。しかし、その勝利のせいか、艦隊全体には大きな慢心が広がっていったという。呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)館長の戸高一成氏の書籍『日本海軍 失敗の本質』より解説する。
※本稿は、戸高一成著『日本海軍 失敗の本質』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。
米国との決戦に備えるためのインド洋作戦
真珠湾攻撃以降、日本軍は第一段作戦(南方作戦)のほとんどを、順調に成功させた。
第一段作戦の目的は、南方地域の重要拠点を攻略して英米勢力を一掃し、資源地帯を確保することだった。
陸軍は東南アジアのマレー、ジャワを攻略し、昭和17年(1942)3月8日、ビルマの首都ラングーンの占領に成功した。
一方で海軍は、英国東洋艦隊を撃破することによって、イギリスとインドの連携を断ち、日独伊の連携を図るために動く。
昭和16年(1941)12月のマレー沖海戦で、英国東洋艦隊の戦艦プリンス・オブ・ウェールズや巡洋戦艦レパルスを撃沈。翌年2月にはオーストラリアのダーウィンを空襲、3月にはジャワ海掃討戦を成功させた。
そして、第一段作戦は最終段階を迎える。
来るべき米国との決戦に備えるためには、英国艦隊の脅威をインド洋方面から排除する必要があった。米軍との戦いにあたって、西方から東南アジアへ英軍が進出するのを防ぐ必要があったからだ。
そのために実行されたのが、インド洋作戦であった。
この作戦は、インド洋の英国東洋艦隊の主要艦船と、セイロン島にある二大基地、商港コロンボと軍港トリンコマリーを破壊することを目的としていた。
もしも英国艦隊が出動してこない場合は、セイロン島攻略などを行なうことで、誘き出そうとも考えていた。
作戦には、第一航空艦隊の空母を中心とした兵力と、南遣(なんけん)艦隊とが投入された。この作戦中、昭和17年4月5日から9日にかけて起こったのが、セイロン沖海戦である。
東洋の制海権確保に力を入れていた英国東洋艦隊には、最新鋭の戦艦が投入されていた。しかも航空母艦3、戦艦5、巡洋艦7、駆逐艦16、潜水艦7という大兵力である。
対する南雲忠一中将率いる機動部隊の戦力は、航空母艦こそ5隻と英軍を上まわるものの、戦艦4、巡洋艦3、駆逐艦9であった。
数値的には、英国が日本を上回っていた。
また、航空戦力という点でいえば、日本軍は零戦などの新鋭機を有しているものの、陸上基地の航空兵力を加えれば、数的には互角の勢力だった。
しかし結果は、日本軍の完勝だったのである。
行なわれなかった艦隊同士の正面衝突
当初、英国東洋艦隊司令長官サマヴィル中将以下、艦隊指導部は、暗号解読により、日本艦隊が4月1日にセイロン島を攻撃するという情報を摑んでいた。
実際、南雲機動部隊は3月21日にセレベス島スターリング湾を発し、4月1日にセイロン島の攻撃を予定していた。
英軍は3月31日に艦艇を洋上で集結させ、万全の態勢で日本艦隊の出現を待っていた。ところが、予定の日になっても日本軍を見つけることができなかった。
それもそのはず、3月に南鳥島への空襲があり、その対応に追われて、セイロン島への攻撃予定が4月5日に変更されていたのだ。
この日本軍の計画変更によって、両艦隊の正面衝突は行なわれなかった。
依然として日本艦隊を見つけられず、燃料を消費するばかりの英国艦隊は、2日に作戦を中止。艦隊主力をモルディブ最南端にあるアッドゥ環礁へと待避させる。4月5日、南雲機動部隊はコロンボを空襲したが、当然ながら英国艦隊の姿はない。敵機およそ50機撃墜のほか、駆逐艦1隻、仮装巡洋艦1隻などを沈めるも、主だった戦果は見られなかった。機動部隊は、第二次攻撃を余儀なくされた。
そこで南雲中将は、敵水上部隊の出現に備えて雷装(魚雷を装備)待機していた艦上攻撃隊に、爆装(爆弾を装備)への転換を命じる。しかしその最中、索敵機から敵巡洋艦2隻を発見したとの報告を受け、急遽、爆装から雷装への再転換を指示した。
各空母の艦内が混乱しつつある中、別の索敵機より敵駆逐艦2隻を発見との報告が入り、駆逐艦なら艦上爆撃機のみで十分と、南雲は準備ができていた艦爆機を出撃させた。
しかしインド洋に現れたのは、重巡洋艦のドーセットシャーとコーンウォールであった。慌てた南雲は艦攻および艦爆の追加出撃を命じたが、予想に反して、艦爆機の攻撃によって2隻とも沈没させることに成功した。
開戦直後のマレー沖海戦で、戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスが撃沈されたと聞き、チャーチル英首相は泣いたというが、セイロン沖海戦でコーンウォールとドーセットシャーが撃沈されたときには、「地中海でのイタリア空軍との戦いでは、全くなかったことだ」と慨嘆したという。その後は両軍ともに艦隊を見つけることができず、南雲機動部隊はトリンコマリーの攻撃に移る。
4月9日、攻撃隊が飛行場と港湾施設を破壊した直後、索敵機より、敵空母1隻と駆逐艦3隻を発見との報が入った。直ちに第二次攻撃隊が発艦、敵空母ハーミスを捕捉する。
艦爆と零戦で編制された攻撃隊は、ハーミスに対して急降下爆撃を加える。80パーセントを超える命中率で、敵空母と駆逐艦1隻を撃沈させた。
海軍の戦いで、英国がこれほどの完敗を喫した歴史はなかった。
艦隊全体を覆っていた「慢心」
開戦直後のこの南方作戦によって、長きにわたり、英国東洋艦隊をインド洋で行動させなかったことを考えれば、インド洋作戦は成果があったと評価できる。しかし、日本海軍の「虎の子」である航空戦力の、ほとんどすべてを出動させるほどの重要性があったかどうかについては、やや疑問を感じる。
ここまで連戦連勝とはいえ、戦いごとにベテランパイロットを失っており、そうした現実に対する認識は司令部にはなかった。むしろ将来の決戦に備え、この時期は機動部隊のベテラン搭乗員を教官、教員にあてて、内地でパイロットの大量養成を進めるべきであったかもしれない。そして何よりも、本海戦は機動部隊運用の経験値を高めた一方で、いくつもの課題を残してもいる。
まず、真珠湾攻撃以来、どのような敵でも鎧袖一触(がいしゅういっしょく)と、意気揚々としていた南雲機動部隊において、セイロン沖海戦後はさらに大きな慢心が艦隊全体を覆ったことを指摘しておきたい。とりわけ、爆弾だけでは大型軍艦を撃沈できないと考えられていた中で、爆装の急降下爆撃隊で、あっさりと巡洋艦、航空母艦を撃沈したことは、「無敵意識」をいやが上にも高めたであろう。
また、空母ハーミス攻撃の直後、南雲機動部隊は、英軍の陸上基地航空機の奇襲を受けることがあった。これは陸から十分な距離を置かない海域で行動したためだったが、この貴重な教訓となるはずの「失敗」を、日本海軍は十分に生かしていない。攻撃力に目を奪われ、弱点の精査を怠ったのだ。
そして、さらに重要なことがある。
太平洋戦争の分岐点といえるミッドウェー海戦で日本軍は大敗するわけだが、その敗因ともいえる失敗と同様のことを、このセイロン沖海戦で経験していたのだ。
コロンボ空襲の際、二度目の攻撃の要請を受けた司令部は、その後、索敵機からもたらされた異なる情報に右往左往し、艦上攻撃機の雷装と爆装の兵装転換で混乱している。
このときは結果的に、艦爆だけで重巡を撃沈することができたため、大事に至らなかった。しかし後のミッドウェー海戦でも同じことが起こっているのだ。その結果、日本軍は4隻もの空母を失い、壊滅的な敗北を招いた。
現地の指揮官の報告を鵜呑みにしたことは、司令部の作戦推進に対する確固たる意識が弱かったことを示している。
日本海軍は、一瞬の戦機で勝敗が左右される航空戦の危険性を、セイロン沖海戦で深刻に受け止めるべきであった。貴重な経験を得ながら、それを活かすことができなかったのだ。勝利の中でも、冷静に教訓を見つけることが、次の失敗を防ぐ道であることを、これほど感じさせる海戦はないかもしれない。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

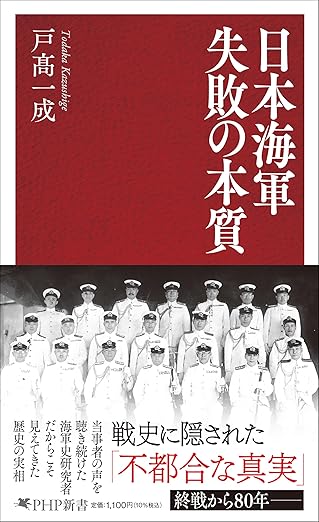





.jpg)


