なぜ二大政党の間で軍部は台頭できたのか? 政党政治の実態

政友会、民政党の二大政党が牽引した戦前の政党政治はなぜ凋落し、戦争に抗うことができなかったのか。
『昭和の政党』は、選挙と金、党勢拡張、政党不信など民衆と政党が関わる諸問題にも着目しながら、テロが頻発し戦争への道を転げ落ちていく激動期における戦前政党の実像を解明する。『歴史街道』7月号では、早稲田大学文学学術院教授の真辺将之さんに、感銘を受けたポイントについて語って貰った。
※本稿は、『歴史街道』2025年7月号「私の一冊」より、内容を一部抜粋・編集したものです
民主政治とは?今あらためて問い直す
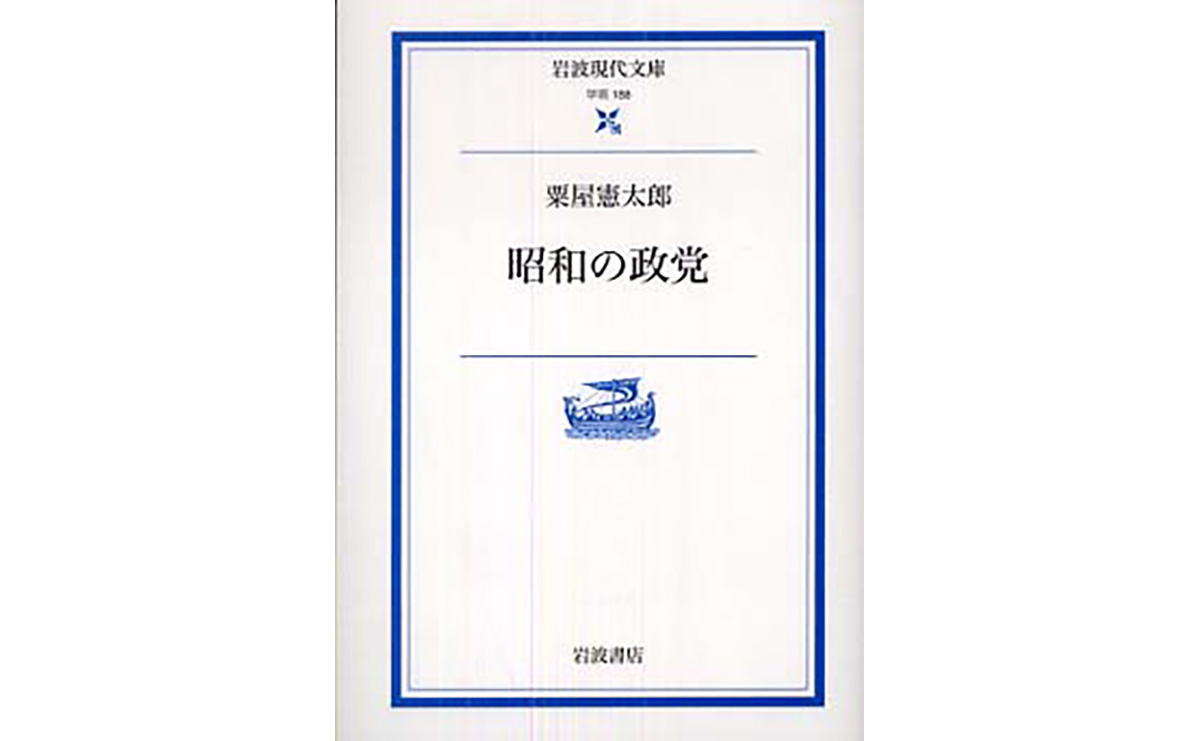
学生の頃何気なく手に取ったのが本書だった。
それまで私は、昭和戦前期に一度は民意に基づく政党政治が成立しながら、なぜ軍部台頭・戦争の時代へと突入していったのか、漠然とした疑問を抱いていた。だが本書を読み、その前提自体が誤っていたことに気づかされた。
本書によれば、政党政治は民意により誕生したのではなく、元老の奏薦によって首相が選ばれ、組閣後に選挙を経て与党が勝利する、というのが実態だったのである。選挙は政権党が干渉や圧力を行使して与党体制を固めるための手段となり、民意はあくまで後付けの正当化装置であった。その事実に、大きな衝撃を受けた。
もっとも、民意は一方的に操作されるだけでなく、軍部台頭をめぐる複雑な動きにも影響を及ぼしていた。立憲政友会と立憲民政党という二大政党の対立軸が存在したにもかかわらず、民意がそこから離反し、既存の政治体制を揺るがしていく過程も、本書は鮮やかに描き出す。
民主政治とは、単なる制度の有無や民意の賛否を問うだけのものではない。それを支える政治的・社会的基盤こそが、不可欠な要素である。いま、国内外で民主政治の足元が揺らいでいる。歴史的条件は異なるが、だからこそ、政治を支える基盤とその変容について考え、私たち自身が民主主義の未来をいかに紡ぐべきかを問い直す契機としたい。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月31日 00:05
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語


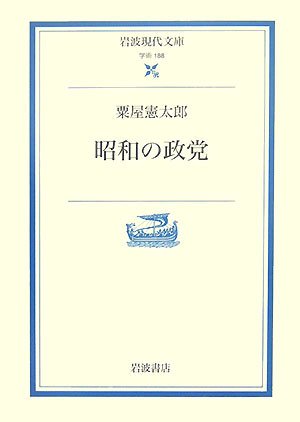
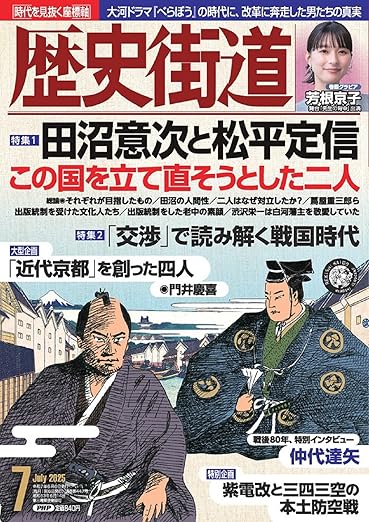



.jpg)


