島津斉彬による「ペリー来航への対処策」 幕府提出前に原文から削除していた本音

ペリー来航に際し、薩摩藩主・島津斉彬は幕府に海防強化の必要性を訴えた。幕末の危機を、単なる領国間の問題ではなく、国家全体の存亡に関わる問題として捉え、積極的な国防体制の構築を提唱していたのだ。斉彬の国家論について、書籍『島津氏』(PHP新書)より解説する。
※本稿は、新名一仁, 徳永和喜著『島津氏 鎌倉時代から続く名門のしたたかな戦略』(PHP新書)より、内容を一部抜粋・編集したものです
斉彬の国家論・経営論
藩主に就任した斉彬の現実的な国家論・藩主論をみる。
天璋院篤姫の入輿は、島津斉彬が中心となって展開した政治的婚姻であったことはいうまでもない。ここでは、斉彬が藩主として、また、斉彬個人として篤姫を将軍家に入輿させれば「全く心おきなく外圧防備のための防備を充分に仕り、より一層の奉公に励むことができる」と語っている(「御一条初発より之大意」『斉彬公史料第四巻』)。
斉彬の国家論は領国内の防備体制の確立という狭い領国論ではなく、国家存亡の危機を意識した国家論を基底に持つものであった。
斉彬は幕末の外圧による危機を為政者による国家観の欠如と考え、今後必要とされる国家観の概念を、「公儀も諸大名もこれまでの一国一郡支配の考えであっては日本国を守備することはできない」と、領国支配から日本国全体を意識した国家観を共有することが必要であることを示している(『島津斉彬言行録』)。明確な国家観を持って、どのような施策を組み立てるかを考えなくてはならないという。
領国にあっては、「国の本は農とこそ言えり、勧農は政事の本なり」とし、農業の絶対的必要性を確認しながらも、急務とすべきは工業を誘導することであるというのである。工業の育成は緩急の区分があり、「緩」とは工業育成発展の基礎は教育であり、幼少からの教育が重要であるという。
しかし、今時の工業化は軍艦・大砲の製造など軍事基盤の早急なる体制づくりを意識する「急」であり、まず工業の技術や工業製品を導入することにあると論じている。斉彬といえば近代化工業化としての藩営マニュファクチャー・集成館事業が知られているが、教育の重視を徹底的に実行した人物であることが忘れられている。
ペリー来航 幕府諮問への上書と本音
ペリー来航に対処するための施策を諸大名にも諮問した阿部伊勢守正弘への回答では、「一朝一夕の考えにてはこれなく」と、琉球開国問題を経験した上での持論を展開している。
アメリカ合衆国でも日本が鎖国をしていることは承知の上で条約交渉に来たのであるから、一通りのことでは引き下がらないと思う。しかしながら、幕府の打払令を実践するには海防が手薄で成功する見込みはない。3か年程度の猶予期間が得られるならば、全国の海防が整備され、日本人は元来勇壮の精神を持っているから必勝の策略も見出されるであろう。
もし、「彼(アメリカ合衆国)を知り、己を知りて、のちのご処置ござなく候ては、必勝の御良策は行き届き間敷存じ奉り」と、回答している。諸大名はおろか幕閣・幕臣に至るなかでも、最も識見に富む意見であったことは知られる通りである。
その後、斉彬が理論を実践したのが集成館事業であり、政策遂行には教育による導入文化の定着と、地域文化・職人文化の最大限の融合利用を意図し、軍艦・大砲など軍事防備体制の基礎である反射炉や溶鉱炉建造と国内最先端・最大規模の工業地帯が形成されていったといえる。
薩摩藩は500万両を借財する日本一の貧乏藩であったが、調所広郷の財政改革によって財政が再建され、50万両の蓄財をなしたとされる。家老調所の功績なくしては、斉彬の事業の推進はあり得ないことであった。
この幸運に恵まれながら、国家経営論や世界的視野に立って国家・国防論を展開した斉彬自身の秀でた能力は当時別格なもののようである。
斉彬の情報分析の能力は阿片戦争情報、琉球への開国要求、ペリー来航情報などオランダ風説書によって事前に入手した情報であり、薩摩藩はオランダ風説書や唐風説書を秘密裡に入手し、分析を続けた実績に加え、斉彬の個人的能力の高さが独自の国家論・世界観をつくり上げていったと思われる。
老中阿部の諮問への回答である「薩摩守上書」は、前述の内容であるが、幕府への上書の原案が存在することから両者を詳細に比較することができる。原案が上書化される段階で削除された事柄をみることができるのである。
なお、削除は不必要から削除されたのか、本音を吐露することに不都合があるとの判断からなされたのか、吟味が必要となろう。まずは原文のまま箇条書き的に摘記する。
①「公辺にて御手始在らせられ、御入用構いなく海防の御手当仰付られ度、左候て、当時諸大名困窮の折から柄御座候間、軍賦に応し金銀御配当成下され」
②「御手当の内、大砲相備候軍船御造立御座なく候ては、外の儀如何程仰付られ候ても、全備の御手には相成間敷奉存候」
③「通商御免の儀は宜しからざる事に候得とも、(中略)、軍備相整候上は仰付られ候ても然るべき哉と存じ奉候」
④「魯・亜両国の分は和蘭同様、何ケ年の間、御試の為商法御免仰付らるべく、尤邪宗の儀は堅相守様、其余の国々はきっと御免仰付られず」
①は、幕府の進める海防に対応するには経済的負担が大きく、幕府からの財政的援助もなく海防を命ぜられても、諸大名は困窮している。そのための海防軍備費相応の軍資金の提供を要請している。
②は、軍備援助のなかでも、大砲を備えた軍艦造船がなければ、その外の軍備が充実しようとも軍備が完備したとはいえない。
③は、幕府政策は鎖国であり、外国との通商は禁止されているけれども、国家海防・軍備が完成した後には、通商を許可することが適切である。
④は、ロシア・アメリカの両国はオランダ同様の扱いとし、何か年間は通商を試みてはどうか。邪宗の国々についてはこれまで通り禁止する。
以上の四点が原案から削除された主な内容である。この内容が斉彬にとっては最も重要で本音といえるものであることが、次に挙げる嘉永6年8月29日付徳川斉昭宛斉彬書状で確認できる。同書状ではさらに詳細な内容となっているが、上書・原案・書状を一覧で比較する。
さらに、書状のなかで特筆すべきことは、幕府からは海防費用捻出のために質素・倹約の儀が再三達せられるが、幕府が海防防備を一筋命じてくるのは理解できるが、書付による命令書だけではどうにもならないのが現状であることを吐露している。財政困窮の大名の海防対策には幕府の資金援助か、インド・中国への貿易船一艘派遣を許可するなどの機会を与えることの必要性を説いている。
最も斉彬が重視していることは「艦建造及び軍事必要品購入の允許」であり、斉昭に書状の最初に書いていることにもその重要性が読み取れる。結局、斉彬は開国論者といえるが条件付きとなっている。
上書にみられるように、現段階での開国は国体に影響することを認識した上で、幕府の打払令による攘夷論ではなく、国防・海防が不充分であるから、一時(3か年程度の猶予時間)の時間を稼ぐ間は避戦を唱え、国防・海防対策をして初めて対等な立場で条約が結べる。開国通商が絶対的要件と認識しているというのが本音といえる。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月12日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

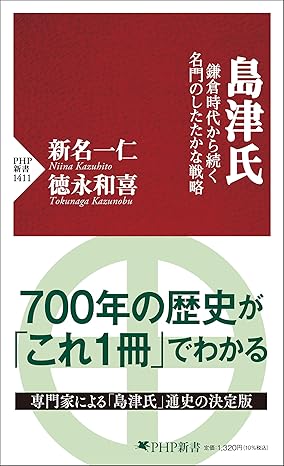





.jpg)


