キングダムの時代を書き残した『史記』が別格な理由は? 司馬遷の革新的な筆致
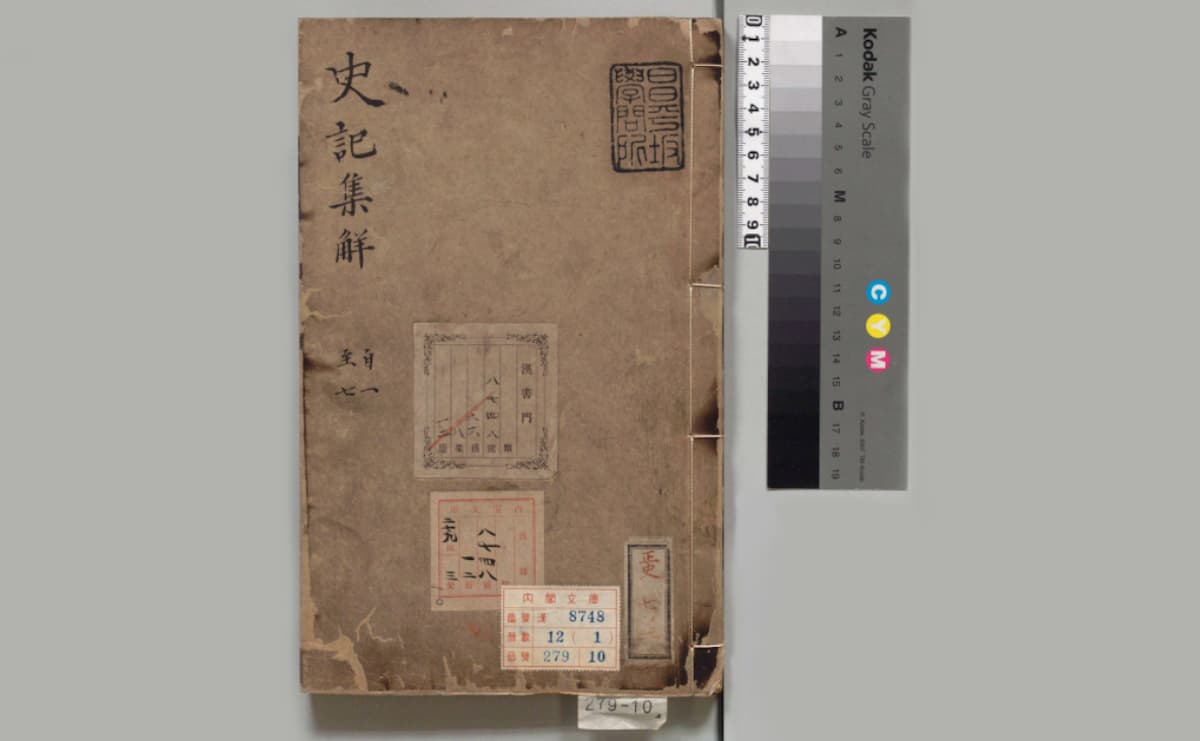 (国立公文書館蔵)
(国立公文書館蔵)
大ヒット映画『キングダム 大将軍の帰還』を観て、古代中国の戦国時代に興味を抱いたという方も多いのではないか。その時代を知るための史料といえば『史記』が有名だが、その史書としての真価といえば、ほとんど知られていないのではないか。歴史作家の島崎晋氏が、それについて解説しよう。
※本稿は、島崎晋著『いっきに読める史記』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです
中国で最初の正史『史記』が別格の扱いをされた理由とは?
原泰久の漫画『キングダム』の人気はいまだ上昇中。アニメ化と実写映画化の成功により、読者層がさらに広がったからだ。物語の舞台は中国大陸、時は紀元前三世紀の後半で、時代区分でいえば戦国時代終盤にあたる。項羽と劉邦がまだ少年の頃の話である。
ここ四十年余、日本人の中国史に対する関心は三国志にばかり集中する珍現象が続いたが、『キングダム』の成功により状況は一変。三国志の独壇場は崩れ、戦国時代終盤にも熱い視線が注がれるようになった。
原泰久『キングダム』が単純な歴史漫画であれば、ここまでヒットすることはなかったはず。大筋では史実をなぞりながら、細部では史実一割、フィクション九割くらいの比率で、主人公とその関連人物たちの成長、興亡を丹念に描いている。少年漫画の王道と史実の見事なまでのミックス。原泰久によるストーリー構成と絵柄が多くの読者を引き付けてやまないのである。
作品の舞台は今から2000年以上前だから、その時代のことを知ろうにも、史料は自ずと限られる。原泰久が主に頼っているのは前漢・武帝時代(前141〜前87年)の司馬遷により著わされた『史記』と、前漢末の劉向により編纂された『戦国策』の2つのはず。『戦国策』が権謀術数の羅列であるのに対し、『史記』は神話伝説の時代から司馬遷の生きた時代までを網羅した紀伝体の歴史書。中国で最初の正史である。
正史とは公式に編纂された歴史書のこと。唐代(618〜907年)以降は徹頭徹尾、国家事業として推進されるが、『史記』の編纂はあくまで宮廷の史官(記録係)を代々務める司馬家の個人事業として行われ、のちに最初の正史として数えられるようになった。
司馬遷の『史記』より前にも歴史書は存在した。それにもかかわらず、『史記』が別格の扱いをされたのは、構成と内容の両面で画期的な仕上がりとなったからである。
司馬遷以前の歴史書はすべて編年体で記されていた。各王の在位期間に起きた出来事を時系列順に並べるという単純なものだった。記録を残すという観点に立てば、これはこれでありかと思うが、司馬遷はそれに飽き足らぬものを感じ、前例のない紀伝体に踏み切った。
後でも触れるように、『史記』は「本紀」12巻、「書」8巻、「表」10巻、「世家」30巻、「列伝」70巻の全130巻からなり、「本紀」は王者、「世家」は諸侯、「列伝」は傑出した個人および異民族の記録。「書」は制度史、「表」は年表を指す。
「書」と「表」はともあれ、「本紀」「世家」「列伝」の内容もまた独特だった。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスがそうであったように、司馬遷も現地取材を欠かさず、古老からの聞き取りを熱心に行った。
司馬一族はもともと周王朝の史官の家系で、周の衰退に伴い、周の都から晋の国へ移住。そこから衛や秦、韓、魏、趙などへ散らばった経緯があるため、司馬遷は取材に出るたび、各地の司馬一族に便宜を図ってもらった可能性がある。
宮廷書庫にある文献上の記述と取材での成果を摺り合わせ、歴史上の人物の性格と生涯を再構築する。気の遠くなるような作業だが、司馬遷は父の司馬談が始めたそれを引き継ぎ、見事に完成させた。
『史記』という古典の価値
中国の正史といえば、『史記』や後漢時代(25〜220年)に編纂された『漢書』から清の時代(1644〜1911年)に編纂された『明史』までの「二十五史」を指すのが一般的で、『史記』で採用された「本紀」「世家」「列伝」「書」「表」からなる構成は、「本紀」と「列伝」および天文・地理・礼楽・政刑などを記した「志」の3本立てに変更されながら、紀伝体の形式は踏襲された。
極端に単純化すれば、『史記』以前の歴史書は「本紀」と「表」を足して二で割ったようなもので、司馬遷はそれでは言及できないことが多すぎるとの判断から紀伝体を選び、なおかつ「世家」と「列伝」という2つの枠組みを考案したのだろう。
司馬遷の工夫はこれに留まらず、現在の歴史学の基準で見るなら、明らかに不合格とされる手法で執筆にあたった。その人物を取り上げた理由を端的に示す象徴的なエピソードを多用したのである。
その中には宮廷での上奏もあれば、戦地での献策、さらには一対一の密談や親しい者との雑談もある。公の場で語られたことは記録に残されただろうが、密談や雑談の中身はその場にいた当事者しか知りえないはず。司馬遷はどういうルートでそれらの情報を入手したのか。
一つや二つであれば、当事者の回顧が情報源とも考えられるが、あまりに多いと、何者かの創作ではないかと疑わざるをえない。
これらの事情から、現在の歴史学の世界では、『史記』の記述に絶対的な「信」を置けないとの見方が定着しているが、そのことは『史記』という古典の価値をいささかも貶めるものではない。
史実の探求を必須とする現代歴史学の基準で見るからおかしいだけで、歴史と神話伝説、歴史と説話が不可分の時代の作品であれば、ヘロドトスの『歴史』や日本の『古事記』がそうであるように、何もおかしくはない。
司馬遷の文章が、客観的な事実を淡々と並べたものであれば、「二十五史」の一番手にはなれても、現在まで読み継がれることはなかっただろう。非常に高い文学性、物語性に富んでいるからこそ、『史記』は読みやすく、かつ面白い古典として、時空を超え愛され続けているのである。
司馬遷が後世の歴史観に与えた影響
善悪は別として、司馬遷の『史記』が後世の歴史観に大きな影響を及ぼしたことは疑いえない。
われわれは、殷から西周、春秋戦国、秦、前漢という中国史の流れを当然のごとく受け入れているが、この図式を作ったのは司馬遷である。『史記』が最初の正史とされたことで、司馬遷の歴史認識が客観的な事実であるかのように、後世の読者の脳裏にも刷り込まれた。
中国のあるべき姿、中国の枠組みについても同じことが言える。東方六国の併合により天下統一を果たした秦の版図、東西に大きく拡大した前漢・武帝時代の版図を固有の領土のごとく捉える認識も、司馬遷の筆による刷り込みである。
後世のわれわれは、多分に司馬遷の手のひらの上で転がされていると言えるが、司馬遷にも悪意があったわけではなく、彼には自分の労作が長く読み継がれることを第一とした節がある。異国の庶民から愛読されようとは、思ってもいなかったであろうが。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月02日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由

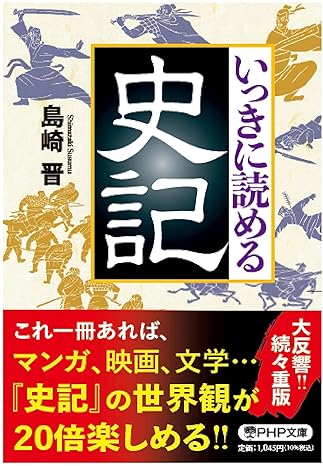





.jpg)


