太原雪斎~ 坊主頭にはちまきをし、戦の指揮をとった、今川義元のナンバー2
2018年10月01日 公開
2024年12月16日 更新
次代のナンバー2を育てよ
ナンバー2がナンバー1に警戒されるのは、次のような場合だろう。
・ナンバー1よりナンバー2のほうが、組織員に人気がある。あるいは人望がある場合
・ナンバー1が持っている権限を、ナンバー2がまるで自分の権限であるかのように振舞いだした場合。
今川家におけるナンバー2としての雪斎が、このふたつのことと、まったく無縁だったとはいえない。この時代はまだ「誰が実力者か」という物差しで人間を見るから、今川家を実際に牛耳っているのは、ナンバー1の今川義元ではなく、ナンバー2の雪斎というお坊さんだとわかれば、人々は争って雪斎のところに押しかける。自分の今後の出世、すなわち人事についていろいろな頼み事もするだろうし、また仕事上でもいろいろと指示を仰ぎに来る。義元にそういう報告をしても、義元は、
「すべて、あなたのいいようにやってください」
という。だから雪斎は、はじめのうちは渋々こういう声に対応してきた。が、たとえお坊さんでも雪斎も人間である。権力を思いのままに行使して、面白くないはずがない。とくに人間を将棋の駒のように動かす人事ほど、権力者を喜ばせるものはない。雪斎がどこまで今川家の人事を操り、また彼自身が喜びを感じたかわからないが、今川家における経営の重要施策は、ほとんど彼が牛耳るようになってしまった。
いかにダミーとはいいながら、彼自身が坊主頭にはちまきをして、鎧を着て戦場の指揮をとるくらいだから、本人自身も結構ノッていたに違いない。まったく嫌だったら、そんなまねはしないだろう。
一方、リーダーシップのとり方でいえば、彼は、うしろのほうにいて、部下に、
「あそこへ行け」
というタイプではない。自分が真っ先に危険なところに行って、
「ここへ来い」
というタイプである。
戦国のリーダーは、やはりこういうタイプでないと部下はついてこない。そういう点、雪斎は、リーダーとしてもなかなかの力を持っていた。
このころ、三河の松平広忠が、隣国の織田信秀と戦って敗れた。信秀の攻撃はすさまじく、広忠の本拠である岡崎城にも攻撃を仕掛けてきた。そこで広忠は、急遽、
「どうか、助けていただきたい」
と今川義元に泣きついてきた。これをきいた義元は、
「どうしようか」
と雪斎に相談した。雪斎は「そうですなあ」とあごをなで、こういった。
「三河を制圧するためには、何か担保を取っておいたほうがよろしいでしょう。広忠には確か竹千代という子供がいたはずです。これを人質に出せば援軍を送るという条件で、いかがでしょうか」
「名案だ」
雪斎のいうことはなんでも名案だと考える義元は承知した。そこで、今川家の使いが、このことを松平家に告げた。松平広忠は承知した。そこで、彼の息子である竹千代(のちの徳川家康)が、人質として駿府(静岡)に連れてこられることになった。ところが、竹千代が駿府へ向かう途中、彼の叔父である戸田康光という男が、いきなり竹千代を奪った。そして、こともあろうに敵方である織田信秀のところに連れていってしまった。このとき戸田は莫大な賞金をもらったという。そのために、
「叔父でありながら、戸田は甥を金で売った」
といわれて評判が悪い。
このことをきいて、雪斎は怒った。
「戸田も戸田なら、織田も織田だ。人質を金で買うとは、いったい何事だ」
そう考えると、改めて先年の小豆坂の敗戦が思い出された。頭にきた。あのときは、今川義元が指揮をとったために負けてしまった。雪斎は心を決めた。
(よし、おれがリターンマッチをしてやる!)
雪斎は出陣した。織田信秀軍も出てきた。両軍は小豆坂で激突した。ところが人間というのは恐ろしいもので、戦いというのはやはり怒っているほうが強い。この戦いでは雪斎のほうが怒っていた。そして策をめぐらし、彼は、
「おれが正面から織田軍にぶつかる。二隊、三隊は、左右の横からやっつけろ」
と命じた。別にむずかしい作戦ではなかったが、この作戦が成功した。坊主頭をふり立てて突入してきた雪斎の軍勢に、織田方は、
「あれ?」
と驚いた。一瞬たじろいだところを、今度は側面から攻撃された。織田信秀軍は散々に負けて、尾張に敗走した。
これが天文17年(1548)の出来事で、天文20年、織田信秀は急死した。前後するが、天文18年には松平広忠も突然死んでしまった。広忠の場合は、部下に殺されたのだという。つまり、
「このトップは、トップとしての能力がない」
と見限った部下たちが、命を奪ってしまったのだという。恐ろしい世の中である。駿府にいた少年竹千代は、この報告をどのような気持ちできいただろうか。
織田家は、信秀が死んだあと、ポスト信秀をめぐってゴタゴタ続きになる。そこで雪斎は、
「一挙に尾張に討ち入りましょう。そして、信長という小僧を平らげ、尾張まで今川家の領国にし、いずれは天下統一への道を歩みましょう。京は間近です」
といった。お坊さんにしては、かなりの積極策である。義元はその気になった。そして、雪斎について、少しずつ軍学書を読みはじめた。
天文23年(1554)、小田原の北条氏康が、突然駿河国に入り込んできた。すると、それを待っていたように甲斐の武田信玄が出陣してきた。そして、北条軍と武田軍は吉原川をはさんで向かいあった。驚いたのは今川義元である。
「いったい、なんで北条と武田が、おれの領内で戦争するのだ?」
雪斎にそうきいた。雪斎にもわからない。軍が行動するのは、ある種の行動原則に基づいているので、その原則が、今川家にかかわりあいのある場合もあれば、ない場合もある。北条は北条で、武田は武田で、それぞれの運動法則によって動くから、こんなことが起こるのでしょう、とはなはだ客観的な判断を話した。義元には、そんな理屈はわからない。
「とにかくなんとかしてくれ」
といった。
そこで、雪斎は斡旋に乗り出した。
そして、北条氏康、武田信玄、今川義元の三者の間に平和条約を結ばせた。
武田信玄は、このころ上杉謙信との間がいよいよ急を告げていたし、北条氏康も、そういう状況を見ながら、虎視眈眈と関東をねらっていた。いずれにしても、このころの武田信玄も上杉謙信、北条氏康も、主として関東地方に目を向けていたのである。京に目を向けていたのは、わずかに今川義元だけであった。したがって、雪斎としては、有力な戦国大名の関心を関東地方に向けさせておいて、その隙に主人の今川義元をなんとかして京に入れ、天下を取らせようと考えていたのだ。そのためには、ここで戦争が起こるのはまずかった。この和議は成立した。雪斎はほっとした。そして、
「いよいよ、京へ上る日がまいりましたな」
とニッコリ笑った。
「うむ.このあとも、よろしく頼む」
義元も笑ってうなずく。が、そうは事はうまくいかなかった。というのも、翌年の弘治元年(1555)閏10月10日に雪斎が死んでしまったからである。そして、馬鹿にしていた尾張の織田信長という若い小僧が、どんどん力を伸ばしはじめた。彼は、自分の邪魔をする一族を次々と倒し、まず織田家の内部を固めた。そうしておいて今度は美濃国に攻め入って、妻の父を殺した斎藤氏と果敢に戦った。勝敗は簡単にはつかなかったが、いずれにしても織田信長の名がどんどん高まり出していた。
今川義元はあせった。が、いまは相談すべき雪斎というナンバー2がいない。雪斎がナンバー2になってからは、みんなの依存心が雪斎に集中してしまって、雪斎の跡を継げるようなナンバー2が育っていない。
義元は慨嘆した。
「雪斎がいてくれたらなあ」
いなくなってはじめて雪斎の存在価値がはっきりわかったのである。
それから5年後に、今川義元は京に向かって進撃する。軍勢は4万とも2万5千ともいわれた。あるいは2万5千を4万と水増ししてPRしたのかも知れない。しかし、有名な桶狭間の合戦で、若僧と馬鹿にしていた織田信長に負け、首まで取られてしまった。今川軍は、駿河を目指して敗走した。
しかし、このとき、
「逃げるな! 逃げるな!」
と敗走する兵を押しとどめ、反転して、織田勢と勇敢に戦った武士もたくさんいた。また、決死の覚悟で織田の陣にやってきて、
「どうか、せめて主人の首だけでもいただかせてください」
と頼んだ武士もいた。
勝ち誇った織田の軍勢は、こういう武士たちを、
「殺せ!」
といきまいたが、信長が止めた。信長は、今川家のそういう武士たちに感心した。そこで、
「作法によって、首は数日さらす。しかし、その後は丁重に送り返す。それまで待っていてくれ」
といった。
さらす期間が終わって、信長はその武士たちに首を返した。そして、そのとき数十人の坊主を一緒につけたという。数十人のお坊さんの読経に囲まれて、今川義元の首は、無事に静岡に戻ってきた。今川家にもそういう勇気のある武士がたくさんいたのだ。これは、今川義元にとってせめてもの救いであった。しかしそれは、今川義元がナンバー1として立派なリーダーシップをとっていたからそうなったのか、それともナンバー2の雪斎が普段からそういうしつけをしていたのか、そこはよくわからない。
いずれにしても、この今川義元と雪斎の例は、
「たとえナンバー2でも、ナンバー1と同じような行動を取りすぎると失敗する」
ということと、もうひとつは、
「ナンバー2も普段から後継者を養っておかないと、不測の事態が起こったときに困る」
ということをはっきり示したといっていいだろう。その意味では今川義元もだらしがなかったが、雪斎自身もまた少し調子に乗り過ぎていたのではないかと思う。今川義元がなんでも任せたとしても、雪斎も自重して、
「いや、私のやることはここまでです」
といって、義元に委ねられた権限を返すか、あるいは返さなくても、自分なりにひそかに後継者を養っておいたなら、こんな無残な滅び方はしなかっただろう。
現在でも、
「余人をもって代えがたい」
とよくいわれる。これに対して、
「いや、そんなことは絶対にない。もし、余人をもって代えがたいという存在があるとすれば、人間は死ぬことなんてできないじゃないか。にもかかわらず、多くの優秀な人材が死んでいっても、あとはつつがなく物事が運ばれているではないか」
という説もある。その説も間違っているとは思わないが、しかし今川家の例を見ると、雪斎がいなくなったあとは完全にコケてしまっている。その意味では、ナンバー1だけでなく、ナンバー2の後継者づくりも欠かすことができないといっていい。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月21日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】






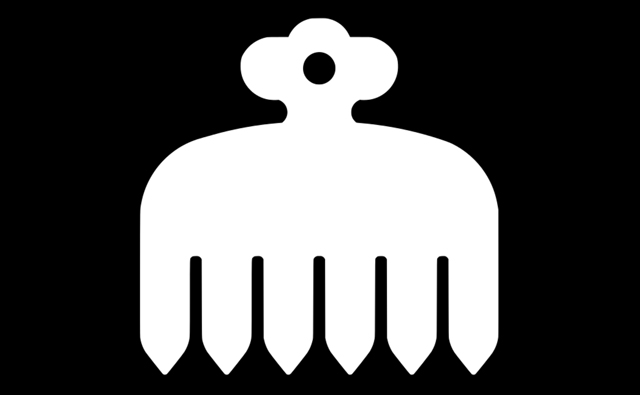

.jpg)


