「恵まれた環境に文明は生じない」日本で高度な文明が生まれなかった背景
2025年10月08日 公開

なぜ日本では四大文明のような高度な文明が誕生しなかったのか――。本稿では、その背景を比較し、日本に欠けていた「ある一つの条件」について、書籍『教養としての「世界史」の読み方』より解説します。
※本稿は、本村凌二著『教養としての「世界史」の読み方』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
文明発祥に必須な条件とは?
何をもって文明と言うのか、いわゆる文明の定義には、いろいろな意見があると思いますが、よく言われるものの一つに「文字の発明と使用」があります。
四大文明でも、メソポタミアでは楔形文字、古代エジプトではヒエログリフ、インダス文明ではインダス文字、そして黄河文明では漢字のもととなった甲骨文字が、それぞれ発明・使用されています。
でも日本は、大陸から漢字が伝来するまで文字を持たなかったためか、太古の歴史区分に土器の名称が用いられているためか、日本人は文明の発祥と聞くと土器の使用を思い出します。
もし文明と土器がそれほど密接に結びついているのなら、世界最古の土器が出土したところが世界最古の文明が生まれた場所だということになります。
では、その世界最古の土器が出土した場所とはどこなのか。
実は日本が、その一つなのです。
--------------------------
現在、世界最古と考えられる土器の一つが、青森県大平山元(おおだいやまもと)遺跡の縄文土器だ。放射性炭素年代から推定すると、約1万6千年前。これらのことから、多くの研究者は、遅くとも1万5千年前には、日本列島で土器が使われていたと考えている。
ところが、他地域の最古の土器をみると、南アジア、西アジア、アフリカが約9千年前、ヨーロッパが約8500年前──。学校で習ったいわゆる「四大文明」の故地と比較しても、日本は飛び抜けて古い。
(2009年10月3日『朝日新聞DIGITAL』
「日本の土器、世界最古なの?」〈宮代栄一〉)
--------------------------
四大文明より古い時代から日本では土器が使用されていました。しかし、四大文明以前の日本に、それに匹敵するような高度な文明は生まれていません。
なぜ、日本では高度な文明が生まれなかったのでしょう。
それは、文明の発祥に必要不可欠なある条件が日本にはなかったからです。
「乾燥化」が文明を生んだ
文明発祥に必須なもの、それは「乾燥化」です。
事実、四大文明など文明が発祥したとき、世界では大規模な乾燥化が進んでいました。
これはとても重要なことなのですが、あまり指摘されていません。だから、なぜ前5000年から前2000年にかけて各地で文明が発生したのか、という問いにはっきりと答えられないのです。
実際、社会人向けに書かれた世界史の教科書『もういちど読む山川世界史』(「世界の歴史」編集委員会編・山川出版社)には、なぜ文明がこの時期に生まれたのかについては、ほとんど書かれていません。
--------------------------
文明の諸中心
前3000〜前2700年ころ、農耕文化は、ティグリス川・ユーフラテス川流域に多くの都市国家をうみだし、ナイル川流域でも前3000年ころ統一国家がうまれた。このオリエントの文明は東西に伝わり、西方ではエーゲ文明の発生をうながし、東方インドでも前2300年ころインダス川流域に青銅器をもつ都市国家が成立した。
また、中国大陸北部の黄河流域の黄土地帯でも、前5千年紀(前5000〜前4001)に磨製石斧と彩文土器(彩陶)を特色とする農耕文化がおこった。
--------------------------
なぜ明記されていないのかわかりませんが、現在、学者のあいだでは、文明の発祥に乾燥化が深く関わっていることは、ほぼ認知されています。
事実、前5000年頃から、アフリカの北部から中東、ゴビ砂漠を通って、中国に至るラインで、乾燥化が始まっています。
アフリカ北部に広がる広大なサハラ砂漠は、地球環境の変化に伴い、何度も湿潤と乾燥を繰り返してきた地域です。現在は広大な砂漠ですが、現在にいたる砂漠化が始まったのは前5000年頃と考えられています。それ以前のサハラは緑に覆われていたことから「グリーンサハラ」と言われています。
サハラに今も残るタッシリ・ナジェールの洞窟壁画を見ると、当時、湿潤な気候風土の中で人々が生活していた様子をうかがい知ることができます。今でこそ、あんな砂漠でどうやって生活していたのかと思いますが、当時は水も動植物も豊かなグリーンサハラの時代だったのです。
こうしてアフリカや中東の乾燥化が進んでいったことで、そこに住んでいた人々が水を求め、大きな川や水の畔に集まっていきました。それがアフリカの場合はナイル川の畔であり、中東の場合はティグリス・ユーフラテス川の畔であり、インドの場合はインダス川の畔であり、中国では黄河や揚子江といった大きな川の畔だったのです。
いろいろな水の畔に人が集まってくるわけですが、その中でも特に立地条件のいいところに人は集中していきます。その条件のいい場所というのが、ティグリス・ユーフラテス川の畔やナイル川の畔だったということです。
乾燥化と、それに伴う人々の水辺への集中が、なぜ文明発祥につながるのかというと、少ない水資源をどのようにして活用するか、ということに知恵を絞るからです。
つまり、環境的に恵まれなくなったから文明が生まれた、と言っても過言ではないのです。
まず、人の生存に欠かすことのできない「水」が非常に大きなファクターとなり、人口が一カ所に集中することで、それまで小さな村ぐらいでしかなかった集落が都市的な規模になる。その結果、水争いを防ぐための水活用システムが生まれ、そうしたことを記録する必要から文字が生まれたのです。
実際、古代の記録は、取引記録など実務的なものが多く見られます。文字は必要だから生まれてきたのですから、なぜ必要になったのか、ということを追究するには、何が記録されているのかを見るのが一番です。
どの地域でも、どの時代でも、歴史を知るための共通項は、「なぜ」を追究していくところにあるのだと思います。
なぜ文明が生まれたのか。
なぜ文明は都市と結びついているのか。
なぜ都市は生まれたのか。
なぜ人々は一カ所に集まったのか。
こうして「なぜ」を追究していったとき、文明発祥に至る一連の流れの大本にあるのは、「乾燥化」だということです。
恵まれた環境に文明は生じない
乾燥化が文明発祥の大本にあったということがわかれば、なぜいち早く土器を生み出した日本が、なかなか「文明」と言える段階に至らなかったのかが見えてきます。
それは、日本では乾燥化が起きなかったからです。
大きな文明が生まれたところというのは、大河があるものの、その周りは乾燥化が進んでいます。
しかし、日本は島国であるにもかかわらず、水がとても豊かです。
自然環境に恵まれ、乾燥化が起こらなかった日本では、人口の集中も起きず、少人数の集落で安定した社会が長く営まれていたと考えられます。実際、縄文時代は一万年もの長きにわたっています。
日本がなかなか「文明」という段階に至らなかったのは、水が豊かすぎて水活用システムをつくる必要がなかったから、そして、人口の集中が起きなかったからだと考えられます。
稲作が伝わったときも、日本では灌漑にさほど苦労しませんでした。何しろ、そこら辺を流れている川から、ちょっと水を引っ張れば、それで済んでしまうのです。
今でもそうですが、日本の悩みは、むしろ水が豊かすぎることです。水が豊かだということは、それだけ湿度が高いということでもあります。湿度が高すぎる環境は、物が腐りやすくなったり、カビが繁殖しやすくなったりと、実はとても厄介なものなのです。
ですから古代の日本では、収穫した作物を保存するために、高床式の倉庫をつくるなど湿気対策にさまざまな工夫がなされました。作物の保存だけではありません。奈良時代の宝物庫として知られる正倉院は、校倉造と呼ばれる特殊な形式の建物ですが、これも宝物を湿気から守るための工夫だったと言われています。
日本は水に恵まれていたがゆえに、なかなか「文明」に至りませんでした。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月18日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

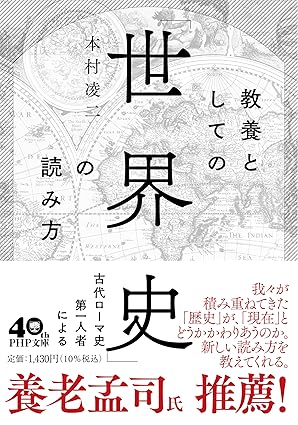





.jpg)


