マリアナ沖海戦での敗因となった 「アウトレンジ戦法」の真相とは?

1944年6月19日、戦闘の初期段階で日本軍の爆弾が、米空母バンカーヒルのすぐ横で爆発した(Naval History and Heritage Command, Washington, DC)
マリアナ沖海戦で日本海軍が大敗した原因は何だったのか。呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)の戸高一成館長は、その要因の一つとして、機動部隊の「生みの親」ともいえる小沢治三郎が実行した「アウトレンジ戦法」を挙げる。書籍『日本海軍 失敗の本質』より解説する。
※本稿は、戸高一成著『日本海軍 失敗の本質』(PHP新書)を一部抜粋・編集したものです。
機動部隊の「生みの親」
小沢治三郎は、航空に関して先見の明があった。もとをたどれば、小沢は水雷長や水雷戦隊参謀などを歴任した「水雷のプロ」である。そんな彼が、航空関係者から学び、自分なりの航空戦術を考え、海軍大臣に進言したのは昭和15年(1940)6月のことである。それは、航空機を主要な決戦部隊に位置づけ、航空母艦の集中運用を図るというものであった。
小沢の構想した「将来あるべき機動部隊の姿」は、昭和16年(1941)につくられた第一航空艦隊そのものといっても過言ではない。その意味で、小沢は機動部隊の「生みの親」といえる。これを機に、小沢は日本の航空戦術の専門家と見なされ、以降、「小沢を機動部隊の指揮官に」と期待する声は様々な形で出た。特に昭和17年(1942)のミッドウェー海戦の敗北後からソロモン海戦の頃まで、小沢を機動部隊長官に推す声は多い。
しかし、小沢が第一機動艦隊司令長官に就任するのは、太平洋戦争が始まってから2年余りが過ぎ、戦局が悪化していた昭和19年(1944)3月である。
なぜ、遅かったのか。その原因は、年功序列優先の人事制度にある。日本海軍では、指揮下に自分より先任(上位)の人間がいてはいけないとされたので、小沢を長官にすると、彼より先任の将官を更迭しなければならない。この硬直した人事制度により、機動部隊指揮官の就任が遅れたのだ。
もっとも、就任当時の第一機動艦隊は真珠湾やミッドウェーのときを上まわる数の空母を有し、陸上航空部隊も使うことができたので航空機の数も多い。また、若い搭乗員の練度は低いものの、ハワイ、ミッドウェー、ソロモン海戦を生き残ったベテランがまだおり、航空隊も十分に機能していた。
戦況は芳しくないが、戦力の規模でいえば、日本海軍の歴史上、最も有力な機動部隊だった。うまく使えばきちんと戦えるだけの戦力を揃えたのだから、決戦に耐え得る態勢であったといえるだろう。そのため、マリアナ沖海戦に臨む第一機動艦隊に対して、「決戦を挑めば勝機はある」と海軍の上から下までが信じ、「これで一気に挽回できる」と、期待を抱いていたのである。
「アウトレンジを軍令部はよく理解していなかった」
昭和18年9月、東條英機首相はマリアナ諸島を「絶対国防圏」とした。特に、サイパン島が重要であった。ここをアメリカに取られると、航空機による本土攻撃が可能になってしまう。その意味で、マリアナを失うことは、日本本土を取られることに等しかった。
実際アメリカも、日本をダイレクトに攻撃できる足場としてサイパン島を狙っていた。したがって、日米双方が「決戦」という認識をもって戦ったのが、マリアナ沖海戦である。日本の海軍史上最大規模の機動部隊を預かる小沢治三郎としては、アメリカ軍を押し返し、当時の言葉でいえば「不敗体制」にもっていこう、と考えていたはずだ。
昭和19年6月、第一機動艦隊がマリアナ海域へ進出したアメリカ軍と交戦した。このとき、日本の軍令部並びに連合艦隊から出た作戦命令は、「航空攻撃は、敵母艦の航空攻撃圏外より、大兵力をもって昼間先制攻撃を行なうを重視する」である。
「敵母艦の航空攻撃圏外より」とは、アウトレンジ戦法を指示している。これは、「敵の兵器の射程外から攻撃することで、自分は被害を受けずに敵を叩く」というものだ。理屈の上では有利に見えるが、実際はあまり効果的ではない。
「兵器は60パーセント程度の能力を使え」といわれる。射程距離の長い戦艦大和の大砲を敵の弾の届かないところで撃ったとき、距離的には届くかもしれないが、まず当たらないのだ。遠くまで飛ばすことと、命中することは、意味が違うのである。しかも、航空攻撃の場合は、砲撃とは性質が異なる。航空機の搭乗員は長距離を飛び続け、心身ともに疲労した状態で戦い、その後、疲れ果てて帰ってこなければならない。「航空攻撃は敵母艦の航空攻撃圏外より」という命令は、航空機に乗る人間のことを考えていないのだ。
日本海軍には、戦闘を兵器の数字でしか考えない傾向があり、航空機の機数と能力値を見て、1000キロメートル先を攻撃して帰ってこられる航続力があれば、1000キロ先を攻撃する計画を立てたりする。
アウトレンジ戦法は、搭乗員のストレスや疲労という「人間の要素」を見落として立てた作戦であり、それでは成立しないことはいうまでもない。空母部隊にとっては攻撃する航空部隊が戦力であり、母艦が生き残ったとしても攻撃手段である航空機が失われたら意味がない。大事にすべきは、航空部隊そのものである。
このアウトレンジ戦法は小沢が唱えたとされるが、気になるのは、小沢の下で働いたことがある軍事史学者の野村実氏が、戦後、「小沢のアウトレンジを軍令部はよく理解していなかった」と書き残していることだ。
それは、小沢と連合艦隊や軍令部との間に、溝があったことをうかがわせる。射程4万メートルの九三式魚雷の破壊力は、戦艦の主砲弾に匹敵、あるいはそれ以上と考えられた。この魚雷が登場したとき、水雷のプロである小沢は、九三式魚雷を使って先制攻撃をかけ、敵を攪乱する戦術を考えたようだ。
つまり、小沢にとっての「アウトレンジ」とは、先に敵を発見して部分攻撃するというものであり、本格的な戦いは全勢力を揃えた接近戦を想定していたのではないか。
一方、軍令部や連合艦隊は「アウトレンジ」を文字通り「全力をもって、敵の射程外から攻撃する」と捉えた。野村氏の記述がこの違いを暗示しているとすれば、小沢と連合艦隊軍令部の間で、アウトレンジの考え方が整合されないまま、作戦が始まってしまったと考えられる。
マリアナ沖海戦の敗因

日本軍の攻撃に向かう艦上攻撃機TBFアベンジャーとSB2Cヘルダイバー(National Archives,Naval History and Heritage Command, Washington, DC)
小沢が第一機動艦隊司令長官に就任したのは、マリアナ沖海戦の3カ月前である。アウトレンジの採用に際して、作戦を練る時間が足りないままで実施に踏み切ったのであれば、それは敗因の一つといえるだろう。
また、作戦命令の「大兵力をもって昼間先制攻撃を行なう」という部分もおかしい。白昼堂々、大編隊を組んだら、敵に発見されやすくなるのは明らかだ。
パイロットが十分に揃っているアメリカは、前哨戦でも偵察機を飛ばし続け、常に空に飛行機がいる状態をつくっていた。さらに艦隊のレーダーと無線通信などを活用し、濃密な防空システムを完成させていた。これによって防空戦闘機を有効にコントロールし、長距離を飛行してきた日本軍機を苦もなく撃墜したのである。
アメリカ軍はその一方的な展開を、「七面鳥狩り(ターキーシュート)」と呼んだ。モールス信号を主に使っていた日本軍に対し、アメリカ軍が、即座に意志が通じる電話機を自由に使えたことは大きな差を生んだ。モールス信号であっても、時間的な余裕があれば、「何度の方向に何機の編隊が来る」という連絡はできる。だが、即応性という点では電話には及ばない。
アメリカの技術は日本の想像を超えていたわけだが、少なくとも日本は、アメリカがレーダーを有効活用していたことを知っていた。当然、早い段階で日本の攻撃隊が発見されることは、十分考え得ることである。
大編隊での攻撃を計画した作戦担当者は、マリアナ沖海戦敗北の最大の責任者というべきだろう。水雷の本質は夜戦であり、水雷出身の小沢が、昼間の大編隊攻撃を考えるとは思えない。だが現実には、第一機動艦隊は白昼堂々、大編隊で攻撃を仕掛け、約四百機を落とされ、大敗北を喫した。
しかしながら、それをもって小沢が無能だったとは、一概にはいえないだろう。
日本海軍には、ミッドウェー海戦ですべての空母を失ったことへのトラウマがあり、空母1隻が沈んでも容易に補充できないため、「空母を惜しむ」という意識があった。事実、当時の日本には、作戦で消耗した兵力、航空機を直ちに補充できる力はなかった。このような現実を受け、忸怩たる思いはあったものの、小沢は味方の消耗を恐れて、アウトレンジ作戦を採用したのかもしれない。
日本の指揮官は皆「兵力を失えば補充がない」というプレッシャーを抱いており、指揮官だけの責任とはいえない背景があるのだ。
惜しむらくは、小沢が上から来た命令通りに作戦を実行したことだ。厳密にいうと、連合艦隊の命令は、あくまで「この戦法で敵を撃破するのがよい」という願望混じりのコンセプトであり、命令ではないのだ。細かい戦術指揮は現場の長官が権限をもつ。
敵機動部隊を撃破することが目的であり、これを達成するためには自分の作戦を混ぜても問題ないのである。そのために、長官の部下に参謀がいるのだが、小沢は、悩みながらも連合艦隊の命令を忠実に受け止めたのだろう。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

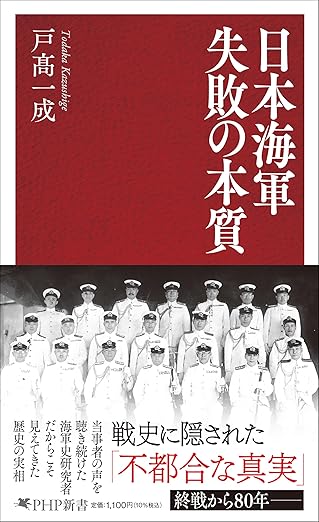





.jpg)


