『源氏物語』の時代は「一夫一妻制」だった? 男女関係におおらかな平安貴族の結婚制度

大河ドラマ『光る君へ』を見ていると、当時の結婚制度がどうなっているのか、気になる方も多いだろう。そして結婚制度を知ることは、『源氏物語』を読解するうえでの鍵ともなる。著述家の古川順弘氏が、『源氏物語』の時代の結婚制度について、解説しよう。
※本稿は、古川順弘著『紫式部と源氏物語の謎55』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです
通い婚が原則だった時代
現代人が『源氏物語』を読もうとするとき、まず理解の障壁となるのが難解な文章・文体だが、これに加えて読者を戸惑わせるのは、作中では当たり前のこととして描かれている、その時代の社会制度や習俗だろう。言い換えれば、『源氏物語』の時代、平安時代の社会のしくみや慣習をある程度理解しておかないと、物語の面白さをよく味わえず、真意を誤解してしまうことにもなりかねない。
そこでここでは、『源氏物語』を読解するうえで鍵となる平安時代の社会制度・慣習のうち、最も根本的で重要な「結婚」について解説しておきたい。
まず、古代日本の貴族層の結婚制度を、昭和戦後にこの分野で先駆的な研究を行った高群逸枝の所説にしたがって概観してみよう。
奈良時代から平安時代前期にかけては、男(夫)は夜に女(妻)の家を訪ね、朝起きると自分の家に帰るという「妻問い婚」が主流であった。これを「前婿取婚」と言う。いわゆる通い婚で、この場合、生まれた子供は妻方の一族が養育することになる。
平安中期になると夫の通いがなくなってゆき、夫婦は結婚当初から妻方の家に同居する。その後、妻の親からその家を譲られて(妻の親は他に移る)、あるいは妻または夫の親が提供する家に移って、独立した家庭を築く。これを「純婿取婚」と言う。
平安後期になると、夫婦は結婚当初から独立し、妻方の親が提供する仮居・新居に住んだ。これを「経営所婿取婚」と言う。
しかし、この高群説に対しては、高群は自らが構想する母系制論に矛盾する資料を意図的に排除していたとする批判があり、前婿取婚期には夫婦同居のケースもみられたとか、平安時代には嫁取婚の夫方居住も行われていたとする指摘もある。
議論のあるところだが、藤原道長が正妻源倫子との結婚を機に、倫子が住んでいた土御門殿に居住して、純婿取婚の形態をとったことは事実である。総じて、平安時代の貴族層の結婚では、妻方の男親が夫婦の後見として重要な役割を担い、その身分や経済力が娘夫婦の将来を大きく左右したということは言えるだろう。
本当は一夫一妻制だった平安時代
一般に、平安時代の人びとは男女の性に対しておおらかで、貴族層では夫が同時に複数の妻をもつ一夫多妻制が公認されていたととらえられてきた。
ところがこれに対して、国文学者の工藤重矩のように、法制度上はあくまで一夫一妻制であり、夫は妻以外の女性を「妾(しょう)」という形で配偶していたにすぎないとする見方もある(『平安朝の結婚制度と文学』)。この場合の「妾」とは、いわゆる「めかけ」とイコールではない。「正妻以外の妻」「第二夫人・第三夫人......」に近い意味合いで、彼女たちが生んだ子供が婚外子扱いされることはない。
ここでの「妻」と「妾」の違いを「正妻」と「側室」のそれに置き換えることもできなくもないが、建前としては重婚は不可で、一時点で正式に「妻」を称することができる女性はあくまで一人に限定され、一夫一妻であったというところが、この見方のポイントである。
そして工藤は、平安期史料にみえる「嫡妻」「本妻」「妾妻」の語の違いについて、およそ次のように解説している。
男Aがまずはじめに女B子と結婚して彼女を「嫡妻」とした。いわゆる正妻である。ところが、子が生まれないので離別し、別の女C子と結婚した。この時点でB子は「もとの妻」ということで「本妻」と称されるようになり、C子が嫡妻となる。それでもなお子が生まれなかったのでAは新たにD子を娶った。この時点でAがC子と離別していなければ、D子は「妾妻」すなわち妾となり、離別していれば嫡妻となる。
とはいえ、平安時代の貴族たちの間で、実質的には一夫多妻の婚姻形態が横行していたことは確かである。この場合、夫人たちが揃って同居するということはなく、男はふだんは正妻(妻)と同居し、それ以外の夫人(妾)のもとへは個別に通うという格好を多くとった。ちなみに、正妻は邸宅の「北の対」に住むのが慣例だったので、しばしば「北の方」とも呼ばれた。
紫の上は妻だったのか、妾だったのか
『源氏物語』をみると、光源氏はまずはじめ、左大臣家の長女である葵の上と結婚する。葵の上は源氏の正妻であり、源氏は婿取婚スタイルで彼女の家へ通っている。関係が順調であればやがて二人は同居することになっただろう。
しかし、気が合わなかったので源氏の通いは間遠になり、その代わりに六条御息所や末摘花のもとに通ったり、空蟬や夕顔との逢瀬を楽しんだりすることになったのである。このうち、空蟬は人妻であり、夕顔とはゆきずりの恋だが、六条御息所や末摘花は源氏の「妾」とみなせなくもない。花散里や明石の君も妾とみることができるかもしれない。
問題は紫の上である。源氏が自邸で愛育した紫の上と契りを交わすのは、葵の上の急逝後だ。したがって、紫の上は葵の上に代わって正妻の座についたと思いたいところだが、『源氏物語』の作者は紫の上を正妻として明記することを慎重に避けている。
やがて女三の宮が源氏のもとに降嫁してくるのだが、彼女は明らかに正妻として迎えられている。女三の宮が皇女で、身分の高い女性であったからだ。この時点で、紫の上は明らかに「妾」である。しかし、女三の宮が出家して事実上源氏と離婚状態になると、紫の上は正妻格の待遇を受けるようになる。
一夫多妻的な形態がごく普通で、それをとくに不道徳なものとして咎める風潮もなかった時代だったとはいえ、女性の側からすれば、夫の愛を自分一人につなぎとめておきたいと思うのは、ごく当然のことであったはずだ。そんな平安朝の女性たちが抱える悩みを描き出したのが『源氏物語』だったとも言えるだろう。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月13日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

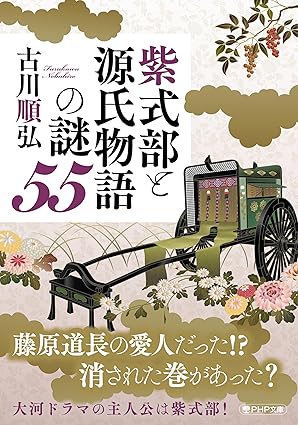





.jpg)


