名将・今村均は、自決を覚悟した軍司令官をどうやって制止したか――「ガダルカナル島撤収作戦」の内側で起きた真実
玉砕か、撤退か――大本営の決定を待つなかでの究極の判断
一方で、前述したように中央ではガダルカナル島を巡って参謀本部と陸軍省の対立があり、作戦部長の田中新一が南方軍司令部附に、作戦課長の服部卓四郎が陸相秘書官に更迭されるという事件が起こった。
さらには、12月12日、現地海軍側からもガ島奪回について次のような申し入れがあった。申し入れを行なってきたのは、第八艦隊参謀の神重徳大佐である。
《今や海軍はガ島確保の自信はない。大本営からも近い中に命令が来るであろう。ガ島に対しては、従来要求せられている次期攻撃計画とともに、撤退計画を立案することが必要と考える》(井本熊男『作戦日誌で綴る大東亜戦争』より)
海軍の方では、ガ島をすでに諦めていたのである。ただし、今村の方にもガ島を簡単に諦めるわけにはいかないという理由があった。
「全般のため一部を犠牲にする」ことを「戦場の常」として理解はしていたが、それでも感情の上でガ島3万人の兵士の餓死を見過ごすわけにはいかない。いざとなれば、自らガ島に赴いて兵士と運命を共にしようと決意していた。
ガ島の状況については、大本営派遣参謀として第十七軍にいた杉田一次からも説明があった。杉田は説明を報告書の形にして方面軍首脳部に配り、ガ島奪回の望みはなく、「次善の策」を検討すべきとして自分自身で説明もしたが、「奪回」の命令を受けている今村らには受け入れられなかった。
それでも、杉田は今村について、《極めて困難な立場におかされていた。出征に当り天皇より直接「ガ島」奪回の大命をいただき、今や、これに基づき努力を傾注すべきや、或いは次善の策を講ずべきやの岐路に立たされたわけである》と理解していた。(杉田一次『情報なき戦争指導 大本営情報参謀の回想』)
12月下旬になると、新しく作戦課長となった真田穣一郎の一向がラバウルを訪れた。この時、方面軍参謀の井本は「個人としては〔ガ島奪回は〕相当難しいと思う」と率直に述べ、参謀長の加藤は「海軍はガ島に対して自信は無い」と海軍側が奪回を諦めているさまを強調した。そして今村は、次のように発言した。
《海軍は陸軍の航空に手頼りたいと云う気持ちになりあり。真に意外なり。ガ島は何れにしても至難、仍りて死中に活を求むるの策なきやを研究せしめつつあり。転換はこちら丈けで謂えるものに非ず。中央は海軍との関係をも考えられ、大局的に定められ度。唯如何なる場合に於ても「ガ島の者は捨てて了うのだ」と云う考を持たれずに、或時期に於て出来る丈けの人々を救出出来る様に考えて貰い度。之が漏れたら、ガ島の人々は皆一度に切腹して了うであろう。機密保持に注意あり度》(『戦史叢書』より)
右をみても、今村がガ島奪回の至難を十分承知していたことがわかる。そして、それ以上に「ガ島からの撤退」が難しいこともわかりながら、「見捨てる」という手段は避けようとしていた。
大本営で正式に決定されれば、一刻も早く、少しでも多くの兵士を撤退させようとしていたのである。参謀本部でも、人員の交代でその機は熟しつつあった。
撤退作戦への方針転換、それでも大きな損害を生じさせた戦い
年が明けて、1943(昭和18)年1月4日。前年田中新一の更迭で新しく作戦部長となった綾部橘樹がラバウルを訪れた。午後四時、今村の官邸にて綾部から「㋘号」作戦の説明を受けた。(防衛研究所蔵の佐藤傑少将の日記より)
「㋘号」作戦とは、他ならぬガダルカナル島撤退作戦である。今村に対して大陸命(大本営陸軍部命令)にて「第八方面軍司令官は海軍と協同し現に「ガダルカナル」島に在る部隊を後方要地に撤収すべし」と命令が出たのである(『戦史叢書』より)
「㋘号」作戦の打ち合わせはそれから連日行われた。1月10日、その作戦要旨がガ島の第十七軍司令官に打電され、12日には連絡のために佐藤、井本の二人の参謀がガ島へと渡った。
撤収作戦は、2月の初め、新月の夜を選んで行われる予定だった。それまでの期間は手段を尽くして食料を送り、現陣地から撤退場所まで(約20キロ)を歩けるだけの体力を付けさせなければならない。敵の襲撃を避ける重要性はもちろんのこと、それ以前にジャングルの中を歩けるだけの体力を回復させなければならなかったのである。
ガ島への糧食の輸送は、ドラム缶に物資を詰め、それを高速の駆逐艦で運ぶという手法がとられていた。「ネズミ輸送」と呼ばれたこの方法では大量の物資を送ることは出来なかったが、他に方法がなかったのである。
ガ島に上陸した井本らは、現地の悲惨な状況を目の当たりにした。道には腐乱死体が横たわり、すでに白骨化しているものもある。名ばかりの「野戦病院」の多くはただ地面に樹皮を敷き、椰子の葉か携帯天幕を気休め程度の雨避けにしている。杖を頼りに歩ける者はまだよく、多くは糞尿も垂れ流し状態であった。(井本熊男前掲書より)
井本は軍司令部に辿り着き、方面軍の方針を伝えた。ガ島からの撤退は2月1日を第一次とし、2月7日の第三次撤収をもって完了した。大規模な撤退作戦であったが連合軍側に気取られることなく、ガ島からの撤退を果たした。とはいえ、ガ島での損害は非常に大きなものとなった。生還者は1万人ほどだった。
生き残ったものの「責任」とは何か――今村均に、自決の赦しを乞う百武晴吉
ガダルカナル島の戦いは一つの島嶼を巡る争いに敗れたというだけではない。補給の軽視、火力不足、情報収集の不徹底など、日本陸海軍、特に陸軍の内包していた弱点を一気にさらけ出すような戦いだった。
撤収が終わったあとの2月10日、今村はラバウルの南方、ブーゲンビル島にあるブインに第十七軍将兵を見舞いにいった。青白く痩せ細った兵隊を見た今村は、「生ける死屍」という言葉を想像せざるを得なかった。百武軍司令官は余人を交えず今村と話がしたいといい、夜分、今村のもとを訪れた。
「部下の3分の2を斃し、遂に目的を達せず、他方面戦場から閣下までを煩わし、事態を収拾していただいたような戦例は我が国の戦史上にはないことです。武人として、こんな不面目のことはありません。ガ島で自決すべきでありましたが、生存者1万人の運命を、見届けないで逝くことは、責任上許されないと思い、恥多いこの顔をお目にかけた次第です。恐れ入りますが、今後の始末は、どうか方面軍でやっていただき、私が敗戦の責任をとることをお認め願います」
百武は、己の責任の重さを十分に自覚し、ガ島よりの撤収が終わった以上は、自らの命を断つことの赦しを今村に乞うたのである。
「お気持はよくわかり、自決して罪を詫びることも、意義があります。お止めはいたしません。唯その時機につき、参考のため私の考えを申しておきます」
そうして今村はガ島の「英霊のため」後世に残すための記録を書くべきこと、ガ島の死者、特に餓死者は軍部中央部の過誤によって起きたこと、英霊たちの死の記録をきちんとその遺族に伝えること、そしてかつて乃木希典が連隊旗を敵に奪われる屈辱を忍んで死期を遅らせたことを述べ、「どうか自決の時機の選定を、熟考されることを希望します」と結んだ。
百武は涙を流してこれを受け入れ、時機を選ぶことを約束した。
しかし、それから1年ほど経って不幸にも百武は脳溢血のために半身不随の身となってしまった。今村は、「あの時思い通りにさせていたら、こんな事にならんですんだのだろうに」と深く後悔している。
こうして、ガ島戦は多くの教訓を残して終わった。
※特に注記のない引用は、その多くを、今村均本人の回顧録『私記・一軍人六十年の哀歓』『続・一軍人六十年の哀歓』に拠った。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月04日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語


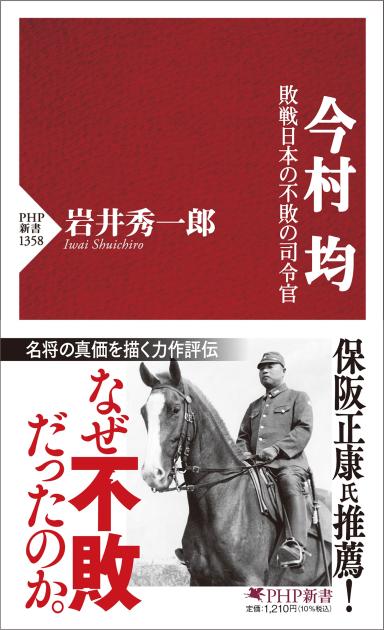





.jpg)


