陸軍大将・今村均は、敵中に孤立したラバウルで、10万将兵の命を守るために何をしたか
輸送途絶に備えた「自活」への道をつくる
今村は自給自足 ―以後は「自活」と呼ぶ ―を可能にするために、様々な手をうった。自活計画としてそれぞれの兵団が計画を作り、毎旬その進捗度を報告させることにした。
しかし、輸送船がラバウルに入ってくる間は実行が計画より遅れがちだった。人間の真理として、やはり「まだ物資の輸送がある」と考えると、どうしても安心してしまうのだろう。
とはいえ、現地で自活態勢が確立する前に輸送船が入って来られなくなるか、もしくは連合軍の反撃があるかもしれない。今村はラバウル付近7万将兵の3カ月分の食糧を軍需物資の倉庫に入れ、一切手をつけないようにした。
輸送された物資を使わず、すでに各部隊に配給された物資のあるうちに、農耕で収穫を得なければならないように仕向けたのである。これには今村自身も協力し、自ら2百坪ほどの土地を耕した。
今村から自活計画の調査研究の要請を受けた森田親三経理部長は、早速カナカ人の食生活を調べてみた。するとカナカ人は野生の果実芋類を採取して生活しており、耕地といえば数百名のオーストラリア人や華僑の食を支える農園と白人投資の椰子林バナナ園ぐらいしかないことがわかった。
これでは、10万の日本軍の食糧を賄うことは出来ない。そうなると、軍では独自にジャングルを開拓し、耕作するしかなくなる。
森田は陸軍省に農業技術者の派遣を依頼した。そうして送られてきた技術者、参謀と協力して自活計画を策定し、さらに農機具、労務者の派遣も頼んだ。
やってきた農事指導員は農業報国連盟50人、台湾奉公団170人、労務者はインド、インドネシア、広東などから4千人などだった。さらには、農作物の種子として陸稲、甘薯、なす、かぼちゃ、大豆、大根、小松菜、農機具は鎌、鋸、釜などである。
森田らは、次のような計画を立てた。(以下、ラバウル経友会編著『南十字星の戦場』より)
《(一)主食は陸稲と甘薯の作付により、副食は養鶏、養豚と野菜の栽培により、調味品は海水より採る塩とヤシの実から採る油をもって充足する。
(二)開墾耕作面積は一人当たり主食のため六十坪、野菜のため十五坪とし総面積2千5百町歩を目標とする。
(三)開墾耕作中主食は軍が一括して実施するも、野菜は各部隊ごとに行う。
(四)ラバウル地区において軍の経営する農場は、タボ、タブナ、ウナリマ、タウリル、ルナパウ、ウルプナの六箇所と予定し、貨物厰、兵站司令部が主体となって実施に当たる。
(五)以上実施のため必要とする農事指導員、労務者、種子、農具等は計画にもとづき3月上旬までに現地に到着するよう陸軍省に追送要求する。
(六)指導機関として、軍経理部内に「現地自活班」を設置し、軍参謀太田少佐を軍経理部兼務とし、軍経理部長の指揮下に入らしめる。現地自活班は野村一彦主計少佐を班長とし、見習士官(幹部候補生出身)四名を配属する。
(七)給養人員は、ラバウル地区陸軍6万5千人、海軍2万人、ボーゲンビル島1万5千人合計10万人と予定する。》
こうして、自活計画は立てられ、のちの輸送途絶に備えることになったのである。
「士気の維持」に気をつかい続けた今村大将
今村が、自活以外にも気をつかったことはある。その一つが、「士気の維持」であった。
当時第八方面軍で通信司令官だった谷田勇(中将)は、戦後角田房子に次のように語ってる。谷田によれば、今村は戦闘訓練に非常に熱心だったらしい。
《私のような通信関係の者まで多くの時間をとられ、まことに迷惑だった。なにしろ通信隊は連日非常に忙しい。それだのに大将は戦闘、戦闘といわれる。そこで私は、若い時から親しい38師団長の影佐さんに「敵はラバウルを飛び越えて、ニューギニア北部のホーランジアをとり、今はもっと西へ進んでいるじゃないか。今さら後方にあるラバウルなんかに、大犠牲を覚悟で来るとは思われん。今村さんは戦闘、戦闘といい続けているが、おかしいじゃないか」》(角田房子『責任』)
と聞いたという。すると、影佐はこれに答えて、
《おかしいと思うだろうが、あれは士気をたかめるためだ。もう敵は来ないと思えば、たちまち皆の気がゆるみ、秩序が乱れ、収拾のつかないことにもなろう。常に精神の緊張を保って、一致団結の集団生活を送らせるには、「敵が来るぞ」と軍司令官が叫び続ける必要があろう》(角田房子『責任』)
こうして、今村は最後まで戦闘訓練を怠らず、ラバウルの統率を全うした。ラバウルは日本側にとって重要拠点ではあったものの、連合軍はこの場所の攻略を避け、先に進んでいたのである。その理由の一つとして、「ラバウルを攻略した際の損害」が攻略した場合の利益に見合わないということが挙げられる。
ラバウルは敵の上陸こそ受けなかったものの、爆撃は何度も受けた。今村の司令部も被害を受けたことがあり、その経験から例え一トンの爆弾を落とされても耐え得る、洞窟の防空壕が作られた。
今村の司令部は昭和19(1944)年4月にラバウル市街から東南約10キロ地点に移った。「図南嶺」と名付けられたこの場所は、司令部の人員約1千人が収容可能で、作戦室、参謀部などが設置された。
病院施設もすべて地下化され、15カ所の病院は5千5百人が収容可能だった。すべて手作業で行なった洞窟陣地の建設であったが、その総延長距離は450キロにも及んだという。結果として、ラバウルの将兵は敵を迎えても相当な打撃を与えてみせる、という自信に満ち溢れた。
武器弾薬も工夫した。いくら食糧があり、地下壕をめぐらせても武器がなければ戦闘は出来ない。火薬類も製造することにした。例えば、黒色薬の材料となる硫黄。これは火山の火口から採取した。木炭は適当な木を指定して中隊が作業にあたり、硝石も技術将校が知恵を絞って集めた。こうして製造された火薬は、終戦までに4トンに及んだ。
こうして、輸送なき太平洋の孤島としては出来得る限りの準備を整えて「その時」を待ったラバウルだが、ついに敵を迎え撃つことなく敗戦を迎えることになったのである。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月04日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語


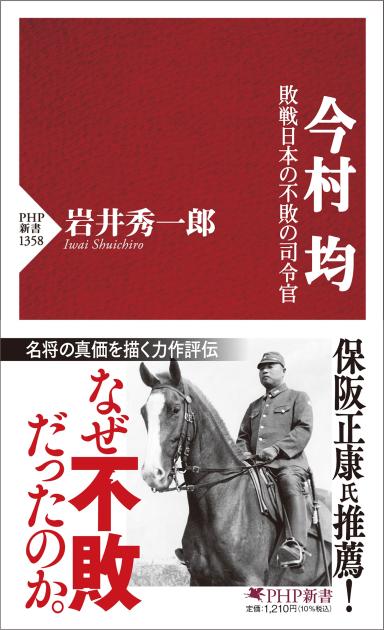





.jpg)


