国破れて名指揮官あり――「責任」を全うした今村均という「不敗」のリーダー
今村大将は「いまも生きておられる」
今村がその生涯を終えたのは、昭和43年10月4日のことだった。
今村はこの日敬愛する乃木希典を祀った乃木神社境内の「乃木将軍と辻占売り少年像」碑の題字を書いた後入浴し、居間に戻った際に心筋梗塞で世を去った。晩年は多少健康を害することはあったが、その最後は穏やかなものだった。
かつてラバウルで今村の部下だった太田庄次は翌日5日に今村死去の報を聞き、すぐに自宅へとかけつけた。家人に案内されて座敷に横たわっている今村を目の前にした太田だが、不思議なことに悲しみを感じなかったという。
《しかし、それは凡人にたいしての言葉であり、大将の場合は、昨日の大将もきょうの大将も、神さま、仏さまであることに変わりなく、ただ生理的に心臓の鼓動が停止したことが違っているにすぎないのだ。つまり、生き神様の呼吸が止まり、お声が聞けなくなったというだけのことである。大将はいまも生きておられるという感じであった。私はもう一度合掌した》(『丸別冊 回想の将軍・提督』に収録)
戦争末期、今村はすでに戦後を見据えた指導を行なっていた。昭和20年6月ごろ、今村は方面軍の若い中、少尉を集め、戦闘とは直接関係のない技術教育(講座)を開始した。
今村は講座を開くにあたって、「日本陸軍の科学技術を軽視した精神至上主義が今日の日本の悲運を招いた」と陸軍を批判し、講座開設の目的を語った。
また、戦争が終わってオーストラリア軍の管理下に置かれた後も、将兵に旧制中学校卒業程度の学力をつけさせるために、一般教養科目の教科書・資料を編纂させ、部隊ごとに適任者をもって臨時の教育を行わせた。
早くに「現地自活」に舵を切り、将兵を飢えさせない工夫を行なったことを含め、今村は現実を適切に判断し、これから必要となるものや技術を判断する能力があったといえるだろう。
そして今村の最も特徴とする部分として、将兵に対する「仁徳」を欠かすことは出来ない。
それは、彼の戦後における身の処し方で明らかであるが、戦時中も「兵を大切にして欲しい」と士官たちに説き、キリスト教や仏教の教えを交えながら、「尊い命であるだけに無駄にしてはならない」と述べたのである。
それが単に言葉の上のことだけではなく、真実として感じられたからこそ終戦時の混乱でも秩序を維持し、戦後も彼を慕う部下たちが跡をたたなかったのではないだろうか。
生涯にわたって反省と修養
彼は生涯にわたって我が身を反省し、修養を怠らなかった。井本熊男陸軍少佐が関東軍参謀副長の時と師団長の時の今村に格段の成長を感じたというが、今村は修養によって自分の能力を磨いていった。
現在も彼の人気が高く、その著書が時代を重ねても読み続けられているのは、人は常に成長を続けることが出来るという単純でありながらも大切な教訓をその人生で証明しているからではないだろうか。
今村は、若い頃から新約聖書と歎異抄を座右から離さなかった。それは戦後になっても変わらず、敗戦直後に収容されていたラバウルの収容所にいた頃もそばに置いていた。
ある時、部下の谷田勇が「閣下は、クリスチャンですか」と尋ねたことがある。すると今村は笑いながら、「そうじゃあないが、修養として読んでいる」と答えた。
当時の軍人が宗教書を耽読することは珍しくはないが、今村の特徴はそれが長年月に及んだことと、東西二つの宗教の教典を併読していたことだろう。
今村自身、歎異抄と聖書には「同一程度の感激を覚える」と述べており、宗教の違いの根底にも共通の価値観があることを指摘している。
そして、こうした違った宗教をそれぞれ尊重しつつ、どちらかに偏することなく「修養」として読んでいたというのは、やはり今村の人間的な特徴のひとつだといえるだろう。
今村均という人間は一見平凡にみえながらも指導者として欠いてはならない修養を重ね、大東亜戦争という日本最大の危機に可能な限り対処した。
戦争そのものは今村、というより一個人の能力の及ばぬ部分で敗北してしまったが、自分の権能が及ぶ範囲ではその責任を全うしたのである。
※特に注記のない引用は、その多くを、今村均本人の回顧録『私記・一軍人六十年の哀歓』『続・一軍人六十年の哀歓』に拠った。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月01日 00:05
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語


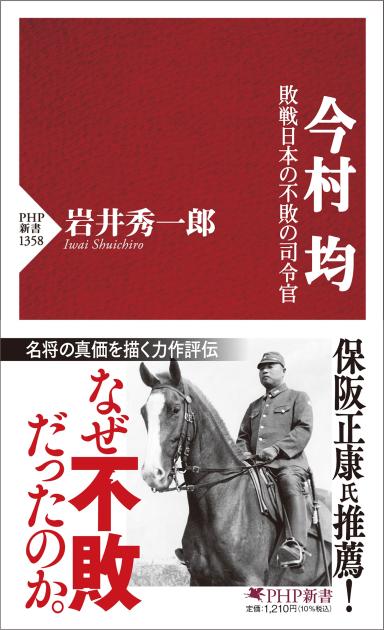





.jpg)


