縄文の新常識!三内丸山遺跡の衝撃
縄文観を塗り替えた三内丸山遺跡
三内丸山遺跡を象徴するのは、大型掘立柱建物跡だ。掘立柱は、穴を掘って礎石を用いず直接柱を建てる方法だ。それは、集落の北西の端、台地の縁に建っていた。直径2メートル、深さ2メートルの柱穴が4.2メートル間隔で3本、これが2列あって、それぞれの穴に直径1メートルを超えるクリの巨大木柱が屹立していたと推定された。
6本の柱はトーテムポールのように立っていたのではないかとする説があったが、柱が2度ほど内向きに傾いていることから、建物説が生まれた。土台には、砂と粘土を入れて、固く叩いている。
柱穴の土壌を分析した結果、1平方メートルあたり16トンの荷重がかかっていたこともわかっていて、高さ17メートル程度の柱が建っていたことがわかり、現在では、建物説に従って巨大タワーが復元されている。
この大型掘立柱建物跡のすぐ脇に、大型住居跡が存在する。長さは32メートル、幅9.8メートルの楕円形だ。住居ではなく、集会所か厳冬期の作業場とする考えもある。いずれにせよ、縄文人が現代人の想像を遥かに超える巨大建造物を作る知恵と技術を持っていたことが明らかになったのだ。
三内丸山遺跡から出土した他のクリのDNAを調べてみると、特定のパターンがそろっていた。
木製や骨角製などの多種多様な道具が使用されていたこともわかった。
縄文尺(長さの基準。35センチ)が存在したこともわかっている。この尺は、福井県から北海道に至る縄文時代の他の大型住居跡にも当てはまり、各地で供用されていたことがわかる。
さらに大切なことは、色々な地域と交流し、交易をしていたことで、黒曜石は、北海道十勝、秋田県男鹿、長野県霧ヶ峰などのものを使い、接着剤に用いたアスファルトは秋田県から、ヒスイも、約600キロ離れた新潟県糸魚川市から流入している。また、4000年前の三内丸山遺跡から出土した円筒土器と同型の代物が中国大陸で発見されている。
中国だけではない。三内丸山遺跡は北の文化ともつながっていた。北海道の西海岸、サハリンの西海岸、シベリアの東北との交流が盛んだった。中国との往き来もあって、日本海の時計回りの航路が利用されていた可能性も出てきた。
縄文時代に階級の差が生まれていた
かつて、縄文社会は平等で上下貴賤の差はないと信じられていた。農耕が本格化した弥生時代に至って、階級差が生まれたと考えられていたのだ。特に、唯物史観が、この考えを後押ししていた。実際、縄文人の集落は、真ん中に広場があって、その周りを住居が囲んでいたために、「仲良しで、平等」な姿に映ったのだ。
しかし、多くの遺跡が発掘されて、縄文時代に、階級の差が存在したことがわかってきた。集落の住居も、均等に並んでいたのではなく、グループ分けがあった。住居や墓は、同じように造られていたわけではなく、配置や種類、墓の場合副葬品にも差が見られる。「部族」や「氏族」の違いも認識されていたようだ。
たとえば、三内丸山遺跡の南西斜面の環状配石遺跡の下層部から、土坑墓三基が重なって見つかり、北側に隣接する遺構からも、土坑墓の遺構二基が発見された。同じ場所への埋葬にこだわっていたことがわかる。
松木武彦は、「個体どうしが競争することは、生物の本質だ」といい、「ホモ・サピエンスの社会は、根本的には、時代を問わず不平等だということだ。むろん、縄文社会も例外ではない」と、考える(『日本の歴史一旧石器・縄文・弥生・古墳時代列島創世記』小学館)。原則論としては、これは当然のことかもしれない。
ただし、縄文時代の階級の差は、われわれの想像するものとは異なるようだ。少なくとも、縄文時代に組織的な戦争はほとんど起きていないようだから、強い王を求めた様子もない。むしろ独裁者の出現を嫌っていた可能性が高い。
また渡辺仁は、『縄文式階層化社会』(六一書房)の中で、北太平洋沿岸部(北海道アイヌや北西海岸インディアン)のように、特殊条件下では、石器時代でも階層化がおこりうると指摘している。
しかも、それは単純な経済や技術の分化から起きるわけではないというのだ。単純に富を蓄えた者が貧しい者を力で支配するのではなく、「不可分の信仰・儀礼の分化を伴う点」に特徴があるという。
縄文社会の階層化の証拠の一つが装飾的な縄文土器で、非実用的(宗教的、芸術的)な土器を作らせ手に入れることができる富者と貧者の差ができたといっている。非実用的工芸が発達したのは、威信経済が存在したからで、しかも集団儀礼が発達した社会だからこそ成り立ったのだ。そしてそれは、「自然界との儀礼的関係即ち神々との関係の深さの差を意味する」といい、単純な権力社会ではないという。
さらに渡辺仁は、縄文から弥生への移り変わりは革命ではなく進化で、縄文社会のエリート(上層部)が高度の知識を持ち、スペシャリストだったからこそ、なしえたというのである。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

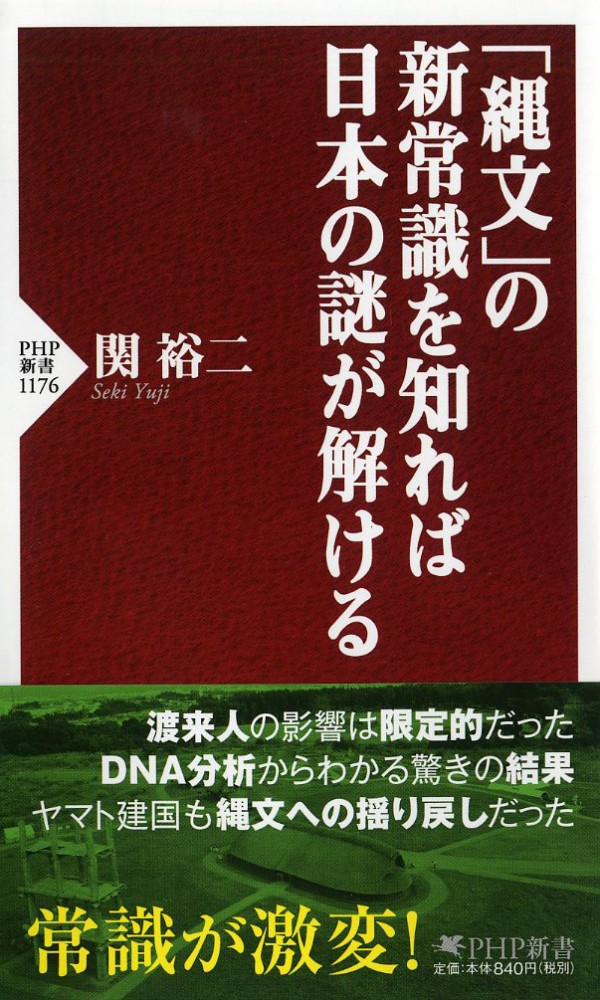




.jpg)


