徳川光圀は、なぜ『大日本史』を編纂したのか
2019年02月21日 公開
2024年12月16日 更新
大義を正す日々
寛文元年(1661)7月に、父の頼房が死んだ。59歳だった。8月19日、光圀は跡を継いで水戸徳川家の第2代藩主になった。
藩主になってすぐ光圀が出したのは「殉死禁止」の令である。殉死の禁止は、すでに徳川本家でも触れていたが、まったく守られていなかった。将軍が亡くなる度に、多くの武士が殉死した。10年ほど前、3代将軍・徳川家光が死んだときも多くの大名や旗本が後を追って腹を切った。人命尊重の気持ちを募らせていた光圀は、父の死に対して藩の武士が腹を切ることを禁止した。この厳命は守られて、水戸家では父・頼房の死に対する殉死者は1人も出なかった。
光圀は、自分の政策を発表した。
●民政を重視し、農民の暮らしを豊かにする
●『大日本史』の編纂を続行する
●領内に水道を建設する
●よこしまな宗教を禁止する
●農民の負担を軽減するために、雑税のいくつかを廃止する
などであった。
そして、最も藩内を驚かせたのは、相続人を定める方法である。光圀は、「今後、水戸徳川家の相続は、四国高松の松平家と、交代で行なう」
と宣言した。みんな目を見張った。光圀は実行した。すなわち、兄・頼重の息子である綱条(つなえだ)を養子に迎えた。頼重には、
「わたしの息子を、高松の世子にしてもらう」
と告げた。頼重は、
「そこまでやらなくてもいいのではないか」
といったが、光圀は承知しなかった。18歳のときに読んだ『史記』の「伯夷伝」の衝撃が、ずっと胸の中に残っていた。三男の自分が、兄の頼重を差し置いて水戸の当主になったことに、何ともいえないうしろめたさを感じていたのである。
水戸領内の民政を重視して、民の暮らしを豊かにしたいというのも、そういううしろめたさの裏返しであった。同時に『大日本史』の編纂を続行すると宣言したのも、そのためであった。『史記』の「伯夷伝」に感動した光圀は、
(日本にも、探ってみればこういう事例がたくさんあるのではないか。それを掘り起こして整理し、後世に伝えよう)
と思いたったのである。
『大日本史』編纂の企ては、かれが当主になる前の明暦3年(1657)から行なわれていた。かれが30歳のときである。江戸駒込の中屋敷に史局を設け、編纂に従事する専門の学者たちを集めた。特別な予算も用意した。この事業は相当な金食い虫であったので、批判も多かった。
しかし光圀は、藩主になってもこの編纂は続けると宣言したのである。実をいえば、この『大日本史』の編纂は明治39年(1906)までかかる。250年にわたる大規模な修史作業であった。かれは、『史記』によって学んだ「人倫の道」すなわち「大義を正す」ということを、水戸藩内だけでなく、日本全体のコンセンサスにしたかったのである。
『大日本史』という本は、南北両朝に分かれていた頃の皇統問題に言及し、「南朝が正統である」とした。そのため、楠木正成や新田義貞たちが忠臣となり、足利尊氏たちは逆賊と呼ばれた。しかし、足利3代将軍・義満のときに、南朝の後亀山天皇は、北朝の後小松天皇に「三種の神器」を渡し、両朝は合一した。そして以後は、後小松天皇系の天皇が続いて、今日に至っている。
光圀の意図はどこにあったのだろうか。『大日本史』の思想は、のちに「水戸学」と呼ばれ、幕末の尊皇運動の理論的根拠になる。南朝を正統とし、北朝を偽朝とすれば、徳川政権は足利政権と違って正当な武士政権として存立できる。天下の副将軍・徳川光圀の真意はこんなところにあったのではなかろうか。
しかしその後、水戸思想は独り歩きをし、幕末の志士を奮起させた。もし、光圀に初めから倒幕思想があったとすれば、そういう危険思想の持ち主を、幕府が副将軍として扱うはずはない。この辺は謎だ。もっと追究されるべきテーマだ。
愛される「ご隠居」に
光圀は、元禄3年(1690)10月14日に藩主の座を退いた。63歳だった。後は、約定に従って四国高松藩主・松平頼重の子綱条を指名した。徳川将軍は、家光の後4代目は家綱が継いだが、家綱が死んで、5代目に綱吉が就任していた。ところが、綱吉は有名な悪法である「生類憐みの令」を出した。これが拡大解釈されて、民衆が酷い目にあった。
光圀は、この綱吉の悪政を諫めるために、藩主の座を退いたのだともいわれる。隠居の身なら思いきって意見ができるからだ。それまでのかれは副将軍として江戸城で政務に励んでいた。が、綱吉には柳沢吉保という側近がいて、ほとんどこの2人で政治が行なわれていた。なかなか光圀には口を出す機会がなかった。また、綱吉も光圀を煙たがっていた。
隠居した光圀は、常陸(茨城県)の太田というところに引っこんで「西山荘」と名づけた隠居所に籠った。『大日本史』の編纂は、駒込から小石川の本邸に移された彰考館で行なわれていたが、これも水戸に移した。西山荘に移った光圀は、付近に梅の木が多かったので自分の号を「梅里」と名づけた。
身近に『大日本史』を編纂する有名な2人の学者がいた。佐々宗淳(さっさむねきよ)と安積澹泊(あさかたんぱく)である。2人は『大日本史』の記事を正確にするためによく諸国を探索して歩いた。宗淳の通称は介三郎、澹泊の通称は覚だったので、これが後の「助さん・格さん」に発展したのだと思う。『水戸黄門漫遊記』そのものは、まったくのフィクションである。光圀が歩きまわったのは、常陸国内か、せいぜい近隣の地域にすぎない。おそらく、佐々と安積が歩きまわったことが、漫遊記に発展したのだろう。
『大日本史』の編纂は相当な金食い虫であり、またこの編纂に携わる職員を優遇したので、藩内でも不平の声が多かった。光圀がこの頃寵愛していた家臣に、藤井紋太夫という男がいた。才覚があるので光圀は重宝していたが、この藤井が将軍・綱吉の側近・柳沢吉保に接近した。2人の動きを見ていると、どうも光圀を力のない立場に追いこむような企てをしている。藤井にすれば、『大日本史』があまりにも金を食うので、この編纂をやめさせようとしたのかもしれない。これを知った光圀は、ある日突然、藤井を刺殺した。天下は驚いた。
光圀は同じ頃、江戸城に出かけていっては将軍・綱吉に『大学』など、中国の古典の講義を行なった。暗に「生類憐みの令」のような悪法を、早く廃止すべきだという意見である。しかし、綱吉は聞かなかった。綱吉もまた、「生き物の命を大事にしたいというのはわたしも同じだ。だから、小動物の命を大事にすることが、即人間の命を大事にすることにつながるのだ」といって聞かない。光圀は「そんな馬鹿なことはない」といったが、綱吉とは見解の相違があった。
『大日本史』の編纂だけでなく、この頃の光圀はしきりに領内を歩きまわった。藩主になったときに約束した上水道も笠原水道として完成していた。怪しげな宗教も全部なくなっていた。善政を行なったので、領民は光圀を「黄門様」と呼んで敬愛した。
元禄13年(1700)12月6日、光圀は死んだ。生前の行ないを偲んで「義公」と贈名された。73歳だった。黄門というのは官位で中納言のことをいう。したがって、中納言であれば誰もが黄門で、光圀の専売特許ではない。しかし、黄門といえばすぐ徳川光圀を思いだすのは、やはりかれの人徳だろう。
子供の頃、危うく「水」にされそうになったかれは、「人間の傷の痛み」を知っていた。自分の傷の痛みを知るからこそ、他人の傷の痛みがわかった。それが弱い人間への優しさや思いやりになった。
黄門漫遊記は、そういうかれの気持ちをシンボライズしたドラマだ。明治22年(1889)の憲法発布の直後から流行しはじめたという。明治天皇の積極的な地方巡幸と、はたして関わりはなかったのだろうか。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月22日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち





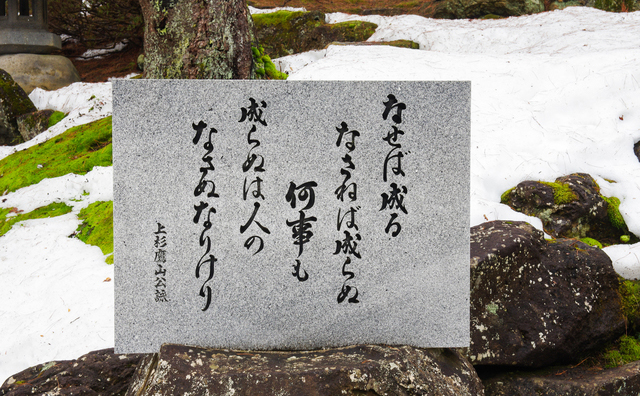

.jpg)


