徳川光圀は、なぜ『大日本史』を編纂したのか
2019年02月21日 公開
2024年12月16日 更新

※本稿は、童門冬二著『歴史人物に学ぶ 男の「行き方」 男の「磨き方」』より、一部を抜粋編集したものです。
徳川光圀の若き日々
不良少年
徳川光圀の出生は、必ずしも幸福なものではなかった。父の徳川頼房が歓迎しなかったからだ。頼房は、初代の水戸藩主だった。徳川家康は、九男、十男、十一男をそれぞれ尾張、紀伊、水戸に封じて、いわゆる「御三家」をつくった。もし、徳川本家に相続人が欠けたときは、この御三家の中から候補者を出すということだ。
母は谷久子といった。水戸藩に仕える武士の娘で、水戸城の奥づとめをしていた侍女である。頼房に愛されて、光圀を身籠った。しかし頼房は、三木仁兵衛という信頼する家臣に久子を預け、「生まれてくる子は水にせよ」と命じた。「水にする」というのは、当時の言葉で「間引き」といって、赤ん坊が生まれるとすぐその命を絶ってしまう慣わしである。
しかし三木仁兵衛は、非常に心の温かい人物で「この世で人の命ほど大切なものはない」と信じていた。三木は妻と相談して、主人の頼房には内緒で光圀を育てることにした。母の久子は感謝した。父の頼房が「水にせよ」といったのは、光圀が初めてではなかった。久子は七年前にも、頼房の子を身籠った。そのときも頼房は「水にせよ」といった。その子も、三木仁兵衛夫妻はそっと育てた。これが、後の四国高松藩主になる松平頼重で、この兄の存在が、やがて光圀に大きな心の転機をもたらす。
光圀は幼名を長丸といい、後に千代松と改めた。やがて父に認知されて、世子(相続人)に指名されると、時の将軍・徳川家光から名前を一字もらって「光国」とした。「圀」と改めるのは50代になってからである。光圀は頼房の三男になるが、2人の兄を差し置いて相続人に指名された。光圀は少しも喜ばなかった。
かれには子供のときから心に受けた深い傷があった。それを、三木夫妻は必死になって隠したが、いつしか少年光圀の耳にも「千代松様は、本当は水にされるお子様だったのだ」という噂が入った。
(父は、わたしを殺すつもりだったのか?)
という思いは、身体を骨の底からガタガタにするようなショックだった。
この頃はまだ戦国の余風が残っていて、武士らしさが求められたが、光圀は逆な生き方をした。三味線を弾いたり、サイケな服装をした。自分でデザインを考えた衣類を、色とりどりに染めさせ、これを着て江戸の町を歩きまわった。世間の人々は、「水戸様の若様はまるでかぶき者だ」といって、指をさした。かぶき者というのは、もともとは「傾く」からきている。ただ歌舞伎役者の真似をするということよりも、拗ねて世の中に対し斜に構える生き方をいった。
事実、少年時代の光圀は斜に構えていた。それは、胸の底にある父への不信感と怒りであり、同時に悲しみでもあった。かれは、そのことを思いつめると、まっとうに生きることができなくなった。だから、斜に構えてかぶき者を気取り、江戸の町をサイケな格好で歩きまわるパフォーマンス活動を、自ら許していた。つまり、「自分は、この世に生まれたときから不幸な星の下に育ったので、このくらいのことはしてもよかろう」という気持ちであった。いってみれば、自分の個人的な不幸を社会への対抗要件としていた。斜に構えることは、自分の出生を喜ばなかった父をはじめ、世の中に対する報復でもあった。遊廓である吉原にもよく出入りした。ここで喧嘩もした。こうして、少年時代の徳川光圀は、世間からうしろ指をさされっぱなしの、鼻持ちならない不良少年であった。
しかし、頭は鋭く、大人が理屈に合わない話をするとすぐ、「そんな馬鹿なことはありえない」と矛盾点を指摘した。話し手は得意の鼻を折られて白ける。この「常に真実を追求する」という態度は、光圀が成人してからの邪教の追放や『大日本史』の作成などでも見受けられる。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:12月18日 00:05
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 江戸城松の廊下事件の真相~浅野内匠頭はなぜ、吉良上野介を斬りつけたのか
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 中川州男とペリリュー島の戦い~バンザイ突撃の禁止、 相次ぐ御嘉賞と将兵の奮闘





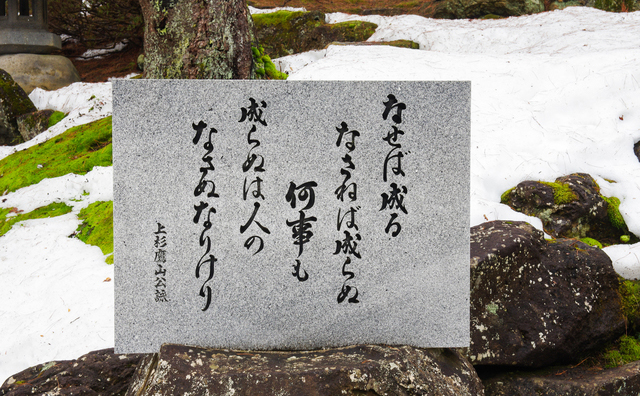

.jpg)


