「第34期の三羽烏」服部卓四郎の知られざる前半生 日露戦争に憧れた少年が辻政信と出会うまで

山形県鶴岡市の由良海岸と白山島
太平洋戦争における帝国陸軍の問題は様々に指摘されているが、歴史研究者の岩井秀一郎氏は、その著書『敗北の作戦参謀』で、「服部卓四郎」を典型とした「作戦参謀」という存在の重要性を指摘している。その服部はどのような経歴の人物なのか。その前半生をたどる。
※本稿は、岩井秀一郎著『敗北の作戦参謀』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
「第34期の三羽烏」
服部卓四郎は明治34(1901)年1月2日、山形県鶴岡市に生まれた。父は元庄内藩士の服部正徳で、卓四郎はその名の如く4男である。卓四郎の生まれた年は20世紀最初の年でもあり、彼は文字通り「新しい時代」、それも世紀の幕開けとほぼ同時に生を受けたことになる。
数年後、日本の存亡をかけてロシア帝国との戦争の火蓋が切って落とされるが、この時服部はまだ4歳(数え年、以下同じ)であり、事の重大性を理解するのは当然不可能だったと思われる。
しかし、この戦争が幼少の服部に与えた影響は決して小さいものではなかった。大東亜戦争後の回想で服部は、「毎日のように『日露戦争実記』という写真入りの雑誌を繙いては軍人に憧れた」というから、軍人になるきっかけの1つでもあったのである。
それでも、小学校時代には書が得意だったことから、「大きくなったら書家になろうかなどと考えたことがあった」と述べているように、絶対的と言えるほど人生を左右されたわけでもなかった。
また5歳から碁を打つことも覚え、父の代わりに打ちにいく腕前にもなった。父からは「中学に進学したいならば今日限り碁を止めよ」と迫られると、「もう一切碁を止めるから、中学に入れて下さい」と答え、ここでようやく中学を卒業して陸軍幼年学校に入る道が開かれたのである。服部が書家の道、または棋士になることを選んでいたのであれば、日本の歴史はどうなったのであろうか。
服部は荘内中学校を卒業すると大正4(1915)年9月、仙幼(仙台陸軍地方幼年学校)へと入学する。戦後編纂された仙幼の学校史には服部は第19期生の筆頭として名を挙げられ、その経歴を述べて「かれは戦将にあらずして謀将であり、しかも戦場の謀将ではなく、高等統帥部の作戦家ともいうべき智将」と評している。服部が「高等統帥部の作戦家」だったのは事実であるが、その立場が的確だったのかどうかは後述する。
仙幼を出た服部は大正7年9月、今度は東京の中央幼年学校へと進み、同9年10月には第34期生として陸軍士官学校に入校する。ここでは、後に日中戦争(支那事変)の早期終結に奔走する堀場一雄、戦後防衛庁で戦史編纂に尽力する西浦進と机を並べ、「第34期の三羽烏」と称された。
この3人の結びつきは特別なものがあったようだ。3人は陸軍の中でも違う道を歩きながら、戦後相寄って活動を共にする。その中で、最初に世を去ったのは堀場一雄であるが(昭和28年10月)、その堀場への弔辞の中で、服部は次のように述べている。
君と西浦と服部とを、人は評して、合わせて1人前だと云います。私は全くその通りであると思います。しかも誇りを以って。
その服部も堀場の死から10年と経たないうちに逝くが、そこで葬儀委員長を務めたのが3人の中で最後に残された西浦進だった。西浦は40数年間の付き合いがある服部の死を悼み、「いま大きな心の支柱を失い、孤影残る人生を歩む寂しさを泌々と感じている」と記している。3人がいかに強固な絆で結ばれていたかがうかがえよう。
中でも、服部と西浦はそれぞれ統帥(参謀本部)と軍政(陸軍省)の中枢で大東亜戦争に関わり、戦争遂行にも影響を与えたといえる。
異質な同期生
さらに同期で重要な人物といえば、秩父宮雍仁親王がいる。言わずと知れた昭和天皇の弟であり、後々歴史の重要な転換点(二・二六事件、日中戦争など)でも名前が出る人物だ。秩父宮とは中央幼年学校時代から同窓であったが、仙台から東京へ赴く際、教官から「お前たちのような田舎者が、殿下とご一緒の区隊に入ったら、それこそ大変だぞ」と「なかば冗談のように」脅されたという。皇族、それも後に昭和天皇となる人のすぐ下の弟となれば、場合によっては皇位につく可能性もある。教官の言葉も、大袈裟ではなかったであろう。
秩父宮はその後参謀本部などにも勤務し、戦時中は東條内閣の末期に東條英機の政治手法を問い糺すということもしている(昭和19年5月)。戦後になって50歳を少し超えたばかりで亡くなった(昭和28年)。
秩父宮の死後編まれた伝記には、服部も1文を寄せている。服部によれば秩父宮は「平民的」で特別扱いを嫌ったという。
皇族だからという、特別待遇は特に御嫌いで、演習等でも、背のうを負われ、銃を担いで終始、一緒に行動された。
庶民的で、自ら泥に塗れることも厭わない秩父宮の人気は高かったようだ。
秩父宮と関連してもう1人、重要な人物が服部と机を並べていた。
彼の名は、西田税。後の二・二六事件でクーデターの裏側にいた人物として刑場の露と消える人物である。西田は当時すでに国家革新運動に関与しており、庶民的な秩父宮に期待をかけていた。1時期などは、秩父宮を「大化の改新」で蘇我氏を倒した中大兄皇子に、自分を中臣鎌足に擬していたという。
この2人は服部の同期生の中でも異質といえるだろう。
秩父宮とはともかく、服部と西田の接点はそれほど多くない。しかし、1方は帝国陸軍の花形ともいえる作戦課の参謀として大東亜戦争に関与し、1方は「体制の変革」を求めてついには処刑される、という真反対の人生を辿った2人に加え、天皇に最も近い皇族の1人が同時期に士官学校にいたというのは、時代の巡り合わせのようなものを感じさせる。
運命の邂逅
大正11(1922)年7月、服部は士官学校を卒業する。10月には歩兵少尉に任官し、第37連隊付となる。
元号が変わって昭和2(1927)年の12月になると、陸軍大学校へと入学する。陸大は将来軍を担うエリート養成コースであり、服部の後の経歴から考えても、敗戦さえなければ参謀総長や陸軍大臣となる可能性もあったといっていいだろう。
昭和5年に陸大を卒業した服部は連隊に戻って中隊長を務め、参謀本部付を経験した後に参謀本部第1部第1課の編制班に入った。ここで、服部と職場を共にしたのが辻政信であった。明治35(1902)年10月生まれ、士官学校は服部の2期下である辻は、当時(昭和7年)陸大卒業間もない頃であったが、第1次上海事変に参加し、受傷している。
辻は後年もしょっちゅう前線に出て数カ国の銃弾をその身に受けたが、その最初がこの上海事変だった。彼は野戦病院に入院したが脱走し、逃げるのではなくよりによって戦闘に参加し、病院長の怒りを買っている。
そして服部と辻は、この時期すでにお互いを認め合う関係になったようだ。これより少し後のことになるが、昭和12(1937)年、すでに日中戦争が勃発していた頃のことだ。当時、早期和平を目指していた石原莞爾は強硬派の武藤章らとの対立により関東軍に転出しており、辻もまた関東軍にいた。
服部は、同じく関東軍で少佐だった片倉衷に対し、「石原閣下関東軍に転出して」から参謀本部は中心を失っている、そこで「此の際辻君を是非当部第2課に転出せしめ度」、つまり石原を失った代わりとして、辻を呼び戻したいと訴えているのである。
服部の辻への評価はかなり高く、「目下の陣容を以てしては心細く此の際私共としては是非辻君を呼び度次第に御座候」とまで述べている。服部と辻が第1部でどのような点をもって意気投合したのかはわからないが、以後この2人は切っても切れない縁で結ばれることになる。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月31日 00:05
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語


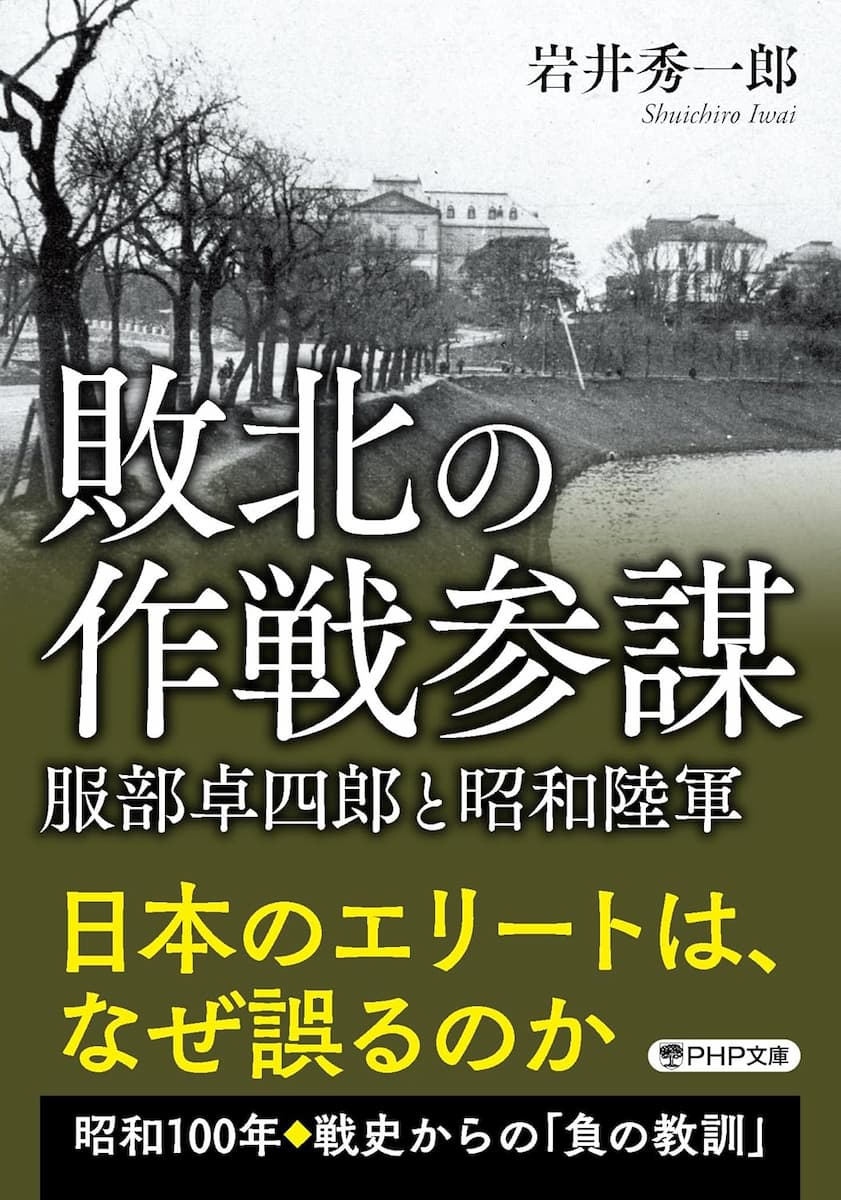


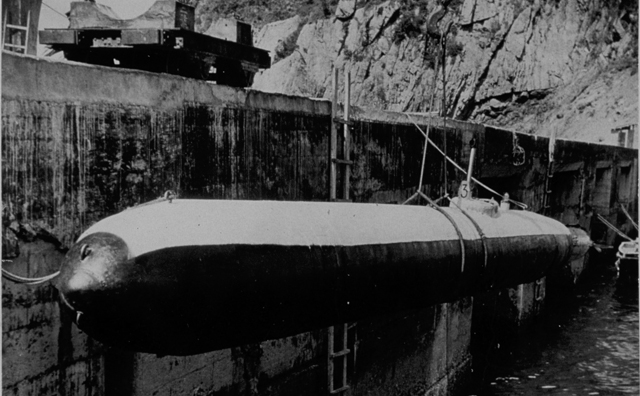
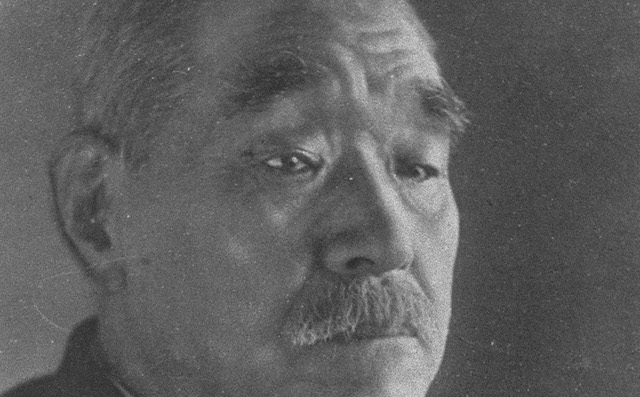

.jpg)


