現代と重なる江戸の経済変動 田沼改革はどう位置づけられるか?

大河ドラマ『べらぼう』によって、江戸時代の経済状況が注目されている。特にドラマでは田沼意次が改革に尽力することから、停滞した社会のようにも見えるかもしれない。しかし経済評論家の岡田晃氏は、江戸時代は高度経済成長の時代もあり、その経済変動には、現代日本と重なる部分も多いという。江戸時代の経済変動を、岡田氏が概説する。
※本稿は、岡田晃著『徳川幕府の経済政策――その光と影』(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
徳川長期政権を支えた経済発展
今から420年前の慶長8年(1603)、徳川家康は征夷大将軍に任ぜられた。これを以て江戸幕府が開かれ、江戸時代が始まったとされている。
家康はすでに慶長5年の関ヶ原の戦いで勝利し、実質的に天下を手中に収めていたが、征夷大将軍となったことで名実ともに武家のトップに立った。
こうして家康がつくった江戸時代はその後、260年余りにわたって続くことになる。その間、大坂冬の陣・夏の陣と島原の乱はあったものの、それを除けば戦乱は完全になくなった。日本で明確な記録が残る6世紀頃から以降の歴史で、これほど長期間にわたって戦争や内乱がなかった時代は他にない。世界を見渡しても類を見ない平和な時代だったのである。
ただ現代の我々が描く江戸時代のイメージは、必ずしも肯定的なものばかりではない。容赦ない大名取り潰し、厳しい身分制や年貢の取り立てなどが思い浮かぶ。また江戸時代の世相を表す「天下泰平」という言葉は、裏を返せば「平和ボケ」あるいは「停滞した社会」などのニュアンスを含んでいる。
特に鎖国の影響もあって、欧米に比べ発展が遅れたことは否定できない。このことは幕末の黒船来航によって明らかとなり、幕府崩壊に向かう転機となったことは周知のとおりだ。
筆者はそうした側面があったことは十分に認めつつも、江戸時代には我々のイメージ以上の経済発展があったことに注目している。260年余りに及ぶ徳川長期政権が実現したのも、この経済発展があったからこそなのである。
ただそれは一本調子ではなかった。成長と後退、好景気と不況、そして政策の成功と失敗を繰り返しながら、江戸時代中期以降は経済が停滞していった。
江戸時代前期は"高度経済成長の時代"
ここで江戸時代の経済発展の足取りを概観してみよう。
まず江戸時代前期、慶長年間の1600年頃から元禄年間の1700年頃までの約100年間は、近代以前では最も経済が成長した時代と見られる。戦乱の世が終わり社会が安定したことで、経済発展の条件が整ったのである。
経済成長と言っても、もちろん現代の経済成長とは比べ物にならないが、当時の日本は世界主要国の中では、7つの海を制覇し躍進したイギリスに次ぐ成長率だったという推計もある。そこで、江戸時代前期をあえて"高度経済成長の時代"と呼ぶことにしたい。
経済成長の主な柱は、以下の5つだ。
第1の柱は、江戸の都市づくりだ。慶長8年(1603)に幕府を開いた家康は、全国の諸大名に工事を割り当てて江戸城の大規模な増改築に着手するとともに、海岸部を埋め立て、ここに新たな市街地を形成した。江戸は急速に人口を増やし日本最大の都市として発展していく。
第2の柱は、各大名による城づくりと城下町の整備だ。家康が関ヶ原の戦い以降、大名の改易(取り潰し)と転封を行った結果、各大名は新しい領地で城を築き、城下町を建設していった。全国的に建設ブームだったと言ってよいだろう。昭和40年代に日本列島改造ブームがあったが、「江戸時代版・日本列島改造」といったところだ。
第3の柱は、交通網の発達と経済活動の広域化だ。参勤交代や物流の増加に対応して街道整備が進み、宿場町や港町、門前町が発展した。大坂などから江戸への物資や商品が船で運ばれるようになり、海運も発達した。
戦国時代までは領主や豪族の勢力圏内に経済活動の範囲がとどまるケースが多かったが、天下が統一されたことで経済活動が広域化していくことになる。
第4は、新田開発ラッシュと米の増産だ。平和な時代となり農民は農作業に専念できるようになった。江戸や地方都市の発展によって食料需要が増加し、全国各地で新田開発が活発に行われた。
江戸時代研究の大家、大石慎三郎・学習院大学名誉教授(故人)によると、1700年頃の全国の耕地面積は1600年頃の2倍近くに達していたという。江戸時代の前期は「大開墾時代」とも「大開拓時代」とも呼ばれるほどだ。
その結果、農業生産が増加した。周知のように、江戸時代は米を中心とする農業が経済を支える最大の基盤だ。農業生産の増加がまた経済発展を促進した。
第5の柱は、幕府財政の確立と貨幣経済の発展、つまり財政政策と金融政策だ。農業生産の増加は幕府直轄地からの年貢収入の増加につながり、幕府財政を潤した。全国の主要鉱山も直轄地とし、金や銀の採掘による収益も幕府財政を支え、金貨・銀貨発行の"原資"ともなった。幕府の金融政策は貨幣経済の発展を促し、江戸後期には貨幣改鋳が財政危機乗り切りの切り札となる。
以上の5つの柱による経済発展は人口増加をもたらした。近年の研究によると、1600年に約1700万人だった全国人口は、1721年には約3100万人になったという。こうした人口増加がさらなる経済発展につながった。
戦国末期から江戸時代前期は、多くの商人が創業するベンチャーの時代でもあった。経済発展と消費市場拡大という新しい変化をいち早くつかみビジネスチャンスを広げたのだ。それらの中から住友、鴻池、三井などの豪商が生まれ、そのほかにも竹中工務店、松坂屋(現・Jフロントリテイリング)、キッコーマンなど、現代まで事業を継続し大企業となっている例も少なくない。
このように、平和体制への移行を背景に"高度経済成長"を遂げた江戸前期の時代は、太平洋戦争後に平和国家となった日本が昭和20年代以降に戦後復興と高度経済成長を遂げた昭和の歴史と重なって見えてくる。
そして昭和末期から平成初期にかけてバブルの時代を迎えたように、江戸の経済発展は元禄時代(1688~1704)にピークを迎えた。いわゆる元禄バブルである。
元禄バブルの崩壊、経済は長期低迷へ
だが高度成長もそこまでだった。幕府財政は悪化し始め、経済全体も急速に悪化していった。バブル崩壊である。
5代将軍・綱吉の後を継いだ6代・家宣の側近、新井白石は、元禄時代に貨幣改鋳を行った荻原重秀を憎み、緊縮策をとった。そのためバブル崩壊に拍車をかけ、デフレに陥った。これが、江戸中期から後期まで経済が停滞していく始まりとなる。
これに対応すべく幕府は何度か改革に取り組んだ。まず動いたのが、享保元年(1716)に8代将軍となった吉宗だ。
江戸城内の質素倹約からスタートしたが、その一環として大奥に勤める女性のうちから美人をリストアップさせ辞めさせた話は有名だ。大奥という「聖域」もリストラの対象にしたわけで、前例や格式にとらわれずに改革に取り組んだ。
この「享保の改革」は当初は、歳出削減や年貢率の引き上げ、つまり増税など緊縮策が中心だったが、新田開発の奨励、甘藷(サツマイモ)栽培、殖産興業に役立つ洋書(漢訳書)の輸入緩和など、規制緩和や経済活性化にも力を入れた。
さらに、貨幣の供給量を増やすため、金の含有率を下げる改鋳を行った(元文の改鋳、1736)。新井白石以来のデフレ政策からインフレ政策に転換したのである。リフレ政策の元祖と言える。
田沼意次の構造改革、頓挫の後、デフレに
この吉宗の改革を引き継ぎ発展させたのが、田沼意次だった。
意次は特産物の生産拡大や鉱山開発などの殖産興業、株仲間の公認拡大などで、発達する商品経済に対応しようとした。海産物の輸出拡大や蝦夷地開発調査などにも動いた。従来の米偏重の経済構造を変えて経済活性化を図ろうとしていたのである。
今風に言えば、構造改革と成長戦略だ。
田沼意次は賄賂政治家と言われ「悪役」のイメージが強いが、このような開明的な経済政策はもっと評価されてしかるべきだと思う。だが天明の大飢饉(1782~88)が起き、その批判もあって意次は天明6年(1786)に失脚、構造改革は頓挫する。
意次の後に老中首座に就いた松平定信は田沼政治を全面的に否定し「寛政の改革」に着手した。だがその内容は、緊縮政策と「米本位制」への回帰、統制の強化が中心で、時代の変化に逆行するものだった。そのため幕府財政は一時的に黒字を回復したものの、国内経済は再びデフレに陥り不況が続くこととなる。
結局、定信も6年後に失脚。その後の文化・文政時代(1804~30)には老中・水野忠成が貨幣の改鋳を行い(文政の改鋳、1819)、貨幣の流通量を大幅に増加させた。デフレからインフレへと転換させるリフレ政策である。
これによりデフレ不況から脱し、景気は回復していった。経済の安定とともに、浮世絵や川柳、歌舞伎など、化政文化と呼ばれる町人文化が隆盛をきわめたのもこの時代の特徴だ。
こうした中で、今度は水野忠邦が老中となり、「天保の改革」に乗り出す。だがこれもまた、統制強化と緊縮政策が中心だった。
これら「享保の改革」「寛政の改革」「天保の改革」は「江戸の三大改革」と言われるが、経済発展の観点から言えば、寛政の改革と天保の改革は明らかに失敗だった。
むしろ、田沼政治こそ改革と呼ぶにふさわしいと言えるが、当時の幕府、あるいは世論はそれをつぶしてしまった。結局、江戸後期は幕府の力が次第に弱まり、やがて黒船来航を経て幕府崩壊に至ったのだった。
江戸時代に令和の日本経済復活のヒントあり
このような元禄以後の経済変動の軌跡=経済低迷トレンドと数度のデフレは、平成バブル崩壊後の経済低迷とデフレの長期化に重なって見える。
また吉宗の享保の改革や田沼政治は、平成の小泉構造改革やアベノミクスになぞらえることができるだろうか。しかしそれらも、江戸時代と同じように道半ばで終わっている。
このまま現在の日本経済が江戸時代の「幕府崩壊」と同じような道をたどることがあってはならないのは、言うまでもない。幕府の経済政策の失敗は、今日への教訓ともなっている。令和の日本経済復活のためには何が必要か─江戸時代にはそのヒントが詰まっている。
その一方で、幕府首脳や大名、サムライたち、商人や農民、学者など、多くの人たちが危機や苦難に立ち向かい乗り越えていったことも事実である。そうした力が、やがて幕末の動乱を経て、明治の近代化を成し遂げる原動力となったことにも目を向けたい。彼らがどのようにしてピンチをチャンスに変えたかを知れば、我々も元気になれるはずだ。
筆者は、日本経済新聞とテレビ東京時代、そして現在に至るまで日本経済や世界経済を取材し報道・解説する仕事を続けているが、経済の変動が激しく先行きが読みにくい今こそ、歴史に学ぶことが重要だとつくづく実感している。
【岡田晃(おかだ・あきら)】
1947年、大阪市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。記者、編集委員を経て、1991年にテレビ東京に異動。米国現地法人の社長、理事・解説委員長を歴任、経済番組のキャスター等を務めた。2006年にテレビ東京退職、大阪経済大学客員教授に就任。2022年より同大学特別招聘教授。経済評論家。著書に『明治日本の産業革命遺産』(集英社)などがある。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

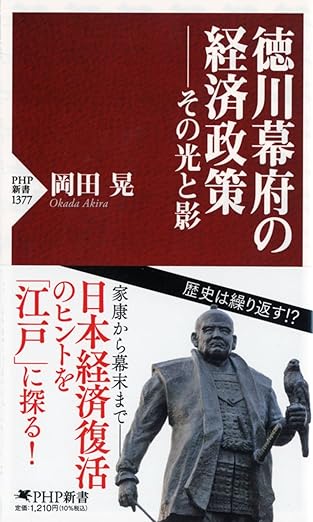




.jpg)


