藤原道長が、紫式部の文章に加筆した? 注釈書が指摘した『源氏物語』作者複数説
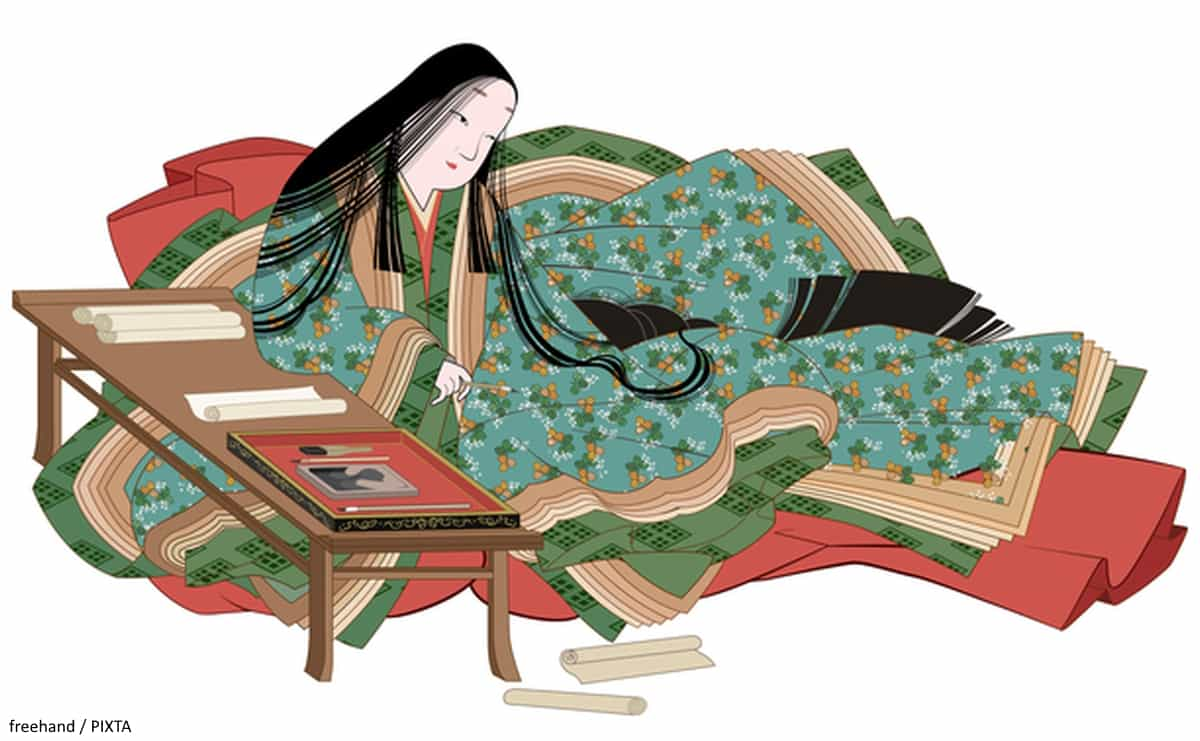
大河ドラマ『光る君へ』で注目される『源氏物語』。作者は、いわずと知れた紫式部......といいたいところだが、実は古くから、作者は紫式部だけでなく他にもいたのではないかという、作者複数説があるのだ。著述家の古川順弘氏が、作者複数説の概要と、それが唱えられる背景について解説する。
※本稿は、古川順弘著『紫式部と源氏物語の謎55』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです
『河海抄』に記された藤原道長加筆説
鎌倉時代初期に書かれた貴重な文芸評論『無名草子』(筆者は藤原定家の姉妹と言われる)は、『源氏物語』を傑作と評したうえで、「とても人間業とは思えない」(凡夫のしわざともおぼえぬことなり)と記す。こんなにすばらしい物語の作者はいったいどんな人物なのか、尋常な人間ではあるまい、というわけである。
現代の『源氏物語』読者にも、これと似たような感想を抱く人は決して少なくあるまい。筆者も、現代の小説家が束になってかかっても『源氏物語』の作者には敵うまい、と思うことがある。
そして、こうした感想から得てして生じるのが、「こんな洗練された大作を、たった一人で書けるわけがない。紫式部以外にも作者がいたのではないか」という疑念であり、邪推である。それは昔も同じだったようで、紫式部以外にも作者がいたとする「『源氏物語』作者複数説」は古くからみられる。そこで、各説の当否はひとまず措いて、主な作者複数説を瞥見してみよう。
南北朝時代に編まれた『源氏物語』注釈書『河海抄』の巻第一冒頭に、「珍しい物語を読みたい」という大斎院選子内親王(村上天皇の皇女)の求めに応じる形で、紫式部が石山寺で『源氏物語』を起筆したという有名な伝説が書かれている。じつは、この伝説の続きには、こんなことも書かれている。
「(紫式部は)その後次第に書き加えて五十四巻とした。これを権大納言藤原行成(藤原道長の側近で、書家としても有名)に清書してもらって、大斎院のもとへ届けようとしたが、法成寺入道関白(道長のこと)が奥書を加え、『この物語は世間では紫式部の作とばかり思っているようだが、老比丘の加筆になるものだ』と言ったという」
最後の方に出てくる「老比丘」というのは、晩年に出家して荘厳な法成寺を創建した藤原道長のことだ。つまり、『源氏物語』は、紫式部が書いたものに道長が加筆することで完成したというのである。
この伝説の出所を『河海抄』はとくに記しておらず、もとより揣摩憶測の域を出まいが、道長加筆説は「『源氏物語』作者複数説」の嚆矢と言えよう。
繰り返し出現する「作者複数説」
『河海抄』を補正したものと言われる文明4年(1472)成立の一条兼良による『花鳥余情』も、「『源氏物語』作者複数説」に言及している。
まず冒頭には、「『宇治大納言物語』による」として、「『源氏物語』はまず式部の父藤原為時が書き、細部を娘の式部に書かせ、このことを后の宮(中宮彰子のことだろう)が耳にして、式部を召し出した」という説が紹介されている。『宇治大納言物語』は散逸したと考えられている説話集で、成立は平安時代後期かという。『宇治拾遺物語』とは別の書である。
さらに、「宇治十帖」の解説(第二十五巻)の冒頭では、「或人」の話として、「『宇治十帖』は式部の娘大弐三位(藤原賢子)が書いたもので、その証拠は明らかだという」説が引かれている。前記の為時執筆説と合わせるなら、『源氏物語』は為時・式部・賢子の三代によって書かれたことになる。
しかし、江戸時代の本居宣長は『源氏物語玉の小櫛』の中で、『河海抄』や『花鳥余情』にみえる作者複数説をいずれも後世に生じた作り事として一蹴していて、「宇治十帖」も含めて『源氏物語』はすべて式部一人の手になるものだと抗弁している。
近代に入ると、哲学者の和辻哲郎が微妙なニュアンスで作者複数説に言及する。
和辻は、大正11年(1922)発表の評論「源氏物語について」(『日本精神史研究』所収)の中で、『源氏物語』には描写の技巧に巧拙が混在していることを論じたうえで、こう述べる。
「もし我々が綿密に源氏物語を検するならば、右のごとき巧拙の種々の層を発見し、ここに『一人の作者』ではなくして、一人の偉れた作者に導かれた『一つの流派』を見いだし得るかも知れない」
和辻は作者論についてこれ以上は展開していないが、彼の言わんとすることは、「『源氏物語』は一個人ではなく一流派によって書かれたのではないか。だから時にすばらしかったり、時に凡庸だったりという文章表現のアンバランスが生じているのではないか」ということだろう。つまり、式部の監督のもとに何人かの書き手が分担して『源氏物語』を書いたのではないかという、「紫式部監修説」である。
与謝野晶子は「紫式部新考」(1928年)の中で、「併し私は現在の『源氏』五十四帖が悉く彼女(紫式部)の筆に成つたとは決して思はない」と記し、式部が書いたのは第一部(第一巻「桐壺」〜第三十三巻「藤裏葉」)であって、第二部(第三十四巻「若菜 上」~第四十一巻「幻」・第三部(第四十二巻「匂宮」~第五十四巻「夢浮橋」は別人の補作であり、その補作者は式部の娘藤原賢子以外には考えられないと論じている。
民俗学者・国文学者の折口信夫も作者複数説に立ったようで、昭和26年(1951)に木々高太郎(作家)、池田弥三郎(国文学者)らと行った座談会(「源氏物語研究」として雑誌『三田文学』に掲載)の中で、「(『源氏物語』は)あとから書き足されたらうと思はれる部分が多く考へられます」と発言し、さらに、文法の変化を理由に、「宇治十帖」を含む後半部の作者は式部とは別人であろうという趣旨の発言も行っている。
折口に師事した国文学者の西村亨は、『知られざる源氏物語』(1996年)の中で作者複数説に触れ、国文学者・武田宗俊が唱えた「玉鬘系後記説」を踏まえて、『源氏物語』第一部の「紫の上系」の巻々(「花散里」は除く)は紫式部の筆に間違いないとするが、「玉鬘系」巻(「紫の上系」巻のスピンオフ的な内容を持つ巻)の作者については式部とは別人である可能性を指摘している。
なぜ作者複数説がくすぶりつづけるのか
ここに紹介した作者複数説は、いずれも出所の不明瞭な伝説や、裏付けを欠く仮説・推測であり、決定的な証拠があるわけではない。
作家瀬戸内寂聴は「作者は紫式部一人ではなく、複数かも知れないという説もあるのは、これだけの壮大華麗な傑作が、到底一女性の手では書ける筈がなかろうという、男性研究者の想像と仮説から出たもので、根拠はない」と手厳しく批判している(1996年初刊『源氏物語 巻一』巻末の「源氏のしおり」)。
しかし、では逆に、『源氏物語』は紫式部がすべて一人で書いたという説に確証があるのかというと、そういうわけでもない。
『源氏物語』には「作者まえがき」や「作者あとがき」などは存在しないし、作者が紫式部であることが『源氏物語』内に明記されているわけでもない。この基本的な事実が、『源氏物語』作者複数説が絶えずくすぶりつづけてきた主たる要因なのではないだろうか。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月23日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

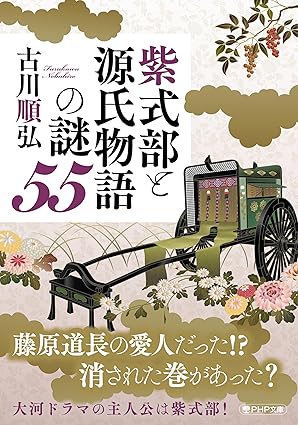





.jpg)


