紫式部と清少納言の関係は? 日記に残された「浅学で鼻もちならぬ人物」という罵り

大河ドラマ『光る君へ』では、紫式部と清少納言は若かりし頃からの知り合いで、やがて清少納言が紫式部に対抗心を抱くように描かれている。実際の二人の関係はどのようなものであったのか。著述家の古川順弘氏が解説しよう。
※本稿は、古川順弘著『紫式部と源氏物語の謎55』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです
一条天皇の後宮に仕えた二人
周知のように、紫式部と清少納言はともに一条天皇の後宮に女房として仕えた優秀な女流文学者であり、仮名文字を用いて、前者は物語文学の名作を、後者は随筆文学の名作を著したこともあって、何かと比較対照されることが多い。そこで、この二人の関係についても触れておこう。
清少納言のプロフィールから入ろう。彼女もまた式部と同じく生没年不詳だが、康保3年(966)頃の生まれとするのが通説である。式部よりはやや年長だったとみられる。
父は歌人の清原元輔だが、母は不詳。清原氏は天武天皇の後裔で、貴族としては中級・下級だが、漢学や和歌に通じた人物が輩出している。清少納言は天元4年(981)頃に陸奥守橘則光と結婚し、子ももうけるが、夫婦仲はうまくいかなかったようで、やがて離別。
正暦4年(993)頃から一条天皇の中宮定子(後に皇后)の女房となり、敬愛する定子に近侍して華やかな宮廷生活を満喫してゆく。このときの女房名が清少納言である。清は清原の略だが、少納言の由来はわからない。例によって本名も不明で、なぜ定子に仕えることになったのかもわからない。
清少納言が定子の女房になった頃は、道長の兄で、定子の父親である道隆が関白、道隆の子伊周が内大臣で、道隆一族(後年、中関白家と呼ばれる)が政権を掌握していた。
定子が一条天皇に入内したのは、正暦元年(990)、14歳時のこと。このとき天皇は元服してまもない11歳で、まさしくお雛様のような夫婦だったが、二人の仲はきわめて睦まじく、このことが中関白家政権の安泰にも結びついていたのである。
そんな中関白家全盛期を背景に、一条天皇と中宮定子を中心とした華やいだ宮廷社会を見事に活写したのが、清少納言の『枕草子』であった。
『枕草子』の成立期については議論があるが、長保3年(1001)頃には大部分が書かれていて(この時点では清少納言は宮仕えを退いていた)、その後も加筆修正が行われたとみるのが主流である。
約300編の章段から成り、それらは「山は......」「河は......」あるいは「すさまじきもの」「にくきもの」といったようなスタイルで事象を列挙してゆく「類聚章段」と呼ばれる章段、宮中での見聞を日記風に記した章段、純然たる随想の章段の3つに分類されるが、いずれにも分類しかねる章段もある。有名な冒頭に置かれた「春は曙......」ではじまる章段は、類聚と随想の混成とされている。
書かれた目的ははっきりしない。跋文には、定子の兄伊周が紙を献上したとき、定子が「これに何を書こうかしら」と尋ねたので、清少納言が「それなら枕でございましょう」と答えると、定子は「ならば、あなたにあげましょう」と言って紙を下賜した、それで本書を書いた、というエピソードが記されている。
清少納言の言う「枕」は、寝具の枕ではなく、枕のように分厚い草子(白紙の帳面)のことをさしているそうで、これが書名「枕草子」とも関係があるようなのだが、この跋文には意味を汲み取りにくいところもあって、正確な執筆動機はわからない。
宮廷生活をひたすら賛美する清少納言の『枕草子』
『枕草子』は宮廷生活の賛美に徹していて、そこが人間の陰影両面を描く『源氏物語』や『紫式部日記』との大きな違いである。その特色はともすると高慢とも映りがちな陽性で外向的な作者の性格の反映でもあった。
有名な「香炉峯の雪」の記事には、彼女のそんな性格が垣間見える。
ある雪が深く積もった日、御格子(上に押し上げると開く板戸)を下ろして女房たちが話していると、定子が「少納言よ、香炉峰の雪はどんなかしら?」と尋ねた。すると清少納言は、御格子を上げさせてから御簾を巻き上げ、外の雪景色を眺めさせた。定子はいかにも満足気に笑ったという。
この話は、平安時代に広く読まれた漢詩集『白氏文集』の中の句「香炉峰の雪は簾をかかげて看る」を踏まえている。要するに、定子は「外の雪景色を見たい」ということをエスプリをきかせて表現したのだが、清少納言はこれをちゃんと理解して絶妙な応答をしてみせたのだ。居合わせた女房たちは清少納言の機転をしきりにほめそやしたそうだが、本人も得意満面であっただろう。
しかし、このような幸せな日々はそう長くは続かなかった。
長徳元年(995)には道隆が病死。子の伊周がその後継をめざすも、道長が政界で躍進し、やがて伊周は失脚。中関白家の没落につれて定子の境遇も沈んでゆく。長保元年(999)には第一皇子敦康親王を生むが、この頃には政権は完全に道長のものとなっていて、同年にはついに道長の娘彰子が入内し、翌長保2年(1000)には中宮に。皇后となった定子は同年末に内親王を出産するが、その翌日、不幸にも25歳の若さで急死してしまった。
清少納言はこれを機に完全に後宮を退いたらしい。『枕草子』が完成した頃には、定子後宮の輝かしい日々はすっかり過去のものとなっていたのだ。
清少納言をこき下ろす『紫式部日記』
そして、清少納言の退場後に中宮彰子の女房として後宮に現れたのが、紫式部だった。ただし、定説では彼女の宮仕えは寛弘2年(1005)頃からで、清少納言の退出からすでに5年ほど経過しているため、二人が宮廷で直接顔を合わせることはなかったはずである。
とはいえ、式部は清少納言の文名はかねて耳にし、彼女が書いたものを読む機会もあったらしい。だが、式部の清少納言への評価はたいへん厳しいものであった。『紫式部日記』の消息体部分には、和泉式部や赤染衛門ら同世代の女流歌人への穏当な批評のあとに、清少納言をこき下ろす言葉が続いている。
曰く、いつもしたり顔をした鼻もちならぬ人物で、漢学の知識はお粗末、風流をきどってやたらともののあわれを感じる風を装い、軽薄で......といった調子である。そして最後は、「そのあだになりぬる人の果て、いかでかはよくはべらむ」、こんな軽薄な女は碌な死に方をしないだろう、とまで痛罵している。
確かに、「香炉峰の雪」のエピソードからは清少納言のキザな性格を想像することもできようが、それにしても苛烈な評言である。式部の主人彰子は清少納言が仕えた定子のライバルであったので、それで余計に清少納言に対抗意識を燃やしたのだろうが、それだけでは説明はつくまい。
もしかすると、式部はかつて清少納言と直接会ったことがあり、そのときに非常に嫌な思いをさせられた、というようなことでもあったのではないだろうか。
他方、清少納言は式部のことをどう見ていたのだろうか。残念ながら、後宮を退いた後の清少納言の動静はほとんどわからず、彼女の式部評を知る術はない。鎌倉時代の説話集『古事談』には、晩年の清少納言が零落していたことを示す話が載っているが、これがどれだけ事実を伝えているかは不明である。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月04日 00:05
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟

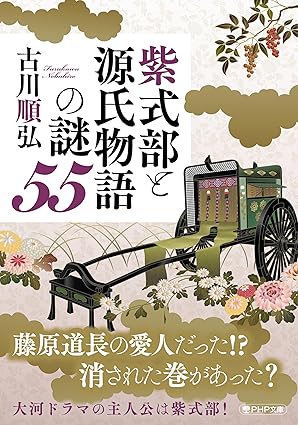





.jpg)


