米英と並び「世界三大海軍国」と賞された日本海軍は、なぜ太平洋戦争で負けたのか
昭和以降、精神主義に傾いていった海軍
教育の中身を見てみよう。明治時代、海軍はエンジニア教育にも重きを置いていた。エンジニアとしての知識もなければ、海戦の指揮ができないからだ。したがって、兵学校は、数学を始め、工業学校のような科目がたくさんあった。
これが昭和に入ると、カリキュラムの中に精神教育が増える。明治の海軍は現実的で冷静だが、昭和になってから精神主義的な組織になっていった要因の一つである。
なぜ精神主義が強くなったのか。説明は難しいのだが、一つには、新たな軍艦などを上に要求しても、なかなか予算がつかず、十分な兵力が整えられなかったことが考えられる。
海軍から見て、たとえ不十分な軍備であっても、「国を守る」という絶対任務は変わらないので、戦うしかない。そういう状況に置かれ、士気を高めるためには精神主義に傾かざるを得なかったのではないか。
それでも、現場では兵隊が頑張って、戦果を挙げることもあった。防弾装備で劣る零戦に乗り、アメリカの最新鋭機を撃墜したパイロットは多数いるが、これは「腕前」の要素が大きい。
日本の場合、飛行機の搭乗員教育は徒弟制だった。教官1人が3、4人ずつ教える。戦時中は間に合わなくなって増やしたが、6人程度が限界だった。教官、教員は一緒に飛ばなければいけないから、それ以上の生徒を担当できないのだ。
日本の海軍は最後まで、マンツーマンで教える傾向があった。それに比べて、ドイツは教室での座学の比率が高く、早めに単独飛行させて、飛べる者はどんどん戦場に送り出した。その代わり、ドイツは訓練中の事故殉職が多かったという。
日本のやり方はきめの細かい教育ができるが、大量養成ができない。ドイツのやり方は大量養成できるが、デメリットもある。
どちらがいいかは簡単にいえないが、きめ細かい教育、訓練をしたからこそ、空母機として太平洋上で戦うことのできるパイロットが養成されたともいえる。
速度、航続距離、運動性…カタログデータ重視が招いた結果
海軍の技術力は、凄まじいスピードで成長を遂げた。明治から技術導入を始めて60年で、世界一の戦艦「大和」をつくるまでになった。飛行機も零戦、九六陸攻という世界水準のものをつくりだした。
そして、足かけ4年、アメリカと互角に戦った場面もあった。これは驚異的な進歩である。短い期間にこれだけ進歩した国は、世界を見まわしてもないといっていい。
ただし、日本は本当の意味で、「完成された技術」まで至っていなかった。
たとえば、飛行機の修理をしていて、パーツが合わないことがあった。そういうときは、現場でパーツをやすりで削って合わせている。しかし、これは大量生産の理念に反する。具合の良し悪しが生じるのは、全く同じものをつくる能力が弱いということである。
また、海軍は完璧主義のところがあり、少しでもいいものを追求し、「こうやったらよくなる」と思うと、次々に改良を加えた。
その結果、零戦でも10種類ほどの改造型がある。しかし、何種類もあると、生産ラインが崩れ、現場のメンテナンスも大変になる。
アメリカはF4Fが零戦に負けていたが、しばらく我慢したのち、一気にF6Fに切り替えた。戦争中は一度つくったら、少々のマイナスには目をつぶり、新型を大量に準備したほうが現実的ということだ。
技術において決定的ともいえる問題は、兵器を要求する側の、「どのように使うか」「何のためにつくるか」というコンセプトが曖昧なことである。
日本は「カタログデータでよければ勝てる」という意識をもってしまい、速度、航続距離、運動性などの数値を要求した。
そこには「戦って勝つ飛行機」という、実戦に即した考え方が見あたらない。その結果、防弾の装備がない飛行機や、急降下したら壊れるような戦闘機をつくってしまった。
大砲にしても、魚雷にしても、射程の長さが重視されたが、遠ければ当たらなくなる。当たらなければ、兵器としての意味がない。
実戦を見据える視点が弱く、カタログデータがよければ高性能兵器だと思いこんでいたのだ。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月04日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語




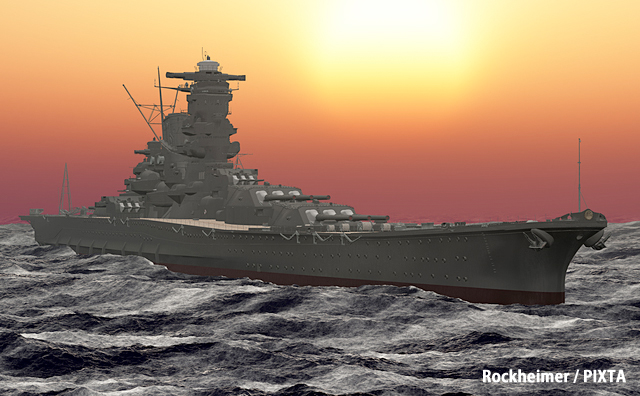


.jpg)


