幕末明治を生きた“新選組屈指”の剣士・斎藤一

幕末、京都の治安を守り、過激な不逞浪士相手に日々、最前線で斬り結んだ最強の剣客集団・新選組。その中でも屈指の剣士とされるのが、斎藤一であった。
副長助勤、組長を務め、池田屋事件、天満屋事件で活躍。局長近藤勇、副長土方歳三から絶大な信頼を寄せられ、会津戦争では、土方から新選組を託された男。
一方で出自、剣の流派、度々の改名、会津での進退など、従来、斎藤には謎が多いとされてきた。しかし最近の研究で、不明だった部分はかなり明らかになってきている。
「誠」の旗の下、凄腕の剣士は果たして何のために戦い、また警察官として生きた明治の世に、何を貫いたのか。
※本稿は、『歴史街道』2012年9月号 総力特集より、内容を一部抜粋・編集してお届けします。
明らかになってきた斎藤一の謎
「元徳川臣タリ。故有テ京地ニ到リ新選組ニ加入シ助勤役タリシガ撃剣ヲ能クシ柔ニシテ能ク剛ヲ制スノ器アリ。后会津ニ来テ縷々戦功アルニヨリ昇任シテ終ニ隊長トナリ…」。
新選組隊士中島登が、箱館で降伏した後に描いた「戦友姿絵」の、山口次郎(二郎)こと斎藤一の姿絵に添えられた文章の一節です。
斎藤一。新選組副長助勤、組頭(組長)を務め、剣の腕は隊内屈指。会津戦争では隊長として新選組を率いた男…。そんな斎藤一の人気がここ数年急に高まっているのは、コミックやゲームなどの影響のようです。
たとえば今年3月に聞催され、私が問題を監修した「新選組検定」の受験者へのアンケートでは、好きな新選親隊士のベストスリーは土方歳三、沖田総司、そして斎藤一でした。
一の特徴を挙げれば、新選組幹部の中で最年少ながら、剣をとれば抜群の強さであり、会津では新選組隊長として最後まで戦い抜いた点などがありますが、もう1つ、よく言われるのが、謎が多いということです。
たとえば出自や、剣の流派がよくわからない。一方で局長の近藤勇や副長の土方から深く信頼されて、御陵衛士に潜入したのはなぜか。また度々名前を変え、会津では土方や他の隊士と別れて残留したのはなぜか…。
そうした不明な点が多いとされることが一種謎めいた、ポーカーフェイス的な印象を与え、それもまた魅力となっているのかもしれません。
とはいえ新選組を研究する立場から申し上げると、たとえば原田左之助と比べて、一は格段に史料が少ないというわけではないのです。むしろこれまであまり脚光を浴びてこなかったため研究が進んでおらず、謎が多いイメージが先行してしまったのが実情でしょう。
しかし最近の研究によって、不明だった部分はかなり見えてきています。本稿では研究の成果を踏まえ、明瞭になってきた斎藤一の実像に迫ります。まずは従来、不明とされてきた点や通説などを簡単に解説してみましょう。
出自は明石浪人なのか
一は維新後、藤田五郎と名を改め、現在も藤田家のご子孫がいらっしゃいます。藤田家には『藤田家の歴史』という文書が伝わり、そこには藤田家は播磨国明石町の山口家の出で、明石藩の足軽であった。
そして五郎の父・山口祐助が江戸に出て、神田小川町付近の鈴木某(幕臣と思われる)に足軽として仕え、その後、御家人株を買った、という内容が記されています。
当時、御家人株は安くても200両といわれ、足軽の祐助には高価な買い物であることから、祐助は足軽奉公ではなく、商人だった可能性があるかもしれません。
いずれにせよこの記録に拠れば、一の生まれは幕府御家人となります。なお、祐助の次男として一が誕生するのは、弘化元年(1844)1月1日、あるいは2日のことです。
斎藤一の剣の流派は何か
一の剣の流派は、これまで一刀流、無外流、聖徳太子流など諸説ありましたが、裏付けとなる史料が不十分でした。むしろ史料から窺えるのは、近藤勇の試衛館の門人であり、天然理心流を学んでいたという事実です。
たとえば永倉新八の『浪士文久報国記事』には、近藤の試衛館道場の稽古人として「近藤勇始め山南敬助、土方歳三、沖田総司、永倉新八、佐藤彦五郎、大月銀蔵、斎藤一、藤堂平助、井上源三郎…」と、一が名を連ねます。
このうち永倉と藤堂は他流派の食客ですが、一はそうではありません。それを裏付けるものとして、御陵衛士として新選組から分離した阿部十郎の証言があります。「高弟には沖田総司、これがまあ勇(近藤)の一(番)弟子で、なかなかよくつかいました。
その次は斎藤一と申します。それからこれは派が違いまするけれども、永倉新八という者がおりました。この者は沖田よりはチト稽古が進んでおりました」(『史談会速記録』八三輯)。阿部は、永倉は沖田、斎藤とは流派が違うといっているわけで、逆にいえば一が沖田同様、近藤の弟子であると語っているのです。
新選組結成時、斎藤一は最年少幹部か
弘化元年生まれの一は、壬生浪士組結成時の文久3年(1863)に20歳です。山南より11歳、近藤より10歳、土方より9歳、永倉より5歳、原田より4歳、沖田より2歳年下で、藤堂と同い年。藤堂と並ぶ最年少の副長助勤でした。
斎藤一が近藤、土方から深く信頼され、御陵衛士に潜入したのはなぜか
一が他の隊士と異なる点があるとすれば、慶応3年(1867)に伊東甲子太郎ら14人が新選組から分離し、御陵衛士を結成した際の行動です。一も14人の1人に加わり、半年ほど新選組を離れますが、実は近藤や土方の密命を受けた「間者」でした。
近藤や土方が、危険かつ秘密保持が求められる困難な任務を、なぜ一に託したかといえば、まず同じ天然理心流であることへの信頼でしょう。
また一の孫・藤田實氏の証言では「祖父は無口な性格で、大変眼付きの鋭い人で、常に武人らしい生活ぶりでした…」(『時代とともに生きた剣客』)とあり、無口で武人らしく折り目正しい性格は、間者役に適任であったとも考えられます。
そして一もまた、近藤や土方と心を1つにしていました。永倉の回顧録『永倉新八』には、「勇は一に言い含めて、伊東甲子太郎の真意を探ってもらいたいと頼む。彼は一語のもとに伊藤(東)等と脱することを定める」とあり、黙々と危険な任務に臨む姿が窺えます。
斎藤一は、なぜ度々改名をしたのか
一はその名を、山口一 → 斎藤一 → 山口次郎 → 一瀬伝八 → 藤田五郎 と度々変えていますが、すべて理由あってのことです。
『藤田家の歴史』によると、山口一と名乗っていた19歳の時(文久2年(1862))、小石川関口で旗本を殺したため、父・祐助がかつて世話をした吉田某が京都で剣術道場を開いているのを頼り、江戸を出奔したとあります。それを信じれば、追及を逃れるために姓を斎藤に改めたのでしょう。つまり別人となったのです。
次に斎藤一を山口次郎に改めるのは、慶応3年のことです。御陵衛士に潜入した一は、近藤の暗殺を伊東らが計画していることを知り、御陵衛士を脱して近藤に急報しました。
しかし新選組と御陵衛士には、相互に隊士の移籍は認めない約定があるため、一の新選組復隊を公にはできず、一は名を山口次郎に改め、近藤の計らいで油小路事件の当日まで紀州藩士のもとに身を隠します。
以後、復隊後も一は山口次郎で通しました。なお一瀬伝八、藤田五郎への改名については後述します。
斎藤一は武田観柳斎を斬ったのか
「斎藤意を決し、仮橋(銭取橋)を渉るや否や抜き打ちに武田の背後より大袈裟に切る」。西村兼文の『新撰組始末記』の一節で、薩摩藩に内通した武田観柳斎を、慶応2年(1866)9月28日に一が斬ったとします。
しかし実際に武田が竹田街道で斬られたのは慶応3年6月22日。御陵衛士の分離後で、当時一は新選組に在籍していません。武田を斬ったのが新選組であったとしても、一ではないのです。
斎藤一の左利きは本当か
「斎藤は笑いながら、『槍の先生が、お突きを見事にやられているね、篠原君』という。篠原も笑って、『左お突きさ、相手は君と同じに左利きの遺い手だよ。わッはッはッはッ』『君と同じは止してくれ』」。これは子母澤寛の『新選組物語』の一節です。
祇園石段下で殺害された谷三十郎を検分する篠原泰之進が一に、「君と同じに左利き」と指摘していますが、一が左利きだったとする記述は他の史資料にはありません。
また谷の死因について永倉新八は『新選組同志連名控』で「病死」とし、西村の『新撰組始末記』には「故ナクシテ頓死ス」とあり、祇園石段下で殺害された記録はないのです。
左利きも含め、逸話自体が子母澤寛の創作である可能性が高いでしょう。なお「左利き説」から映画などで一が刀を右腰に差す設定も見られますが、考証的にあり得ないことをお断りしておきます。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月21日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】

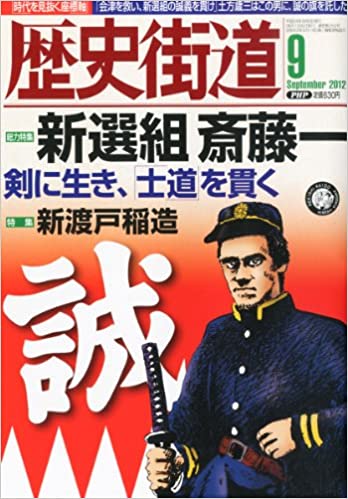

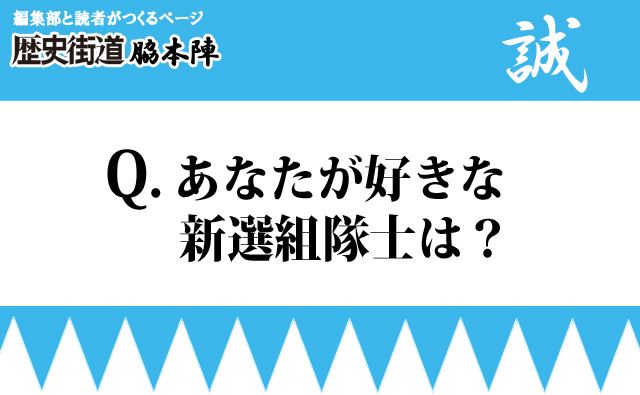


.jpg)


