坂本龍馬は「大事業のコーディネーター」だったと言える理由
2024年03月29日 公開
2024年12月16日 更新

昭和史の語り部として知られた故・半藤一利氏は、幕末史についての執筆も案外多い。自称「歴史探偵」が見抜いた歴史の裏側に潜む真実とは――。
人間的魅力と度量の大きさで、幕末という時代を駆け抜けた志士・坂本龍馬。
当時はもちろんのこと、いまの時代になっても人の心を惹きつけてやまないその龍馬の人間像を、半藤一利氏は「頭脳だけでなく、人間そのものが開明的だったと言うべき」だと評した。
近世から近代へ――時代を大きく動かした幕末のリーダーたちの言動に、激変するいまの時代を乗り越えていくためのヒントが秘されているのかもしれない。
※本稿は半藤一利著『もう一つの「幕末史」』(PHP文庫)より、一部を抜粋編集したものです。
たった5年で国を揺さぶる男に変貌した坂本龍馬
龍馬の脱藩は文久2(1862)年、これから亡くなるまで、わずかに5年余です。この短期間に超人的な行動力を見せ、幕藩体制の屋台骨を揺さぶりました。龍馬が世に出るのは勝海舟の門人になってから。開国派幕臣の勝の影響下、立場を超えた各藩要人との人間関係が急速に広がるのです。
司馬遼太郎さんは龍馬を「人たらし」と書きましたが、たしかに人間的魅力と度量の大きさがありました。同時代の龍馬評もすこぶるよく、貶す人はほとんどありません。これは権謀術数が渦巻く時代にあって、稀有なことです。
龍馬は学問の素養はありませんでしたが、理解力と咀嚼力が人並み以上に優れていた。勝海舟が世界の情勢を説き、海軍の振興、貿易の必要、人材登用を力説すると、たちまち海運商社の亀山社中を興し、血肉とします。
文久2年という年は、尊皇攘夷運動の波が高まり、京都では暴力や殺人の嵐が吹き荒れていました。さすがの幕府も土台の根腐れが露見し、権力にも翳りが兆してきます。その幕府に対して、まず楯突いたのが長州藩です。長州は朝廷を立てて幕府に対抗します。長州同様、朝廷を梃子に幕府に反旗を翻したのが薩摩藩です。
ただ当時、長州と薩摩は不仲でした。そんな時勢に活躍したのが脱藩浪人・坂本龍馬です。龍馬の大きな業績は2つあります。慶応2(1866)年の「薩長同盟」と翌慶応3年の「大政奉還」です。
実はどちらも龍馬独自の考えではありません。薩長同盟を率先提唱したのは同じ土佐の志士・中岡慎太郎、大政奉還は幕臣・勝海舟と大久保一翁のそもそもの発案です。龍馬の才は独創より斡旋、交渉、説得に発揮されたのです。
なかでも、藩の面子にこだわる長州・桂小五郎(木戸孝允)と薩摩・西郷隆盛を怒鳴りつけ、同盟を締結できたのは、人たらしの面目躍如です。
龍馬は考え方が自由で発想も豊か、そしてイデオロギーにとらわれません。さらに非戦論者で内乱を望みませんでした。龍馬が土佐藩の後藤象二郎を通じて幕府に大政奉還を促したのも、国内戦争を避けるためです。ここが武闘倒幕を企図する薩摩とは相容れません。
私は龍馬暗殺の黒幕に大久保利通がいて、潜伏情報を得て京都見廻組の頭取・佐々木只三郎に知らせたと推理しています。
龍馬は幕末の慶応3年、京都の近江屋で、中岡慎太郎とともに、佐幕の京都見廻組の手により斃れます。司馬さんは「天が、この国の歴史の混乱を収拾するためにこの若者を地上にくだし、......」と書いています。そして、用がすんだから天に召した、と。
しかし、彼の死後まだ混乱は続きました。龍馬は明治期、一時忘れ去られますが、私は龍馬の魂魄が司馬さんに傑作『竜馬がゆく』を書かせたように感じています。
日本人の深層心理にあって、ことあるごとに噴き出してくる「攘夷の精神」
黒船という武力に屈した形で幕府が開港を受け入れてしまったことをきっかけに、日本には尊皇攘夷の大合唱がわき起こりました。それが、明治維新への思想的エネルギーとなりました。
明治政府が成立すると、日本は近代化の道を邁進し、尊皇攘夷は、過去の言葉となったように見えます。しかし、それは日本人のなかから消え去ったわけではなく、実は、地下水脈のように流れ続け、ことあるごとに形を変えて噴き出してくると私は考えています。
二・二六事件は、尊皇精神の噴き出しの最たるものですし、大和魂という精神論で欧米と戦ってしまった太平洋戦争そのものが攘夷の精神の暴発であったと見ることもできます。
日米経済交渉などを見ても、どうも日本という国は、外圧に対する反応として、攘夷の精神が噴き出してしまうと思えるのです。これは、国際社会のなかで日本が生きていく上で、まことに厄介な問題です。
現代のわれわれも解消できずにいるこの攘夷の精神を、幕末にありながら完全に脱ぎ捨てていた人の一人が、坂本龍馬ではないかと私は思うのです。もちろん、龍馬も当時の青年志士同様に、攘夷いっぺんとうから出発しています。
こととしだいによっては、斬り捨てる覚悟で勝海舟を訪ね、かえって勝の開明的思想に目を見開かされ門弟になったと言われていますが、そうスッパリと自分の考えを転換できたわけではありません。
その後、長州藩は攘夷の実践として下関戦争を起こしていますが、このときの龍馬は乙女姉さんにあてた手紙に、ひと戦して夷敵を追い払わん、といったことを書いています。
しかし、龍馬は勝が神戸に開いた海軍塾の塾頭になり、そこから大きく変貌していきます。薩長連合を実現したのが32歳、大政奉還の報を聞いた33歳でその生涯を閉じています。あらためて龍馬の歴史上の活躍期間が非常に短いことに驚きますが、わずか数年の間に、恐るべきスピードで自己改革をなし遂げたのが龍馬なのです。
実際に龍馬が書いたものではないという説もありますが、龍馬の精神を物語る「英将秘訣」というものがあります。その一部を見てみましょう。
一、俸禄などいうは、鳥に与うる餌の如きもの也。天道あに無禄の人を生ぜん。予が心に叶わねば、やぶれたるわらじをすつる如くせよ。
一、義理などは夢にも思うことなかれ。身を縛らるるもの也。
一、恥という事を打ち捨てて、世の事は成るべし。
一、なるだけ命は惜しむべし。二度と取りかえしのならぬもの也。拙きということを露ばかりも思うなかれ。
一、礼儀などいうは、人を縛るの器也。
ここで龍馬は、日本人の美意識とも言える義理も恥も礼儀も、大きなことを成すには邪魔ものだと言い切っています。もちろん、義理とは封建制度に縛られること、恥は、思想的転向を恥じるなと言い換えるべきでしょうが、これほどの割り切りようは、日本人離れをしていると言わざるを得ません。
人間そのものが「開明的」だった龍馬
薩長連合の実現。「船中八策」を起案し、大政奉還への道筋をつけたこと。これが、龍馬の2つの偉業と言えますが、両方ともアイデア自体は龍馬のものではありません。
意地悪な言い方をすれば、龍馬は、他人の褌で相撲をとった。龍馬は政策マンではなく、大事業を実行する際のコーディネーターだったと言えるでしょう。
人と人を結びつけ、プロジェクトを完成させるという点では天才的な力を持っていました。しかも、それを実現するために走り回ることをまったく苦にしない稀有な能力を持っていました。
龍馬は中岡慎太郎と土方久元から薩長同盟の策を聞き、それは名案、さっそく薩摩を説こうと動きました。中岡らと違い、龍馬には、西郷と交流があったのです。
当時長州は、朝廷を追われ、幕府からは征長令が出て、孤立無援の窮地に立たされていました。薩摩は幕府側に回っていたわけですから、長州の薩摩に対する不信感は、ちょっとやそっとでは拭い去ることができないものでした。
この感情のこじれを修復するために、龍馬は、薩摩に話をつけ、海援隊を使って、薩摩の金で長州に軍艦と武器を供給します。理屈を説くだけではなく、いわば"実弾"を用いたところが、龍馬の本領と言えるでしょう。
いよいよ両藩縁組という段になり、長州の桂が薩摩屋敷に西郷を訪ねるわけですが、待てど暮らせど、一向に西郷からその話は出てこない。当時、追い詰められていた弱い立場の長州は、薩摩と連合したくとも面子があり、自分の側からは頭を下げてまでして言い出せない。
一方薩摩の側も長州の側から言い出させることによって、自分らの立場を優位に持っていこうと考えていたのでしょう。龍馬から見れば、面子や優越感にとらわれて、大事を見失っている事態でした。
ことの成り行きを知った龍馬は、「おれが両藩のために挺身尽力するのは、決して両藩のためにあらざるなり、区々の痴情を脱却し、何ぞ丹心を吐露し、天下のために将来を協議せざるのか」と西郷と桂を叱りつけた。
この龍馬の怒りがなければ、薩長連合は成立しなかったわけですから、まさに龍馬の精神が歴史を動かしたと言えるでしょうね。
大政奉還に関して言えば、「船中八策」を起案したことにより、それを土佐藩参政、後藤象二郎に見せたことに、龍馬の非凡さがあります。後藤象二郎は、土佐藩の中枢にいた人物ですから、土佐勤王党の盟主、武市半平太を殺した男と言ってもいい。
同志を殺した男とは、口を利きたくもないというのが普通でしょうが、龍馬には、それも小さなことでした。それより天下のことのほうが大事です。後藤に話せば、前藩主山内容堂に伝わり、この策が実現に向かうと踏んだのです。まさに、恥とか怨みにこだわっていてはできない発想です。
人間は感情の動物です。いくら論が立ってもそれだけで人は動きません。龍馬の場合は、頭脳だけでなく、人間そのものが開明的だったと言うべきでしょう。
もし、死んでいなかったら龍馬はどうしたか?
慶喜の大政奉還の決断を知り、龍馬は、「よくも断じ給えるものかな。自分はこの将軍のために命を捨てよう」と涙を流します。ところが、この大政奉還という機に乗じて、薩長は武力倒幕に動いていきます。
新政府のメンバーに自分の名を連ねず、「世界の海援隊でもやります」と言ったほど権力に執着のなかった龍馬から見れば、すでに大政を奉還した幕府をつぶすために血を流す国内戦争など、愚の骨頂でした。
それより早く新しい国づくりにかからなければならない。龍馬は、京都の近江屋で、武力倒幕すべしという中岡慎太郎と大激論を交わしている最中に、京都見廻組の刺客に襲われ命を落としましたが、そのときすでに、薩摩は倒幕の兵を出発させていました。
時局は、龍馬の理想を裏切る方向にヒタヒタと歩み出していたのです。薩摩は岩倉具視と謀り、偽勅を発して、遮二無二倒幕への流れをつくり出しています。明治政府は、薩長が関ヶ原以来の徳川への怨みを晴らすべく打ち立てた政権であったという側面も見落とすことはできないのです。
もし、龍馬があそこで死んでいなかったらどう動いたか? やはり、倒幕戦を止めるために動いたろうと思います。
龍馬が動いたら面倒なことになる、薩長は、とくに薩摩はそう思った。邪魔者は殺せです。龍馬を殺さねばならぬと薩摩は考えたと私は想像します。私は龍馬暗殺の背後に、薩摩がいたとする説をとっていますが、もちろん仮説です。
薩摩も長州も龍馬には大きな借りがあるわけですから、龍馬が生きていて反対側に回っていたら、武力倒幕の大きな障害になったことは間違いありません。
龍馬を起点に「今」を問い直してみると......
国家というものは、ヨーロッパであればキリスト教、アメリカであれば民主主義といったように、精神の機軸というべきものが必要です。明治政府もそれを必死になって探し、天皇を機軸に据えた立憲君主国家を目指していきました。
しかし、それは同時に薩長による暴力革命という色彩を消すことも意味していました。明治10年代に沸騰した自由民権運動も、エモーショナルな部分では、薩長独裁への非難が渦巻いていました。帝国議会の設置は、その批判をかわす装置としては実は見事に機能していたのです。
もちろん、明治という時代は、教育機会も国民に与えられ、奇跡的とも言える近代化を達成し、欧米の侵略から自国の独立を守ることができました。
しかし、議会を開設する一方で、軍の統帥権というものもあみ出され、軍は議会のコントロール外に置かれていきました。やがて、この独立した統帥権は、独り歩きを始めて、太平洋戦争という破局に向かったのです。
龍馬が夢に描いた新国家と現実の歴史は、似て非なるものと言わざるを得ないでしょう。そして今、われわれはいかなる国をつくりたいのか。
龍馬が非業の死を遂げたところを起点に、もう一度歴史を問い直すことは、今の日本に噴き出している問題を考える上で欠かすことができません。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月13日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

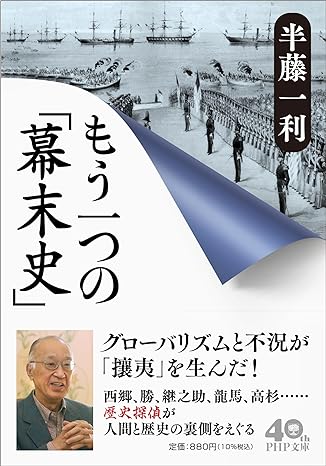





.jpg)


