甘党だった牧野富太郎が“菓子店で恋した二人目の妻”...その生い立ちとは?
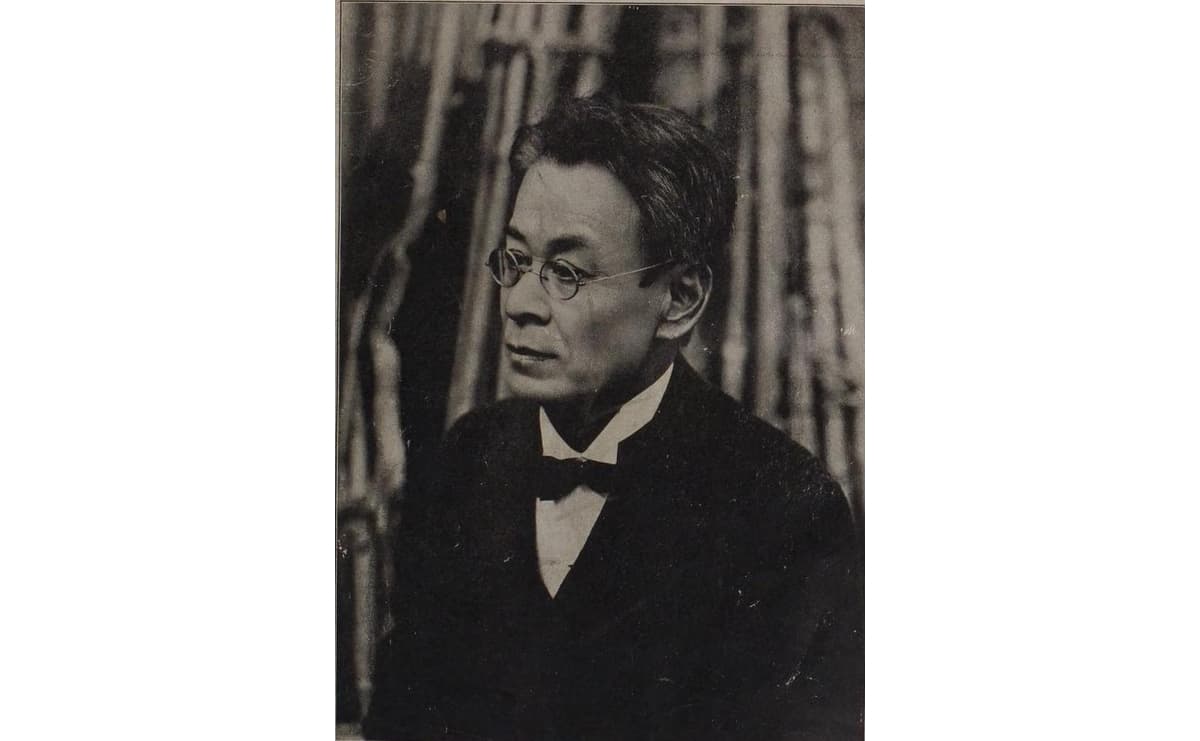
出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/328/)
NHK連続テレビ小説『らんまん』の主人公のモデルである牧野富太郎。「日本植物学の父」と呼ばれ、どこまでも植物一筋に生き続けた富太郎を懸命に支えていたのは、妻・ 壽衛だった。牧野富太郎と壽衛の出会いについて、作家の鷹橋忍氏が紹介する。
※本稿は、鷹橋忍著『牧野富太郎・植物を友として生きる』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
池野成一郎との友情...22歳・明治17年(1884)
富太郎は毎日のように植物学教室に通い、熱心に学んだ。彼の植物に関する知識の深さは、植物学教室の人たちも一目置くものがあり、富太郎は次第に植物学教室の重要な存在となっていく。
「狸の巣」と称された富太郎の下宿には、植物学教室の松村任三や、動物学の石川千代松(1860〜1935)など、いろいろな人々が訪れた。
そのなかでも、一番に気が合い、親しかったのは池野成一郎(1866〜1943)だ。
池野は植物学教室の学生だった。のちにドイツ・フランスに留学し、帰国後は東京大学教授となり、ソテツの精子を発見した。英語、フランス語に堪能で、ローマ字の普及にも尽力している。
池野は富太郎の下宿に来ると、上衣を脱いでごろりと横になり、両足を高く床柱にもたせかけたという。無遠慮な振る舞いに思えるが、こういうことが許されるほど、二人は親しかった。
富太郎と池野はともに植物の採集に出かけ、本郷の梅月という菓子屋で買った「ドウラン」と呼ばれる栗饅頭風の菓子を一緒に食べた。
富太郎も甘党であるが、池野も大変な菓子好きであった。10個や20個は、造作もなく平らげた。また、池野は食べるのが速かった。一緒に牛鍋を囲んだとき、ちょっと油断すると、皆食べられてしまう危険があったという。
富太郎が書いた英文を添削したのも、のちに富太郎が苦しい立場に追い込まれるたびに、最も積極的に助けたのも池野である。富太郎は、池野との友情を生涯大切にした。
このように東京での生活に基盤を置きつつも、富太郎は岸屋の跡取りであり、佐川の実家を捨てきれずにいた。よって、この後数年、東京と佐川をたびたび行き来することになる。
同年11月、帰郷した富太郎は、「公正社」を学術研究だけを目的とする「佐川学術会」へと変えた。
また、教員時代にオルガンを習い、東京で多少なりとも西洋の音楽に触れた富太郎は、いまだ佐川には一台のオルガンもないことや、小学校の音楽教育の水準が低いことも気になった。富太郎は子どもたちだけでも西洋音楽に触れさせたいと願い、そのための活動もはじめた。
このころ富太郎は、祖母・浪子の強い望みによって、従妹の猶(なお)と結婚したとみられている。結婚についての詳細はわからない。最初の妻について、富太郎自身は何も語っていないのだ。
富太郎が語るのは、2番目の妻となる壽衛(すえ)だけだった。
三度目の上京...24~25歳・明治19~20年(1886~1887)
富太郎の最初の妻とされる猶は、師範学校を卒業した、教養ある女性であった。岸屋にもよく手伝いに来ていたので、店のことも熟知していただろう。岸屋の主人の妻として、申し分のない女性であったと思われる。
しかし、富太郎とは性格が合わなかったらしい。時期は定かではないが、二人は間もなく離婚したという(入籍はしていなかったとも)。
二度目の上京の翌年(明治18年〈1885〉)、富太郎は幡多郡(はたぐん)に、二度目の植物採集の旅に出ている。
膝丈の着物に唐木綿の白い帯を締め、白い横緒の下駄を履き、肩から大きな採集用の胴乱(どうらん:ブリキ製のカバン。富太郎の愛用品は、左に小さな蓋があり、そこにおむすびを入れられた)を掛けた富太郎は、植物好きの友人たちとともに、郷里で植物の研究を続けていたが、同年7月、佐川学術会は解散した。
やはり上京への思いが強く、翌明治19年、24歳の年に、再び東京へと向かった。三度目の上京である。
次のページ
祖母・浪子の死...25歳・明治20年(1887) >
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

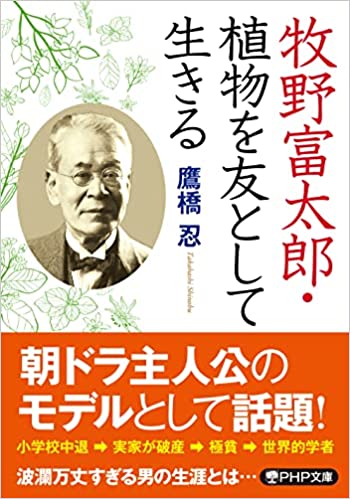




.jpg)


