信長6万の軍勢をも退けた雑賀孫一と鉄砲衆...秀吉・家康も恐れた「雑賀衆」の強さとは?

『太平記英勇傳』に描かれる鈴木孫市(部分)。別名、雑賀孫ー(東京都立中央図書館蔵)
時には一斉射撃で織田軍をなぎ倒し、時には狙撃で信長を負傷させる...。10年に及ぶ石山合戦で信長の前に立ちはだかったのは、雑賀孫一と雑賀衆であった。信長を苦しめた彼らの戦ぶりとは。
※本稿は『歴史街道』2022年11月号より、抜粋・編集したものです。
豊かな土地が生んだ「最強の鉄炮集団」
天文23年(1554)、12歳で本願寺11世法主の座に就いた光佐・顕如は、北陸の一向一揆の勢力増大を背景にその勢威を大きくした。
しかも婚姻政策を取り、室町管領・細川晴元の妻の妹(左大臣・三条公頼の三女)を正室に迎えた。
さらに寺内町に新興商工業者を集めて財政を豊かにし、石山本願寺の防備施設を強固にするなどして、本願寺を戦国大名と対抗する一大勢力に発展させた。こうした顕如の前に立ちはだかったのが、畿内に勢力を拡大する織田信長である。
足利義昭を奉じていた信長の当面の敵は、摂津の野田・福島に拠点を構えた、阿波出身の三好三人衆であった。この三好一族との抗争の過程で信長は、本願寺の顕如が三好一族と結託しているのではないか、と疑心を抱いた。また、本願寺のある石山は「要地」であり、西国攻略の拠点としてこの地を欲しいとする信長の野心もあった。
一方、顕如は信長出兵の本当の狙いが本願寺攻撃ではないかと考え、元亀元年(1570)9月12日の夜半、先手を打って攻撃に出た。「十年戦争」といわれる「石山合戦(本願寺一向一揆)」の始まりである。この直前、紀州の雑賀衆は顕如から本願寺守備の要請を受けていた。
雑賀衆というのは、紀ノ川下流域にあった五荘郷(雑賀庄・十ヶ郷・宮郷・中郷・南郷)に住む人々を総称した名である。五縅とも呼ばれる地域共同体で、その最も得意とする技術が「鉄炮」であり、「雑賀衆」といえば一族郎党を上げて鉄炮上手で知られていた。
これには、海に面した雑賀という土地柄が関係している。紀州水道から太平洋に繫がり、一方で大坂湾から瀬戸内海に繫がっていたことから、日本国内遠隔地(あるいは海外)との接点を持ち易く、鉄炮の技術や薬品などの素材を導入でき、さらには交易を通じて豊富な経済力を備えていたことも「鉄炮集団」としての成長に繫がったのである。
雑賀衆は、従属する主君を持たず、依頼された先で働く「傭兵」の形で諸国に出向いた。宗教的には強固な門徒組織(一向宗)を形成していた。この雑賀・十ヶ郷の棟梁が、鈴木孫一重秀である。通称を「雑賀孫一」ともいう。
孫一は本願寺・顕如からの要請に従って、3千ともいわれる鉄炮集団を率い、和泉山脈から泉州平野を経て石山本願寺を目指した。雑賀衆3千は、顕如にとっては3万の兵力にも等しい軍団であった。
本願寺挙兵直後の淀川堤の戦闘で、雑賀衆は鉄炮を自在に使って織田軍を翻弄した。孫一の戦い方の特徴は、個々の鉄炮ではなく、集団として大量の鉄炮を使うことにあった。大量の鉄炮を集中して使うことで、有効性が高まるのである。
孫一は、これ以外にも「鉄炮構え」と称して鉄炮隊の前面に柵を結んで畳を立て掛けたり、土塁や空堀を使ったりもした。後年、信長が(長篠合戦などで見られるような)鉄炮を機能させるために「馬防柵」を有効活用したのは、孫一らを真似たものであろう。
苦杯を喫し続けた信長は、元亀三年(1572)10月に講和を結ぶ。だが、この講和も翌年には早くも破れてしまう。戦いが再開されると、孫一は再び本願寺に駆け付けた。
信長が憎悪した鉄炮の威力
孫一同様に信長も忙しい。天正元年(1573)から天正4年(1576)までの間に、強敵・武田信玄の病死、将軍・足利義昭の追放、伊勢長島・一向一揆の壊滅、長篠合戦、越前・一向一揆の壊滅など、信長にとって有利な(逆に顕如にとって不利な)出来事が次々に起きていた。
この天正4年5月、再び本願寺を包囲して攻め掛けた織田軍に対して、孫一は自ら鉄炮を抱え雑賀衆を指揮した。この時点で、本願寺・顕如は雑賀衆に頼り切っている。
信長は、本願寺の補給が木津川河口を利用して行なわれていることを知り、その補給路を断つために陸上からの攻撃を企図した。この方面の担当武将は、原田(塙)直政であった。孫一は、この情報を事前に察知した。
「織田軍に、本当の鉄炮の使い方を教えてやろうぞ」
雑賀衆の鉄炮の強みは、確実に敵が倒せる範囲内に入ったところでの一斉射撃にある。孫一の号令が掛かると、雷が辺り一面に広がって落ちたかのような轟音が響いた。
硝煙が霧のように一帯を覆い、織田軍の先頭を走る足軽が吹っ飛んだ。数回の一斉射撃で、アッという間に300人ほどが倒れ伏し、その背後で鑓を掲げていた司令官・原田直政が落馬した。討ち死にである。
孫一は容赦なく指揮を続け、自らも鉄炮を構えて遠方の武将たちに狙いを付ける。織田軍の被害は増加するばかりである。何の成果のないまま織田軍は撤退した。雑賀衆に歓声が上がった。
敗報を知った信長は数日後、河内・若江城に入り、四天王寺に籠もっていた本願寺勢に攻め掛かった。これを知り、孫一は雑賀衆と共に援軍に駆け付けた。
織田軍の中に異様な風体の武将を見つけた孫一は、傍らにいた配下に「あの唐人兜(ヨーロッパの兜)が信長のようだな」と確認した。
配下は頷く。「御大将自らの御出陣か。では、その首を貰い受けるか」とばかり、孫一は弾込を終えた鉄炮を構えた。遙か先にいる信長が何事かを叫んだのが見えた。そこをすかさず孫一は引き金を絞った。肩に軽い衝撃があった。
孫一の放った鉄炮の弾は、その瞬間に偶然信長の前で立ち上がった足軽の身体を撃ち抜いて、さらに信長の足を掠めた。信長は、足軽の倒れた直後に、右足をがくりと折り転倒した。信じられないものを見た気がしたのであろう。
信長は立ち上がりもせずに、四方を将兵に囲まれたまま後方に下がった。信長の怒りが憎悪に変わった。この瞬間、信長は「雑賀攻め」を決意したのだった。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月25日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

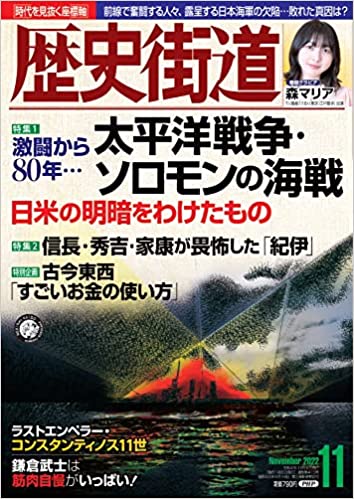
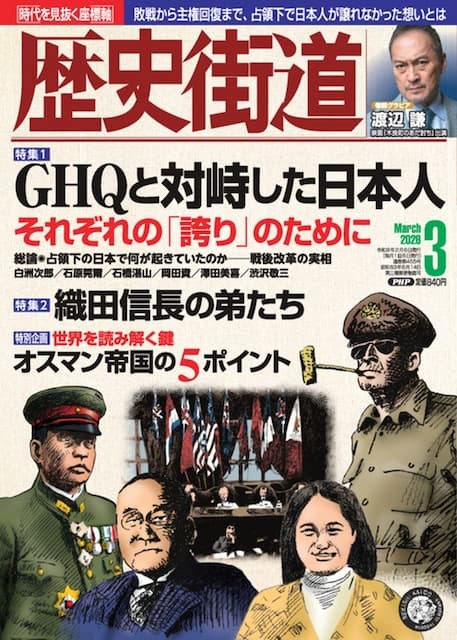




.jpg)


