赤穂の旧藩士は、なぜ吉良邸に討ち入ったのか?~東大名物教授が解説
2019年11月27日 公開
2024年12月16日 更新
大石と浪士が考えていた名誉に対する違い
赤穂の旧藩士たちは、実は藩主が切腹したことについては理不尽だとは一言も言ってはいません。これは、江戸城内で人に斬りかかれば切腹になるのは仕方がないと、藩士たちもわかっていたからです。ただ問題なのは、吉良が生きているということでした。
刃傷事件を起こしたということは、武士の世界では「互いに喧嘩をしている」ということになるわけです。だから、喧嘩両成敗というのが当時の法律的な常識であって、喧嘩をして浅野が切腹になったのなら、相手の吉良も切腹するのが当然であろうと考えるわけです。その喧嘩相手の吉良に切腹をさせないという処置に対して、赤穂の旧藩士たちは怒っているのです。
しかもそういう状態を放置していることは、自分たちに恥が降りかかってくることを意味します。だからこそ、吉良をなんとかしなければいけないというのが、赤穂の旧藩士たちの考え方なのです。これは、当時の史料にも出てくる言葉の「片落ち」ということです。
吉良は生きていました。しかも軽傷です。赤穂旧藩士の急進派としては、とにかく吉良が死んでいないのなら、吉良を殺すことによって喧嘩両成敗を実現することができるわけです。
赤穂藩家老の大石内蔵助は、最初に浅野家再興を考えます。この浅野家再興というのは、単に浅野家を内匠頭の弟、浅野大学が継いで復興することだけで果たせるものではなく、同時に吉良上野介に何らかの処分がなければ、意味がないと大石は言っています。処分が下れば、浅野家は本当の意味で再興が叶い、大学の面子も立つわけなのですが、それも最終的には実現しませんでした。
そのころ、江戸の町人たちもこの赤穂の武士は討ち入りするのではないか、と噂していたようです。主君が切腹になりながら、吉良上野介が生きているという状態は、赤穂の武士たちが許すはずがない、当然討ち入りに行くだろうと考えていました。
しかし、その討ち入りがなかなかないものですから、赤穂の武士たちは腰抜けであるという評判も立ってしまいます。他藩も、腰抜け侍を雇うわけにはいきませんから、再就職もうまくいきません。
だから彼らは、名誉を回復しなければいけない。その一番手っ取り早い手段が、吉良上野介の屋敷に討ち入って、吉良の首を取ることだったのです。
結局、浅野の切腹から討ち入りまでに1年9カ月もかかるのですが、堀部安兵衛たちは、そうした江戸の噂が我慢ならず、大石に一刻も早く吉良邸に討ち入ろうと突き上げています。ただ堀部がおもしろいのは、最初にすぐに討ち入ろうと思ったけれど、そのときには吉良の親戚である上杉家の家臣たちが屋敷を警護していたので、ここで討ち入れば、当然死ぬ、死んだら名誉は回復されるわけですが、「犬死にする必要はない」と言っています。
要するに、自分一人が死ぬことによって武士としての名誉は回復するかもしれないが、赤穂藩全体の名誉は回復できないので、ここで討ち入るわけにはいかないと考えたのです。
本当は自分はすぐにでも討ち入りたいのだけれども、多くの同志がいないと討ち入りが成功しないので、大石が自分に同意するのをずっと待っているという状況になったのです。
元禄15年(1702)7月、浅野大学が本家の広島藩浅野家にお預けになると決まり、これで最終的にお家再興の希望は潰えます。大石は最初から堀部に「お家再興の望みがまだある。それがダメだったら自分にも考えがあるから待ってくれ」というふうにおさえていましたが、その望みが潰えることでついに決断します。
ただ大石も、浅野家再興と吉良上野介への処分を幕府がやってくれるとはおそらく思っていなかったので、最終的には討ち入りをやらなければいけないだろうとは思っていたでしょう。
大石は家老の身分ということもあって、当初、なんとか浅野家自体の名誉を回復しなければいけないと考えていました。主君に対する忠義だけではなくて、お家に対する忠義があるので、いろいろな手段を使って名誉を回復することはできると考えていたようです。浅野家再興もその一つの手段だったのです。ただそれが潰えれば、これはもう吉良を討つしかないとなるわけです。
それで12月14日、「四十七士」と言われている47人の討ち入りとなります。討ち入り後、一人いなくなるので「四十六士」と言われることもあります。
だいたい赤穂藩には藩士が300人くらいいました。討ち入ったのはそのうちの47人です。六分の一1近くに減っています。赤穂藩が断絶して赤穂城を明け渡したとき、大石と行動を共にすると誓った者がまだ120人くらいいたことを考えると、ずいぶん減ったと言えるかもしれません。ただ、討ち入りすれば、成功したとしても必ず幕府の処罰があって死ぬことになると彼らは考えているわけで、そういう意味では47人という数は少ないというより、よくこれだけ残ったと言えると思います。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

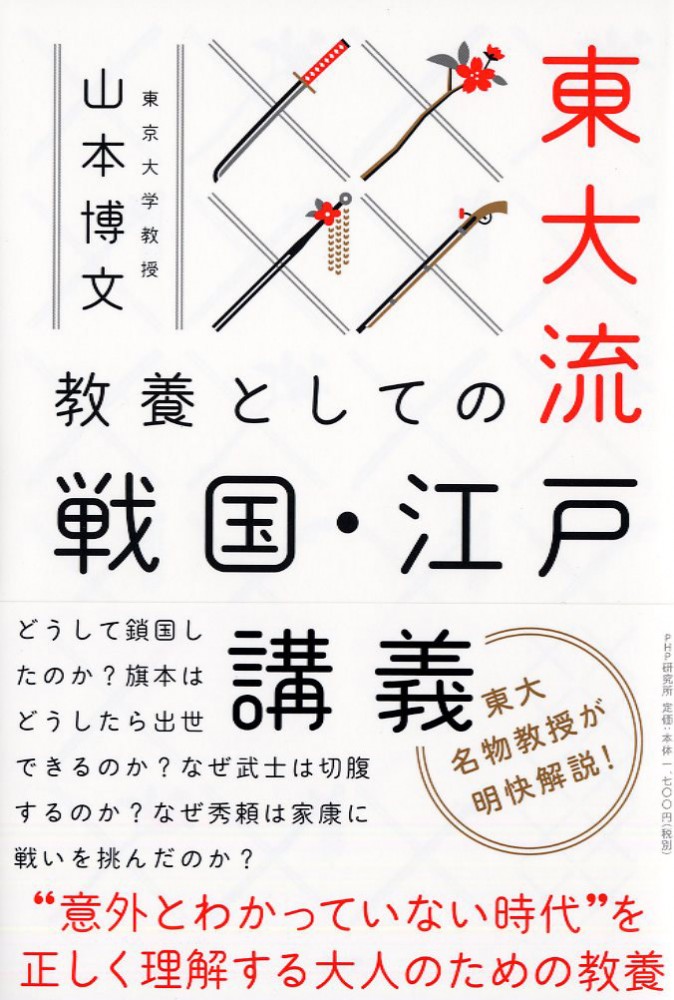





.jpg)


