天下分け目の天王山!山崎合戦~五十五年夢、明智光秀の最期
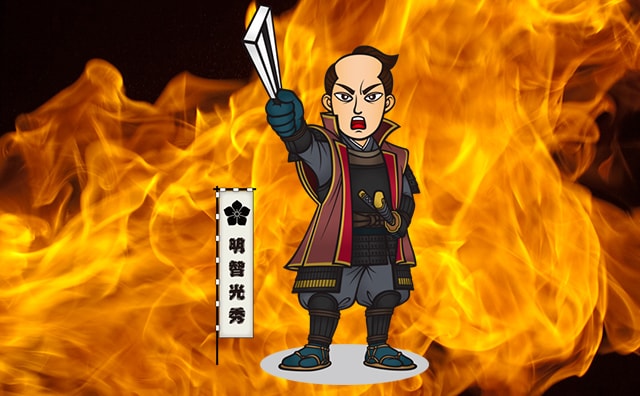
天正10年(1582)6月13日、明智光秀は、中国大返しを強行した羽柴秀吉と、摂津国と山城国の境で激突した。いわゆる天王山の戦い、山崎合戦である。その戦いの経過とその後の光秀について、小和田哲男著『明智光秀と本能寺の変』(PHP文庫)より紹介する。
山崎の戦いの経過
明智光秀は、羽柴秀吉の軍を京都で迎え撃つことはまずいと考えていた。京都を戦場にすることは避けたいと思ったのと、やはり、朝廷・天皇を掌中の玉として自分の手の中に握っていたいという思いがあったのであろう。
西国から駆けつけてくる秀吉軍を迎え撃つには山崎のあたりが最適と考えた。そこは、京・大坂のほぼ中間点であり、天王山と淀川とにはさまれた隘路となっていて、防戦するにはもってこいの地形だったからである。
実際の山崎の戦いといわれている両軍の激突は13日であるが、その前日、早くも山崎周辺では両軍の先鋒同士の小競りあいははじまっていた。
秀吉軍の先鋒は、池田恒興・高山重友・中川清秀といった摂津衆である。これは何とも皮肉なことといわねばならない。本来なら、光秀軍の先鋒となって秀吉軍を防ぐべく期待されていた光秀の与力衆が、逆に、秀吉先鋒として、光秀軍に戦いを挑む形なのである。
もっとも、当時は、たとえば寝返ってきたばかりの部将を最前線に置いて、その忠誠度を試すということは一般的に行われていたので、このときの布陣は、いってみればセオリー通りだったのかもしれない。

翌13日、いよいよ合戦の当日である。光秀は下鳥羽から御坊塚に本陣を移し、天王山麓を進んでくる秀吉軍に備え、円明寺川の自然堤防背後の低湿地に布陣した。『太閤記』では、このときの光秀の軍勢を1万6000としているが、本能寺の変のときの1万3000からふえた形跡はなく、むしろ、近江の安土城・坂本城・長浜城にも兵を残しているので、せいぜい1万ほどではないかと思われる。
それに対する秀吉側であるが、秀吉本隊が約2万、それに織田信孝4000、丹羽長秀3000が加わり、さきにふれたように、光秀の与力だったにもかかわらず秀吉側についた池田恒興5000、中川清秀2500、高山重友2000で、合計3万6500という大軍にふくれあがっていた。
仮に、光秀与力の摂津衆三人が、秀吉側ではなく光秀側についていれば、軍勢の数では光秀軍も遜色はなかったわけで、摂津衆を味方にできなかったことが、ここにきて、戦局を圧倒的に秀吉有利な状況にしてしまったわけである。
『太閤記』では、この日、午前6時ごろから天王山の争奪戦がはじまったかのように書かれているが、実際は、『兼見記』によって、申の刻、すなわち午後4時ごろ戦闘がはじまったことがわかる。
光秀軍の最前線の一つで、天王山東麓に布陣していた並河易家・松田左近隊が、中川清秀・黒田孝高・神子田正治ら秀吉軍の先鋒に攻撃を仕懸けたのが開戦の合図となり、両軍の本格的な戦闘となった。
ところが戦いがはじまって少しして、光秀軍の最前線のもう一隊斎藤利三隊が秀吉軍の池田恒興隊、加藤光泰隊らに包囲され、孤立状態となり、その乱戦の中で斎藤利三隊が敗れ、斎藤隊が崩れはじめたのである。
光秀家臣の中でも、最も勇猛な部将として知られ、それだけに、光秀としても一番頼りにしていた斎藤利三が敗走したことで、早くも戦いの帰趨は決した感じであった。
光秀軍の中で最高の3000を擁していた斎藤利三隊が崩れたことで、そのまま御坊塚にとどまることができないとみた光秀は、本陣を後方の勝龍寺城に移した。
しかし、勝龍寺城は、規模もそう大きくはなく、また平城だったので、光秀は、籠城してももちこたえることは不可能と判断し、日が落ち、暗くなるのをまって、城からの脱出をはかっている。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月24日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか





.jpg)


