蜀山人・大田南畝~ワークライフバランスの達人
2018年05月09日 公開
2024年12月16日 更新

仕事も趣味も充実させた幕臣・大田南畝
大田南畝は寛延2年(1749)、幕府の御徒・大田吉左衛門の長男として、江戸牛込仲御徒町に生まれました。通称、直次郎、七左衛門。南畝、蜀山人の号などでも知られます。
小身の幕臣の倅である南畝は、若い頃から学問で身を立てることを考え、15歳の時に内山賀邸に入門します。賀邸は通称伝蔵。牛込加賀町に住む幕臣でしたが、近隣の子弟に国学や和歌を教えていました。一方で賀邸は狂歌を好み、門人にも勧めます。南畝は近所なので通ったのでしょうが、賀邸に相当な影響を受けたようです。
明和2年(1765)、17歳で父の跡を継いで幕臣となりました。またその頃、篠山藩の儒学者・松崎観海に入門、徂徠派の漢学を学んだといわれます。一方で賀邸門下の平秩東作ら、後に戯作や狂歌で名をなす人々と親しく交わりました。
明和3年(1766)、18歳の時に作詩用語集『明詩擢材』を編集、翌年、戯作第一集の『寝惚先生文集』を平賀源内の序を付して著わすと、これが評判を呼びます。当時、源内は38歳。よく19歳の南畝の作品に序を寄せたものですが、源内の眼鏡に狂いはなく、この作品が江戸の狂歌ブームの火付け役となりました。
それから20代から30代にかけて、南畝は狂歌や洒落本など、戯作の世界で存在感を増していきます。当時はちょうど老中・田沼意次が幕政を主導していた田沼時代でした。田沼は蘭学を支援し、平賀源内とも交流があったことが知られています。学問や文化が花開いた時代に、南畝も活躍しました。
ところで南畝の家は、泳法を代々伝えていたようです。水泳は今でこそ一般的ですが、江戸時代は泳法を限られた家が継承し、それを教えたりしていました。 安永2年(1773)、25歳の時、10代将軍家治上覧の水泳の催しに南畝も泳者の一人として参加し、褒美に時服を賜ったといいます。文学だけでなく、運動にも長けていたのでしょう。
天明3年(1783)、35歳の時、『万載狂歌集』(『千載和歌集』のパロディです)を発表、翌年には小説で『頭てん天口有(あたまてん てんにくちあり)』を発表します。後者は高級料理店「桝屋」に江戸の料理店が料理で勝負を挑むストーリーで、実在の店名や料理が登場し、本邦初のグルメ小説とされるようです。
天明6年(1786)には吉原・松葉屋の遊女を身請けして妾としました。粋な文化人の南畝ですが、しかし、この年を境に南畝は狂歌から距離を置くことになります。理由は翌年から始まる老中松平定信の寛政の改革でした。
田沼意次が失脚して松平定信が政権を握ると、緊縮財政、風紀取締りなど、世の引き締めを図ったことはよく知られます。この時、政治を批判する狂歌として「世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといひて夜もねられず」が庶民に受け、その作者は南畝であると疑われました。南畝はこれを否定します。事実であれば、幕臣として取り返しのつかないことになるところでした。
そして職務に精励する意味も込めて寛政6年(1794)、46歳にして、昌平坂学問所で学問吟味(人材登用試験)を受験し、5日間にわたるハードな試験でしたが御目見え以下の身分の首席で合格します。やはり只者ではありません。
その後、享和元年(1801)には大坂銅座出役として大坂に赴き、銅を「蜀山居士」とも呼んだことから、「蜀山人」の号を使い始めています。さらに文化元年(1804)には長崎奉行所に赴任。これは左遷であったともいわれます。この時、初めてコーヒーを飲んだ南畝は「紅毛船にてカウヒイというものを飲む。豆を黒く炒りて粉にし、白糖を和したるものなり。焦げくさくて味ふるに堪えず」と記したとか。
1年ほどで長崎勤務を終えた南畝は江戸に戻り、文化5年(1808)には堤防を調査する玉川巡視の役目に就きました。この頃のことでしょう。『調布日記』に、谷保天満宮が神無月に目白あたりで開帳を行ない、賽銭稼ぎをしたことについて、 「神ならば出雲の国に行くべきに 目白で開帳やぼの天神」 と詠み、ここから「野暮天」という言葉が生まれました。
文政6年(1823)、南畝没。享年75。辞世の句は、 「今までは人のことだと思うたに 俺が死ぬとはこいつはたまらん」とも 「生き過ぎて七十五年食ひつぶし 限りしられぬ天地の恩」ともいわれます。 当時を代表する文人でありながら、幕臣としてもきちんと務めを果たした南畝。仕事も趣味も充実させたそのワークライフバランスは、現代人も見習うべきかもしれません。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月05日 00:05
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- 国宝級の発見「巨大蛇行剣」から何が分かったのか? 謎の4世紀の姿を探る鍵
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 『豊臣兄弟!』丹羽長秀役・池田鉄洋が訪ねる 盟友・柴田勝家を裏切った男の真実


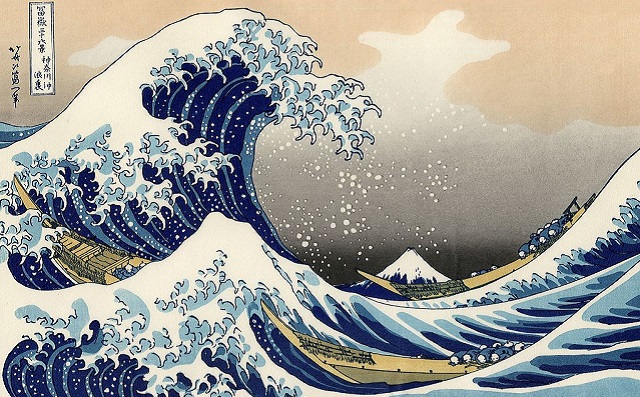



.jpg)


