本能寺の変で栄華から転落 「信長の弟・織田有楽斎」が心の拠り所にした茶道

国宝茶室「如庵」
戦場での活躍こそが華とされ、武功を挙げた人物が注目されることが多い戦国武将。しかし、合戦での功績は少なくとも、文化面で大きな足跡を残した武将たちもいました。時代が違えば、より評価されていたかもしれない人物も...。本稿では、信長の弟・織田有楽斎を紹介します。
信長の弟として生まれるも...
織田有楽斎は本名を長益という。天文16年(1547)、織田信長の13歳下の弟として生まれた。
天正9年(1581)の京都左義長に織田連枝衆4番手として参加し、同じく大馬揃に6番手で参加。そのままいけば安穏と信長の天下の下で生きていけるはずだったのだが、天正10年(1582)、本能寺の変で長益の運命も大きく変転することになる。
本能寺の信長を明智光秀の軍勢が襲うと、長益は信長嫡男・信忠とともに京・二条城に籠もったのだが、信忠に自害を勧め、自身は敵の包囲をかいくぐって安土城へ脱出してしまったのだ。
この振る舞いに、当時の口さがない人々は「織田の源五(有楽斎の通称)は人ではないよ、お腹召せ召せ召させておいて、われは安土へ逃げるは源五、むつき(6月)2日に大水出て、おた(織田)の原なる名を流す」とあざ笑う。
これでは、もはや誰もついていく人はいない。その上、信長亡き後の天下は豊臣秀吉のものとなり、彼の政治生命は完全に断たれてしまった。
そんな長益の拠り所は、茶道しかなかった。
彼と茶道の関係がいつから始まったのか定かではないが、茶道に熱心な兄・信長の影響を受けたものだろうから、永禄11年(1568)の上洛以降、早い時期が起点と考えられる。
天正18年(1590)、甥(信長次男)の織田信雄が秀吉に改易されたあとも、「御伽衆」(話し相手)のひとりとして秀吉に仕え、摂津で2千石の捨て扶持をもらい、「有楽斎」の号を名乗って茶湯の道に精進していく。
あるとき、秀吉は利休の「台子の法」の伝授権を自分が独占したが、有楽斎に対してだけは、「お前は名人だから特別だ」と利休からの直接伝授を許可した。利休は秀吉の前で有楽斎に法を直伝するのだが、直後利休は有楽斎に「極意を言い残した」と耳打ちし、「自分の創意工夫こそが本当の極意」と伝えたという(新井白石『紳書』)。
利休は独創性の無い秀吉には形式だけを教え、期待を寄せる有楽斎には、「他人に習うことなど何も無い」と茶人としての覚悟を説いたのだろう。
秀吉の死後、有楽斎は慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いで徳川家康に従い、大和で3万2千石の大名となり、庶長子の長孝も美濃で1万石を与えられる。
秀吉の側室・淀殿は有楽斎にとって姪にあたるので、慶長19年(1614)、大坂冬の陣が起こると大坂城で後見役を務め、淀殿の子・豊臣秀頼を補佐して、幕府軍との和睦交渉をリードした。
だが翌年、夏の陣に向けて大坂城内の強硬派が主導権を握ったため、城を退去し京・建仁寺の正伝永源院に侘び住まいして茶道に没頭。 元和7年(1622)12月13日に75歳を一期として世を去った。死因は卒中と思われる。
彼の筆による茶杓の絵には「寒熱の 地獄へかよふ 茶杓柄も こころなければ くるしみもなし」との自画賛が添えられていた。天下人・信長の御連枝としての栄華から転落し、プライドをズタズタにされる地獄を経験した有楽斎は、茶道によってそれを乗り越え、「有楽流」の茶道を世に遺したのだ。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月07日 00:05
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 江戸城松の廊下事件の真相~浅野内匠頭はなぜ、吉良上野介を斬りつけたのか
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語


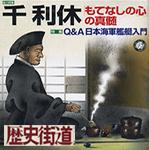


.jpg)


