南紀勝浦の名産「生まぐろ」 高度経済成長期の食を支えた勝浦漁港の歴史
2025年01月24日 公開

写真:「紀の松島」ともいわれる、紀伊半島南端に近い勝浦海岸の景勝。近くには、大規模な老舗温泉旅館もあり、勝浦港との間で送迎の船が行き交う
あのまちでしか出会えない、あの逸品。そこには、知られざる物語があるはず!「歴史・文化の宝庫」である関西で、日本の歴史と文化を体感できるルート「歴史街道」をめぐり、その魅力を探求するシリーズ「歴史街道まちめぐり わがまち逸品」。
今回の逸品は、和歌山県那智勝浦町の「生まぐろ」。生鮮まぐろとも呼ばれる生まぐろとは、漁獲されてから一度も冷凍されていないまぐろのことをいい、一般的な冷凍まぐろと比べると、流通量はわずかで希少なものとなっている。その水揚げ日本一を誇るのが勝浦漁港であり、地域の名産として知られている。この地のまぐろ漁の変遷とともに、生まぐろの魅力について現地で聞いた。
【兼田由紀夫(フリー編集者・ライター)】
昭和31年(1956)、兵庫県尼崎市生まれ。大阪市在住。歴史街道推進協議会の一般会員組織「歴史街道倶楽部」の季刊会報誌『歴史の旅人』に、編集者・ライターとして平成9年(1997)より携わる。著書に『歴史街道ウォーキング1』『同2』(ともにウェッジ刊)。
【(編者)歴史街道推進協議会】
「歴史を楽しむルート」として、日本の文化と歴史を体験し実感する旅筋「歴史街道」をつくり、内外に発信していくための団体として1991年に発足。
まぐろ──太古より日本人に食されてきた魚
 写真:勝浦魚港に面して、飲食店などが入る「にぎわい市場」や足湯などの観光施設がある
写真:勝浦魚港に面して、飲食店などが入る「にぎわい市場」や足湯などの観光施設がある
刺身や寿司種の代表格として愛されるまぐろ。漢字では「鮪」や「真黒」とも書き、体が黒いことからこの呼び名があるとされる。古くは縄文時代の貝塚からその骨が見つかり、『古事記』や『万葉集』などの古書にも「しび」の名で登場する。
もっとも、まぐろは時間とともに劣化しやすい魚であり、冷凍・冷蔵技術が発達する戦後までは、食用魚としての地位は低かったという。それでも、醤油漬けの切り身「づけまぐろ」を握り寿司にしたり、ネギと交互に串に刺して焼いた「ねぎま」にしたりして、江戸時代から庶民に親しまれてきた。
そのまぐろは、和歌山県の「県の魚」にも指定されている。その理由の一つでもあろう、勝浦でのまぐろ漁の歴史を追ってみたい。
高度経済成長期の食を支える
 写真:勝浦漁協のせり場に水揚げされた生まぐろ。写真を見ただけでも、およその良し悪しがわかると、目利きである木下さんはいう〔写真提供:木下水産物株式会社〕
写真:勝浦漁協のせり場に水揚げされた生まぐろ。写真を見ただけでも、およその良し悪しがわかると、目利きである木下さんはいう〔写真提供:木下水産物株式会社〕
勝浦をはじめとする紀伊半島南部の沿岸地域では、明治時代までさんま漁が盛んであった。現在、さんまの漁獲はほとんどなくなったが、地域の食文化の一つに「さんま寿司」があるのは、その名残りだという。大正時代に入ると、それに代わって沖合に出てのかつお・まぐろ漁が中心となり、昭和初期にはすでに、まぐろが水揚げの主となっていた。
国内のまぐろ漁が興隆を見せるのが、戦後の高度経済成長期である。人口と所得の増加とともに食の需要が高まるなか、冷凍技術を導入した漁船による、遠洋まぐろ漁業がこれに応えた。また、水産庁もまぐろ漁業を奨励したことで、新規の参入者が増え、活況を呈することになる。
こうして獲られた大量のまぐろは、刺身や寿司用に生食で活用されるだけでなく、缶詰に加工されてヒット商品ともなった。まさに経済の成長を支える、たんぱく源となったのである。
遠洋まぐろ漁業は、地球規模で移動する回遊魚であるまぐろを追って、太平洋だけでなく、インド洋や大西洋まで、果敢に漁場を求めて向かう。出航すると1年近く、場合によってはそれ以上も帰港できず、荒海での長時間の作業を要する過酷な労働で知られた。
しかし、その利益は大きく、乗組員の報酬も当時のサラリーマン年収の数倍にも及び、給与数か月分の前渡し金を得て、出航前にそれを遊んで使い果たす者もいた。勝浦漁港もこの時期、遠洋漁業の基地となり、そうしたまぐろ漁業関係者によって、町は殷賑(いんしん)を極めたという。
だが、その繁栄は長くは続かなかった。昭和48年(1973)のオイルショックによる燃料の高騰、昭和52年(1977)以降の各国の排他的経済水域設定、さらには昭和60年(1985)のプラザ合意以後の円高による輸入魚の増加などの影響を受け、日本の遠洋漁業は衰退への道をたどることになる。最盛期には1200隻を数えた国内の遠洋まぐろ漁船も、近年操業するのは200隻に満たないと見られる。
現在の勝浦漁港で水揚げするまぐろ漁船は、太平洋側の日本近海を漁場とし、1回の出航で長くて30日、短いと10日ほどで漁を終えて帰ってくる。まぐろを冷凍することなく、活け締めを施したうえ、冷水で保管して運んで来られるのは、この漁場との距離の近さと、漁の期間の短さによるところが大きい。
また、延縄(はえなわ)漁という漁法による利点もある。延縄漁とは、幹縄に釣り針が付いた多数の枝縄を等間隔に付けながら船から流したのち、幹縄を巻き取って、釣り針にかかったまぐろを引き揚げるもの。まぐろ延縄漁の場合、幹縄の全長は数十キロから百キロメートルにも及ぶ。
延縄漁は、他のまぐろの漁法である一本釣りや巻き網漁より、魚体に与える負担が少ないという。まぐろ漁の場合、このことは重要で、運動能力の高いまぐろは激しく暴れると体温が上昇し、極端な場合、80度もの高温になるといわれ、身が変質してしまうのである。
太平洋で世界につながる地にて
 写真:旧漁師町にある天然温泉の公衆浴場。町の店舗などの軒先には、延縄漁の縄に浮きとして付けられたガラスの「ビン玉」が吊るされていて風情を感じさせる〔写真提供:(公社)和歌山県観光連盟〕
写真:旧漁師町にある天然温泉の公衆浴場。町の店舗などの軒先には、延縄漁の縄に浮きとして付けられたガラスの「ビン玉」が吊るされていて風情を感じさせる〔写真提供:(公社)和歌山県観光連盟〕
勝浦漁港で水揚げされるのは、本まぐろともいわれる重さ300キロから100キロぐらいの大型のクロマグロ、大きいもので100キロくらいまでのメバチマグロ、同じく80キロくらいまでのキハダマグロ、30キロから20キロと成魚でも小型のビンチョウ(ビンナガ)マグロと種類が多く、ビンチョウマグロが水揚げのおよそ7割を占める。
「まぐろは良いものと、良くないものの品質の違いが大きいのです。クロマグロでも、ビンチョウマグロでも、同じ種類のなかでグレードによって値段も大きく異なることになります。それを見極め、値を付けるのが私たちの仕事です」
そう語るのは、勝浦で創業して110年あまり、生まぐろを全国の市場や大型量販店に出荷する木下水産物株式会社の代表取締役の木下勝之さん。漁港のすぐ近くの加工場に併設した店舗やオンラインショップでの直販も行なっている。
「上質の生まぐろは、赤身部分はルビー色でゼリーのような透明感があり、質感は羊羹(ようかん)のようにねっとりとしていて、包丁を入れるとくっつくような感じがします。そうしたまぐろは見た目だけでなく、もちもちとした食感で、ほんのりとした甘みもあって味がよいのです」
急速冷凍によって、身の劣化を極力抑える現在の冷凍まぐろであっても、そうした生まぐろの味わいにはかなわないという。
かつて関西で生まぐろというとすべて勝浦産だったが、産地が注目されることがあまりなかったと木下さん。ところが40年ほど前から、輸入の生まぐろが出回るようになり、それらが勝浦産として販売されることもあった。そうしたことを受けて、平成12年(2000)に生鮮食品の原産地明記が義務化され、「国産」「勝浦産」ということが見直されることにつながったという。
「現在は国産・天然・生という3つのキーワードのもと、勝浦産のマグロが注目されるようになり、ありがたいなと思っています」
勝浦港でのまぐろ漁の最盛期は12月から5月。ただ、周年で水揚げがあり、年中、まぐろが獲れるのは、本州では勝浦だけである。
「最盛期には1日に大小2000本から3000本。多い日には6000本近くになることもあって、市場のフロアに置くスペースがなく、1度入札してから再度、水揚げしてフロアに並べることもあります。50本とか、100本とか、まとめて入札してなんとか1日で片付けるのです」
「ただ、流通するまぐろ全体のなかでは、国産天然の生まぐろというのは、とても少ない。だからこそ、こんな小さな港で全国一ともいえるのです。私はここで生まれ育ち、中学生くらいから休みの日にはゴム長靴をはいて手伝いをしながら、生まぐろが毎日、水揚げされるのを見てきました。それが普通のことのように思ってきたのですが、大学生時代とその後の修業で外に出て、初めて勝浦が特殊で貴重な場所であることを知りました」
「いまはそうでもないでのですが、昔は地元では、まぐろは買うものではなく、もらうものという感じがありました。特に私たちは専門の業者なので、恥ずかしくないものを贈ります。そうしてあたりまえのように、この地域ではおいしいまぐろを食べてきたのです」
美しい自然景観や、世界遺産である那智の滝や熊野那智大社を背景にして、豊かに温泉が湧く地でもある勝浦。その地で生まぐろもまた、歴史的産物として息づいてきたことを感じさせられる。
最近は、勝浦漁港や漁協卸売市場を見学に訪れる海外の旅行者が増えている。その一方で、近年のまぐろ漁船の乗組員にはインドネシアなどの外国人も多い。木下さんから聞いた、創業者である曽祖父の話が心に残った。
明治期の青年時代、オーストラリアに出稼ぎに出て、真珠貝を素潜りで採る仕事をしていたのだと。当時の和歌山の勝浦や太地の若者たちは、移民や出稼ぎで海外に出ることが多かったのである。そうして資金を得て、勝浦に戻った曽祖父は、船で各地に魚を卸す事業を始めたという。勝浦は、大いなる海で世界につながる、開拓者の地でもあることを教えられた。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月21日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

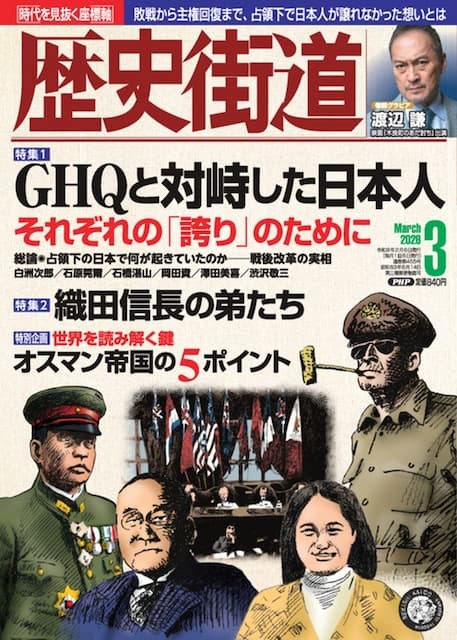




.jpg)


