後醍醐に天皇位を剥奪され、尊氏から2度の裏切り...北朝初代・光厳天皇の生涯

南北朝時代の北朝初代である光厳(こうごん)天皇は、業績と、後世への影響の大きさに比べて、その生涯が、あまりに知られていない。
光厳天皇を主人公とした長編小説『風と雅の帝』を上梓した歴史小説家が、後醍醐天皇に勝利し、天皇のあるべき姿を追い求めた、その人生に迫る。
※本稿は、『歴史街道』2023年9月号より、一部抜粋・編集したものです。
後醍醐天皇の「真の敵」とは?
南北朝時代は、後醍醐天皇と足利尊氏の対立、抗争とされる。南朝と北朝を代表する双方の主役がこの二人というわけだ。が、これはおかしい。南朝の後醍醐には北朝側の天皇を対置してこそだ。
では、北朝の天皇とは誰か。名前が即座に出てくる人はよほどの歴史通だろう。ことほどさように光厳天皇は歴代の中で影が薄い。いや、後段で改めて触れるが、当今で126代を数える「歴代」天皇に含まれてはいないのである。
そんな光厳の北朝といえば、絶対的な庇護者の足利尊氏に擁立された、非力で、か弱い、寄生的存在、傀儡(かいらい)──等々がこれまでの歴史評価だった。よって後醍醐と尊氏の対立、と。
かかる認識はデフォルメにもほどがある。後醍醐の敵、宿敵、真の敵は、尊氏ではなく光厳だった。光厳もまた後醍醐と対決することを義務づけられて、この世に生を享けた宿命の帝である。
自らの運命から逃げることなく、己に課された歴史的使命を双肩に担い、後醍醐に敢然と戦いを挑み、浮沈の末ついに勝利を果たした「戦う天皇」なのである。後醍醐に裏切られた尊氏を己の陣営に引き入れ、手駒とした戦略家でもある。過小評価もはなはだしい英邁(えいまい)の帝・光厳の軌跡を見てゆこう。
その誕生は鎌倉幕府滅亡の20年前に遡る。父の後伏見天皇は26歳にしてすでに上皇で、天皇位には弟の、光厳には叔父にあたる花園が即いていた。
花園天皇は光厳六歳の時、在位11年で譲位し、代わって後醍醐が天皇となる。後醍醐は、光厳の父と同い年で再従兄弟の間柄。祖父を異に、曽祖父は同じくする。すなわち、二つの系統の天皇家が皇位を争って久しかった。
それというのも──。
100年ばかり前に後鳥羽上皇が発令した北条義時追討、いわゆる承久の乱による敗北で天皇の権力がいよいよ失墜してゆき、数代を経て後鳥羽の孫である後嵯峨(ごさが)の即位が、鎌倉幕府の強い意向により決定される。
上皇に退いた後嵯峨は、相次いで即位させた二人の息子──兄の後深草(ごふかくさ)、弟の亀山、どちらを正嫡と決めることなく崩御、天皇位をめぐる争いを招く。
兄家を持明院(じみょういん)統、弟家のほうは大覚寺統といい、持明院統が後の北朝、大覚寺統が南朝だ。両朝の対立はここに淵源する。
以降、双方の系統から代わるがわるに天皇が出て、これを両統迭立(てつりつ)と称する。もちろん決定者たる幕府の裁可を得てのことだから、天皇の力のさらなる衰微凋落は目を覆わんばかりだった。
後醍醐の配流によって...
そうした変則的な状況の下、光厳は後深草天皇の曽孫、父後伏見の嫡男として、兄家持明院統の次代の天皇たることを期待されて出生した。
期待とは、両統迭立状態の打破、つまり天皇位の持明院統による独占、一本化をも含む。生まれながらにして大覚寺統を敵とすべく、熾烈な戦いの星の下に誕生した光厳には、徹底した帝王教育が施されてゆく。
かたや大覚寺統とても望みは同じく天皇位の独占、一本化だ。もちろん、それは大覚寺統によるもの。のみか後醍醐は恐るべき野望を秘めていた。鎌倉幕府を滅ぼし、天皇が政治権力を回復することである。
即位7年目、倒幕計画は密告者が出て未遂に終わるが、側近が責めを負っただけで後醍醐は逃れ得た。とはいえ残された時間は少なかった。「在位10年を過ぎれば譲位」という両家の和談が、幕府を磐石不動の調停者として成立していた。
期限が来れば、和談に従い(実質的には幕府の命令により)皇太子の光厳が天皇となる。2度目の倒幕計画は慎重に、かつ性急に進めねばならなかった。
7年後、再び後醍醐は蹶起(けっき)。京都から奔って南の笠置山に籠城し、倒幕の兵を挙げた──まではいいが、武運つたなく1か月余りで落城、捕われの身となり、承久の乱における後鳥羽上皇処分の先例を踏んで隠岐島に配流されたのは、周知の通りである。
以上のような激動の経緯を経て、光厳は待望の天皇になる。19歳の時だ。先立つ皇太子時代、叔父の花園上皇から『誡太子書(かいたいしのしょ)』と題する誨諭の文章を授けられた。
「太子は宮人の手に長じ、未だ民の急を知らず」
花園は光厳の未熟を鋭くも厳しく誡め、
「請うらくは太子自ら省みよ」
君主としての慎みと徳の大切さとを切々かつ懇々と説き諭したうえで、
「朕(ちん)、強いて学を勧む」
学問天皇──これぞ新時代の天皇のありようだ、と。
そのグランド・デザインの遂行を光厳は叔父上皇から託されたのだった。
とはいえ父の後伏見上皇が院政を敷き、為政者としての出番はなく、それどころか恐るべき風雲が迫りつつあった。これも周知の通り、後醍醐が配流先の隠岐島を脱出、伯耆(ほうき)国船上山(せんじょうさん)に倒幕の旗を翻した。
光厳の即位から1年半という急転直下の展開である。しかも今度は多くの同調者が後醍醐の下に馳せ参じた。極めつきが鎌倉から追討軍の主力たるべく派遣された足利尊氏(高氏)だ。大軍を率いて上洛した尊氏は、主君の北条氏を裏切って後醍醐に寝返り、京都に攻め入った。
幕府の出先機関たる六波羅探題は足利軍の猛攻を持ち堪え得ず陥落、総大将の北条仲時は後伏見、花園の両上皇と光厳を擁し、近江路を敗走する。東下して鎌倉に逃げ延びようというのである。
安徳幼帝を抱いて西走した平家の故事をなぞるかの如くであった。が、美濃国を目前にした番場宿で叛乱軍に前途を要扼され、進退谷まった末に路傍の小寺、蓮華寺で腹を切った。
その14日後には、新田義貞によって陥れられた鎌倉の東勝寺で、北条高時以下の八百数十人余りが集団自刃を遂げ、頼朝以来の幕府が滅亡するが、番場でも仲時だけが自害したのではなかった。
従っていた武士全員が屠腹して果てた。「その数判明するものだけでも四百三十余人、その名はいまも『番場蓮華寺過去帳』に留められている」(黒田俊雄『日本の歴史(8)蒙古襲来』)
蓮華寺に堆く築かれた500人近い死体の山、満々と湛えられた流血の赤い海の中に父、叔父と取り残された光厳天皇は、叛乱軍によって捕虜の身となり、京都へ送還される。
凱旋した後醍醐から下された処分は天皇位の剝奪だった。それも廃帝というより偽帝、つまり即位すらしていなかったことにされてしまった。後醍醐は隠岐島でも、ずっと天皇であり続けていた、という理屈である。
光厳には名目上「上皇」の尊号が与えられた。これぞ後に後醍醐最大の失策となるものだが、この時は父の後伏見上皇が失意の余り落飾し、光厳にも勧めるほどだった。
「思ひもよらぬ」(『増鏡(ますかがみ)』)
と21歳の光厳はきっぱり拒絶する。出家しては後醍醐と戦えない。闘志を熾火として胸に秘めつつ時局の推移を見守った。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月22日 00:05
- 鎌倉幕府を滅ぼした「モンゴル帝国の貨幣経済」 宋銭の流入による社会の変動
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち


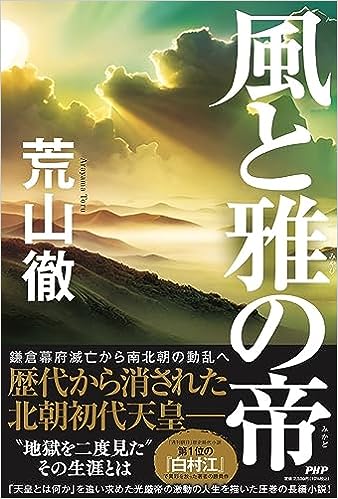





.jpg)


