虎退治で有名な勇将・加藤清正は、実際のところ、どこまで強かったのか

戦国武将のイメージの「通説」は江戸時代以降に作られたものが多い。鈴木眞哉著『「まさか!」の戦国武将 人気・不人気の意外な真相』(PHP文庫)では、名将たちの意外な評価を解き明かしているが、ここでは本書より、虎退治で有名な勇将・加藤清正のほんとうの強さについて紹介したい。
清正には、それほどの武功はなかった?
加藤清正(1562〜1611)は、勇将ベストテンといったものでは、必ず上位に顔を出す人であるが、彼の武功が実際にどの程度だったのかは、疑わしいところがある。「直木三十五氏が、加藤清正は山路将監を討った以外、あまり武功がないとけなしていたが、山路将監を討ったと云う事も伝説に近いのである」(菊池寛『日本合戦譚』)といった声は早くからあった。
清正の代表的武功は、賤ケ岳の戦いで七本槍の一人に数えられたことだが、そのとき柴田方の勇将・山路将監と一騎討ちして討ち取ったとされているのである。そのほか本能寺の変ののち、東上する羽柴秀吉を待ち伏せていた明智光秀の部将・四王天但馬守と取っ組み合いを演じて討ち取ったとか、九州攻めのとき、島津家きっての勇将・新納武蔵守と渡り合ったとかいう話も知られている。だが、これらは、いずれも昔の通俗歴史小説や講談の類が言い出したことで、史実とはほど遠い。
もう一つ、清正を有名にしているものに朝鮮での虎退治の逸話がある。彼が片鎌槍を振るって虎と戦っているありさまは、武者絵や五月人形にも仕立てられている。これは、まったくの事実無根の話ではないのかもしれないが、槍で仕留めたのではなく、鉄砲で撃ちとめたというのが真相のようである。
清正の武功がどの程度のものであったのかを、彼の伝記である「清正記」によって見ていくと、十代のころ、秀吉の城下の近江長浜(滋賀県長浜市)で、人を殺して屋内に立て籠もった者を捕らえたのが最初である。当時、170石だった清正は、この功で200石加増された。この程度の働きに対しては多すぎるが、秀吉にとって清正は又従兄弟にあたるから、この機会に引き立ててやったのではないかと、海音寺潮五郎さんは言っている。
その後、秀吉の中国攻めに従い、天正9年(1581)6月、鳥取城の近くで伏兵と戦い、首を一つ取って100石の加増と感状を受けた。翌年3月、冠山城で一番乗りして首を一つ取ったというので、また加増と感状を受けたが、べつに名のある者ではなかったらしい。
天正10年(1582)6月の山崎の戦いでは、明智光秀の部将・伊勢貞興の鉄砲頭(銃士隊長)の近藤半助という者を討ち取った。翌天正11年2月には、滝川一益の部将・佐治新介の籠もる伊勢亀山城を攻めて、鉄砲頭の近江新七を討ち取った。いずれも、ひとかどの武士ではあるし、「清正記」の言うとおりなら、みずから刀あるいは槍を振るって討ち取っているが、大物と言えるほどの相手ではない。
その次が、天正11年4月の賤ケ岳の戦いであるが、実際に討ち取ったのは、山路将監ではない。柴田の部将・拝郷家嘉の鉄砲頭だった戸波隼人という者である。これで七本槍に数えられたのだが、近藤や近江の場合と違って、具体的にどのように討ち取ったのかは語られていない。この人も、ある程度は名のある侍だったのであろうが、柴田勝家の養子・勝豊の家老だった山路とは〈格〉が違う。
その後も戦場には出ているが、みずから接戦格闘したのは、天正17年(1589)11月、小西行長の応援に出て、天草(熊本県)で土豪たちの一揆と戦ったのが最後であろう。一揆側の客将・木山弾正という者が矢をつがえて迫ってきたので、大将と戦うのに飛び道具はいかがなものか、太刀打ちしようと言って、手にした十文字槍を捨ててみせた。弾正もやむなく弓矢を捨てたところ、清正は槍を拾って突き伏せたというのだから、あまりフェアな話でもない。
清正は、木山弾正と戦ったときには、すでに肥後半国を領する20万石ほどの大名となっていた。それまでの戦歴を見れば、たしかに勇敢に働いて功名は立てているが、比類のないというほどのものではない。この程度の武功を立てた者なら、どこの戦国大名の家にも何人もいただろう。それでも大名として最低クラスである1万石に届いた者など数えるほどしかいない。清正は、たまたま豊臣秀吉のような人物の下にいたから、運よく出世できたのである。同じことは、福島正則など多くの豊臣系大名についても言えるところである。
そうは言っても、清正の勇将としての評判は在世中から聞こえていた。関ケ原のとき、清正は肥後(熊本県)にいて東軍に与したが、西軍に加わった薩摩(鹿児島県)の島津家は、武名の高い清正が来攻することをすこぶる警戒した。
このときは、結局、島津が徳川に屈服したため、戦闘はないままに終わったが、肥後一国をもらった清正が薩摩への押さえのため、数年がかりで築いた熊本城は、二百数十年後に途方もない効用を果たすことになった。
明治10年(1877)、薩摩の西郷隆盛一党が挙兵して西南戦争が始まったとき、熊本城には政府軍の兵営が置かれていたが、そこにいた将兵は、清正のつくった堅固な塁壁を頼りにして、東上をめざす西郷軍に激しく抵抗した。
西郷たちは、そんな事態をあまり予想していなかったし、仮に抵抗されても簡単に蹴散らして通れるつもりだったので、完全に当てが外れた。そのことが最後の最後まで響いて、西南戦争は西郷軍の完敗に終わった。西郷は、わしは政府軍に負けたのではなく、清正公に負けたのだと述懐したという。死せる清正、生ける西郷を走らすというところだが、西郷がほんとうにそんなことを言ったかどうかは定かでない。ただ、西郷軍に加わった人びとの多くは、そう感じただろう。
生きているうちは、あくまでも一介の武将であって、一つの合戦の行方を動かすほどの働きもなかった清正だが、死後長い時間を経て、彼の残した城郭がわが国の運命までも左右したのである。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月16日 00:05
- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」
- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」
- 徳川家は戦国大名の「富」を恐れた? 鎖国を200年貫いた江戸幕府の狙い
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件


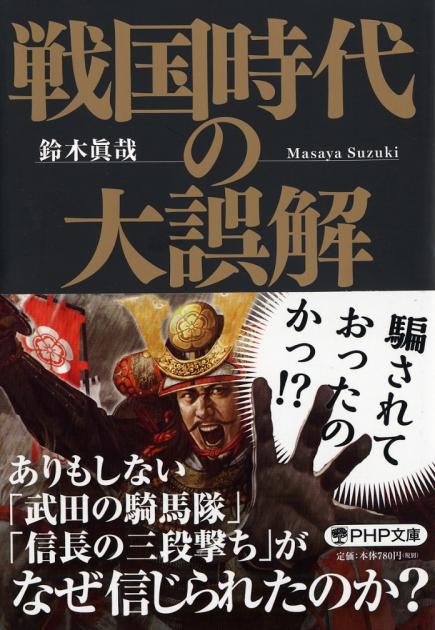

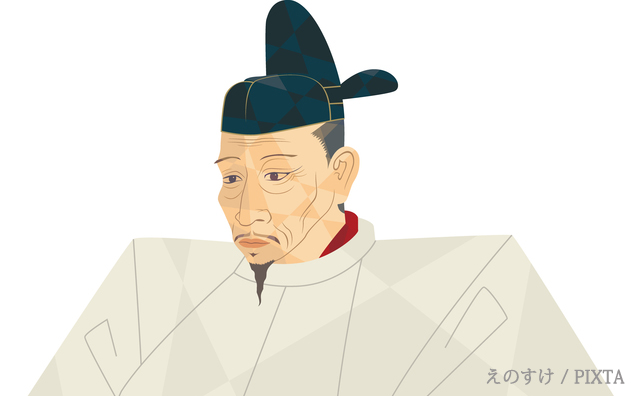



.jpg)


