三国同盟は「ある時点」まで日米交渉を有利に導いた~戦争調査会による検証
2019年07月24日 公開
2024年12月16日 更新

松岡洋右
第2次近衛内閣の外相となり、1915年に日独伊三国同盟、1916年日ソ中立条約を締結。
駐米大使・野村吉三郎の証言
もう一つ、新鮮に感じたことを挙げると、日米交渉に対する見方だ。
日米開戦に至った経緯については長らく、「松岡洋右外相の日独伊三国同盟路線がなければ良かった」と指摘されてきた。
昭和16年の段階では、戦争を回避する二つの方向があった。一つは野村吉三郎駐米大使のワシントンにおける日米交渉、もう一つは松岡洋右外相の独自路線である。
松岡は「三国同盟+日ソ中立条約」によって立場を強化した日本ならば、アメリカと一対一で交渉して戦争回避ができるだろうと考えていた。しかし結局、松岡の路線はうまくいかず、開戦へと至った。
これを踏まえて、「野村駐米大使の日米交渉路線をメインにしていれば、日米戦争は避けられた。松岡の三国同盟路線がなければ良かった」と言われてきたわけだ。
ところが戦争調査会において、野村自身が「三国同盟があったことによって、日米交渉は途中までうまくいった」と語っている。
野村によると、三国同盟の圧力を背景にしてアメリカ側に強く出ることができて、アメリカ側も譲歩の姿勢をみせた。ところが、独ソ戦でドイツが劣勢になり始める。すると今度はアメリカが強く出るようになり、日米交渉が挫折したという。
「三国同盟はある時期まで、日米交渉を進める有利な材料だった」というのは、当時の状況を知るうえで、貴重な証言と言える。
現在の研究では、米国務長官ハルによる文書、ハル・ノートに記された「中国大陸からの日本軍撤兵」との条件には、満洲国を含まない可能性があったと考えられており、日米戦争はギリギリまで回避可能だったという見方がある。
しかし、野村の証言を踏まえると、日本は「アメリカ側が外交ポジションを強くしている」と認識していたことがわかる。つまり、アメリカは、「劣勢に陥っているドイツと同盟を組んだ日本は怖くない。日本が大きく譲歩しなければ、妥協する必要はない」と見ているだろうと。
当時の政策決定者がこのように受け止めていれば、日米の合意点は、容易には見出だせなかったに違いない。
後世の我々は、論理的には「ハル・ノートが出ても、最後まで戦争回避の可能性は残っていた」と言うことができる。
しかし、実際の外交交渉を考えた場合、「野村駐米大使の日米交渉が挫折した段階で、戦争は不可避になった」という戦争調査会の議論は、説得力がある。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月08日 00:05
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本

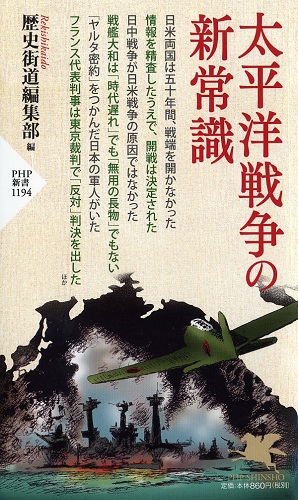


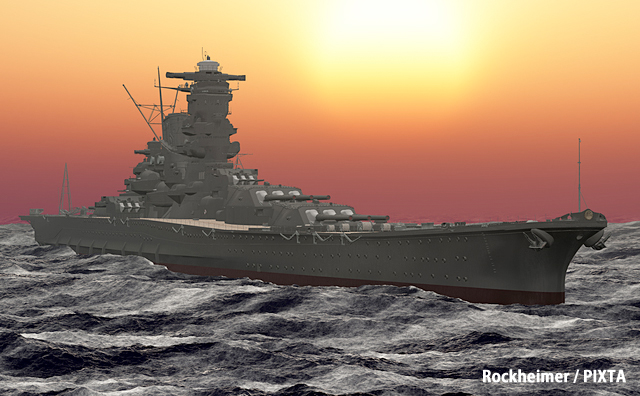

.jpg)


