三国同盟は「ある時点」まで日米交渉を有利に導いた~戦争調査会による検証
2019年07月24日 公開
2024年12月16日 更新

近衛文麿
昭和12年、第1次近衛内閣を組閣。盧溝橋事件を契機に日中全面戦争へ突入する。以後3次にわたり首相をつとめた。
南部仏印進駐をめぐる日米のギャップ
太平洋戦争というと、「満洲事変から日米開戦まで一直線に進んでいった」とイメージする方も多いだろう。
既に終わったことを後の時代から考えると、どうしてもひとつながりに見えてしまうものだが、政治・外交における実際の過程は、紆余曲折を経ていた。
戦争調査会は、当事者が戦争の原因を追究したこともあって、「満洲事変が起きたから、日米戦争は避けがたくなった」と考えてはいない。
「満洲事変、日中戦争、日米戦争には区切りがあり、それぞれの段階で戦争を回避する方法があった。しかし、それは実現しなかった。なぜ、実現しなかったのか」といった形で議論を進めている。
つまり、日米開戦に至る間にいくつもの「分岐点」があり、各局面における「分岐点」を検証しているところが、戦争調査会の一つの特徴なのである。
そうした戦争調査会の中で、私が新鮮だと感じたのは、昭和16年(1941)6月の南部仏印進駐に関する議論だ。
調査会の中で、昭和15年(1940)から陸軍省整備局戦備課長をしていた岡田菊三郎は、「アメリカの態度を硬くし、戦争が避けがたくなってきたと思わせたという点では、南部仏印進駐が非常に重大な転換点だった」と指摘している。
なぜ、アメリカが態度を硬化させたのか。南部仏印に日本軍の基地ができると、アメリカ領だったフィリピン、イギリス領だったシンガポールに、日本の爆撃機や戦闘機が直接、行けるようになり、それを脅威に感じたのだというのが、岡田の見解だ。
では、なぜ、日本はそんなことをしてしまったのか。これについては、当時の首相だった近衛文麿が遺書の中で書いている。
それによると、昭和16年6月22日に独ソ戦が始まり、当初はドイツの調子がいいように見えたので、「ここでソ連を叩くべきだ」と陸軍が主張していた。近衛はその陸軍をソ連と戦わせないために、南方に目を向けさせる目的で仏印進駐を決めたのだという。
仏印進駐の是非をめぐり、戦争調査会で議論になっていたように、南部仏印進駐を行なった日本側の意図と、米側の受け止め方のギャップが、日米開戦を不可避にしたという視点は、今日の研究状況からしても、新しいと思わせるところがある。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月31日 00:05
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 織田勘十郎信行~信長に反逆して殺された実弟
- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流
- これだけ知っておけば大丈夫! 日本海軍艦艇10の基本
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

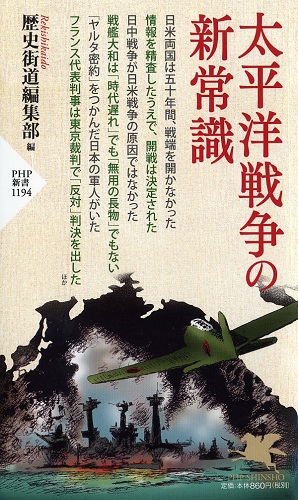


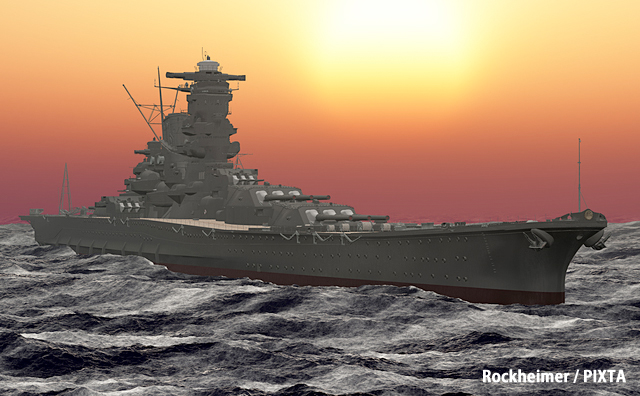

.jpg)


