戦国最強武将・立花宗茂と真田信繁、それぞれの「返り咲き」

関ケ原後にそれぞれが抱いた思い
関ケ原の戦いでは、真田信繁は上田城に徳川軍本体というべき徳川秀忠軍をくぎ付けにし、立花宗茂は大津城を落とすという戦局を左右する活躍を見せた。
ところが結果は周知のとおり、西軍本体が敗れたため、2人は「負け組」となってしまう。しかしその後の人生は、まったく異なる方向に進んでいく。
宗茂は柳川を取り上げられ、浪人となった。
その宗茂を慕って付き従おうとする家臣は、かなりの数にのぼる。宗茂は家臣たちの身の振り方を心配し、加藤清正に預けるなどして、再就職の道をつけた。
それでもなお、宗茂の側を離れず、宗茂が生活できるように尽力する家臣たちがいたのだ。
彼らの逸話はいくつも残っているが、取り潰された大名の家臣が、これほどまでに主君を支え続けた例はあまりない。強い者になびくという当時の風潮の中で、己の信念を貫いて浪人となった宗茂の生き方に共感し、「この人のためなら」という思いがあったのだろう。
また、宗茂を見捨てなかったのは、家臣だけではなかった。東軍の諸大名にも手を差し伸べる者がいたし、何よりも徳川家康が、宗茂を拾い上げようとしたのである。
関ケ原後、加藤清正らが島津を攻めに向かう際、すでに降っていた宗茂は、無用な戦をさけるべく、島津方に降伏を説いて実現させている。
宗茂にとって島津家は、実父・高橋紹運を討った仇敵だが、この頃はその恨みを超えて親しい関係にあり、だからこそ仲介役を果たせたのである。
おそらく家康は、そうした宗茂の人間性を高く評価したのではないかと思われるが、慶長11年(1606)に陸奥・棚倉を与えられて、宗茂は大名に返り咲くのである。
豊臣家に尽くした宗茂が、徳川家の大名となったわけだが、これは変節とはいえないだろう。
秀吉に取り立てられた恩は、関ケ原で西軍に与し、そして柳川を失うことで返した、といえるのではないだろうか。
宗茂に、立花家を残す意思がどの程度あったかはわからない。しかし、浪人した家臣たちの身の振り方を考えたときに、「次に大名として復帰できる道があるならば、それに従うのが自分の生きる道だ」と考えたように思う。
慶長19年(1614)に始まる大坂の陣で、宗茂は将軍・徳川秀忠の側近くに従軍した。徳川家に取り立てられた大名として、秀忠に従って戦陣に立つ。それはそれで、筋が通っているのである。
そのような宗茂と比べて、信繁の置かれた立場は、「差し伸べられる手」が皆無に等しい。
信繁は父の昌幸とともに九度山での蟄居生活に入り、昌幸の死後も許されることなく、9度山で暮らす日々が続いた。
これは、「真田親子は許せない」という家康の意思の表われだろう。
有名な話だが、家康が昌幸と信繁を死罪にしようとしたとき、信繁の兄である真田信之が「自分の手柄に換えて、父と弟を許して欲しい」と嘆願し、信之の妻の父である本多忠勝が同調して家康を説得した。その結果、2人は殺されて当然のところを、9度山に流されただけで済んだのである。
こうして命を長らえることはできたものの、徳川の世が続く限り、信繁はこのまま9度山で蟄居し続け、死ぬよりほかになかった。
そこに、大坂城から誘いが来た。
「このままでは終わらない」
「もう一花咲かせたい」
信繁はそんな思いから大坂城に入り、「ここで死んでもいい」という気迫をみなぎらせて、真田丸の攻防戦に臨んだと思われる。
なぜ、共感を呼ぶのか
元和6年(1620)、立花宗茂はふたたび柳川に封じられた。関ケ原後に改易され、旧領に復帰できた大名は、宗茂ただ1人である。
また、徳川秀忠の相伴衆を務め、寛永15年(1638)の島原の乱に出陣するなど、徳川の時代になっても存在感を発揮した。
一方、真田信繁は大坂冬の陣の後で、徳川方から「信濃一国を与える」という条件で調略を受けたが、これに乗ることなく、夏の陣で散った。
しかし、後世に「日本一の兵」と呼ばれる栄誉を、信繁は得た。宗茂とは違うが、これもまた「返り咲き」といっていいだろう。
宗茂と信繁の「返り咲き」のかたちが異なったのは、関ケ原後の置かれた立場が違ったからだ。
しかし、2人には共通するものがある。
関ケ原で負け組となり、ほとんどすべてを失いながら、めげることなく、自分の生き方を貫き通したことだ。
文字通り生きるか死ぬかの戦国時代に、揺らぐことなく、1本の筋を通した。だから2人の生き方は、時代を超えて共感を呼ぶのだろう。
言い方を変えれば、闇雲に権力者に抗ったのではなく、それぞれの「理にかなう生き方」を全うした。そこに、人は「美しさ」を感じるのではないか。
それにしても、「負け組」から返り咲いた生き方は驚嘆に値する。
1度や2度の失敗であきらめない。自らを信じ、その生き方を貫いた「不屈の精神」こそ、現代のわれわれが2人から学ぶべきものだろう。
歴史街道の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月10日 00:05
- 豊臣秀長なくして「墨俣一夜城」は実現しなかった?秀吉の出世を支えた弟の戦略
- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング
- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語
- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち
- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語
- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史
- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件
- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯
- 織田信長の妻・帰蝶は“本能寺の変の後も生きていた”と思える理由
- 秀吉を天下人にした弟・豊臣秀長 正反対の兄弟はなぜ仲違いしなかったのか

.jpg)


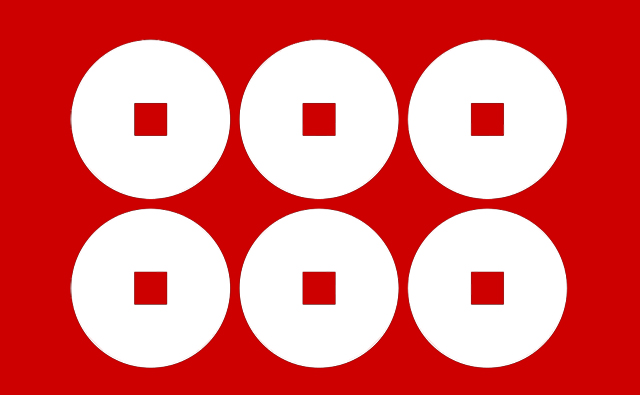

.jpg)


